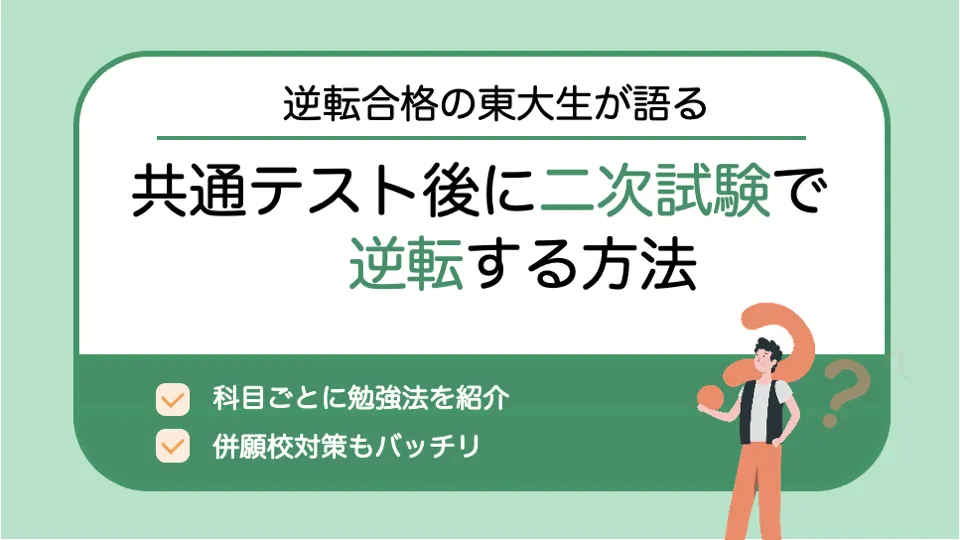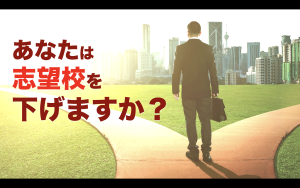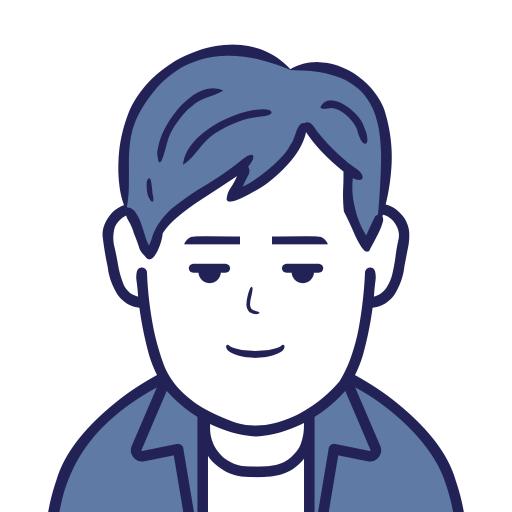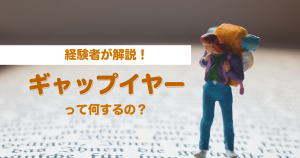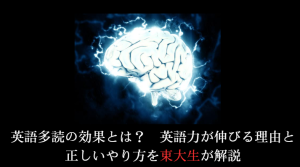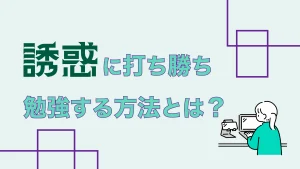共通テストが思うようにいかなかった――。そんな不安を抱えている受験生も多いのではないでしょうか。しかし、まだ諦めるのは早いです。実は、共通テストで失敗しても二次試験で大逆転することは十分可能です。
本記事では、共通テストの得点が合格者平均より約100点も低かったにもかかわらず、東大合格をつかんだ東大生ライター・生島光流が、二次試験で「どう挽回したのか」「何を意識して勉強したのか」を具体的に解説します。
生島光流へのインタビュー記事をまだ読んでいない方は、ぜひお読みください。【2025年10月15日更新】

はじめに
大学受験では、誰もが一度は壁にぶつかります。共通テスト(以下共テ)の結果が思うようにいかなかった人もいれば、これから本格的に二次試験対策を始める人もいるでしょう。どんな状況であっても、共通テスト終了からの過ごし方次第で、結果は大きく変わります。
共通テストは出題形式や難易度の変動が大きく、短時間で膨大な情報処理を求められる非常にタフな試験です。そのため、思うように点が取れなかったとしても、それは珍しいことではありません。国公立志望の人にとっては、むしろ本当の勝負は二次試験から始まります。二次試験では、思考力・表現力・論理性など「じっくり考える力」が問われるため、ここで逆転することは十分に可能です。
共通テスト後に起こりやすい「共テボケ」とは
共通テストが終わったあと、多くの受験生が直面するのが「共テボケ」です。これは、共通テスト形式の問題演習を続けすぎたことで二次試験の記述型問題に対応できなくなったり、一次試験が終わった達成感から気が緩んで勉強への集中力が落ちてしまったりする状態を指します。
この共テボケを放置してしまうと、二次試験当日までに本来の実力を発揮できないまま本番を迎えることになり、取り返しのつかない結果になりかねません。
共テボケは、共テ受験後の受験生が陥りやすい現象です。共通テストという大きな山を越えた後、心身ともに一度緊張の糸が切れてしまうからです。私自身も共テが終わった直後、苦手な形式から解放された安心感でダラダラと過ごしてしまい、勉強のペースを取り戻すのに時間がかかりました。
しかし、ここでいかに早く切り替えられるかが、二次試験の結果を左右します。
共テボケを断ち切る3つの方法
切り替える方法として一番手っ取り早く、かつ一番効果的なのはやはり、緊張感を強制的に持たせることです。緊迫感を煽り、危機意識を向上させることで無意識的に体を勉強へ向けさせることができます。
時間を測ってニ次試験の問題を解く
1つめの方法は、時間を測ってニ次試験を解くことです。これは本番と同じ状況をつくって自分を試す方法であり、本番と同じ環境で演習することで、自然と気持ちが引き締まります。
もし演習結果が思わしくなければ、それが危機意識を高め、勉強に本腰を入れるきっかけになります。共テボケが強い人は全科目を1年分、あまり共テボケを感じない人は苦手科目だけでも構いません。とにかく早めに二次試験の問題に触れることが重要です。
自習室に行く・同じ志望校の友達と一緒に勉強する
2つめの方法は、「同じ目標を持つ仲間のいる場所に身を置くこと」です。自習室で勉強したり、志望校が同じ友人と一緒に勉強したりするだけで、周囲の空気から緊張感が伝わってきます。環境の力を借りて、自然と集中できる状態を作り出しましょう。
併願校の入試を受ける
もし可能であれば、併願校の入試を受けるのが最も強力な解決方法です。実際の試験会場の緊張感は、どんな模試よりも強烈です。これは筆者の実体験ですが、共通テスト後にこの「本番の空気」を再び味わうことで、「自分の受験はまだ終わっていない」という実感が戻り、やる気が一気に高まります。
補足:焦らず、緊張感を味方につけよう
緊張感を高めるための方法を紹介してきましたが、ここで注意したいのは、焦燥感と緊張感を混同しないことです。緊張感は集中力を高め、行動を前向きに変えてくれますが、焦りは心を乱し、勉強が手につかなくなる原因になります。
共通テストがうまくいかなかったとしても、ニ次試験での逆転を信じて全力を尽くすしかありません。志望校によって実施日に変動があるものの、ニ次試験までは約1か月。巻き返しのチャンスは十二分にあります。
第一志望合格に向けてやるべきこと
これまで紹介した通り、二次試験での逆転を狙うためには、まず共テボケを解消し、二次試験の形式に早く慣れ直すことが第一歩です。そのうえで、科目ごとに重点を整理し、限られた時間を効果的に使うことが大切です。まずは
共通テストで触れなかった科目を優先的に演習する
共通テストで出題されなかった科目、特に理科・社会は直前期に最も伸びやすい分野です。主要3科目(英・数・国)が安定している受験生は、理科・社会で「事故」を起こさないようにしましょう。最低でも合格者最低点、できれば合格者平均点を目標に、演習量を確保することが大切です。
苦手な主要科目を優先的に立て直す
主要3科目の中に苦手がある場合は、まずそこを重点的に対策しましょう。英・数・国の大きな失点は合否に直結します。特に数学と古典は、理解が定着すれば短期間でも得点を伸ばせる科目です。
ただし、焦ってすべての科目に手を広げすぎるのは禁物。優先順位を明確にし、点数へのリターンが大きい科目に時間を割くことが重要です。
英語と国語は毎日触れる
英語と国語は、短期間で劇的に伸ばすのが難しい科目です。しかし、放っておくと感覚がすぐに鈍ってしまいます。毎日少しでも文章を読む習慣を維持し、読解のテンポを保ちましょう。
英語なら長文を音読したり、英文要約を行ったりする。国語なら現代文の評論を1題読んで論理展開を意識する。英語でも国語でも、文章に読み慣れておくことの積み重ねが、直前期の安定につながります。
科目バランスを意識して総合点を最大化する
二次試験では、1科目の得意・不得意よりも総合点の安定感が鍵になります。得意科目で大きく稼ぎ、苦手科目で失点を最小限に抑える。そのバランスを意識して勉強時間を配分すれば、第一志望校合格の可能性は確実に高まります。
科目別アドバイス
ここからは、二次試験に向けてどの科目をどのように勉強すべきかを、科目別に解説していきます。
国語(現代文)
共通テスト対策によって、文章には十分読み慣れている状態だと思います。そのため、共通テストでは課されていない、ニ次試験の記述問題を解くことに専念しましょう。ただし、ニ次試験に記述の現代文が出題されない場合はこの限りではありません。
共通テストが終わってからは、毎日現代文の文章に最低1つは触れることを強くおすすめします。先ほども述べた通り、日々の読み慣れが読解の感覚を失わないために極めて重要です。短い文章でも構わないので、継続しましょう。
国語(古典)
古典が得意な人は、記述式の問題を解いて感覚を取り戻しつつ、他の苦手な科目にリソースを割きましょう。苦手な人も、ここからの伸びが期待できます。古典は直前でも十分伸びる科目だからです。
基本的な古文単語、古典常識、古文の助詞助動詞、漢文の句法、漢文の語句の暗記に努めてください。古典で失点をしている人は、ここがあやふやな可能性が高いです。また、古典においても読み慣れが重要であるため、苦手な人は古典の文章に触れる機会を増やしましょう。
数学
数学も直前期の伸びが期待できます。一旦「データの分析」のような出題どの低い単元は忘れて(もちろん学問的には重要な単元ではありますが)、ニ次試験で頻出の分野を重点的に過去問で演習してください。
共通テストとニ次試験で科される問題では、出題形式や難易度に大きなギャップがある場合がほとんどです。記述式の大学を受けるのであれば、しっかりと計算過程や記述までも書けるように過去問に触れてください。
特に理系の人は、数Ⅲが肝です。共通テスト対策期間では数Ⅲに触れず、公式を忘れてしまっていることが多いです。網羅型の参考書をざっと見返したり、軽い計算問題に触れたりすることで、数Ⅲの感覚を早めに取り戻すことが大切です。
理科・社会
直前期の伸びが圧倒的に見込める科目です。主要3科目の中に苦手分野がある場合は、それを克服することも重要ですが、戦略的に理科・社会の得意科目で得点を底上げするという考え方があります。
学校によっては、共通テスト前後にようやく全範囲を終えることもあります。その場合、演習不足の可能性が高いため、とにかく過去問を解きましょう。理科・社会は、解いた量が得点に直結する科目です。どれだけ多くの問題に触れ、どれだけ早く解答の型を身につけられるかが鍵になります。
また、歴史や化学など暗記量の多い科目では、知識のアウトプット練習を重ねることが不可欠です。単語や用語をただ覚えるだけでなく、自分で小論述を書いたり、短い説明を声に出して確認したりすることで、知識が定着していきます。
英語
共通テストでかなりの量の英文を読んできていると思うので、読み慣れやリスニングについては申し分ないと思います。最初に対策すべきは、共通テストで感覚を忘れがちな英作文です。時間を測って演習し、他の人から添削を受けるのを繰り返してください。加えて、英作文は最後まで点数が上がる可能性がある分野でもあります。確実に点数を取りに行きましょう。
あとは1週間に2回ほど、継続的に1年分の過去問を、本番の試験時間内で一気に解く練習をすることが大切です。英語は試験時間が厳しめに設定されていることが多いので、時間配分や問題の難易度の見極めの精度をあげることが直前期では最も重要です。
もしも、現時点で過去問演習をすべて終えている場合は、予備校の模試の過去問を解くことをお勧めします。予備校が出している模試は、解説が充実していて自習しやすいのがポイントです。
短くても良いので、毎日英文に触れることを欠かさないようにしましょう。国語と同じく「読まない期間」をつくると読解感覚が鈍ります。加えて、英単語・熟語・文法の定期的なアウトプットも忘れずに行いましょう。
併願校の対策
多くの受験生にとって悩ましいのが、併願校(滑り止め)の対策です。第一志望校を受ける前に併願校の合否が出る大学を選んでおけば、合格の事実が自信につながり、より前向きな気持ちで本命の試験に挑むことができます。しかし一方で、併願校対策に時間を割きすぎると、第一志望の準備が疎かになるリスクもあります。両者のバランスをどう取るかが、受験後の後悔を減らす最大のポイントです。
まずは「第一志望への集中」が最優先
結論から言うと、第一志望の対策にとにかく集中するべきです。
共通テスト前から第一志望に向けて演習を重ねてきた受験生が多く、特に第一志望校の難易度が最も高い場合、併願校の入試でも十分戦える実力があることがほとんどです。これまで積み上げてきた勉強を信じて、第一志望を軸に据えたまま併願校を受けることが、最も安定した結果につながります。
併願校の過去問は「形式確認」だけでも早めに
とはいえ、併願校の問題傾向を早めに知っておくことは必須です。二次試験の過去問をしっかり見るタイミングが共通テストまでなかった人は、共通テスト後のタイミングで必ず出題形式を分析しておきましょう。
たとえば
英語:文法/読解/要約/和訳のどれが中心か?
国語:現代文と古典の配点や大問数、古典の有無は?
数学:途中式も記述させる形式か、それとも答えのみか?
これらを把握しておけば、直前期に問題形式を見て焦ることを防げます。
対策は「過去問中心」で十分
その後は自分の学力に合わせて、過去問演習「のみ」してください。
併願校用に新しい参考書や勉強法に手を出す必要はありません。それよりも、第一志望の対策に時間を投じた方が、後悔なく受験を終えられます。
目標は過去問を2年分、少なくとも1年分は本番同様の試験時間で解きましょう。本当に時間がない人は英国数のみ、最悪英語のみでも大丈夫です。少なくとも併願校の英語は1年分解いてください。
私は東大を第一志望にしながら、早稲田大学(文化構想学部・教育学部)、慶應義塾大学(商学部A方式)併願しました。本試験の1週間前に各大学の過去問を1年分(英語のみ2年分)を解いて対策し、すべて合格を得ることができました。
国公立大学の後期試験を受ける人は、前期試験が終わってから本格的に対策を始めましょう。
最後に
共通テスト後からニ次試験本番までの勉強の流れを紹介しました。受験がラストスパートに差し掛かっていても、共通テストはあくまで通過点です。戦いはまだ終わっていないという強い意志を持ち、ぜひ最後までやりきってほしいです。
もし、勉強がうまく進んでいなかったり、諦めてしまいそうになったりしても最後まで可能性が残っていることを忘れないでください。残り1か月、短いようですが、時間はあります。残された時間で自分がどう戦うか、しっかりと考えましょう。応援しています。
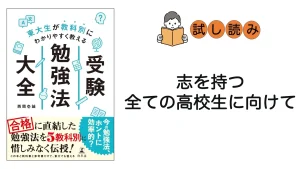
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。