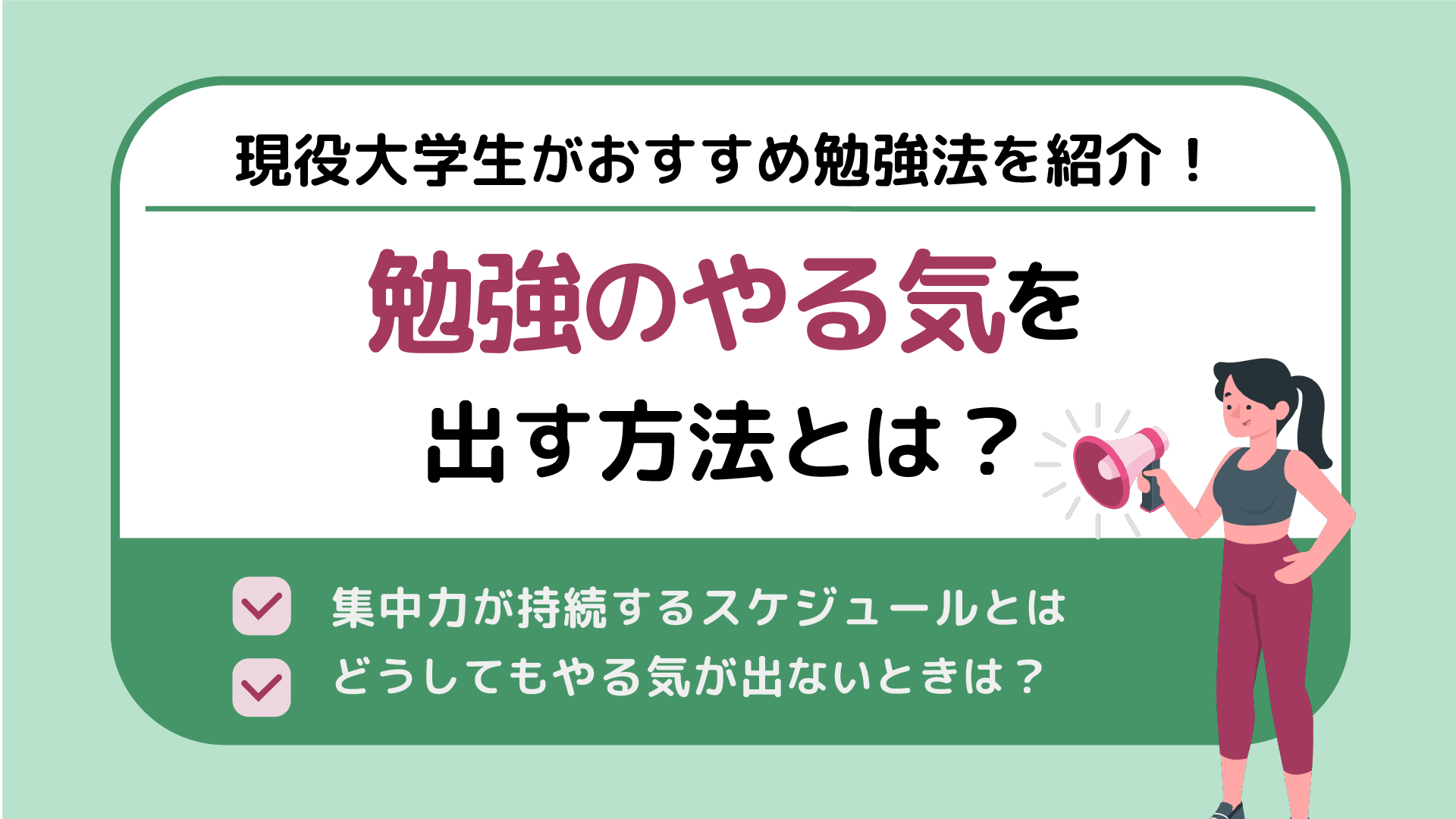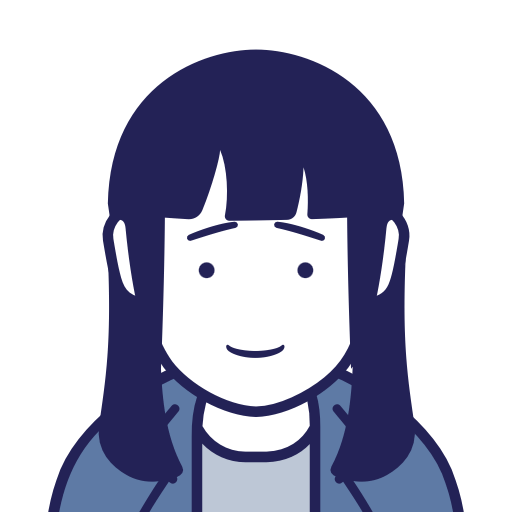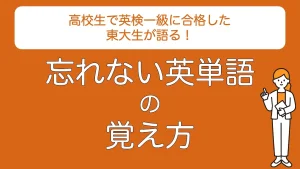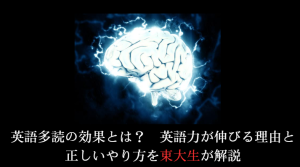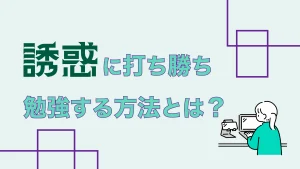「勉強しなきゃいけないのに、全然集中できない……」
そんな悩みを抱えている受験生は多いのではないでしょうか。やる気を出そうとしても、スマホの誘惑、眠気、集中力の低下など、様々な壁にぶつかりますよね。
この記事では、「どうしてもやる気が出ない」という時に試してほしい勉強法を、現役大学生の筆者や友人の経験とともに紹介します。
勉強のやる気を高める基本の方法
目標設定の重要性
勉強のやる気を出す1つ目の方法は、目標設定を行うことです。
目標を立てることが大事だということは分かっていても、目の前の課題に追われて、正しく設定できていない人は意外と多いと思います。やる気の源泉は「目的意識」です。どんなに苦手な勉強でも、「なぜそれをやるのか」が明確になれば、人は自然と前に進もうとします。
たとえば「夏休み中に英単語帳を1冊完璧にする」「模試で数学80点以上をとる」など、明確な数値や期限を含む目標を設定することで、やる気は格段に上がります。達成しやすいものでもいいので、小さな目標から立ててみましょう。
具体的な勉強プランの作成
目標設定のコツは、最終目標から逆算して、短期の目標を設定することです。
「志望校に合格する」「最終試験で100点を取る」など、最終的に達成したい目標だけでは、具体的に何をすれば良いか分からず、モチベーションへの効果は低くなってしまいます。最終的に達成したい目標から逆算して、1ヶ月単位、1週間単位、1日単位の、具体的なプランを作ることが大切です。
たとえば最終目標を「〇〇大学入試の英語科目の特典アップ」とした場合、まずはどの程度のレベルの長文を、何割解く必要があるか、過去問などで確認します。
次に、大まかな計画を立てます。「◯月までに英単語、文法を完璧にし、その後試験に向けて長文を解く」などです。そうすると、1ヶ月ごとにするべきことが見えてきます。「受験直前の1月は、とにかく長文を数こなすことに集中したい」「だから基礎固めは夏休みが終わる8月いっぱいで終わらせよう」などです。
さらに、1ヶ月を4週間に分け、1週間ごとに勉強計画を立てることもできます。最終的には1日単位で「16:00〜16:30 英単語」「16:30〜17:30 長文読解1つ」といった具合に細かく時間と内容を決めることが目標です。
筆者は毎日寝る前に、次の日の勉強計画を立てていました。筆者の場合は時間は指定せず、やるべきことと優先順位を決め、優先順位の高いものから取り組むようにしていました。やることが決まっていれば、朝起きてからすぐに取り掛かることができ、「勉強を始める」ことへのハードルが大きく下がります。
手帳などと組み合わせることもできるこの方法はとてもおすすめなので、モチベーションが湧かず、勉強を始めるまでに時間がかかってしまうな、と感じている受験生の方は、ぜひやってみてください。

集中力を持続させるスケジュール作り
集中力には波があります。朝・昼・夕で一番集中できる時間帯を見つけ、その時間に重要な学習を配置することがポイント。勉強時間を3〜4ブロックに分け、負荷の強いものから軽いものへと流すような構成にすると疲れにくくなります。たとえば、以下のような大→小→大→小の流れを作るのがおすすめです。
- 朝(大):負荷のかかる数学の記述問題や英語の長文
- 昼過ぎ(小):眠くなりやすいため朝の分の丸つけと復習
- 夕方(大):もう1度負荷の大きな勉強(苦手科目など)
- 夜(小):寝る前は暗記系
環境を整える
スマホとの付き合い方
集中できない要因の一つに、環境も考えられます。スマホ通知、部屋の散らかり、座りにくい椅子……これらは無意識にやる気を奪います。
特にスマホは、受験生にとって大敵ですよね。筆者の周りの人の多くは、受験期間にSNSのアプリを削除していました。通知を切るだけでも効果的です。また、自習室にいる間、友達とスマホを預けあっている人もいました。勉強の時間を決めて、スマホの電源を切ってしまう方法も良いかもしれません。
スマホとの付き合い方をよく考え、勉強に集中できる環境をつくる努力をしましょう。アプリを開ける時間を制限する機能や、開いている時に他のアプリを開けなくする集中アプリも存在するので、有効活用しましょう。
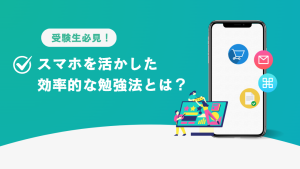
勉強場所
静かな場所の確保が難しい人は、図書館や自習室を活用するのも良いでしょう。同じ場所で集中し続けるのが苦手な人は、1日の中で複数回場所を変えるという手もあります。午前中は家で勉強し、昼からは図書館に移動、疲れたらカフェに移動するといった具合です。
毎日のワークがルーティーン化し、やる気がなくなりやすい受験勉強も、移動することによって、集中力を維持できるそうです。
音楽
人によっては、音楽が集中力を高めてくれます。集中したいときは歌詞のないBGM(クラシック、自然音など)を選びましょう。周囲の雑音が気になるなら、ノイズキャンセリングイヤホンの使用も有効です。どうしてもやる気が出ない時に、好きな曲の力を借りるのも良いでしょう。実際筆者も、やる気が出ない時は、多少効率が落ちる前提で、好きな曲を大音量で聴いていました。
ただし、「音楽を聴くと集中できない」という自覚がある人も多いと思うので、時と場合に応じて使い分けましょう。特に歌詞のある曲は、数学の記述問題や、現代文や英語の長文問題と相性が悪いです。やる気が出ない時は、最初の30分だけ「作業系の勉強×好きな曲」と決めるなど、適切に使えるようにしましょう。

適切な休憩
やる気を持続させるには、意識的に休憩を挟むことが不可欠です。
たとえばポモドーロ・テクニックという有名な勉強法があります。「25分勉強したら5分休憩」を繰り返すことで、長時間勉強するよりも、集中力を維持できます。実際に取り入れている受験生も多く、Youtubeなどの動画サイトでは、ポモドーロ・テクニックのタイマー動画が多数公開されています。
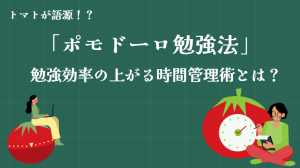
また、休憩時間の過ごし方としては、ストレッチや水分補給、目を閉じてリラックスするだけでも効果的です。休憩時間にスマホを触ってしまうと、かえって目や肩が疲れてしまうので、疲れを感じる時にはスマホを触らず、積極的に体を休めるようにしましょう。
逆に、散歩などをして、適度に体を動かすのも効果的です。筆者は勉強の気分転換に、塾の周りを散歩していました。外の空気を吸うことが良いリフレッシュになることもあります。
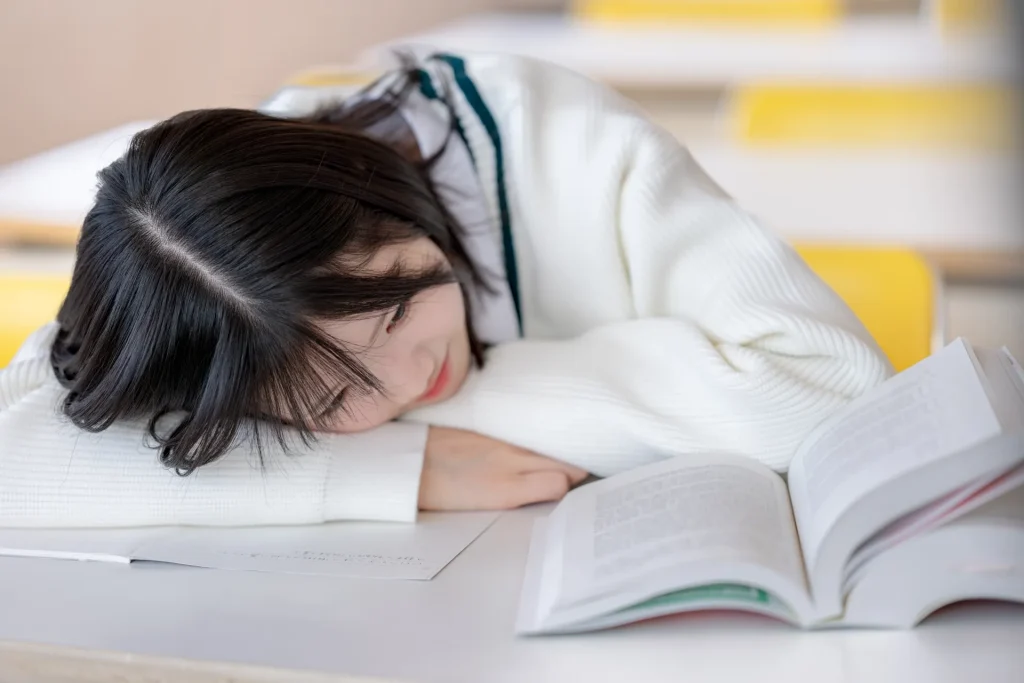
おすすめの勉強法
朝のルーティン
「1日の充実度は、朝の過ごし方で決まる」という話があります。1日のスタートをどれだけ気持ちよく過ごせたかが、その日の充実度を左右するのです。
たとえば、簡単な音読や5分の復習から始めてみてはいかがでしょうか。脳が「勉強モード」に切り替わるためのスイッチとなるようなルーティンを決めると、勉強を習慣化することができます。
筆者はいつも英語の長文を解く前に、すでに解いた長文を音読することから始めていました。こうすることで、脳が英語モードに切り替わり、英文が入ってきやすくなります。また、普段これをやっていたので、本番の英語試験前にも同じことをし、本番も集中した状態で臨むことができていました。このように、自分の集中を短時間で引き出すルーティンを設定しておくことは、普段の勉強だけでなく、大事な本番にも役立ちます。
ごほうびの設定
「〇〇が終わったらYouTubeを10分観る」「5ページやったらお菓子を食べてOK」など、自分へのごほうびを設定する方法です。報酬があると脳は快感を覚え、やる気を出しやすくなります。
注意点は、報酬が目的にならないようにコントロールすること。早く報酬を獲得したいという思いから勉強に集中できなくなったり、タスクを早く終わらせようと焦ってしまうのは、かえって逆効果です。
カルぺの東大生の中には、「模試で続けて学年1位を3回とったら新しい携帯を買ってもらう」など、家族を巻き込んだごほうびシステムを構築している人もいました。自分だけでコントロールするのが難しい場合には、家族や友達にも協力してもらいましょう。
好きな科目でサンドイッチ
これは、筆者が塾の先生に教えてもらった勉強法です。まずは好きな科目でやる気を出し、次に苦手な科目を頑張り、また好きな科目をやるというふうに、交互に行うとやる気を維持できるというものです。
皆さんも、思わず好きな科目から勉強を始めたという経験があると思います。得意な科目から勉強を始めると、問題にも正答しやすく少しずつ勉強のやる気が出てきますよね。ただ、好きな科目ばかりに偏って、苦手な科目の対策が疎かにならないように十分注意する必要があります。やる気の向上と苦手克服のバランスを意識しながら勉強しましょう。
まずは5分だけ
「やらなきゃ…でも今はいいや」と思った瞬間、まずは5分だけやると決めましょう。
心理学的に、人は始めさえすれば継続しやすい傾向があります。小さな行動から始めることが、先延ばしのクセを断ち切る第一歩です。5分後には、「もっとやりたい」と思えているかもしれません。
「あと5秒たったら腰を上げよう」と決め、「5、4、3……0!」のカウントダウンを心の中でするのも効果的です。「やる気はやっているうちに出てくる」とも言われます。まずは5分だけ、やってみる姿勢を大切にしましょう。
学習の進捗を見える化
「どれだけ進んだか」を見える化すると、やる気が高まります。チェックリスト、カレンダー、学習アプリなどを活用して記録を残しましょう。達成感が得られるうえ、復習や改善にも役立ちます。
1日の終わりには、「今日の勉強はどうだったか」を振り返る習慣をつけることも効果的です。反省点だけでなく、「これがよかった」というポジティブな視点も含めて記録することが、次のやる気につながります。時には先生や友人からのフィードバックももらいましょう。
どうしてもやる気が出ない時の対処法
スランプ
勉強にスランプはつきものです。模試の結果が悪く、勉強のやる気を失ってしまうこともあると思います。
大切なのは「なぜうまくいかなかったか」を冷静に分析すること。「この勉強方法では覚えられない」「次はこうしてみよう」と工夫を重ねる思考が、最終的な成功につながります。勉強は対策してもすぐに結果が得られるものではありません。テストの結果によってモチベーションを大きく左右されないために、自分の心の保ち方を模索してみましょう。

一休みしてリフレッシュする
どうしてもやる気が出ないときは、無理に続けず、一度離れることも選択肢の一つです。昼寝をしたり、温かい飲み物、好きな音楽など、気持ちを一新するための小さなリセット時間を取り入れてみてください。昼寝は15分が効果的だと言われています。
友人や家族との会話で気分を変える
勉強の悩みを言葉にするだけでも、頭の中が整理されます。
信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうことで、「また頑張ろう」という前向きな気持ちになれることもあります。孤独を感じる時には、友達と勉強するのももいいリフレッシュになります。友達がゴールに向かって頑張っている姿を見ることは、お互いにとって刺激になります。
まとめ
この記事を読んでくれた方は、やる気が出なくて悩んでいると思います。しかし、人それぞれ、やる気を出すためのきっかけとなる「ヒント」は必ずあります。今回紹介した中から、1つでも「これならやれそう」と思える方法を見つけて、まずは小さな挑戦から試してみてください。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。