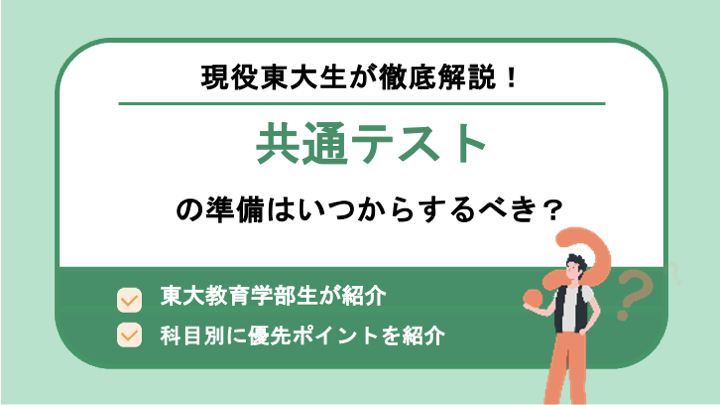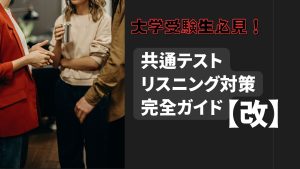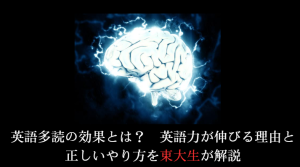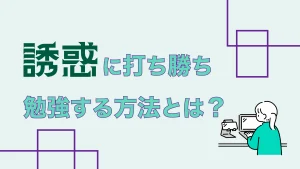日本中の多くの大学受験生の前に立ちはだかる壁、共通テスト。最近はセンター試験が共通テストになったり、さらに学習指導要領の改訂に伴い、科目が再編・追加されたり、変動の大きい試験です。
そんな共通テストの対策はいつから始めればいいのか、想像がつかずに困っている高校生も多いのではないでしょうか。今回は、現役東大生ライター碓氷明日香が、いつからどんな対策をすればいいのかを徹底解説します!
共通テストはどのような試験?
いつから対策するかを説明するまえに 、そもそも共通テストについてある程度知っておきましょう。ここでは、共通テストがどのような試験なのか、そして新課程になって何が変わったのかについて解説していきます。
試験の概要
共通テストとは、大学入試センターが毎年1月中旬の土日 (追試は下旬) に実施している試験です。高校生として身につけておくべき学力の到達度を問うテストとなっています。
共通テストは、国公立大学の一般選抜を受験する学生は必ず受験しなくてはなりません。そして共通テストの成績を踏まえつつ、各大学の二次試験に臨むのです。また、私立大学も「共通テスト利用方式」という受験方法を採用しているところが多く、いずれにせよ、ほとんどの学生が受けることになります。受験者数は毎年約50万人。その中で実力を発揮し、競い合わなくてはならないのです。
全問マークシート式で、記述問題は課されませんが、思考力や判断力が求められる問題が出題されます。
新課程で何が変わったのか
2025年度から、学習指導要領の改訂に伴い、新課程に対応した共通テストが始まりました。旧課程と新課程では何がどのように変わったのでしょうか。
まず、大きな変更点として、新科目「情報」が追加されました。これまでは受けられる限りの科目を受験した場合は900点満点だったのですが、1000点満点になったのです。もともと2日間ほぼ缶詰状態で 行われる試験でしたが、科目が増えることによって拘束時間が長くなり、さらなる集中力が問われるようになりました。
また、社会の科目が再編されたのも大きなポイントでしょう。以前は地理AB、世界史AB、日本史AB、現代社会という科目構成でしたが、地理歴史のくくりが「地理総合」「歴史総合」となり、現代社会がなくなって代わりに「公共」が加わりました。学習内容に大きな変更点はありませんが、科目選択の仕組みが若干煩雑になったので、確認が必要です。
他にも、数学ⅡBCの試験時間が、旧課程の数学ⅡBと比べて10分延長されて70分になったり、国語も10分追加で90分となったり 、細かな変更点はさまざま ありますが、求められる力に大きな変化はありません。これまでどおり 、資料読解や思考力が問われる問題が多く出題されています。
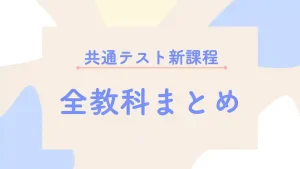
対策はいつから何をやればいい?
共通テストの概要を確認したところで 、本題に入っていきましょう。共通テストで失敗しないためには、対策はいつから何をやればいいのでしょうか。結論から言えば、効率よく安定した点数を取るためには、高3に上がったらすぐ、遅くとも夏ごろまでに基礎知識のインプットと試験の分析を始め、過去問や予想問題を使った演習は直前期の12月〜1月に行うことが必要です。
高3に上がったらすぐ始めるべきこと
高校3年生に進級したら、志望校に関わらず共通テストの問題を解くために必要な基礎知識を身につけ始めてください。基礎固めにはある程度時間がかかります。早く始めるに越したことはありません。遅くとも夏休みごろには始めましょう。内容としては、教科書や付属の問題集を演習するだけで十分です。
また、予備校などが行っている共通テスト模試に積極的に参加することをおすすめします 。そうすることで 、共通テストがどのような 試験なのか、時間配分はどうしたらいいのか、なんとなく想像がつくのです。「敵を知り己を知れば百戦危うからず」と兵法で言われているとおり 、共通テストの対策をするために、まずは共通テストについて詳しくなり、そして自分の現在地を知りましょう。
直前期にやるべきこと
12月の頭くらいから、過去問や予備校が出している予想問題パックなどを使って問題演習を始めます。やるべきはひたすらアウトプットです。
とにかく問題をたくさん こなして、詳しい時間配分や大問ごとの詳しい目標点数を決め、難化したとしても目標を達成できるくらい演習してください。共通テストはたまに異例の難化を見せる年がありますが、それに太刀打ちできるようにしておきましょう。
そして、過去問を時間を測って解いて、間違えた問題を分析してみてください。なぜ間違えたのか、単純に知識不足なのか、考え方が間違っていたのか、計算を間違ったのか、時間が足りなかったのか。原因はさまざま だと思いますが、ひとつひとつ分析して対処していくことで 、少しずつミスを減らし、点数を高めていくことができます。よく間違える単元は教科書や基礎問題集に立ち返って復習しましょう。そうして、点数を底上げしていくのです。
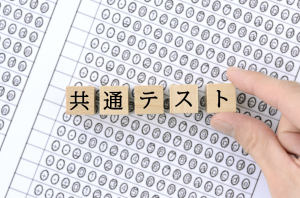
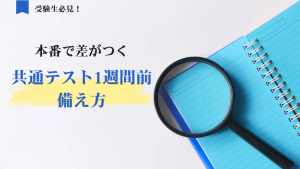
優先して対策すべき科目
共通テストは受験科目が多くて、何を優先的にやればいいかが悩みどころですよね。もちろん、まんべんなく対策は必要なのですが、特に対策に時間がかかる科目を挙げたいと思います。ここで挙げる2科目は3年生に上がってすぐのインプット段階からしっかり時間をかけて対策しましょう。それ以外の科目は、過去問を何年分も解くことで 、問題傾向を掴むことができるので、そこまで優先度は高くありません。
英語
まず、英語です。英語は伸びるのに時間がかかる科目なので、早くから対策が必要になります。また、総合的な英語力を上げておけば、共通テストで高得点が狙えるだけでなく、二次試験でも力を発揮できるという利点もあるのです。
共通テストの英語リーディングは、年々総合単語数が増加傾向にあります。つまり、これまでよりスピーディーに情報を正しく掴み取って、問題を解いていかなくてはなりません。英文の速読力は短期間で身につくものではないので、早いうちからたくさんの英文に触れておく必要があるのです。
また、リスニングのほうも 対策には時間がかかります。そもそもリスニング力を高めるのは一朝一夕ではできませんが、少しリスニング力に自信がある人でもこの共通テストの英語リスニングは要注意です。共通テスト型のリスニングはかなり特殊で、後半は問題文が1回しか読まれないうえ、高度な情報処理能力が求められます。リスニングに限って言えば、過去問や予想問題への着手も直前期まで待たず、夏休みくらいから始めてもいいかもしれません。
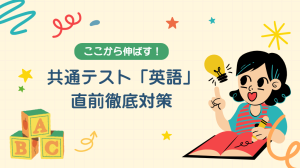
数学
次に、数学です。数学も英語同様、伸びるのに時間がかかる科目と言われています。
共通テストの数学は時間的にかなり厳しい試験です。すべて 解き終わるためには、どの問題も立ち止まらず、素早く解法までたどり着き 、正しく速く計算をして答えを出していかなくてはなりません。
そのため、普段の数学の勉強にも、時間を意識して取り組むようにしましょう。タイマーを使って、大問ひとつひとつ に時間制限を設けるのです。常に時間に追われながら問題を解く練習をしていれば、共通テスト型の問題を解くときも 焦ることはないはず。共通テスト専用の対策でなくても、共通テストを意識した勉強をするようにしましょう。
共通テストと二次対策どちらを優先すべき?
さて、共通テストの対策時期やその中身、優先順位について説明してきましたが、ここで高校生がよくぶつかる悩みについて、解説していきたいと思います。それは、「共通テストと二次対策のどちらを優先して対策すべきか」。この悩みに対する東大生なりの答えを、配点に着目して説明していきます。
共通テストの配点や足切りが高い場合
まず、共通テストの配点や足切りが高い学校を目指している場合についてです。結論から言うと 、12月の頭くらいから の直前期 (不安な人は11月中旬くらいからでも) は共通テスト対策に全振りすることをおすすめします 。一次試験である共通テストで失敗したら、元も子もありません。安定して点数が取れるようになるまで、しっかり共通テスト対策に取り組みましょう。国公立で共通テストの配点が高い場合に限らず、私立の共通テスト利用を活用する場合なども同様です。
共通テストが重視されない場合
一方、共通テストがあまり重視されない大学もあります。足切りさえ突破すれば、合否の判定には二次試験の点数しか使われないところも。そういう大学を受験する場合は、逆にほとんど共通テストの対策をする必要はありません。もちろん、足切りを突破できる点数は必要なので、そのあたりは模試の結果を分析してみてください。
みんなが焦って共通テストの対策に取り組んでいる時間を使って、二次試験のための勉強をしましょう。それが最も効率的です。
まとめ
共通テストの対策はいつから何をやればいいのか、どの科目を優先すべきか、そして二次試験対策との兼ね合いについてなど、詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
基礎が固まっていないと共通テストの問題には太刀打ちできません。直前期に安心して過去問を回せるように、早いうちから基礎固めに時間をかけておきましょう。努力が実り、春に桜が咲くことを願っています。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。