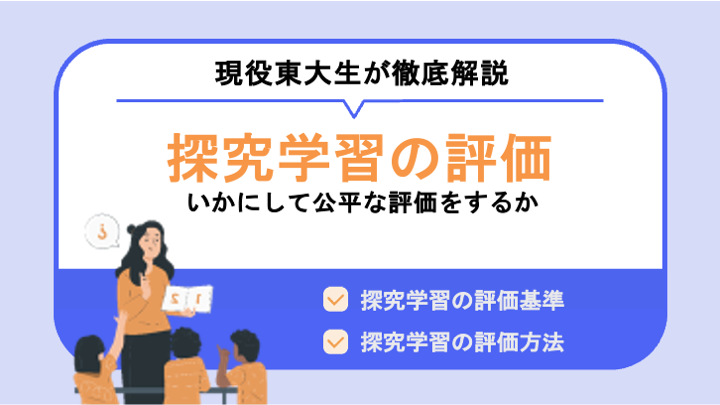2022年から施行されている高等学校学習指導要領においては「総合的な探究の時間」が必修科目に加わるなど、探究学習は年々注目度を増しています。生徒自らが問いを発掘し、周囲と協働しながら解決策を探していくという探究学習の手法は、現実社会と教育を接続させるものであり、生徒の個性を発揮できる場面でもあります。その反面、テストのようなもので数値的に評価することは非常に困難であり、その評価方法はよく検討されなければなりません。弊社では多くの学校で探究学習講座や探究学習に関わる講演会を行っております。この記事ではそういった活動の中で培った探究学習の評価方法について紹介します。
探究学習を評価する上で求められること
探究学習を評価する上では以下の3つのことが注意されるべきであると言われています。
公平であること
いかなる教科においても共通することではありますが、評価においては公平・公正であることが求められます。特に上で述べた探究学習の特性から、探究学習の評価においては教科学習よりも公平性を保つことが簡単ではありません。そのため探究学習で生徒を評価する上では評価の基準や方法、観点を明確にすることが求められます。
基準を作成する際には、評価者が変わっても同様に評価できるものであるかどうかを確認することがポイントです。
あらゆる観点を取り入れること
探究学習を評価する際は、単に1つの成果物のみで評価するのではなく、そこに至るまでの議論のやり方や情報収集の手法、発表の工夫など、多くの観点を取り入れることが求められます。こうすることにより、生徒の探究学習の過程を包括的に評価することができます。
また必ずしも教員のみが評価するのではなく、クラスメイトや保護者、第三者などを交えることによりさらに多面的な評価を実施することができます。第三者の評価を交えるためにコンテストなどにエントリーすることも有効です。
評価のタイミングを複数設けること
探究学習を実施する際は定期的に評価タイミングを設けることがおすすめです。問いを立て終わったタイミング、仮説を立て終わったタイミングなど、各段階においてフィードバックなどを行える環境を作りましょう。あらゆる観点を取り入れることにも繋がります。
探究学習を評価する際の基準
評価の手法の前に、何を評価の基準とするべきであるかを紹介します。
探究学習の目標を参考にする
評価基準を決める際には探究学習の目標を参考にする必要があります。
高等学校の学習指導要領によると探究学習の目標は基本的に学校が決めることとなっています。そしてその目標を決めるための全体の目標が学習指導要領に記載されています。
探究の見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して,自己の在り方生き方を考えな
がら,よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 探究の過程において,課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け,課題に関わる概念を形成
し,探究の意義や価値を理解するようにする。
(2) 実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし,自分で課題を立て,情報を集め,整理・分析
して,まとめ・表現することができるようにする。
(3) 探究に主体的・協働的に取り組むとともに,互いのよさを生かしながら,新たな価値を創造し,より
よい社会を実現しようとする態度を養う。
(文部科学省・学習指導要領)
これを踏まえて決めた目標を元に基準を作成するのが良いでしょう。
目標から基準を作成する
上で決めた目標を評価基準に落とし込む際には、分解の手法を取り入れます。具体的には以下のステップを用います。
①「○○な生徒」など抽象的な目指したいイメージ(理想像)を定義する
②そのイメージに近づくために必要な非認知能力(構成要素)を3つほど定義する
③さらに誰から見ても非認知能力の変化が分かる行動指針を定める
これにより、子どもたちの理想像を細かく具体化した行動指針をアセスメント項目として設定することで、根拠のある探究学習の評価ができるようになるのです。
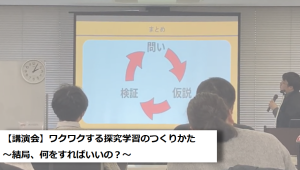
具体的な評価基準の例
上の方法から考えた評価基準の例としては以下のようなものが考えられます。
・必要な調査をどの程度行なったか(特に自身の計画で盛り込まれていたもの)
・クラスメイトとの議論において自分の意見を述べることができたか
・自分で問いを立てることができたか。また問い立てのプロセスを学ぶことができたかどうか
・問いに対して適切に情報収集することができたかどうか
その他、探究学習の各過程に対応して評価基準を設けることが適切です。
評価の手法を紹介
1, ポートフォリオ評価
探究学習でよく用いられるのがこのポートフォリオ評価の手法です。探究学習の過程で作成したものや調査したこと、集めた資料などを生徒自身が適切にまとめ、それを元に評価します。一年を通した探究活動の中でこういったポートフォリオを作成していくのですが、その形式や評価基準については、学習が進むにしたがって生徒と先生が話し合って決めていく「基準創出型」や、先生が事前に評価基準やポートフォリオの形式を決める「基準準拠型」などがあります。
ポートフォリオを作成することによって、先生は生徒の現在の進度状況を把握することができる上、生徒にとってもポートフォリオを試行錯誤して作成する中で、自身の学習を振り返る機会が与えられ、成長を促すことができるというメリットがあります。一方で点数化することは難しいというデメリットがあります。
2, ルーブリック評価
ルーブリック評価とは、生徒が作成した成果物や発表などをルーブリック表を用いて評価します。ポートフォリオ評価の具体的手法として用いることができるでしょう。
ルーブリック表では、まず評価基準が設けられます。その後各評価基準にしたがって1〜5のような点数が設定されます。そして評価対象の成果物(パフォーマンス)を見て各評価基準に対して1〜5の点数をつけていきます。
ルーブリック評価においては1〜5の点数のそれぞれに対し、文章が付されており、なんとなくの基準ではなくその文章に合わせて段階を決めることになっています。たとえば1点には「テーマと主張があっていない」と説明があり、3点には「テーマにあった主張をしているが、引用する資料が適切でない」、5点には「テーマにあった主張で資料を適切に活用している」などといった、各点数に合わせた説明が付されています。こうすることで生徒は自身の不足している部分を知ることができる上、先生はある程度公平な基準で数値化することができます。ただし、生徒の受け取り方によっては単なるチェックリストにしかならず、ここを改善しよう、という方向性の考え方にならない可能性があるので、気を付ける必要があります。
3, リフレクション
リフレクションとは自己評価のことです。探究活動の後にやったことや学んだこと、気づいたことなどを生徒自身が記述します。振り返ることにより、生徒自身が新たな気づきを得たり、自身の活動を俯瞰して観察できるようになります。
自己評価をそのまま生徒の成績の評価へと結びつけることは難しいですが、このリフレクションの活動を先ほどのルーブリック評価の手法を用いて評価することは可能でしょう。
4, ピア評価
ピア評価とは、生徒同士で評価をする手法です。探究学習においてはディスカッションなど、生徒同士が連携して活動を行う機会が多いです。そのような中で相手の良さや改善点などを見つけることは、自分自身を見つめ直すことにも繋がります。また先生が気づかないような良さを吸い上げることもできます。
ピア評価もリフレクションと同様、成績評価に含めることはあまり現実的でありませんが、ピア評価の記録を確認して生徒の見方や観点などを改めるといった形で活用することは可能です。
ピア評価においては評価基準を明確にし、評価された人が傷つかないようにする配慮が求められます。また逆に気を遣って無難な評価しかしなくなることも防止しましょう。
5, 第三者による評価
先生や生徒の関係のなかでは、どうしても「固定概念」や「こういう人だ」という前提に囚われてしまうことも考えられます。また評価基準の固定化や、潜在的な良さを発見できないという可能性もあります。そのようなことを解消する手段として、第三者による評価が勧められます。たとえばコンテストや大会に出て学校外の大人に評価してもらったり、外部講師に依頼してみたり、学校長などにアドバイスをもらったりなどが考えられます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。数値化や評価が難しい探究学習においても、様々な評価基準が考案されています。評価をする上で求められることを踏まえて、生徒にとって意味のある評価を行っていくべきであります。ぜひ評価基準を定めるところから、この記事を踏まえて実践してみてください。ありがとうございました。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。