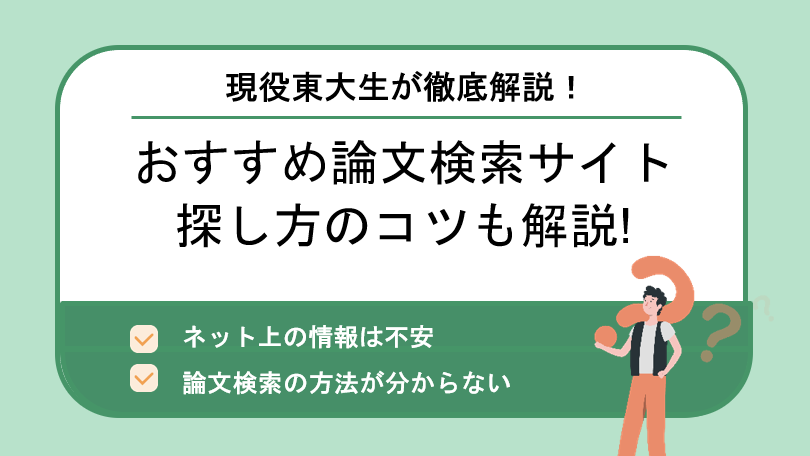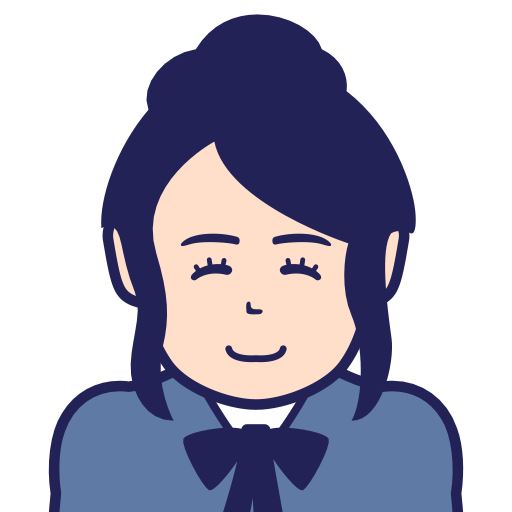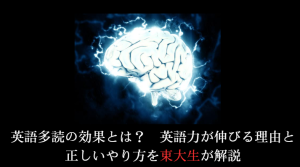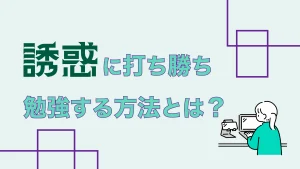皆さんは、論文を読んだことがありますか?
レポートを書くときや、自ら問いを立てて答えを探す探求学習に取り組んでいると、専門的な情報が必要なことが多いと思います。教科書には書かれていないけれど、ネット上の情報をうのみにするのは不安。そこで論文を読もうと思っても、そもそも探し方がわからない! そんな人も多いのではないでしょうか。
かくいう筆者も最初からぴったりの論文を探せたわけではありません。しかし試行錯誤を重ね、今では信頼性の高い論文を効率的に探し出せるようになったのです。本記事では、そんな筆者が探究学習で論文を読むことの重要性から、高校生でも無料で使えるおすすめの論文検索サイト、さらには論文を探す際の具体的なコツや、情報の信頼性を見極めるためのチェックポイントまで、詳しく解説していきます。
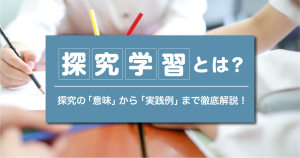

【無料】高校生におすすめの論文検索サイト4選
専門的な論文を探すというと難しく聞こえるかもしれませんが、実は高校生の皆さんでも無料で利用できる便利なサイトが数多く存在します。ここでは、特におすすめの4つの論文検索サイトをご紹介します。
日本語論文ならこれ! CiNii Articles(サイニィ アーティクルズ)
まず一つ目は、日本の学術論文を探すならまず活用したい「CiNii Articles (サイニィ アーティクルズ)」です。
これは国立情報学研究所が運営する、日本国内の学術論文情報を網羅したデータベースです。人文科学から社会科学、自然科学まで、非常に幅広い分野の論文が収録されており、日本語で論文を探したい場合に特に力を発揮します。多くの場合、論文の要旨を無料で読むことができ、全文が公開されているものも少なくありません。
最先端の論文は英語で書かれているものが多いですが、発行されてから時間のたったものは日本語版で出版されていたり、初学者向けに簡単に書き直されていたりします。いきなり論文を読むのは大変かもしれない、と感じる人はまずはCiNii Articlesを使って論文を探してみましょう。
理系には必須! J-STAGE (ジェイ・ステージ)
二つ目は、科学技術分野に強い「J-STAGE (ジェイ・ステージ)」です。
これは科学技術振興機構が運営するプラットフォームで、特に理系の探求学習に取り組む皆さんには心強い存在となるでしょう。医学、工学、農学といった分野の学術雑誌に掲載された論文が多数公開されており、その多くが本文まで無料で閲覧可能です。日本の最先端の研究成果に触れることができます。こちらもCiNii Articlesと同様に日本語論文が多いことも嬉しいポイントです。
(参考:https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja)
まるでGoogle検索! Google Scholar (グーグル スカラー)
三つ目は、世界中の論文を検索できる「Google Scholar (グーグル スカラー)」です。
普段使っているGoogle検索と同じような感覚で、学術的な情報に絞って検索できるのが大きな特徴です。特別な操作もいらないのでとても使いやすく、心理的ハードルが低いのが嬉しいポイントです。
あらゆる分野の論文や学術誌、書籍などを横断的に探すことができ、海外の研究動向を調べる際にも非常に役立ちます。ただし、査読を受けていない研究報告なども含まれる場合があるため、見つけた情報の信頼性には注意が必要です。
またGoogle Scholar上にある論文のほとんどが英語論文であることにも注意が必要です。今はDeepLやGoogle翻訳など便利なツールがたくさんあるので、必要に応じてそれらを利用しながら読み進めましょう。
(参考:https://scholar.google.com/)
情報が必要な時はこれ 国立国会図書館サーチ (NDL Search)
四つ目は、論文に限らず幅広い情報を探せる「国立国会図書館サーチ (NDL Search)」です。
日本の国立国会図書館が所蔵する膨大な資料を一度に検索できるサービスで、論文はもちろん、関連する書籍や雑誌記事、博士論文なども見つけることができます。探求テーマに関する全体像を掴みたい時や、多角的な情報を集めたい時に活用すると良いでしょう。
こちらも査読を受けていない論文が多く含まれるため、それぞれの情報源が信頼できるかどうかは確かめなければなりません。しかしいろいろな媒体が閲覧できる分、自分の知識レベルにあった情報が手に入りやすいため、ぜひ有効活用してみてください。
(参考:https://ndlsearch.ndl.go.jp/)
初心者でも簡単!論文検索3つのコツ
膨大な論文の中から、自分の探求テーマにぴったりのものを見つけ出すには、少し工夫が必要です。なんとなく検索をかけていても、なかなか自分のほしい情報に巡り会えず、心が折れてしまいそうになるかもしれません。
ここでは、論文検索に慣れていない初心者でも簡単に実践できる3つのコツをお伝えします。
大事なのは「キーワード」
一つ目のコツは、キーワードを工夫することです。例えば「環境問題」という大きなテーマだけでは、あまりに多くの論文がヒットしてしまいます。「環境問題 プラスチック 海洋」のように、複数の単語を組み合わせて検索範囲を絞り込んでみましょう。また、「プラスチック」を「マイクロプラスチック」と言い換えたり、「ゴミ」を「廃棄物」という専門的な言葉で検索したりと、類義語や関連語を試すことで、思わぬ発見があるかもしれません。
絞り込むキーワードがわからないときは、普通に検索をかけてみて関連ワードとしてどのようなワードが提案されるかを参考にするのも良いかもしれません。いくつかの論文検索サイトで同時に検索するのも効果的な方法です。
まずは要旨だけ読んでみる
二つ目のコツは、「アブストラクト(要旨)」をまず読むことです。アブストラクトとは、その論文が「どのような背景で」「何を目的とし」「どういう方法で研究し」「何が明らかになったのか」を簡潔にまとめた文章です。日本語で書かれたものであれば3分もかからず読み終わることができるでしょう。
検索で気になる論文を見つけたら、まずはこのアブストラクトに目を通しましょう。全文を時間をかけて読む前に、自分の知りたい内容と合っているかを効率的に判断できます。何本かアブストラクトを読んだあとに本文を詳しく読む論文を決定すると、自分のほしい情報にいち早くたどり着くことができます。
絞り込み機能を使いこなそう
三つ目のコツは、絞り込み機能を使いこなすことです。ほとんどの論文検索サイトには、検索結果をさらに絞り込むための機能が備わっています。例えば、発表された年で絞り込んで最新の研究動向を追ったり、特定の著者名で検索したり、研究分野を指定したりすることが可能です。これらの機能をうまく活用することで、より精度の高い情報収集が実現します。
はじめは難しいかもしれませんが、「地球の温暖化問題を知るためにここ20年に絞ろう」「この本の著者はどんな論文を出しているのだろう」などさまざまな観点から絞ることができます。こういった絞り込みを検討することで、埋もれていた論文に出会うことができます。
その論文、本当に信用できる? 信頼性を見極める4つのチェックポイント
論文は信頼性が高いですが、その中でも特に質の高い、自分の探求学習の根拠として安心して使える論文を見極める視点を持つことが大切です。ここでは、論文の信頼性を判断するための4つのチェックポイントを紹介します。
査読を受けているか
第一に、その論文が「査読(さどく)」を受けているかを確認しましょう。
査読とは、同じ分野の専門家たちが、掲載前にその論文の内容を厳しく審査する制度です。査読を経た論文は、客観性や学術的な価値が担保されていると言えます。論文が掲載されている雑誌が「学術雑誌」や「紀要」であれば、多くは査読を受けています。学術雑誌の名前で検索すると、査読後に掲載されるものなのかどうか判断できます。
査読がないなら全てうそだ! というわけではありませんが、わかりやすい指標の一つとしてぜひ参考にしてみてください。
誰が書いているか
第二に、どこに所属しているどんな人が書いたかも重要な手がかりです。
著者がその分野の専門家であるか、大学や公的な研究機関に所属しているかを確認することで、その研究の背景にある専門性を推し量ることができます。ある研究室で書かれた論文であれば、どの教授のもとで書かれた論文なのかも大事な指標です。時に全く専門外の人が書いた論文も存在しているので、注意して見てみてください。
いつ出版されたか
第三に、いつ(発行年)発表されたかをチェックすることも忘れてはなりません。
科学技術の分野など、情報の鮮度が重要なテーマでは、できるだけ新しい論文を参照することが望ましいです。しかし新しければ新しいほどいいというわけでなく、歴史的な事柄を扱う場合は、古い論文が基礎的な文献として価値を持つこともあります。
自分の興味のあるテーマにはいつ出版された論文を使うことが望ましいのか、考えてみてください。
どのくらい影響力があるか
第四に、その論文がどれくらい影響力があるかも調べてみてください。その際に参考になるのが、どのくらい引用されているかという数です。引用とは、他の論文で参考文献として参照されることです。多くの研究者から引用されている論文は、その分野において重要性が高く、影響力のある研究だと考えられます。Google Scholarなどでは、被引用数を確認できる場合があります。
同様に、インパクト・ファクター(IF)を調べることもできます。これは論文が掲載されている雑誌やジャーナルがどの程度影響力があるかを数値で表したもので、数値が大きければ大きいほど影響も大きいとされています。この数値の算出には、論文がどのくらい引用されたかも含まれているのである程度信頼性の高い指標だと言えるでしょう。
まとめ:論文を味方につけて、探究学習を成功させよう!
探求学習において、信頼性の高い「論文」という情報源を使いこなすことは、学習の質を飛躍的に高めることにつながります。今回ご紹介した論文検索サイトや検索のコツ、そして信頼性を見極めるポイントを活用すれば、皆さんの探求はより深く、より説得力のあるものになること間違いありません。
最初は専門用語の多さなどに戸惑うかもしれませんが、論文を読む経験を重ねるうちに、論理的な文章構成やデータの示し方など、多くのことを学べるでしょう。その力は、大学での研究や社会に出てからの課題解決の場面でも必ず役立ちます。論文を力強い味方につけて、皆さんの探究学習を実りあるものにしてください。
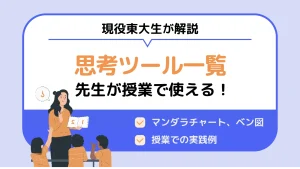
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。