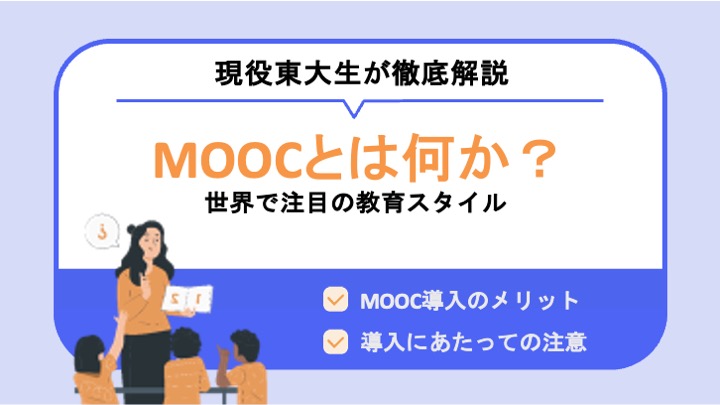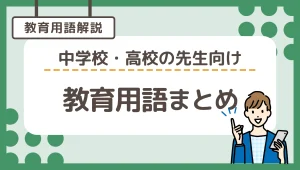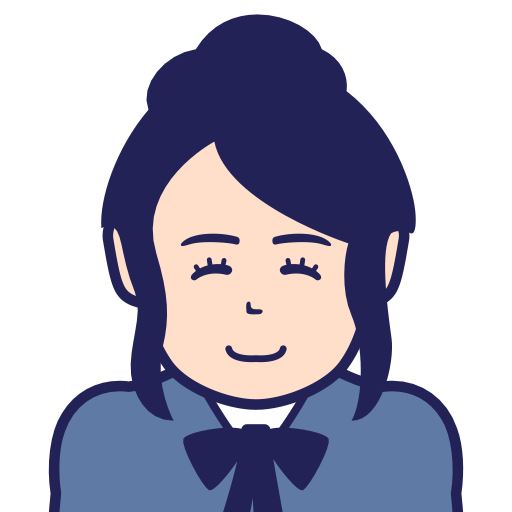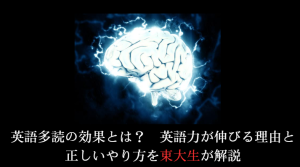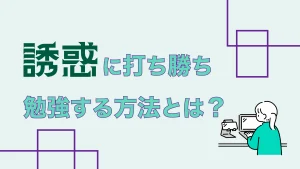変化の激しい現代社会において、高校教育に求められる役割はますます複雑化、多様化しています。2022年度から施行された新学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学び」の実現や、本格化する大学入試改革への対応、そしてGIGAスクール構想によって整備されたデジタル環境の活用など、先生方が日々向き合われている課題は多岐にわたることでしょう。特に、生徒一人ひとりの興味や関心、進路希望に寄り添った「個別最適な学び」をいかにして提供するかは、多くの教育現場における共通のテーマではないでしょうか。
このような状況の中、教育の可能性を飛躍的に広げるツールとして世界的に注目を集めているのが「MOOC(ムーク)」です。MOOCは、単なるオンライン学習サービスではなく、世界中の「知」への扉を開き、生徒の探究心に火をつける強力な起爆剤となり得る存在です。
本記事では、このMOOCとは一体何なのか、その基本的な概念から、高校教育の現場で具体的にどう活用できるのか、導入におけるメリットや注意点、そして実践的な導入ステップまでを、余すところなく詳細に解説していきます。
MOOCとは何か?
MOOCとは、Massive Open Online Coursesの頭文字を取った略称であり、日本語では「大規模公開オンライン講座」と訳されます。
- Massive(大規模な):数万人規模の受講者が共に学ぶ
- Open(公開された):誰でも原則無料で参加できる
- Online(オンライン):時間や場所を選ばずに学べる
- Courses(講座):課題やテストを含む体系的な講座
このように、世界中の質の高い講座が誰にでも開かれているのが特徴です。
このMOOCというムーブメントは、2012年ごろにアメリカのスタンフォード大学やマサチューセッツ工科大学(MIT)などのトップ大学が先導する形で始まり、瞬く間に世界中へと広がりました。その背景には、高速で大容量のデータ通信が可能なブロードバンドインターネットの普及という技術的基盤と、高等教育の機会をより多くの人々に提供したいという「教育の民主化」への強い思いがあったのです。
高校教育におけるMOOC活用の3大メリット
それでは、このMOOCを実際の高校教育の現場に取り入れることで、具体的にどのようなメリットが生まれるのでしょうか。ここでは、進路指導、探究学習、そして教員の自己研鑽という3つの側面から、その価値を深掘りします。
将来の選択肢の幅が広がる
第一に、進路指導やキャリア教育の質を劇的に転換させる可能性を秘めています。
多くの高校生にとって、大学や学部の選択は、パンフレットの言葉やオープンキャンパスでの短い体験だけで判断せざるを得ないのが実情です。しかしMOOCを活用すれば、生徒は興味のある学問分野の入門講座を、大学の正規課程に近い形で体験できます。
たとえば、漠然と「経済学に興味がある」という生徒が、実際に大学レベルのミクロ経済学の講座を受講することで、その学問の面白さや難しさ、求められる思考法を肌で感じられます。これにより、「思っていたものと違った」という入学後のミスマッチを防ぐだけでなく、今まで知らなかった新たな学問分野に興味を抱くきっかけにもなり得ます。
近年では、総合型選抜や学校推薦型選抜において、MOOCの受講を出願要件の一つとする大学も出てきており、大学での学びといかに直結しているかが分かります。
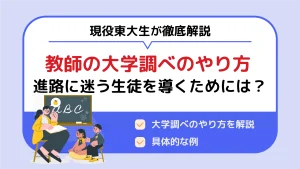
探究学習のサポート
第二に、探究学習の強力なサポーターとしての役割が期待できます。
生徒たちが自ら問いを立て、情報を収集・分析し、表現する探究学習は、思考力や判断力を育む上で非常に重要です。しかし、生徒の興味関心が専門的・先進的であるほど、学校の図書館や教員が持つ知識だけではサポートしきれない場面も増えてきます。
ここでMOOCが、信頼性の高い専門知識を提供する外部リソースとして機能します。例えば、「地域活性化におけるアートプロジェクトの役割」を探究する生徒が、都市社会学やアートマネジメントの講座を参考にしたり、「機械学習の倫理的課題」をテーマにする生徒が、AI倫理に関する最新の議論を学んだりすることが可能です。
探究学習において、適切なフィードバックを生徒一人ひとりに行いたいけれど、全員分は時間が取れないという悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。MOOCを効果的に使用することで、生徒の探究を単なる「調べ学習」で終わらせず、学術的な深みと客観的根拠を持った、質の高い知的生産活動へと昇華させるための羅針盤となるのです。
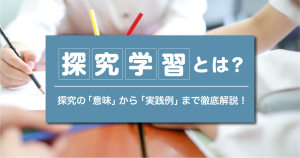
教師自身を助けてくれる
第三に、教員自身の専門性向上と学び直しのツールとしても非常に有効です。
先生方ご自身の担当教科に関する最新の研究動向や、反転授業、アクティブラーニングといった新しい教育手法に関する講座を、多忙な業務の合間を縫って学ぶことができます。部活動の指導があって放課後にあるセミナーに参加ができなくても、オンデマンド形式のMOOCを利用すれば効率よく最先端の知識を得ることができます。また、MOOCは開講科目の幅がとても広いため異分野の知識を吸収することで、教科横断的な視点を持った授業を展開するヒントを得ることもできるでしょう。
これは、先生方自身の知的好奇心を満たすだけでなく、結果として日々の授業の質を高め、生徒たちへ豊かに還元されていきます。効率的な自己研鑽は、教育の質向上と働き方改革を両立させる上でも重要な鍵となります。
導入の際の注意点とそれを乗りこえる工夫
MOOCが持つ大きな可能性の一方で、その導入と運用を成功させるためには、いくつかの課題や注意点を理解し、対策を講じておく必要があります。
英語の講義が多い
最も大きなハードルの一つが「言語の壁」です。日本の大学や会社が公開している授業はほとんど日本語が使われています。しかしMITやハーバード大学など、世界のトップ大学が提供する質の高い講座の多くは英語で行われています。もちろん、これはグローバル社会で活躍するために必要な英語力や異文化理解を深める絶好の機会と捉えることもできます。しかし、誰でもいきなり英語の講義を受講するのはハードルが高いでしょう。
対策としては、まずは日本語字幕が提供されている講座から始める、ブラウザーの翻訳機能を活用する、といった方法が考えられます。最近ではAIを用いて文字起こしを行ってくれるツールもあります。
また、生徒におすすめする際には、英語科の授業と連携し、英語学習の一環としてMOOCの一部を活用するといったアプローチも有効です。英語の勉強に加えて自分の欲しい知識も得られるとしたら一石二鳥で効率のいい勉強方法です。
モチベーションを保ちづらい
次に、モチベーションの維持という課題があります。MOOCは受講が任意であり、強制力がないため、特に生徒においては学習を最後までやり遂げる「修了率」が一般的に低い傾向にあることが知られています。
この課題を乗り越えるためには、生徒の自主性に任せきりにするのではなく、教員による適切な「伴走支援」が不可欠です。例えば、クラス内で同じ講座を受講するグループを作り、進捗を報告し合ったり、ディスカッションの時間を設けたりすることで、孤独感を和らげ、協働的な学びに繋げることができます。教員が定期的に進捗を確認し、「あの講座の○○は面白かったね」といった声かけをするだけでも、生徒の学習意欲は大きく変わるはずです。
先生自身が受講する際は、あらかじめスケジュールを立てておくことをおすすめします。毎日の業務に追われてなかなか時間が取れなくても、「今週中に2本受講しよう」などのルールを設定しておくことで間延びすることを防げます。
種類が豊富すぎる
さらに、「情報の質の担保」と「評価の難しさ」も考慮すべき点です。誰でも講座を開設できるプラットフォームも存在する中、教育現場で活用する上では、信頼できる提供元を見極める必要があります。後述するCoursera(コーセラ)やedX(エデックス)、そして日本のJMOOC(ジェイムーク)といった、有名大学や企業が講座を提供している主要なプラットフォームを選べば、質の面で大きな問題はないでしょう。
また、MOOCでの学びをどのように学校の成績評価に反映させるかという点も課題です。現状では、直ちに単位として認定することは難しいかもしれませんが、探究活動の評価に加点したり、ポートフォリオの重要な要素として認めたりするなど、生徒の主体的な学びを正当に評価する仕組みを校内で検討していくことが望まれます。
代表的なプラットフォーム
近年MOOCの人気が上がっていることを受け、たくさんの講義が公開されています。そのうち信頼性の高いものやよく使用されるプラットフォームを3つご紹介します。
JMOOC (Japan Massive Open Online Courses / ジェイムーク)
日本の大学や企業が連携して日本語の講座を提供する、国内最大のMOOCプラットフォームです。東京大学の「gacco(ガッコ)」や放送大学の「OUJ MOOC」などが参加しており、言語の壁がなく、最も始めやすい選択肢と言えます。歴史、文学、科学技術からビジネススキルまで、多彩な講座が揃っています。
全講座無料なのも嬉しいポイントです。さらに講義によっては対面授業を行なっていたり、修了証を発行しているところもあります。生徒には推薦入試の一助として、先生には自分のキャリアアップの材料として利用しやすいのではないでしょうか。
(参考:JMOOC, https://www.jmooc.jp/)
Coursera (コーセラ)
スタンフォード大学の教授によって設立された、世界最大級のMOOCプラットフォームです。スタンフォード大学、プリンストン大学をはじめとする世界中のトップ大学や、Google、IBMといった企業が講座を提供しています。多くは英語ですが、一部の講座では日本語字幕も利用可能です。
GoogleなどがDegree(学位)を発行している講座も多くあります。正式な学位とは異なりますが、毎日の業務の合間にリスキリングとして新しい資格をとることも可能です。
(参考:Coursera, https://www.coursera.org/)
edX (エデックス)
ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学(MIT)によって設立された、非営利のMOOCプラットフォームです。こちらも世界トップレベルの大学が多数参加しており、特に理工系の講座が充実していることで知られています。質の高い学びを求める生徒にとって、挑戦しがいのあるプラットフォームです。
(参考:edX, https://www.edx.org/)
まとめ
MOOCは、もはや単なるオンライン教材の一つではありません。それは、生徒一人ひとりの知的好奇心と、世界中の最先端の「知」を直接結びつけるための架け橋です。適切に活用すれば、進路指導の質を高め、探究学習を深化させ、生徒の主体的な学習意欲を飛躍的に向上させることができます。GIGAスクール構想で整備されたデジタル端末は、まさにこのMOOCという広大な知の海へ乗り出すための船です。
もちろん、導入には言語の壁やモチベーション維持といった課題も伴いますが、それらを乗り越える工夫と教員の伴走支援があれば、その教育効果は計り知れません。MOOCは、画一的な教育から、生徒一人ひとりが自らの興味関心に基づいて学びをデザインしていく「個別最適な学び」を実現するための、極めて強力なツールとなり得ます。
この記事を読んでくださった先生方が、未来の教育を創造する新たな選択肢としてMOOCに可能性を感じていただけたなら幸いです。まずは先生ご自身が、JMOOCのウェブサイトを訪れ、知の冒険への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。そこから、あなたの教室、そして学校全体の学びに、新しい風が吹き込むはずです。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。