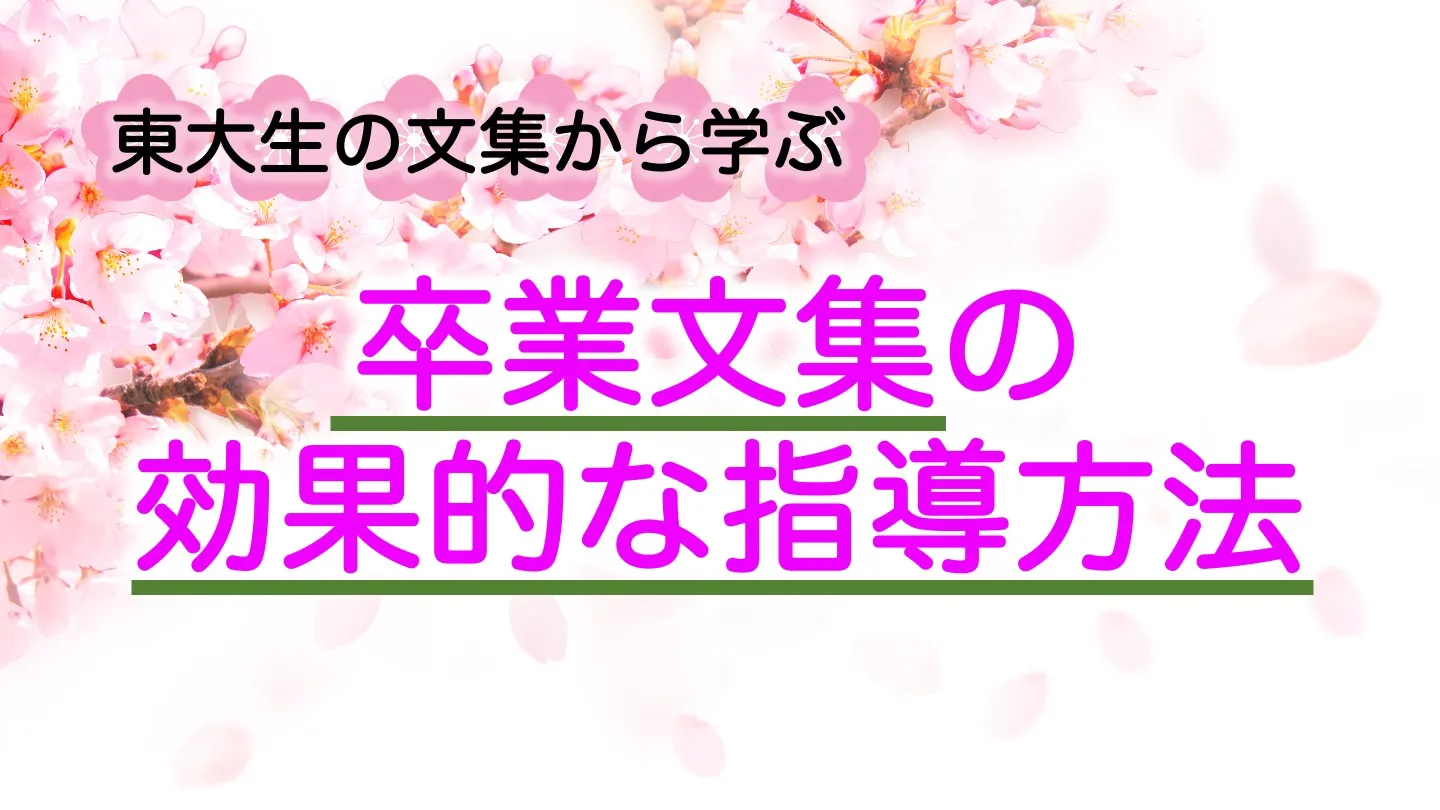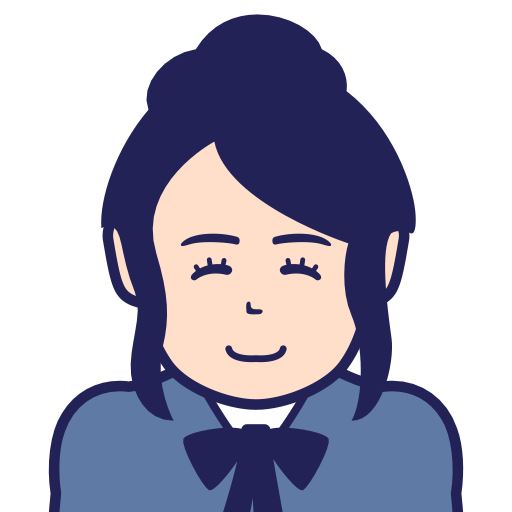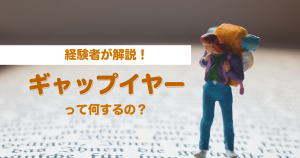卒業式が近づくと同時にやってくるのが卒業文集。生徒の六年間の集大成としていい作文をしてほしいと思いつつ、気がついたらみんな修学旅行のことを書いていてどうしたらいいのかわからない…と悩むこともあるのではないでしょうか。
今回は一人ひとりの個性が出る卒業文集の指導方法を解説していきます。東大生が小学生の頃に実際に書いていた卒業文集も載せているのでぜひ参考にしてみてくださいね。
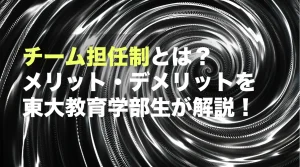
なんのために卒業文集を書くのか?
卒業文集の作成を始める前に、先生自身も児童もなんのために卒業文集を書くのかを正しく理解しておく必要があります。児童の中には作文が苦手な子も多く、できればやりたくないと思っている子も多いかもしれません。そのため、卒業文集の作成を通してのめあてをきちんと設定し、共有することが大切なのです。
成長した姿を残す
卒業文集はその学校で学んだことをまとめる集大成の作文です。小学校なら6年間、自分が学んできたことや感じたことをまとめるものです。卒業文集は6年生の最後に作成することから、ついつい印象的な修学旅行や運動会を題材に選んでしまいがちです。その子にとってそれが最も楽しかった・成長できた物事なら構わないのですが、それだけに偏らないようにしたいものです。
また普段の学習の様子を全て把握することはできない保護者にとっても、卒業文集は非常に楽しみなものです。自分の子は何を感じ、どのように成長したのかを卒業文集を通じて知りたいと思っている保護者はとても多いと思います。
児童個人のためにも、保護者のためにも、個性あふれる魅力的な卒業文集を作成したいですね。
卒業文集は一生残る
また卒業文集は一生ものです。小学校時代の作文や作品は残していないという人でも、卒業文集だけは残しているという人が多いのではないでしょうか。同窓会などでも卒業文集は話題にあがりますよね。
また少し検索すると大谷翔平選手や羽生結弦氏の卒業文集が出てくるように、有名人になって注目されるのも卒業文集です。それを伝えると児童もやる気になってくれること間違いなしです。

個性あふれる文集作りのための授業
ここからは日々の授業から実践できる、卒業文集作成に向けた授業を紹介していきます。
普段の国語の授業から作文の指導を
読み応えのある作文をするには、基本的な作文の手法を理解しておく必要があります。文章は「はじめ」「なか」「おわり」の三つのパートに分かれますが、細かく分けると頭括型と尾括型の文章など、さまざまな形式の文章があります。はじめは理解が難しくても、授業で取り上げる文章について毎回構造を確認すると、だんだんと児童も慣れて理解してくれます。
行事ごとに作文を行う
卒業文集でテーマが偏るのを避けるためには、各行事ごとに作文を行うのも効果的です。林間学校や修学旅行、運動会や文化発表会など大きなイベントがあった後には国語の授業などで作文をするようにしましょう。授業で習った作文の手法を練習できる上に、卒業文集作りの際には今までの作文を参考に書くことができます。卒業文集で取り上げなかったとしても、学年末には自分だけの卒業文集になっています。
テーマ決めの指導のコツ
卒業文集で最も重要と言っても過言ではないのが、テーマ決めです。
全員のテーマが「将来の夢」「印象に残った出来事」などと決まっている場合もありますが、その中にもテーマはさまざま。全員のテーマが似たり寄ったりにならないよう、テーマ決めも工夫して指導する必要があります。
テーマの候補
印象に残った出来事をテーマに作成する場合でも意外とテーマは偏りがちなものです。直前にあった行事である修学旅行や6年生の運動会など、その行事が最も楽しかったのならばいいのですが、もっと日常で起こった出来事や友人との思い出にも目を向けてほしいですよね。テーマの偏りを避けるためにもまずはいくつか具体例を提示するのが効果的です。
テーマ例
・将来の夢
・運動会での組体操
・友人との思い出
・小学校生活を振り返って
・壁にぶつかったこと
出来事に絞る場合
例えば「運動会」というテーマで作文を書こうとすると、「はじめに大玉転がしをして、その次に準備係の仕事をして、最後にリレーがあって…」といった箇条書きの文章になってしまいがちです。それでは各出来事に対する心情の変化を書くことができず、説明文のようになってしまいます。
それを避けるためにもまずは自分が決めたテーマの要素を書き出してもらいましょう。その上で特に書きたいテーマを一つ選び、深ぼりするように指導すると、心情の変化や感情が現れる文章になります。
将来の夢に絞る場合
何か打ち込んでいることがある人や、将来の夢がはっきりしている児童はこのテーマを書いてもらうのがいいでしょう。サッカー選手や野球選手、医者など、はっきりとイメージしやすい職業は書きやすいでしょう。大谷翔平選手や三苫薫選手など、実際に活躍している選手の卒業文集をプリントアウトして配布するとさらにイメージがつかみやすくなるかもしれません。
将来の夢がはっきりしていない児童には、将来の職業ではなく、将来なりたい姿を想像して書いてもらいましょう。自分は何か新しいものを作りたいのか、誰かを助ける仕事がしたいのか、家族を持ちたいのか。解像度は低くてもその子がわくわくすると感じるものを書いてもらいましょう。
東大生が実際に書いていた卒業文集
ここからはカルペ・ディエムに所属している東大生・早稲田生を中心に実際に書いていた卒業文集を聞いてみました!
将来の夢:検察官
当時とても人気のあった「HERO」というドラマの影響から、検察官になりたいと書いた東大生がとても多かったです。硬い文体で背伸びをした書き方をしていて、今読むとむずがゆくなるとのことですが、当時からさまざまな文章に触れていたのですね。
また布施川天馬講師も同じく検察官になりたいと書いていました。卒業文集の全文をいただいたので、ぜひ参考にしてください。
将来の夢:ディズニーキャスト
女性に多かったのはディズニーキャストになりたいというものでした。ディズニープリンセスに憧れたのかな?と思いきや、
「ディズニーキャストになりたい。この世の仕事は今後AIやコンピューターに奪われる。でもディズニーランドは、キャストのおもてなしや温かさ込みでテーマパークとしての魅力であり、ディズニーキャストは今後も代替不能な人力の仕事として残り続けるだろう。だから私は夢を与えるディズニーキャストになりたい。」
と書いていたそうです。当時の楽しかった思い出が将来の夢に結びついていてすてきですね。
初恋の話&海外で働きたい!?
テーマが自由だった卒業文集で、自分の恋話を書いたという人もいました。小学四年生の頃の話を書いたそうですが、その勇気がすごいですね! 話題になること間違いなしです。
そのほかにも当時ホームステイをした経験から、将来は海外で働きたいと書いている人もいました。今では国際寮の運営に関わっている彼女はある意味で夢をかなえているのかもしれません。
まとめ
いかがでしたか。何度も書き直しをしたり確認をとったりと、バタバタと忙しくなってしまいますが一生ものの卒業文集です。少しの工夫をしてすてきな文集を作成してください。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。
カルペ・ディエム告知情報:【無料講座】ワクワクする「探究学習」のつくりかた 〜結局、何をすればいいの?〜
開催概要
探究学習の必要性がさけばれ久しく、幼いうちから非認知能力を伸ばすことが求められる中で、多くの先生方から「結局探究って何をすればいいの?」「テーマは?ゴールは?やりっぱなしになってしまわないか?」といったご相談を頂きます。
そんなお悩みを解決すべく、「ドラゴン桜」「御上先生」などドラマ監修を行う西岡壱誠が登壇!
東京書籍出版『10代から身につけたい探究型思考力アカデミックマインド育成講座』の本にもなった、名物講座の小学生版を開催します!
<主な授業内容>
・探究学習って結局何?
・「問い」の立て方
・「仮説」の立て方
・「検証」までの流れ
・思考の0→1を導く方法
・教科学習との組み合わせ方 など
<ポイント>
① 探究学習の始め方からまとめ方まで授業の流れが分かる!
② 探究学習と教科学習を効果的に組み合わせる方法が分かる!
③ 子どもが楽しみながら学べる授業を実現できる!
日程詳細
【日時】2025年3月16日(日) 13:00~14:30
【会場】TKPガーデンシティ渋谷 4Bルーム
〒150-0002 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル
【参加特典】東京書籍出版『10代から身につけたい 探究型思考力 アカデミックマインド育成講座』(※当日お渡しいたします)
モニター協力のお願い
体験授業にご参加いただいた先生方に、モニターのご協力をお願いしております。
当日、授業終了後に皆様のご感想やご意見などアンケートにお答えいただけますと幸いです。
皆様からいただいたご意見をその後の授業に活かさせていただきます。
ぜひ、現場の先生方の声をお聞かせください!
ご協力いただいた方には、謝礼として下記をお渡しさせていただきます。
Amazonギフトカード3000円分(メールにてお送りいたします)