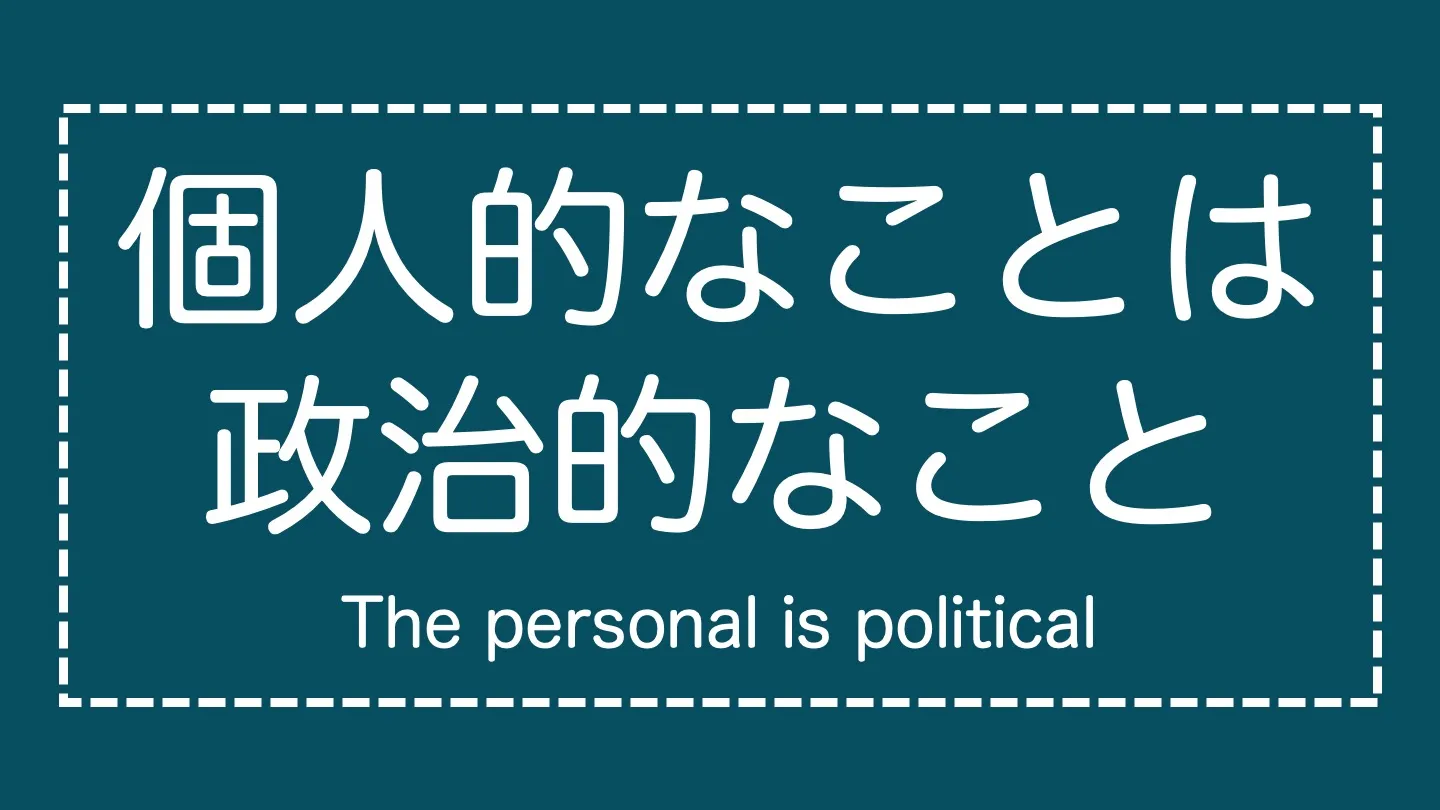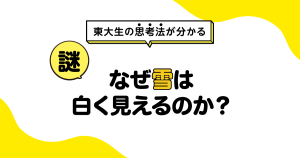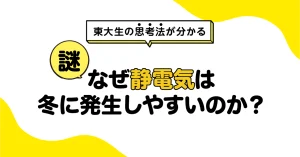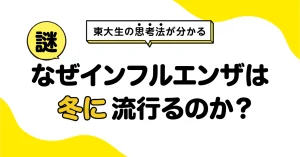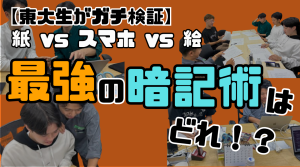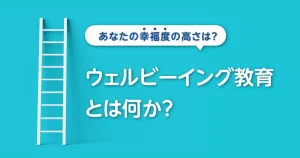こんにちは!メディア事業部の鈴木です。本日はTBSの日曜劇場『御上先生』でよく使われている『(ザ)パーソナルイズポリティカル(The personal is political)』について詳しく解説していこうと思います!
御上先生ではよく『パーソナルイズポリティカル』は『個人的なことは政治的なこと』と訳され使われています。そもそもこの言葉は誰が言い始めた言葉なのか?どういう意味なのか?御上先生ではどうやって使われている?また、現役の東大生や御上先生のような官僚にも意見をもらってきました!
『(ザ)パーソナルイズポリティカル(The personal is political)』について紹介させていただきます!
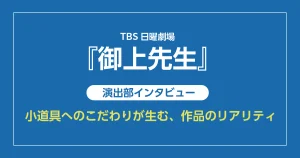
そもそも誰が言い始めたのか?
1970年の『The personal is political』と名付けられた論文には、『これらのグループで私たちが早期に見つけたことの1つは,個人的な問題は政治的な問題であるということである。』(筆者訳)と書いてあります。
しかし、この論文を書いたキャロル・ハニッシュ自身は2006年に
『私がその論文に「個人的なことは政治的である」とタイトルをつけたのではなかった、ということを記録として明確にしたい。私が知っている限り,それはNotes from the Second Year の編集者であるシュリー・ファイアストーンとアン・コートによってつけられたのであり,キャシー・サラチャイルドがそれを初期の選集の中で印刷されうる論文として2人の注意を引き寄せた後のことである。また、「政治的」はここでは権力関係に関係するものとして言葉の広い意味で使われており、選挙政治に関する狭い意味ではない。』(筆者訳)と言っています。
どういう意味なのか?
先程のキャロル・ハニッシュの論文の中では、キャロル・ハニッシュ自身は『女性が家庭内や職場、日常生活で直面する問題(例えば、家事の負担の不均衡、性的ハラスメント、賃金格差など)が、単なる個人的な不満や努力不足ではなく、社会制度や権力関係に根ざした構造的な問題であるという視点である。』ということを強調しています。
つまり、『社会構造そのものが個人の経験と不可分である(わかりやすく言うのなら、切り離せない)』ということです。
「個人の経験が社会構造と不可分である」というのは、私たちが日常で感じることや経験する問題は、単に個人の性格や能力の問題ではなく、社会全体の仕組みやルール、文化的な価値観と深く結びついているということです。
また、例えば、下記の記事においては日経XWOMEN【DUALな名言】個人的なことは政治的である
子育ての問題(保育園への入園、預かってもらっていても熱が出るかもしれない)に対して、保護者は孤独(一人、個人)である。しかし、実際はその問題は政治的であるということを示しています。個人的にも子育ては、例えパートナーがいたとしても2人、どうしても孤独を感じてしまうことに対しては、非常に納得ができます。個人的なことは政治的なことだと言えます。
どういうシーンで使われるのか?
ここでは、実際の書籍の中で『個人的なことは政治的なこと』がどのように使われているのか?というのを、書籍から引用しつつご紹介させていただきます。
『ラディカル・フェミニズム再興』 江原由美子 (1991)勁草書房
『ラディカル・フェミニズム再興』 江原由美子 (1991)勁草書房から引用
『「個人的なもの」と想像力」』 吉澤夏子(2012)勁草書房
『「個人的なもの」と想像力」』 吉澤夏子(2012)勁草書房から引用
『ベル・フックスの「フェミニズム理論」』 ベル・フックス(野崎ら訳) (2017)あけび書房
『ベル・フックスの「フェミニズム理論」』 ベル・フックス(野崎ら訳) (2017)より引用
・(ネタバレ注意)御上先生で『パーソナルイズポリティカル』が出てきたシーン(ここは随時更新していきます!)
次は、日曜劇場『御上先生」で、どのように使われていたかをご紹介させていただきます。
吹き出しの部分は筆者がドラマのセリフを文字起こししたものです。以下、ネタバレ注意。
第1話
御上先生『パーソナル?え、何?』
御上兄『個人的なことは政治的なこと』
御上先生『何それ』
御上兄『そういう言葉があるんだよ』
御上先生『どういうこと』
御上兄『個人が抱える生きづらさ、個人でなんとかしろってなりがちだけど、じつは社会的な問題。つまり政治が解決すべき問題だって意味なんだよね。この説明で分かる?』
神崎くんをを叱責するシーン
御上先生『パーソナルイズポリティカル』
神崎『は?』
御上『個人的なことは政治的なこと』
(回想)御上兄
『パーソナルイズポリティカルって言葉があってさ』
解説:不倫(パーソナルなこと)に対して、それで辞めさせられたのが女性教師。一方の男性教師は他のところでを仕事している。それっておかしくないか?ということを御上先生は問います。
神崎にそこまで考えてやっている?つまり、処遇はポリティカルな部分に関わってくるけど、そこまで考えている?と。
第4話
東雲温『パーソナルイズポリティカル。個人的なことは政治的なこと。』
解説:この4話では、東雲温にフォーカスが当たっています。東雲の親は学校教師、独自の授業をする先生。でも、独自な授業のせいで、学習指導要領から外れていた授業をしていたことから辞めさせられてしまいました。受けていた生徒はその授業が特別な授業だったからこそ、面白くも感じていました。そして、東雲の父が辞めさせられたことをきっかけに東雲の家庭環境は不安定になっていきました。
ここでの一見パーソナルに見えることは東雲温の家庭環境、そしてポリティカルな部分は教科書検定や制度に見えます。しかし、そのパーソナルな東雲の家庭環境を作った原因は、ポリティカルなものによるという。これらをを通じて「パーソナルイズポリティカル」を伝えたかったのように筆者は思います。
第7話
御上先生『亡くなった兄がよく言っていた言葉がある。パーソナルイズポリティカル。個人的なことは政治的なこと。椎葉さんの抱える生きづらさは、社会と繋がっている。政治と繋がっている。僕たちの未来がいいものになるかどうかに繋がっている。決して椎葉さんだけの問題じゃない。』
解説:第7話では、椎葉春乃にフォーカスがあたります。椎葉は両親を事故で亡くしており、現在は祖父母と3人で暮らしています。また、その祖父母の介護も1人で行なっています。1~6話まででは、椎葉は生活苦からアルバイトをしていることで、勉強に身が入らない様子が描かれていました。6話の最後では、生理用品を窃盗が判明し、担任である御上に電話がかかってきます。
ここでのパーソナルなことは、椎葉が祖父母の介護をしていること、貧困(生理用品買うお金もない)、PMS(月経前症候群)が酷いこと。対比としてポリティカルなことをあげるのであれば、そもそもヤングケアラー、PMSが酷い若者に対して理解や、支援が追いついてないことがあげられます。
第10話
御上先生『こんなことが、可能なのだと。君たちが僕に教えてくれた。それは、パーソナルイズポリティカル。その言葉の見事な具現化だった。』
解説:千木良遥が不正入学したことが9話で明らかになりました。
千木良は、不正入試したことで、自分のレベルよりも高い授業を受けています。それにより授業についていくために一生懸命になっています。しかし、三年生になった今では、彼女はクラスでも成績上位です。しかし、4話の文化祭のシーンでも「勉強したいんだけど!」という雰囲気を出し、彼女の勉強についての”焦り”が見られます。また、彼女の父親は国会議員で、そこのパーソナルな部分も千木良の生きづらさに繋がっているように思われます。
御上先生のセリフで言われている、パーソナルなことは生徒それぞれ、個人個人についてでしょうし、ここでいうポリティカルは政治のことを指していると思われます。そして、最終話の10話では、国の大きな問題を白日の下にさらします。これは、パーソナルなことをポリティカルにした、パーソナルな問題の裏に潜んでいる、元凶、大元みたいなものをポリティカルな問題として見つけたと言えます。まさにパーソナルイズポリティカル、個人的なことは政治的なことです。

現役東大生の考える『パーソナルイズポリティカル』、具体例など
現役東大生3人に、「パーソナルイズポリティカル」についてどう思うか?また具体例などを聞いてきました!
東京大学後期教養学部 生島光流
有斐閣から出版されている『国際政治学』の3章の冒頭で、「政治」とは「関係者の同意に基づく価値配分」と定義されている。この意味においては、政治は国会であったり外交であったりの政府の役人で国にまつわる事象を取り決めることに限定されない。例えば、学校の文化祭でクラスの出し物を決めること、自宅で1つのケーキを兄弟間で分けることもまた政治だと言える。つまり、複数人の間で合意を目指して話し合いや議論がなされさえすれば、それが日常の当たり障りのない会話でさえも政治になる。自分は、パーソナルイズポリティカルの標語には強く共感できるし、むしろ、上記のような現代の「政治」の定義からすれば当たり前のことである。
ただし、個々人の日常にも政治が溢れかえっている以上、社会全体で見たときには様々な政治で溢れかえり、もはや個人では対処しきれないような事態も生じる。この点において、脚光を浴びるのが政府である。政府はやはり「政治」のプロが集まっていることは間違いない。個々人の政治的な事柄を、社会全体の政治的な事柄の文脈へ落とし込んで解決に向かうことが必要なのではないか。
具体例: 学園祭での出し物決め。
クラスで行える出し物は1つのみ(限度がある)一方で、出したいものは生徒それぞれで異なる。いかにしてクラス全員の合意を勝ち取った上で出し物を決定するか。クラス内での学級会議は、日常を共に過ごしている人たちのみで構成されているため非常にパーソナル。
一方で、出し物を決める際には、意思表示や、根拠の説明、多数決での決定などを要する点でポリティカル。
東京大学 A.Y.さん
個人的なことは政治的であるについて。
元々の発言は,フェミニズムの文脈から女性をバラバラな個人に分けておくことからの解放に強い意味があるように思われます。
女性を閉じ込め,そこに押し込めておく。そのことによって,女性が抑圧されていることが徐々に常態化する。すると,彼女たちは声をあげることや抗議を行うことや集団でデモを行うことに対して無関心になっていく。このような状態を看過できないものとして考えていたことから,この標語が生まれたのではないか,そのように感じられます。
確かに,このような標語はわかりやすいかもしれません。しかし,この標語を作るきっかけとなった本人も述べているように,標語は広まり方に非常に注意しなければなりません。個人的なこととは一体なんだろうか。政治的であるということの意味とは何か。そこを曖昧なままにしてこの言葉だけを用いることは,言葉の独り歩きを助長し,場合によっては全く関係のない意味に捉えられかねません。御上先生も作中で述べていますが,「考えて」ということは忘れてはならない。作中のどれだけ印象的な言葉であっても,考えることをやめてはならない。そう思います。
東京大学 河内誠人さん
すでに本記事の解説にもあるとおり、「個人的なことは政治的なこと」という一種のスローガンは、もともと用いられてきたフェミニズムの文脈における特殊な意味からはやや離れて、より一般に、個人的な問題として矮小化されてしまう問題も、実は政治的なこと、すなわち人々全体のことに関わるんだ、というような意味で用いられることが多いようです。ドラマにおける、「〔個人的な問題に見えることも〕じつは社会的な問題。つまり政治が解決すべき問題だって意味」というセリフも、これを象徴しているでしょう。
ここでは、注意すべきことがいくつかあります。
まず、ここでいう「政治的」についてもともとハニッシュ自身が想定したのは、選挙政治に関する狭い意味ではなく、権力関係に関わるあらゆること、すなわち、複数人でなされるあらゆる営みを指しえます。よって、確かに「政治が解決すべき問題」もあるかもしれませんが、それには限られないということです。
次に、本来そのスローガンが置かれていた特殊な文脈を離れて一般化してしまっていいかは、各自考えてみる必要があると思います。
特に、日本では、個人的な問題と全体に関わる問題とを十分峻別せず、両者が一体的なものであるかのように語られることが多い印象です。それゆえに、このスローガンが、フェミニズムという特殊な文脈における意味を離れて、日本人にとっても耳馴染みのいい言葉になっているのかもしれません。
そうだとすれば、むしろ、「個人的なことは『個人的なこと』」という、真逆のスローガンの重要性についても考えてみるべきではないでしょうか。
あえて特殊な文脈を離れた議論を許すのであれば、なんでも「政治的なこと」に還元せず、あくまで個人のこと、私的領域に関することはそのままその人の中の問題としてとどめておくという発想も、重要になるように思います。
現役の官僚に『パーソナルイズポリティカル(個人的なことは政治的なこと)』について意見もらってみた
知り合いの官僚に『個人的なことは政治的なこと』についてどう思うか?と聞いてみました! 匿名で所属も出せないという点を留意して頂ければと存じます。
ドラマで登場する「個人的なことは政治的なこと」というフレーズは、本来のラディカル・フェミニズムの文脈からは離れ、個人的な問題とみなされがちな問題が政治的なイシューになりうる、という意味で用いられています。
政治と聞くと、多くの人は国家や共同体が行う「まつりごと」としての政治を想像されるかもしれません。しかし、「政治」という言葉はより広い意味を持ち、2人以上の人間集団が意思決定を下し、それを実行することもまた「政治」と呼ぶことができます。クラスや職場での意思決定(「社内政治」という言葉もあります)、果ては今晩の我が家の夕食のメニューを決めることすら「政治」なのです。
政治の単位が小さくなるほど、その性格は個人的になっていきますが、こうした大小様々な政治は、一見関係がないように見えて実は複雑に繋がりあっています。そのような意味において、「個人的なことは政治的なこと」なのではないでしょうか。
また、官僚という「まつりごと」としての政治に極めて近いところで働いていると、大きな政治の内部にも様々な小さな政治が存在することに気づきます。大々的に報道されるような大きな政治的イシューは極めて少数で、全く議論されない小さなイシューのほうが圧倒的に多いのです。小さなイシューであっても重要ではないわけでは全くないので、どんな仕事でも真摯に対応することが重要だと思っています。

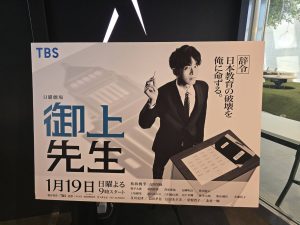
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。