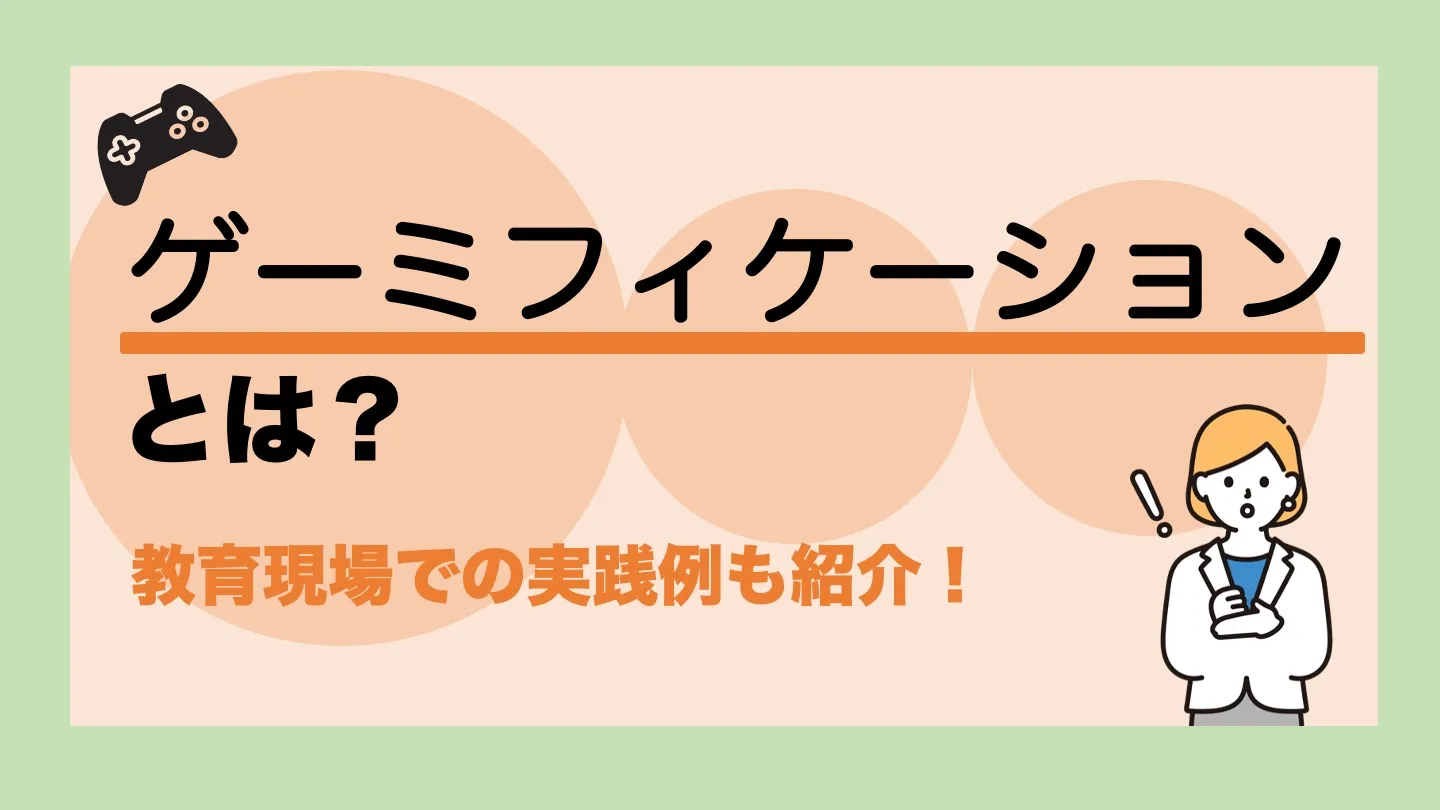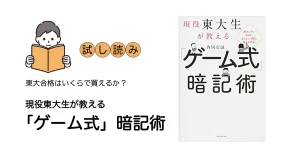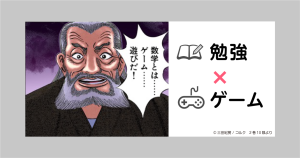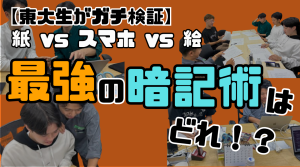近年話題になりつつある「ゲーミフィケーション」。聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
ゲーミフィケーションとは、ゲームの要素や仕組みを応用することで、その分野のモチベーションを高める手法のこと。近年、教育分野でのゲーミフィケーションが徐々に広まりつつあります。
「ゲーム」と「勉強」は対極の存在ではありません。今回は、教育にゲームの要素を取り入れることのメリット・デメリット、そして教育現場での実践例について、東大教育学部生の碓氷明日香が解説します!
ゲーミフィケーションとは
そもそもゲーミフィケーションとは何なのでしょうか。また、どのような背景があって広まってきたものなのでしょうか。
ゲーミフィケーションの定義
前述の通り、ゲーミフィケーションとは、ゲームのメカニズムやゲームデザインの要素をゲーム以外の分野に適用することで、人々のモチベーションを高めることを言います。ゲームは様々な要素から人が熱中しやすいものだと言われていますが、それを他の行動にも活かすことが考えられているのです。
授業内でアプリゲームを取り入れることもゲーミフィケーションですし、もっと簡単な実践例として、小学校の夏休み課題などでよくある、学習時間や問題の進捗に応じてシールを貼ったりマスを埋めたりする「学習チャート」なども広義のゲーミフィケーションと言えます。
自分の現状を明確にし、目標に向かって着実に報酬を得ながら学習を進めること、と言い換えることもできるでしょう。
広がってきた背景
ゲーミフィケーションが広まった一番の要因と考えられるのは、スマートフォンの普及です。それに伴い、教育や学びを目的にしたアプリケーションが次々に開発され、学習にゲームアプリを取り入れやすくなりました。
また、最近では文部科学省の「GIGAスクール構想」を踏まえ、全国の小中学校で1人1台ずつタブレットの導入が進められています。これにより、今までより一層教育現場でのゲーミフィケーションが広がっていくでしょう。
ゲーミフィケーションのメリット
ゲーミフィケーションの概要を踏まえ、ここからはこの取り組みにはどのようなメリットがあるのかについて説明していきます。
モチベーションが維持しやすい
まず、大きなメリットとして、「モチベーションが維持しやすい」ということがあります。何かしらのゲームにハマったことがある方は想像しやすいと思いますが、ゲームは単純に楽しいですよね。それは他者との競争を掻き立てられたり、結果・成長が目に見えたり、即時に報酬が手に入ったりするからだと考えられています。
同じ要素を学習に活かせば、勉強がつまらないものから一気に楽しいものに変わると思いませんか?ただ机に向かって難解な活字と向き合ったり、先の見えない問題と睨めっこしたりするよりも余程自発的に学習に向き合えるようになるはずです。
目標を設定しやすい
次に、「目標を設定しやすい」というメリットもあります。1人で勉強しているとどうしても先が見えづらく、何を目指してどのように頑張ればいいか曖昧なままダラダラと進めてしまいがちです。
しかし、ゲーミフィケーションならば、最終的なゴールが元々設定されていたり、いくつか選択肢が用意されていてそこから自分でゴールを選んだりします。そうであれば、そのゴールから逆算して、必然的にさらに細かい身近な目標も見えてくるでしょう。
明確な目標を持ち、迷わずに学習を進めていけるので、生産性も上がります。
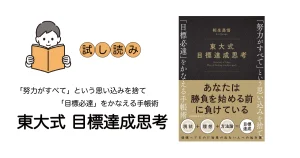
自信がつきやすい
そして、小さなタスクを達成することで報酬をもらえるゲームならば、着実にレベル上げができている感覚を得られ、「自信がつきやすい」です。小さな成功体験を積み重ねることは、積極的に次の課題に臨む姿勢につながります。
そしてこれがまたモチベーションの維持に結びつき、好循環が生まれるのです。
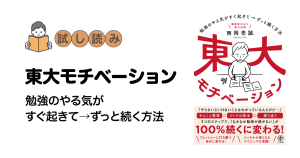
ゲーミフィケーションのデメリット
一方、ゲーミフィケーションにはデメリットもいくつか存在します。ここでは3つのデメリットを説明していきます。
過度な競争意識が発生してしまう
まず一つ目は「過度な競争意識が発生してしまう」こと。報酬をもらい、レベルやランキングを上げていくシステムの場合、周囲の生徒と達成状況を比べてしまい、あの子よりも上に行かないと、と気持ちばかり焦ってしまうことも。
その結果、人間関係のいざこざにつながったり、勉強という本質が見失われてしまったりします。ポイント不正などを働く生徒も出てくるかもしれません。そうなれば、本人はポイントを稼いでも学習内容は身につきませんし、周囲も努力を正当に評価されないことからやる気を失ってしまいます。
競争意識を持たせることはモチベーションの維持のために重要ですが、度が過ぎると問題が起こりかねず、ゲーミフィケーションの本来の機能を発揮できない可能性があります。そのあたりは、教員や保護者の声かけで競争意識を沈めてあげることが大切です。
学習の動機が内容の外側にある
二つ目は「学習の動機が内容の外側にある」こと。ゲーム要素を取り入れることで、生徒たちはやる気を引き出され、勉強に向き合うようになるでしょう。しかし、それでは個人の知的好奇心がきっかけなのではなく、「報酬をもらう」ことが動機になってしまっています。一見、自発的に勉強しているように見えますが、それは勉強したくてしているのではなく、ゲームしたくて勉強している、という状態になっているのです。
この問題を解決するためには、ゲーム要素とは別のところで、生徒の知的好奇心を駆り立てるような経験を積ませることが重要になってきます。成績を上げるためにゲームアプリをやらせていればいい、というわけではなく、他の勉強方法と併用することが必要なのです。
レベル設定が難しい
そして三つ目として、「レベル設定が難しい」ことが挙げられます。ゲームアプリとしてシステムを統一してしまうと、学習スタイルを個人のレベルに合わせるのが難しくなってしまいます。
「簡単」「普通」「難しい」などのモードを設定したとしても、生徒ひとりひとりが自分のレベルに合ったモードを適切に選択できるとは限りません。小学生くらいであれば、友達と同じコースにしたいと考えるでしょうし、中学生くらいであれば、自分だけ簡単なコースなのは嫌だ、と考えるかもしれません。
自分のレベルに合っていない問題を解いていても、楽しくないでしょう。その結果、やる気がなくなったり、飽きてしまったりする可能性も。結局、モチベーション維持のためのゲーミフィケーションが機能しないという結果に終わってしまうこともあるのです。
これも、周囲の大人が子どもの意志を尊重しながら適切なレベルを教えてあげることで解決するでしょう。つまり、ゲーミフィケーションのメリットを得るためには、周囲の大人の支えが必要不可欠なのです。
教育に取り入れるために大切な要素【PBL】
では、実際に教育にゲーム要素を取り入れることについて考えていきましょう。どのような要素を中心に教育を構築すればいいのでしょうか。ここでは、重要な3つの要素、PBLについて説明します。PBLとは、ポイント、バッジ、リーダーボードの頭文字を取ってつなげた言葉です。ひとつずつ分けて解説していきます。
P(ポイント)
まず、Pの「ポイント」とは、みなさんのイメージ通り、行動や結果に応じて与えられる報酬です。
例えば、基本問題を一つ正解するにつき3ポイント、演習問題を一つ正解するにつき5ポイント、発展問題を一つ正解するにつき8ポイント……というように、問題を解くたびにもらえる仕組みにしたり、ログインボーナスのような、アプリを開いて勉強を始めることでポイントをもらえるシステムにしたりすることが考えられます。
ポイントには、「貯まっているということに対する達成感を感じる」「ゲームの進捗がわかりやすい」「進捗を対外的に示すことができる」といったメリットがあります。
B(バッジ)
次に、Bの「バッジ」とは、ポイントをより大きな塊にしたものです。一定の大きさの目標をクリアした時に、プレイヤーに与えられる称号のことを指し、例えば、「一週間連続ログイン」「分数の計算マスター」といったバッジが考えられます。
バッジには「プレイヤーにとって明確な目標になる」「ステータスになり、自信がつく」などのメリットがあります。
L(リーダーボード)
最後のL、「リーダーボード」とは、プレイヤー同士を比較した時の自分の立ち位置を示すものです。代表的なリーダーボードとして、ランキングが挙げられるでしょう。その単元の問題を早くクリアした順にランキングをつけたり、単純にポイントの保有量でランクづけしたりすることが考えられます。
リーダーボードには、「自分が成長している、進んでいることが一目瞭然になる」「競争意識が生まれ、モチベーション維持につながる」といったメリットがありますが、前述の通り、過度な競争意識はむしろモチベーションの低下や人間関係の問題などにつながってしまうので、この要素の使い方には注意が必要です。
教育分野の実践例
実際に、ゲーミフィケーションは教育現場でどのように導入されているのでしょうか。ここでは3つの導入例を紹介します。
小学校の授業にゲームアプリを導入
小学校1年生を対象として、タブレット端末上で動作するアプリケーション「アプリゼミ」を導入する実験が行われました。
数週間にわたってアプリゼミを使用して児童に国語と算数を勉強させた結果、学習した単元のテストの平均点が事前のそれと比べて上昇したそうです。また、児童もアプリゼミを使った勉強は楽しかったと述べているようで、ゲーミフィケーションを教育に取り入れることは確かに学習意欲の向上と成績の上昇に影響を与えることがわかっています。
参考:ゲーミフィケーションの要素を取り入れた小学校1年生向け電子教材の実践と評価
大学の講義に数理モデル教育のゲームを導入
また、大学の講義にゲーミフィケーションを取り入れた実践例もあります。桃山学院大学の社会科学系を専攻とする学生を対象に、共通教養科目「自然科学——定量分析入門」において専用サイトを導入してゲーム要素を取り入れた授業構築がなされるという実験が行われました。
学習成果がアバターによるランキング形式で表示されることでモチベーションのアップにつながったという結果が出ていて、ゲーミフィケーションは大学生に対しても有効であると言えます。
参考:文系学生の数理モデル教育におけるゲーミフィケーション実践
普段の家事をゲーミフィケーション化
普段の家事にゲーム要素を取り入れる研究も行われています。どうしても後回しにしがちな「掃除」をゲーミフィケーション化することで、継続的に家を綺麗にしようという試みです。具体的には、掃除機の動きに応じてポイントが加算されたり、そのスコアに対して様々なゲーム音が鳴ったりする専用システムを掃除機に取り付けることでモチベーションを高めます。
結果的に、掃除が楽しくなったと感じる被験者が多く、家事のゲーミフィケーション化にも一定の効果が認められたとされています。このように、ゲーミフィケーションの考え方は決して教育の分野に限らず、身近な様々なものごとに応用できるのです。
まとめ
対極にあると考えられがちな「ゲーム」と「勉強」をつなげて、学習者のモチベーションを高めるゲーミフィケーションについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。ゲームが楽しいと思われている理由となる要素に注目して、それを他の分野で応用することによって、つまらないと思われがちなものも楽しく進めることができるようになるのです。
他の学習方法と併用しつつ、周囲の大人が適切な距離を保ちながら学習者に協力することで、うまくデメリット部分を打ち消し、最大の効果を発揮できるように工夫することが大切になってきます。そして、それがうまくいけば、学習者の成績は着実に上がっていくはずです。みなさんもぜひ、勉強含め、身近なところからゲーミフィケーションを取り入れてみませんか?
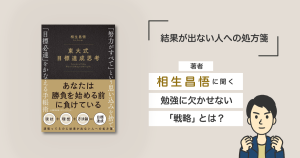
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。