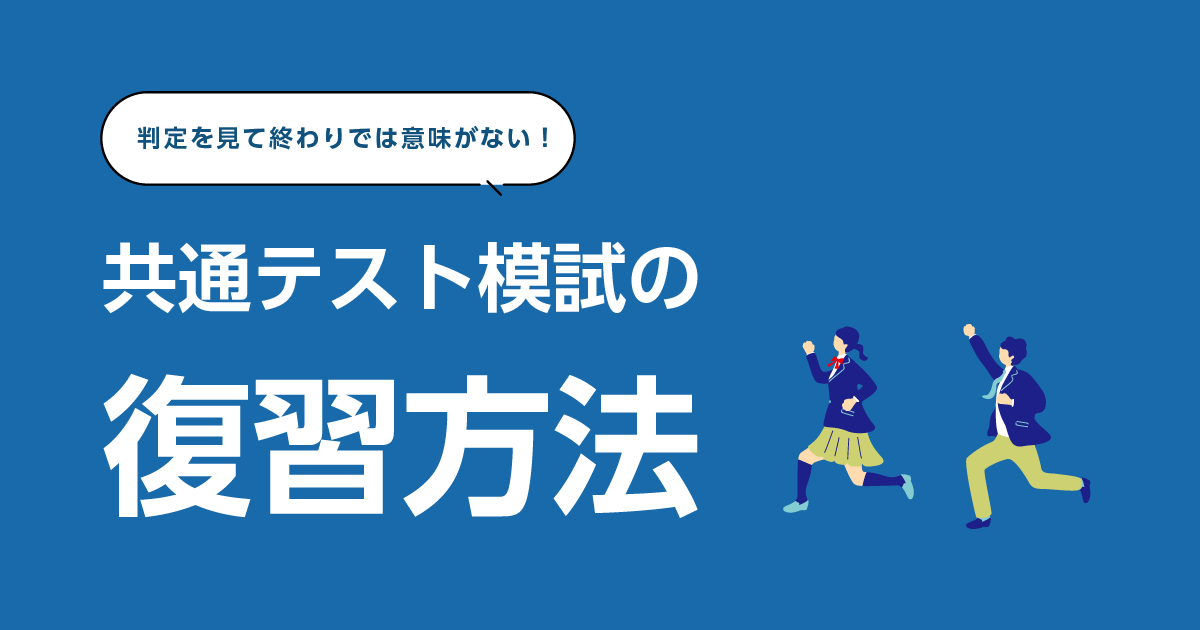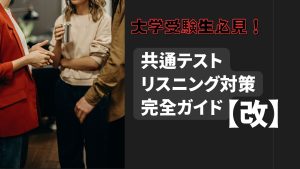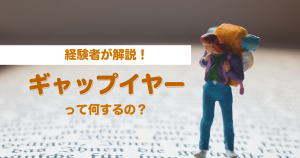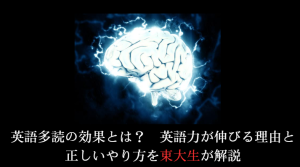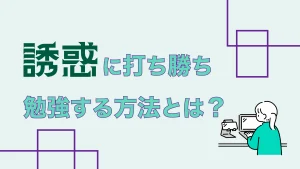共通テストを受験する予定の人の中には、年4回河合塾が行う「共通テスト模試」を受験する人がいると思います。今回は、共通テスト模試の振り返り方と活用方法について解説します!【2025年6月22日編集】
模試の全般的な復習方法をお探しの方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。
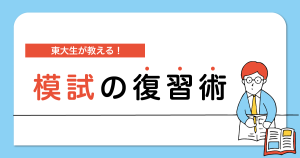
また、記述模試の復習方法を知りたい方は、以下の記事をお読みください。
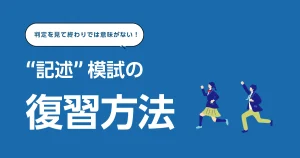
共通テスト模試の落とし穴
共通テスト模試は、全ての問題がマーク問題の模試です。マーク式模試には、記述式模試にはない落とし穴があります。
それは、「まぐれ」で正解になる問題が多く存在すること。考えた過程を書かなければならない記述問題と違って、マーク問題は、正しい選択肢をマークできてさえいれば、正答したことになるからです。きちんと復習せず「何割取れたか」だけを見ていると、自分の本当の実力を誤って認識したまま本番を迎えることになってしまいかねません。力を伸ばすための復習方法を身につけましょう。
問題を種類で分ける
問題は、最終的には「正解」と「不正解」のどちらかに分かれます。しかし、問題に対する自分の理解度には、実はいろいろな種類があるのです。まずは、1問1問がどれに該当するのか把握しましょう。
自信を持って「正解」
まず、正しい過程で自信を持って正解できた問題。これをもう一度解くのはかえって時間を浪費してしまうので、スルーして大丈夫です。
たまたま「正解」
次に、確証なく選んだり、当てずっぽうで選んだりした選択肢が、偶然正解だった問題。これは、実質不正解だと捉え、不正解の問題と同じように解説を読んで復習しましょう。
ただし、正解できたということは、一部考え方が合っていたり、過去の記憶や経験から「なんとなくこれではないか」という「良い勘」がはたらいたりした可能性が少なからずあります。何が理解できていなかったかと同時に、自分の思考過程のどの部分が合っていて、なぜ正解できたかまで、自身を分析できるとよいでしょう。
惜しくも「不正解」
また、考え方や過程は一部合っていたが、どこかで間違えて不正解だった問題。結果的に点数が入らなかったとしても、共通テストの問題で使うことのできる考え方が身についていることは、勉強の成果だと捉え、自分を褒めましょう。
「自分の進歩に気づいて認める」ということは、受験期のメンタルケアとして実はとても重要です。最初の頃は、特に不正解の問題が多いので、「できた部分」にも着目する必要があるのです。
共通テスト模試では、これらの「たまたま正解」と「惜しくも不正解」の2種類の問題が多いです。なぜかというと、共通テストの問題は、たくさんの過程を踏んで1つの選択肢に辿り着くように、複雑に構成されているからです。そのため、問題を解く時に自分が考えた道筋を残しておき、あとで分析できるようにしましょう。
とりあえず飛ばして「不正解」
解き方がすぐに思いつかなかったり、時間が足りなかったりして、とりあえず飛ばした問題もあるでしょう。この種類の問題は、模試が終わって時間がある状態でもう一度考えてみましょう。あまり考えていないのに、すぐに答えを見るのはもったいないです。共通テストに出題されるレベルで考えて作られた問題は貴重なので、有効活用できるように、少しずつ解答を参考にしながら今の自分の実力と照らし合わせるようにしましょう。
まだ習っていなくて「不正解」
共通テスト模試は範囲が限定されているとはいえ、まだ履修していない範囲の問題も出る時があります。復習時は飛ばして良いですが、何ヶ月後かにその模試をもう一度解いてみて、今度は解けるかどうか試してみましょう。正解できれば自分の成長を実感でき、先ほど述べたメンタルケアにも繋がります。
問題を解く時の工夫
では、どうやって問題を上記の種類に振り分ければ良いのでしょうか。復習をしやすくするためには、自分がどうしてその答えを選んだか振り返った時に思い出せるように、「模試本番を解いている最中に」考えた過程を残しておくことが大切です。筆者は模試に限らず、何か演習をする際、問題の番号に印をつけるようにしていました。
・勘やなんとなくで選んで全く自信がない問題番号にはバツ印
・多分正解だけれど解答に迷った問題や、曖昧なので解説を読みたいと思った問題番号には△印
といった様子です。これは受験のためというより、まぐれで正解してしまったが実は理解できていない「取りこぼし」をなくすためで、中学生の頃からずっと続けていました。
続けていたおかげで、新しく履修する分野を他の人より少ない周回回数で身につけることができていたため、皆さんもぜひやってみてください。
どんなタイプの問題が苦手なのかを知る
共通テスト模試は、共通テスト本番に出される問題と同じタイプの問題が出題されます。例えば英語リーディングの長文では、選択肢の文章を時系列順に並べ替える問題が出題されます。
演習は形式別問題集でもできますが、本番の疲労感や焦りの中で体験して、苦手を洗い出すことができるのは、本番の他には模試だけです。時間がかかってしまった問題や、疲れて判断力が鈍ってしまった問題など、模試で不正解だった問題のタイプを「一般化」し、普段の演習から意識するようにしましょう。また、緊張によって最初の方の問題の正答率が低いのか、それとも集中が続かなくて最後の方の正答率が低いのかなど、自分の傾向も、自己採点から総合的に分析しましょう。
1日や2日で共通テスト模試を受ける場合は、科目についても同じことが言えます。たとえば、1日の終わりの方の科目は集中力が切れて、個別で演習する時よりも点数が低い、などといった事態が起こるかもしれません。共通テスト本番は、2日間で全科目の試験を受けるので、模試で起こった問題は本番でも起こりかねません。模試は本番の練習だと考え、自己分析を徹底的に行いましょう。
復習の例〜数学〜
私が実践していた方法の中から、私が特に苦手だった数学の復習方法を紹介します。私はずっと数学が苦手でしたが、この復習方法を続けて、共通テスト本番で自己最高得点を取ることができました。
他の科目は、模試の問題用紙に赤ペンなどで直接ポイントを書き込み、その問題用紙をまとめて保管していました。しかし、数学だけは「復習ノート」を作っていました。数学は模試に書き込むと、何が何だか分からなくなってしまうからです。
復習ノートの作り方
まず、模試の問題をコピーし、ノートに貼ります。次に、ノートとは別の雑紙に問題を解いていきます。ノートに直接書かない理由は、まず自力で挑戦するために、いらない紙にメモ書きや書いて消すことを繰り返し、少しずつ解答を見ながら解法を完璧に理解した上で、復習ノートには綺麗な模範解答を残したいからです。
自力で解く段階では、考えてみて、つまずいた箇所で1行ずつ解答を見るようにしていました。全部見ない理由は、解答にヒントをもらいながら、途中から自力で解くことができるかもしれないからです。これは私の高校の数学教師がおすすめしていた、数学の演習方法です。
雑紙にたくさん書き込んだり解答を見たりして、解法を理解したら、今度はノートに、綺麗な答案を書きます。この時は最後の復讐として、解答を見ずに解法をノートにまとめます。もし解法を理解していればつまずかずにスムーズに最後まで解ききることができ、「私でも大問の最後まで解ける」という自信がつきます。

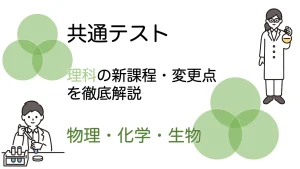
模試の問題を活用しまくれ!
いかがでしたか。共通テスト模試は教科がたくさんある分、復習にも時間がかかります。ただ、共通テスト模試は数年前からたくさんの人が話し合って作った、いわば「良問」だらけの模試です。解いて終わりではもったいない!少し頑張って、本番のために復習してみませんか?
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。