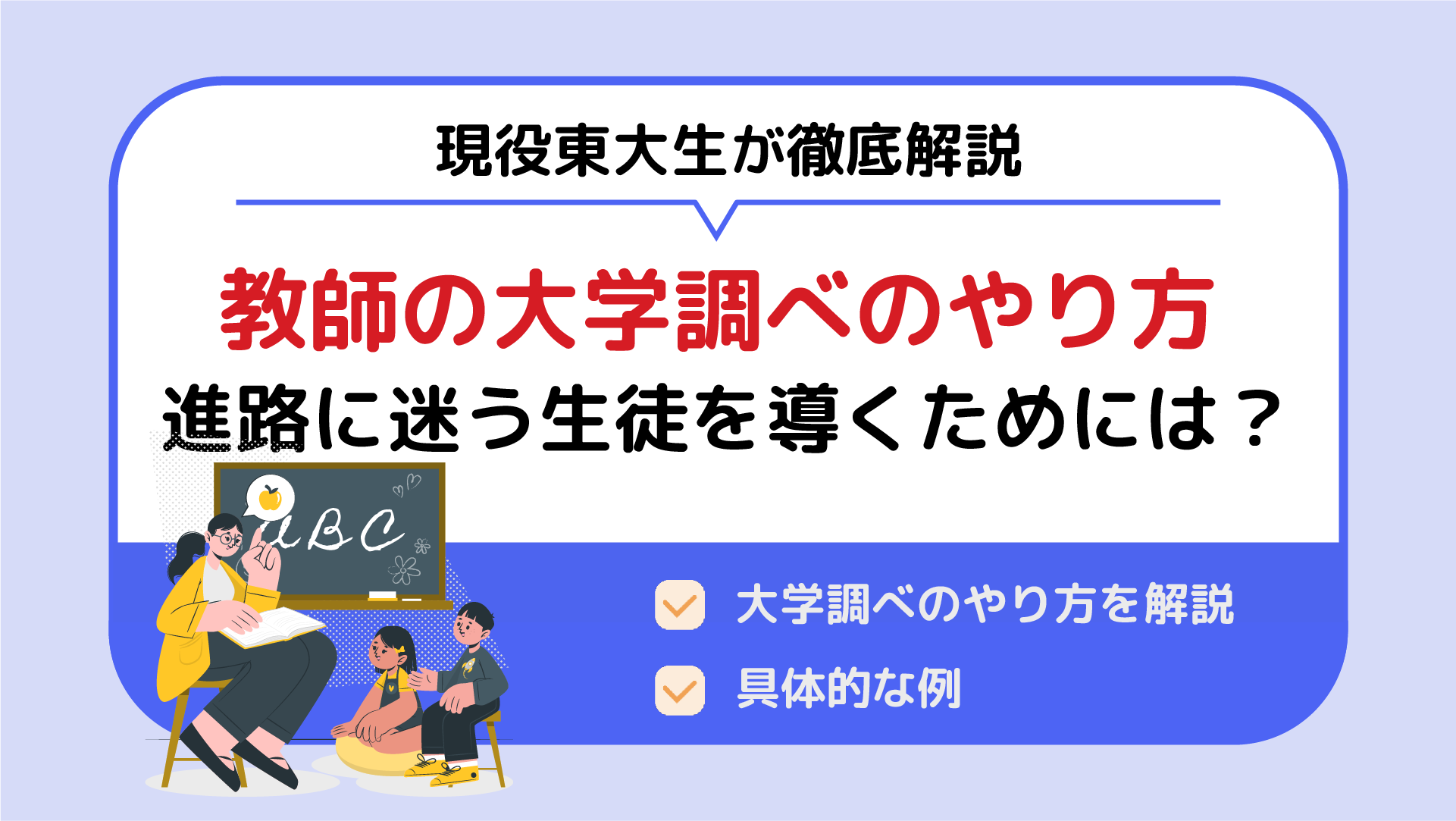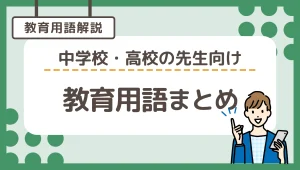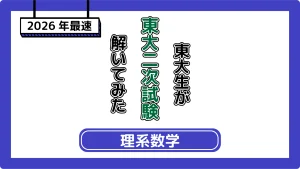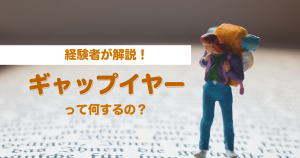志望校がなかなか決まらない、何から調べればいいかわからない。部活も普段の勉強も忙しいし、数年後の受験のことまで考えていられない。そうやって、大学調べを先延ばしにして、進路希望調査で毎回困っている生徒が、どの学校のどの学年にもいることでしょう。
今回は、大学調べのやり方から、そんな迷える仔羊たちを導くためのポイントまで、実際の経験をもとに東大教育学部生の碓氷明日香が徹底解説します!
高校生向けの大学選びの記事はこちら
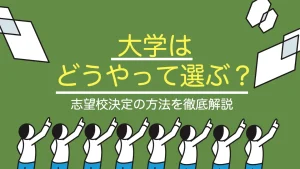
大学調べの方法4選
まず、改めて大学調べの方法を確認していきましょう。ここでは4つの方法を紹介します。
大学調べができるサイト
大学や学部、学問などを調べることができるサイトはたくさんあります。条件を絞って検索することも可能です。そもそも大学の候補すら見つかっていない生徒には、サイトを有効活用してもらうのが手っ取り早いでしょう。
代表的なサイトはマナビジョン、スタディサプリ進路、パスナビ、河合塾の大学検索システムなどでしょうか。教員として、各サイトの使用感を試しておくと、いざアドバイスをするときに役立つでしょう。
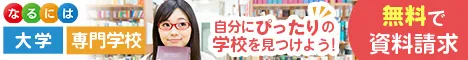
大学の公式ホームページ
大学の候補が複数存在していて、どこを第一志望にするか迷っている生徒の場合は、各大学の公式ホームページをチェックして比較してみるのもひとつの手です。基本、ほとんどの大学には国立公立私立問わず、公式ウェブサイトがあり、どんな学生を歓迎するかなどの情報を発信しています。
学部や学科、コースやカリキュラムなどの詳しい情報もサイトをたどっていけば見つかるはずです。入試の日程や選抜の方法なども詳細に書かれています。これらの情報は教員として把握しておくべきであり、生徒の志望校になり得そうな大学のホームページはこまめにチェックしておきましょう。
オープンキャンパス
大学の雰囲気を一番確実に体感できるのは、やはりオープンキャンパスです。学内の雰囲気や実際にどのような授業が行われているのか、などはインターネット上では知り得ません。
生徒には、早い段階でいろんな大学のオープンキャンパスに参加するよう促しましょう。3年生になってからでは受験に間に合わないかもしれませんし、そもそも3年生は模試などで忙しいため、なかなか時間を取りづらいです。そのため、オープンキャンパスの時期を調べておいて、事前に生徒に声をかけられるようにしておくといいでしょう。
大学受験の情報誌
多くの大学は、その雰囲気を知ってもらうために、大学案内という形で資料を出しています。各大学の入学案内書を取り寄せてみると、インターネット上で見られる以上の情報が手に入るかもしれません。
また、複数の大学についてまとめて掲載している大学情報誌や進学ガイドブックなども書店やインターネットで販売されています。どのような資料が存在するのか、確かめておくといいでしょう。学校として、そういった資料を進路資料室のような教室に置いておくと、生徒が手に取りやすいかも。
大学を選ぶ際のポイント
では、どのようなポイントを意識して大学を選べばいいのでしょうか。生徒から、「どんなことを考えればいいですか?」と聞かれた際、答えられるよう、ここでは4つの選定ポイントを挙げます。
学問や研究内容から
専門的に学びたい学問や研究したい内容があるのなら、それを中心に選ぶのが一番です。興味がある分野の研究を行っている教授がいる大学に入れば、学びたいことを確実に学ぶことができます。
大まかに理系、文系に絞ったら、さらにどの科目が勉強していて楽しいか、もっと知りたいと思えるか、と少しずつ対象を狭めていくのが身近な方法ですが、高校の勉強と大学の勉強は全然違います。自分の大学時代の記憶をたどりつつ、何を基準に学問を選べばいいか、考えてみてください。
校風やアドミッションポリシーから
とはいえ、学びたい学問がよくわからない生徒の方が多いのではないでしょうか。その場合、校風やアドミッションポリシーを調べてみて、ひかれる大学を選ぶといいです。
アドミッションポリシーとは、大学が求める学生像のこと。大学の教育理念や目的を示し、どのような学生に入学してほしいかが言語化されています。各大学のホームページで確認することができるので、それを比較してみると、生徒の個性に適した大学が見つかるかもしれません。
大学は少なくとも4年間(短期大学は2年から3年)通い続ける場所です。校風が自分に合わないと感じる場所は避けた方がいいでしょう。
受験方法や偏差値帯から
大学を選ぶ際に、一定考慮しなければならないのは、受験方法や偏差値帯です。苦手科目の配点が高かったり、生徒の成績の現在地と比べてあまりにも偏差値が高い、もしくは低かったりする大学を目指すのは、あまり得策とは言えないでしょう。
とはいえ、部活を引退してから一気に成績を伸ばす生徒もいますし、受験方法や偏差値帯が必ずしも参考になるとは限りません。どうしてもその大学に行きたいという強い意志があるのであれば、教員がわざわざ口を出す必要もないです。
あくまでひとつの要素として、考慮に入れてもいい条件、くらいの立ち位置で捉えておくと、アドバイスしやすいでしょう。
立地や学費などの条件から
本来なら生徒の希望・意志を尊重すべきですが、家庭ごとに地元から出ないでほしい、あまり学費が高い大学は困る、といった要望もあるでしょう。その辺りも考慮しつつ、大学を選ぶ必要があります。
生徒と保護者の意志が一致していない場合は、教員として助言に困るかもしれませんが、その際、一人暮らしのメリット・デメリット、奨学金制度などについて説明できると、生徒や家庭にとって参考になるはずです。特に奨学金制度は年々変わってきているので、情報を把握しておく必要があります。
進学先に迷っている生徒との面談でのポイント
大学調べの方法や選ぶ際のポイントについて、生徒目線にも立ちつつ確認してきましたが、ここからは、いざ進学先に迷っている生徒と面談するとなったとき、どのようなポイントを意識すればいいかについて解説します。
突き詰めたい、興味のある学問を引き出す
まず、上述の通り、多くの生徒は学びたい学問が見つかっていません。実際、私も高校生の時はそうでしたし、周りも大抵そうだったように思います。そこで、生徒との対話を通じて、何に興味があるのか自覚させることが大切です。
何の科目が好きか、普段考えていること、趣味などから学問に関連づけていくつか候補を挙げてみてください。そして、それらがどのような学問なのか、どの大学で学べるのか、どのような研究がなされているのかを調べてきてもらうのです。調べるきっかけを授けてあげることで、生徒は少しずつ自分の興味の偏りに気づくことができます。
大学調べの方法を生徒に伝え、自分で調べさせる
また、これまで解説してきた大学調べの方法を生徒に伝え、自分から調べてみるよう促してみてください。そもそもどうやって大学を調べたらいいのか、どのように候補を絞ったらいいのかを知らない生徒もいることでしょう。道筋を示してあげるだけで、少しは先が見えてくるはずです。
先述の大学選びの要素も挙げておくと、生徒がその中で何を重視すればいいのか優先順位をつけやすいでしょう。とにかく、生徒が自力で調べられるように準備をして、支えることが大切です。場合によっては、一緒に調べるのもひとつの手かもしれませんね。
あくまで情報提供者としてのスタンスを崩さない
特に意識してほしいのは、教員はあくまで情報提供者であって、進路の決定権は持っていないことです。教員と生徒という関係上、どうしても教員の言葉が絶対的になってしまいがちなので、やり方を示す、候補をいくつも挙げてみるだけに留め、それ以降は本人に調べさせてください。
生徒が「先生がこう言っているから、そうした方がいいのかな」と思って大学や学問を選ぶのでは、生徒の意志が反映されているとは言えません。ひとりひとりにとって重大な決断なのですから、本人が選ぶべきです。情報を与えてあげるだけ、というスタンスを意識しましょう。
まとめ
大学調べのやり方について、そして進路に迷っている生徒にどうアドバイスをすればいいかについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
教員として、どのように調べてどのように選べばいいのか知っておくことが、非常に重要です。そして、それを生徒に伝えて、本人に調べさせる。この流れとスタンスを意識して、進路相談に乗ったり、面談に臨んだりすれば、生徒としてはとてもありがたいのではないでしょうか。
先生向けの教育用語まとめもありますので、ぜひご確認ください!
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。