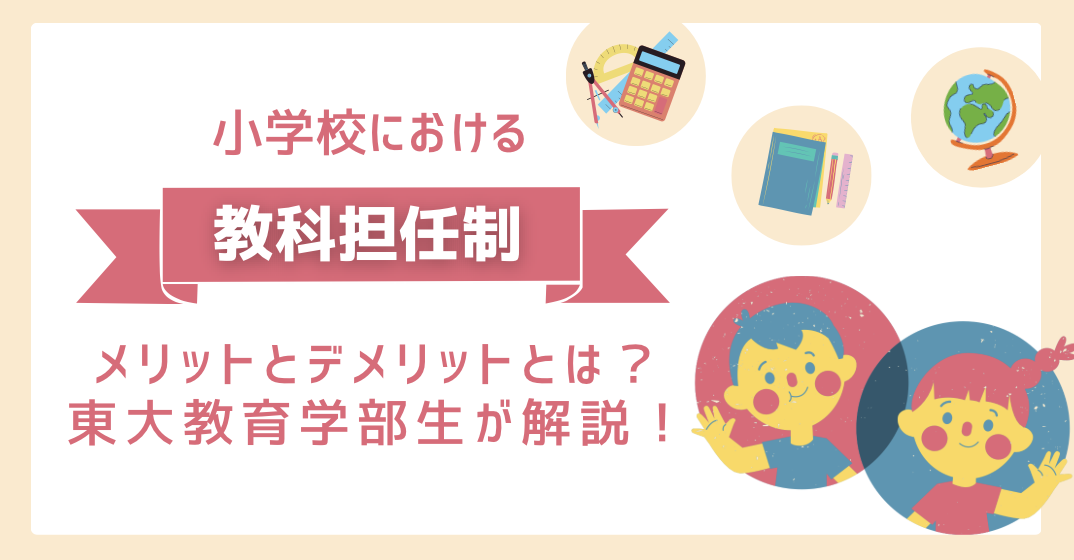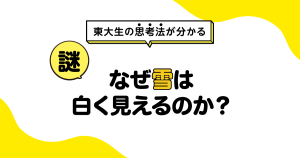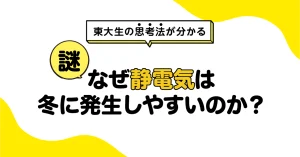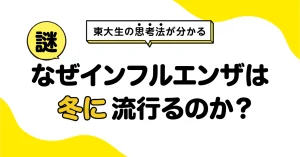2022年度から、小学校高学年における教科担任制の導入が本格的にスタートしましたが、これはそもそもどのような仕組みなのか、そしてどのような目的のもと、拡大が進められているのか、ご存じでしょうか。
今回は、小学校における教科担任制について、メリットやデメリット、実践例も交えながら、東大教育学部生の碓氷明日香が詳しく解説していきます!
教科担任制とは
文部科学省が推奨している「教科担任制」とは、そもそもどういう仕組みを指すのでしょうか。また、どのような背景で導入がなされたのでしょうか。
教科担任制の4つの種類
「教科担任制」とは、教科ごとに専任の教員を置く指導形態のことを言います。中学校や高校を想像してもらうとわかりやすいでしょう。中学校・高校では、学級担任はいますが、科目の指導はその科目専門の先生が行いますよね。しかし一方で、小学校では、基本的にほとんどの科目を学級担任が指導しています。国はこの方式を変えて、中学校・高校と同様に教科担任制を取り入れようとしているのです。
まず、文部科学省は、教科担任制には4つの種類があるとしています。
- 中学校・高校で行われているような、全ての科目で専門の教員が指導をする形の完全教科担任制
- 現状、多くの小学校で行われている、特定の科目だけ専門の教員を配置する形の教科担任制
- 学級担任間で授業を交換する形の教科担任制
- 1教科の指導を複数の教員で分担・協力して指導する、チーム・ティーチング制
この4種類です。国は、各地域や学校の実態に応じた教科担任制の導入を進めています。
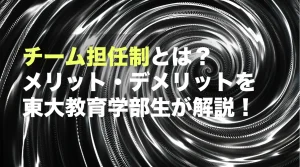
導入された背景
長年「学級担任制」が取られてきた小学校で、教科担任制が導入され始めたのは、どのような背景があったのでしょうか。
大きな目的として、「変動しやすく、予測が困難なこれからの時代を生き抜くことができる人材を育てる」ことが挙げられます。これからの時代を生きていくためには、高い情報リテラシーやプログラミング的思考力が必須です。これらを早くから身につけさせるために、今、教育業界ではさまざまな変革が行われています。この教科担任制の導入・拡大はその変革のひとつなのです。
また、コロナウイルスのパンデミックを踏まえ、GIGAスクール構想が導入されました。これは、児童生徒1人につき1台ずつの情報端末を配備し、ICTを活用した教育を実現させる取り組みです。このGIGAスクール構想がきっかけで、個々の児童生徒の学習状況をきちんと把握し、教科指導の専門性を持った教師がきめ細やかな指導をする必要が出てきました。教科担任制の導入は、この課題解決につながる教育改革なのです。
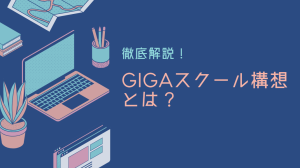
優先的に取り入れるべき科目
文部科学省は、優先的に教科担任制に変えていくべき科目をいくつか定めています。それは、「外国語」「理科」「算数」「体育」の4科目です。それぞれ、優先すべき理由について、次のように述べられています。
外国語
新たに小学校において導入された教科であり、指導体制の早急な充実が求められるとともに、中学校への学びの連続性を持たせながら、外国語によるコミュニケーション能力の基礎を培う系統的な指導を行う専門性が必要とされている。
理科
観察、実験などを中心とした問題解決の過程を通じて、児童自らが問題を科学的に解決したり、新たな問題を発見したりする活動を充実するとともに、ICTの活用やプログラミング的思考など新しい知見も活用しながら、理科の面白さや有用性を認識できるような指導、中学校での科学的リテラシーの育成を見据えた系統的な指導を行うことのできる専門性が必要とされている。
算数
統計教育の充実など社会や日常生活の事象に結び付ける活動の充実や、プログラミング的思考の重視など筋道を立てて考える力の育成の重要性、学年が上がるにつれて内容が抽象的になり躓きが生じやすい状況を踏まえ、数学的活動を充実させ数学のよさに気付かせるような指導、児童一人一人に応じた指導、中学校の内容も視野に入れ児童に算数・数学に興味を持たせながら系統的な指導を行うことのできる専門性が必要とされている。
体育
運動が苦手な児童をはじめ全ての児童に、できる喜びを味わわせていくことが求められるとともに、学年が上がるにつれて技能差や体力差が広がりやすく、個々の能力に適した指導・支援を安全・安心を確保しながら行う必要がある。生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育む上で、高学年児童の発達の段階、能力の適性、興味や関心に応じて、運動の楽しさや喜びを味わい、自ら考えたり工夫したりしながら運動の課題を解決する学習を展開し、中学校の内容も見据えた系統的な指導を行うことができる専門性が必要とされている。
いずれも、これまでの教育の課題を踏まえつつ、これからの時代を生き抜く児童を育てる上で専門性が特に必要な科目ということでしょう。まずはこれらの科目から、教科担任制を取り入れることが進められているのです。
教科担任制のメリット
では、教科担任制を取り入れることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、4つの主なメリットを説明していきます。
授業の質が高まる
まず1つ目は「授業の質が高まる」ということです。教員は専門科目に絞って授業準備を行い、指導をすることができるようになります。これにより、授業の質が格段に良くなり、児童の学習内容の理解度が高まって、学力向上につながります。これは、直感的にもわかりやすい、最も大きなメリットと言えるでしょう。
教員の負担軽減につながる
2つ目は「教員の負担軽減につながる」ということです。教員の業務過多が昨今特に問題視されていることは皆さんもご存じでしょう。教員の働き方改革など、改善に向けた取り組みは行われているようですが、実質的な効果はあまり出ていないのが現状です。
しかしそこで、この教科担任制がうまくいけば、教員の負担を軽減することが可能になるとされています。学級担任制では、学級経営や全教科の授業準備、児童の課題の確認など、幅広い業務が担任にのしかかりますが、教科担任制では、授業準備の必要がある科目が一気に減ります。また、チーム・ティーチングを使えば、これまでは1人で背負わなければならなかった学級経営も、複数の教員で協力しながら行うことができるかもしれません。
教員の負担が減ることは、教員自身のウェルビーイングにつながり、過労による教員の退職を減らし、担当科目の授業準備の時間が増えることで、授業の質が高まる、というように、さまざまな方面に良い影響を及ぼします。これもまた、教科担任制の大きなメリットと言えるでしょう。
児童の心が安定する
1人が1クラスを担当する学級担任制と比較して、教科担任制では、複数の教員が1人の児童を指導することが可能になるため、子どもの状況を正確に把握することにつながります。
また、学級担任制においては、児童にとって担任の先生との相性の良し悪しは大きな問題です。実際に、担任の先生と合わないからといって不登校気味になってしまう児童もいます。しかし、教科担任制を導入すれば、児童は複数人の教員と関わることができ、相談しやすい先生を見つけやすくなるのです。こうした理由から、「児童の心が安定する」というメリットも挙げられています。
中1ギャップの解消につながる
また、近年注目されている問題に、「中1ギャップ」というものがあります。小学校と中学校ではあまりに環境が違いすぎて、中学校に上がった時、その環境の変化についていけずに心身の不調が起こり、不登校に陥ってしまう現象のことです。小学校と中学校の大きな違いのひとつに、学級担任制か教科担任制かというのもあるでしょう。これまでは全て同じ先生に教わっていたのに、突然、教科ごとに別々の先生が来るようになって、その変化になじめないことも実際にあるようです。
小学校の高学年から、教科担任制を取り入れることで、中学校入学とともに経験する環境の変化を軽減することができるようになります。中1のタイミングで感じる小学校とのギャップは、主に「担任制の仕組みの違い」「学習内容の難易度の違い」「クラスメイトが一気に入れ替わること」などが挙げられますが、これらのうち、ひとつでも減らすことができたら、かなりなじみやすくなるはずですよね。
教科担任制の課題とデメリット
一方で、教科担任制の導入にあたって、課題やデメリットも浮き彫りになってきているようです。ここでは、4つのデメリットを説明していきます。
教員数の確保が難しい
まず、過疎地域や小規模校にとって、「教員数の確保が難しい」という問題があります。教科担任制を導入するためには、各教科につき1人以上の教員が必要になりますが、その数に満たない教員しか在籍していない学校にとっては、教科担任制の導入は厳しいでしょう。
文部科学省は、地域や学校に合わせて適切な仕組みを取り入れることを推奨していますが、それでも課題は残ります。また、地域や学校によって別々の方法を取り入れることで、さらなる地域格差につながってしまうとも予想できるでしょう。解決のためには、教員の数を全国的に増やす取り組みが必要になってきます。
小中学校の仕組みの違いを乗り越えるのが難しい
また、学校によっては、中学校から教科担任を呼んで小学校で授業してもらうという仕組みを取り入れているところもあるようですが、そこにも課題が隠れています。「小中学校の仕組みの違いを乗り越えるのが難しい」のです。
小学校の授業は45分なのに対して、中学校の授業は50分です。授業をしている側にとって、この5分が大きな差であるのは明白でしょう。そして、小学校と中学校の教員免許は全く別物ですから、小学校に呼ぶことができるのは両方の免許を持っている教員に限られます。始めのうちは、一部の中学校教員に大きな負担がのしかかることになりかねません。この辺りも、学校任せにするのではなく、文部科学省が改善策を提示することが求められます。
カリキュラム・マネジメントの視点が薄れやすい
「カリキュラム・マネジメントの視点が薄れやすい」ということも、デメリットの一つとして挙げられます。カリキュラム・マネジメントとは、「複数の教科を連携させる指導」のことです。学級担任制であれば、複数の教科を1人の教員が教えるので、例えば「算数でこの授業をしたばかりだから、理科の授業でもそれと関連付けたこんな話をしよう」といった工夫が可能です。しかし、教科担任制になると、他教科で何を教えたのか全てを把握することはできないので、関連付けるのが難しくなってしまいます。
こうした、「学級担任制」の利点がなくなってしまうのも、デメリットとして考えられていますが、変革にはこの問題がつきものなので、新たな方式の中で、元の方式のメリットを生み出せないか考えることが重要になってきます。カリキュラム・マネジメントに限って言えば、他教科の担当教員と授業の進度や児童に伝えたことをこまめに共有し、関連付けの意識を持つことで解決が可能です。
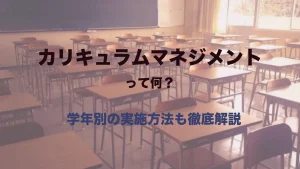
教員の密な情報伝達が必須になり、かえって負担増
前述の「カリキュラム・マネジメントの視点」においても必要なことですが、教科担任制に変えることで、教員同士の密な情報伝達が必須になります。個人の家庭環境、ひとりひとりの特性、そしてその日の体調や状況に合わせた指導を行うためには、教員同士がその児童についての情報を共有する機会が必要なのです。
メリットとして挙げた「教員の負担軽減」ですが、教科担任制に教員が慣れるまでは、この密な連携が難しく、かえって負担が増えることになりかねません。制度の導入にあたって、学年団の連携体制を改める必要がありそうです。
小学校での教科担任制の実践例
北海道のとある小学校では、5、6年生を対象に、教科担任制が導入されています。国語と算数は学級担任の授業交換を、社会は専科教員の配置を、理科と外国語は中学校教員による授業を行っているようです。
この小学校では導入にあたって、専科指導の専門性の担保のため、お互いの授業を参観したり、指導内容や指導方法について話し合う機会を設けたりしています。また、児童についての情報共有を意識することで、いじめなどの児童間の問題を未然に防ぐよう工夫しているようです。
効果として、上記のメリットだけではなく、「複数学級の特定の科目の指導を1人の教科担任が行うため、学級ごとの進度の差が出ない」「複数回同じ授業を別のクラスに対して繰り返すことで、前の授業の改善点を意識して次の授業を行える」といったことも教員から出ています。児童自身も、「授業がわかりやすい」「中学校に行っても知っている先生がいるから安心」といったメリットを実感しているようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。導入・拡大が進められている小学校の教科担任制ですが、多くのメリットがあると同時に、課題やデメリットもあるようです。新しい時代を生き抜く児童生徒を育てるために必要な取り組みではありますが、格差が広がったり、教員の負担がかえって増えたりすることのないように、課題解決のための仕組みを検討することも大事になってきそうですね。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。