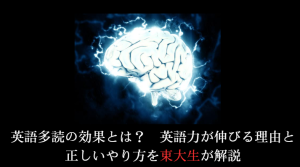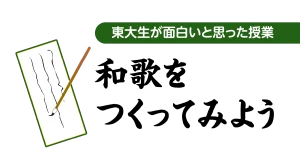「勉強しなきゃいけないのは分かってる。でも、やる気が出ない。」そんな気持ちになったこと、誰にでもありますよね。実は、やる気が出ないのはあなたの意思が弱いからではありません。そこには、脳や環境、思考パターンなど、きちんとした原因があるんです。この記事では東大生の筆者が、
- 勉強のやる気が出ない原因
- 今すぐできる気分転換法
- 東大生が実践していた「やる気を引き出すコツ」
を、「勉強しなきゃ」と焦っているあなたに向けてお届けします。【2025年10月31日更新】
勉強のやる気が出ない原因
まずは、自分の「やる気が出ない理由」を知ることが大切です。原因がわかれば、対処法も見えてきます。ここでは、勉強のやる気が出ないときに考えられる主な原因を見ていきましょう。
環境が悪い
そもそも勉強できる環境が整っていないことが、やる気を奪っている場合があります。たとえば、机の上が散らかっていて、ノートや筆記用具を探すだけで時間がかかる──そんな状態では集中できませんよね。
優れた塾講師や家庭教師は、ある生徒が成績向上するかどうかを判断するときに、その生徒の普段の勉強机を見せてもらうそうです。 成績が向上しやすい生徒は、机がきれいに整っており、どこに何があるのか一目でわかるようになっているのだとか。一方で、机の上が汚い生徒は、そこで勉強することを想定していないため、机上は荒れ放題。ものが散乱して目も当てられない場合が多いのだそうです。
まずは机や部屋を整えること。おすすめは、その日に使う教材だけを机の上に置き、順番にこなしていく方法です。机上の教材が減っていくと、自分がその日に達成したことを実感することができます。
整理整頓こそ、やる気のスイッチを入れる第一歩。勉強に向かう気持ちがぐっと高まり、集中力も自然と上がるはずです。
体調が悪い
体調がすぐれない日もありますよね。頭が痛い、腰が痛い……そんなときにやる気が出ないのは当然のことです。
無理をして勉強しても、集中できないだけでなく、体調をさらに悪化させてしまうかもしれません。1日頑張ったつもりが、そのあと1週間寝込むことになってしまったら、本末転倒です。
そんなときは、思い切って休む勇気も大切です。1日休んで体調を整えることで、翌日以降のパフォーマンスを取り戻せるなら、それは「前向きな休み」です。
一度立ち止まって、「今日無理をすること」と「しっかり休むこと」、どちらが自分にとってプラスになるかを冷静に考えてみましょう。
何をすれば良いか分かっていない
やるべきことがたくさんありすぎて、何から手を付けていいのかわからないこともあるでしょう。「あれもやらなきゃ」「これもやらなきゃ」と頭の中がごちゃごちゃになっていることが原因で、勉強を始めるのが億劫になっているのかもしれません。
そんな時は、具体的に何をすべきなのか、Todoリストを作ってみましょう。書き出す前はただ焦ってしまっても、書き出してみると、実際はそこまで大変ではないと分かることが、筆者にもよくあります。
たとえば「苦手な数学を何とかする」という漠然とした目標ではなく、
「参考書の1章を今日中に10ページ読む」
「間違えた問題を3つ解き直す」
といったように、具体的で小さな行動に分解してみましょう。
数学の参考書を一単元ずつ片づけていく。まず一単元こなすために、今日は1ページ目から10ページ目までをさらってみる。それを今から1時間の間で頑張ってみる。
ここまで分割すれば「数学」という強大な敵が、小さな作業に変わりますよね。戦うべき敵を細分化して、自分ができそうな作業に変えることは重要です。やるべきことが多くなってきたと思ったら、ぜひ細分化をしてみてください。
できれば、Todoリストを作ることを毎日の習慣にしてほしいです。朝や前日の夜に、優先順位をつけて、やるべきことを書き出してみてください。それだけで、取り組むべきことが明確になり、「机に向かい始める」ことのハードルを下げることができるはずです。
他にやりたいことがある
勉強以外にやりたいことがあって、どうしてもそちらに気を取られてしまうこともあるでしょう。スマホを5分触るつもりが、いつの間にか1時間経っていたなんてことも。
こうした「誘惑」に打ち勝つ一番のコツは、最初から誘惑を近づけないことです。人の意志は思っているよりも弱いもの。見える場所にあるだけで、つい意識が向いてしまいます。
スマホを別の部屋に置く、漫画やゲームを片づける、勉強中はテレビのない場所に移動する。そうやって物理的に距離を取るだけで、集中力は驚くほど上がります。
塾の自習室や図書館など、誘惑の少ない環境に身を置くのも効果的です。特に自分1人では気が緩みやすい人ほど、「勉強するしかない環境」に身を置くことで自然とやる気が戻ってきます。
やる気が出ないときほど、自分の意志を頼りにせず、環境の力を借りてみましょう。
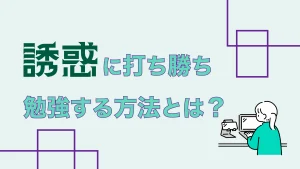
モチベーションが上がらない
「勉強する意味がわからない」「なんでこんなに頑張らなきゃいけないの?」
そんな気持ちになることも、きっと誰にでもあります。目の前の勉強が、未来の自分とどうつながっているのかが見えないと、やる気は出にくいものです。
そんなときは、なんのために自分が勉強しているのか、見つめなおしてみましょう。将来のために勉強しているなら、数年後の自分がどんな仕事をして、どんな毎日を送っていたいかを思い浮かべてみてください。大学で興味のある分野を研究したいなら、大学で学ぶ内容や出会う人たちのことを想像してみるのもおすすめです。
時間に余裕があればぜひ、志望大学に実際に足を運ぶことをおすすめします。実際に大学生活を送っている大学生や建物の雰囲気を見ると、「絶対にここに入学するんだ」という強いやる気が湧き、帰宅してから再スタートを切ることができます。
自分のモチベーションを立て直すための方法を持っておくことも大切です。この音楽を聴く、散歩してこの場所に行く、5分仮眠する──「自分の機嫌を取る」ことができる人は、勉強だけでなく将来の仕事でも強いです。自分のペースで「やる気のスイッチ」を見つけていきましょう。
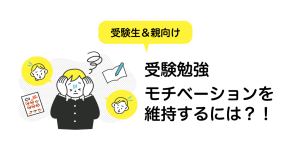
やる気が出る気分転換の方法
ここでは、勉強のモチベーションを取り戻すための、効果的な気分転換の方法を紹介します。
お風呂に入る
どうしてもやる気が出ないときは、思い切って勉強から離れてみるのも大切です。その中でも、お風呂にゆっくり入るのはおすすめのリフレッシュ方法です。
シャワーだけで済ませず、湯船にしっかり浸かりましょう。半身浴もおすすめで、体への負担の少なく、しっかりと全身に血液を巡らせることができます。お気に入りの入浴剤を使ったり、好きな音楽を流したりして、自分をいたわる時間を作るのも効果的です。
また、入浴しながら軽く単語帳を眺めたり、明日の予定を整理したりするのもいいかもしれません。お風呂はリラックスと集中のちょうど中間の時間。上手に使えば、気分転換と勉強の両立もできます。
「お風呂場でもできることがある」と発想を変えてみると、気持ちが前向きになるはずです。温まってリセットしたら、また机に向かうエネルギーも自然と湧いてきますよ。
昼寝する
どうしても眠くて集中できないときは、思い切って昼寝をしてしまうのも一つの方法です。昼寝をした後に眠気が低減される効果は、3時間持続するという研究結果があります。筆者である僕も、やる気が出ないときや頭がぼんやりしているときは、いったん眠ってリセットするようにしていました。
ただし、注意したいのは「布団やベッドに入らないこと」です。一度ベッドに入ってしまうと、ほぼ確実に熟睡コース。気づけば夕方、なんてことにもなりかねません。
昼寝をするなら、机に突っ伏して目を閉じるなど、軽く眠る程度にとどめる工夫をしましょう。個人差はあるものの10分〜20分の短い睡眠が良いとされています。また、昼寝をするとなかなか起きられずに寝すぎてしまうという方は、コーヒーなどのカフェインを昼寝前に摂取しておくと、カフェインの覚醒効果によって起きやすくなるとされています。
短い昼寝でも頭がすっきりして、再び勉強に向かうエネルギーが湧いてきますよ。
散歩をする
気分を変えたいときには、外に出て軽く散歩をしてみるのもおすすめです。筆者である僕自身も、集中力が切れたときによく散歩をしてリフレッシュしていました。
ポイントは、あえてスマホを持たずに出かけること。最初は少し不安かもしれませんが、昼間なら危険も少なく、ちょっとした非日常を味わうことができます。
普段はスマホの画面に向けている視線が、外の景色や通りすがりの人、街の音に向くようになります。すると、いつも歩いている道なのに、なぜか新鮮に感じる──そんな感覚を味わえるはずです。
ちょっとした工夫で、いつもの散歩も刺激的な発見の時間になります。歩いて頭を空っぽにすれば、帰ってきたときには自然と気持ちが整い、勉強へのやる気も戻っているでしょう。
音楽を聴く
気分転換には、音楽を聴くのもとても効果的です。イヤホンで静かに聴くのも良し、スピーカーで部屋いっぱいに音を響かせるのも良し。自分の好きな曲を思い切り楽しんでみましょう。
夜でなければ、家でちょっとしたカラオケ大会を開いてみるのもおすすめです。声を出すことでストレスが発散され、気持ちがスッと軽くなります。
洋楽を聴けばリスニングの練習にもなりますが、ここでは「勉強のため」ではなく、「自分をリセットするため」に音楽を聴くことが大切です。
中途半端に勉強を意識するのではなく、好きな音楽の世界にどっぷり浸かってみましょう。しっかりリフレッシュできれば、次に机に向かうときには、自然とやる気が戻っているはずです。
環境を変えてみる
やる気が出ないときは、思い切って環境を変えてみるのも効果的です。いつもと違う場所で勉強してみたり、部屋の掃除をしたりするだけで、気分が驚くほどリフレッシュされます。
たとえば、普段は学校で勉強しているなら、今日は図書館や喫茶店で勉強してみる。いつもと違う空気や音、香りが、あなたの集中力を刺激してくれます。同じ勉強でも、場所が変わるだけで新鮮さが生まれ、気持ちが切り替わるのです。
また、部屋の模様替えや掃除もおすすめです。机の上を片づけるだけでもスッキリしますし、思い切って大掃除をすれば、気分まで一新されるでしょう。ごみ袋を何枚も出すつもりで、断捨離をしてみてください。きっと心も頭も軽くなって、もう一度やる気が戻ってくるはずです。
思い切って休んでみる。
どうしてもやる気が出ないときは、あえて休んでしまうという選択肢もあります。僕は、受験の1週間前にすべてが嫌になってしまい、丸一日YouTubeを見て過ごしたことがありました。
もちろん、これが習慣になってしまうのは危険です。1日をまるごと休みにしてしまえば、その分勉強時間は減ります。けれど、限界まで張りつめた心をリセットするという意味では、とても有効な方法でもあります。
大切なのは、「ここが限界だ」と自分で感じたタイミングで、この手段を使うこと。上手に使えば、それは最高のストレス解消になります。
もし実行するなら、親や先生などに心配をかけないよう、事情を伝えておくのも大事です。誰にも黙って突然サボるより、「今日はリフレッシュデーにする」と宣言して休む方が気持ちもスッキリしますし、せっかく休んでいるのに誰かに「勉強しなさい」と言われることもありません。
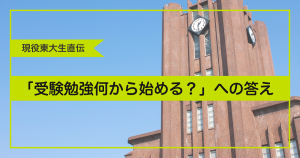
東大生が教えるとっておきの「やる気を出す」方法
ここまで、さまざまな「やる気を取り戻すコツ」を紹介してきました。それでも、「どうしてもやる気が出ない」「何から始めたらいいかわからない」と感じること、ありますよね。
忘れてはいけないのは、「やるべきことは、逃げてもそこに残り続ける」ということです。放っておくほど心の片隅でモヤモヤが大きくなり、「やらなきゃ」と焦る気持ちばかりが募ってしまいます。
では、どうすればこの状況を抜け出せるのか?ここからは、実際に東大生たちが実践していた、やる気を引き出すためのシンプルで効果的な方法を2つ紹介します。
とりあえず手を動かしてみる
僕のおすすめの方法は、とりあえず手を動かしてみることです。
嫌なことがあっても、「明日からやろう」ではなく「今日この後すぐやってみよう」と思い、とりあえず準備をしてみて、部分的でも実行してみるだけでずいぶん変わります。もしかしたら、やる気は実際に手を動かしたあとについてくるものであって、元から存在するものではないのかもしれません。
なんにせよ、まずは行動を起こしてみるということが非常におすすめです。やる気不足に悩まれている方は、騙されたと思ってまずは最初の5分だけでも頑張ってみてください。5分後には「もうちょっとだけやろう」と、自然と机に向かっているかもしれません。
理想と現実を比較する
やる気が出ないと思ったとき、自分の今の成績と、志望校の合格に必要な点数を見比べてみると、「勉強しないといけない」という実感が湧きます。
こうして、理想と現実のギャップを強制的に可視化することで、「焦り」を生み出し、やる気につなげるという方法もあります。
なんとなく漠然と「やらないと……」と思っているだけでは、やる目的が明確ではありません。合格のためには、あと数ヶ月でどれだけのギャップを埋める必要があるのか、実感を抱くことで、机に向かうことができるでしょう。
まとめ
どんなに努力家でも、やる気が出ない日というのは必ずあります。しかし、そうした「やる気の波」とうまく付き合えるようになってこそ、一人前の受験生です。
誰にでも、心の中には“なまけたい自分”がいます。「自分だけが弱い」と思う必要はありません。むしろ、その気持ちと向き合いながら少しずつ前に進める人こそ、本当に強い人です。
やる気が出ないときは、感情をいったん脇に置いて、理性で行動を決めるようにしてみましょう。「やりたくないけど、これは明日までにやる」と決めて、感情ではなく“タスク”として淡々とこなすのです。
最初はうまくいかなくても大丈夫。少しずつ「感情」と「理性」のバランスを取れるようになれば、勉強のリズムも安定していきます。
駄々をこねる気持ちを否定せず、うまく折り合いをつけながら前へ進む──それが、長い受験生活を乗り越えるための最大のコツです。
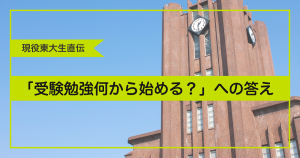
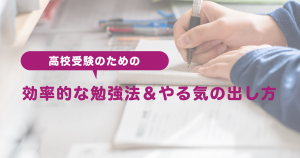
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校様・保護者様のお悩みに対応した講演・講座・ワークショップをご提案&実施しております。
生徒の皆さんの大学選び&学部選びのワークショップ、モチベーションアップを目的とした講演、探究学習授業、長期休暇の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しています。
講師は現役東大生!偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめとして、地域格差・経済格差など、さまざまな逆境を乗り越えた現講師たちが、生徒に寄り添って対応します。
ご相談から受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。