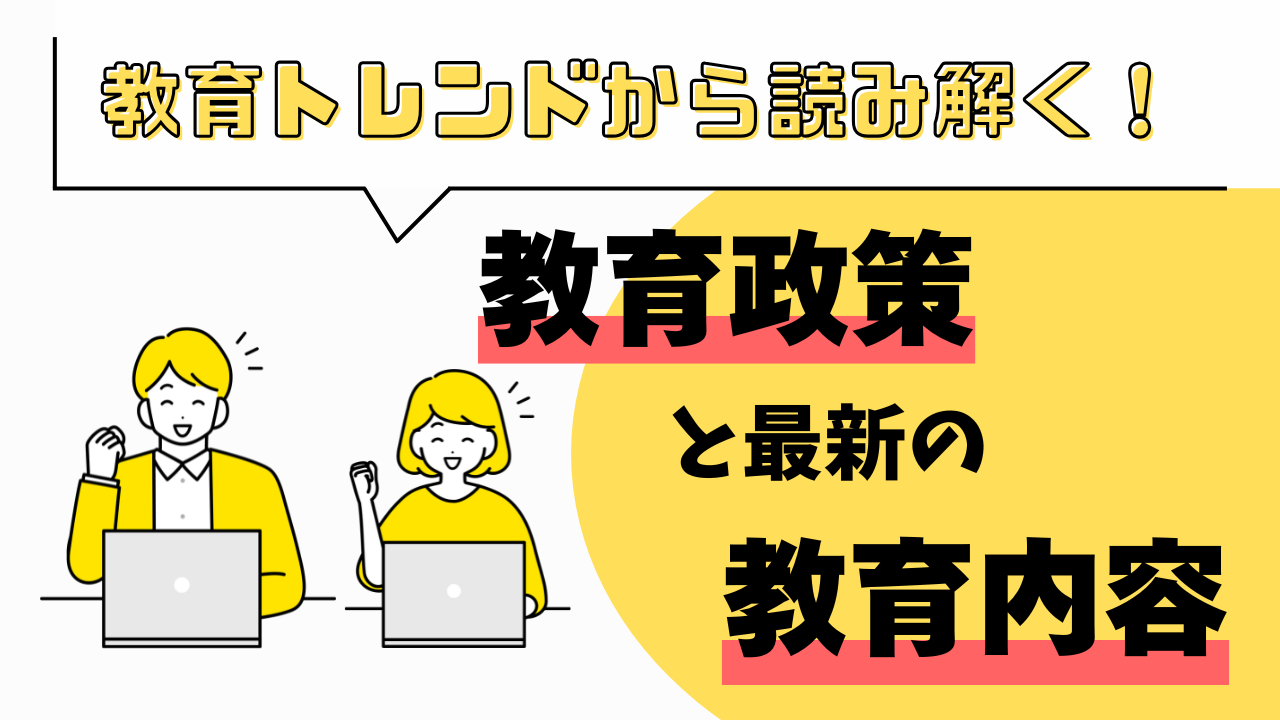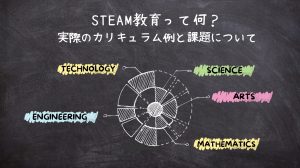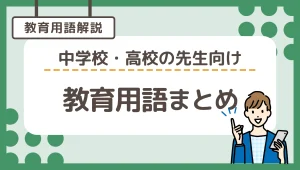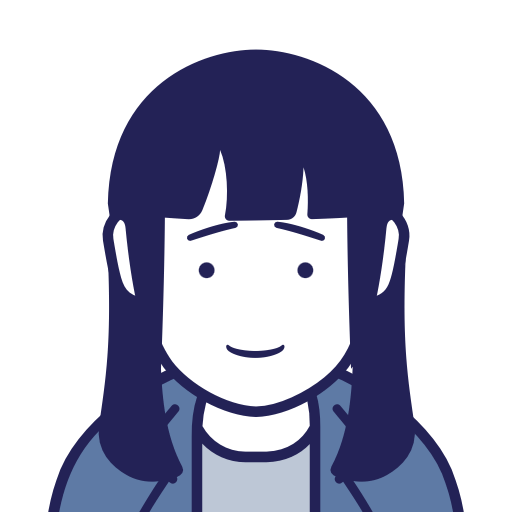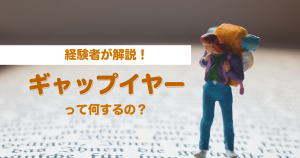近年、教育現場はこれまでにない速度で変化しています。デジタル技術の進展、社会の多様化、子どもたちの価値観の変化などを背景に、教育に求められる役割や方法も大きく変わりつつあります。本記事では、文部科学省の方針や現場の取り組み、そして保護者が知っておくべきポイントを交えながら、2025年現在の教育トレンドを読み解いていきます。
日本の教育政策が目指す方向
2020年代に入り、教育を取り巻く環境は急速に変化しています。文部科学省は、「令和の日本型学校教育」の構築を掲げ、子どもたち一人ひとりに応じた教育を提供することを目指しています。特に、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現が重要視されており、デジタル技術を活用した学習環境の整備が進められています。それでは具体的なトレンドを見ていきましょう。
ICT教育
「個別最適な学び」とは、子ども一人ひとりの個性に応じた学習のことです。指導方法の工夫だけでなく、コンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切に活用することが鍵となります。
また、「個別最適な学び」が孤立した学びになってしまわないよう、子ども同士や、あるいは多様な他者と協働させる、つまり「協働的な学び」を促進させる環境づくりも重要です。
これらの背景にあるのが、GIGAスクール構想です。GIGAスクール構想とは、全国の小学校や中学校の児童・生徒に1人1台のパソコンやタブレットなどの端末を用意し、端末をインターネットへ接続し快適な通信が行える校内LANや無線LANといったネットワーク環境を整備する計画のことです。このように、教育でパソコンやインターネットを活用する環境のことをICT(Information and Communication Technology)環境といい、これを利用した「ICT教育」が近年のトレンドとなっています。
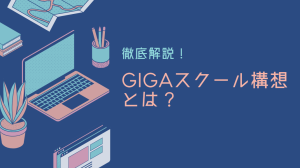
ICTの活用において重要なのは、学習履歴(スタディ・ログ)や生徒指導上のデータを活用することや、教師の負担を軽減することです。1人1台与えられた端末の状況を、教師が把握できる状況でなければ、ICTのメリットを最大限には生かすことができません。一人ひとりの進捗(しんちょく)状況を把握するためによく用いられるのが、「クラウドサービス」と呼ばれるものです。作成物を先生に提出したり、複数人の提出物を一つの画面に表示したりできるプラットフォームで、GoogleやMicrosoft社など、さまざまな機関が開発しています。私の場合は「ロイロノート」と呼ばれるツールを使用していました。クラウドサービスを学校全体で使用することで、連携や共有が簡単にできるようになります。
クラウドサービス以外にも、さまざまなICTツールが学校生活や授業に用いられています。たとえば、大阪府のある小学校の授業では、タイマーを使って話し合いの時間を管理したり、Canvaやスライドでグループの考えを整理して発表する様子が見られます。またある小学校の先生は、丸つけ作業をパソコンやタブレットでできるようになったことで、作業効率を上げることができたそうです。またこの先生は、算数の問題を以前のようなプリントではなく、学習端末にあるデジタルドリルに変更したり、”Kahoot”というクイズ形式で単元を学習するツールを取り入れたことで、子どもの意欲が向上したようです。
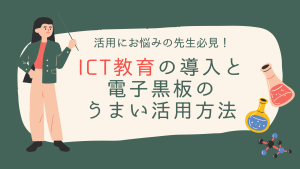


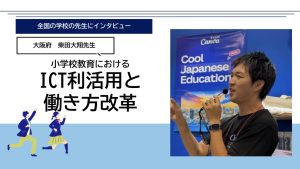
新しいカリキュラム
新学習指導要領の全面実施(小学校は2020年、中学校は2021年)以降、全国の学校ではカリキュラムの見直しが進められています。
たとえば、ある都内の小学校では「探究学習」を中心に据えたカリキュラムを導入し、理科や社会などの教科横断的な学びを実現しています。児童たちは自らテーマを設定し、調査・分析・発表を通じて主体的に学ぶ力を養っています。また、プログラミング教育の必修化を受けて、全国の多くの学校が理科や総合的な学習の時間と連動したプログラミングの授業を設けるようになりました。大学共通テストに「情報」の科目が導入されたことからも、プログラミングが重要視されていることが分かります。
探究学習とプログラミングはどちらも「総合的な学習(探究)の時間」に実施されることになっています。こうした取り組みの背景には、現代社会で求められる力の変化があります。複雑な状況変化の中で、課題を解決し、自己の生き方を考えていくための能力を身につけることが、現代の教育で重視されていることです。
アクティブラーニング
「アクティブラーニング」も、教育トレンドを理解する上で欠かせないキーワードです。アクティブ・ラーニングとは、一方通行の一斉授業とは異なり、グループワークなどで子どもが主体的に学ぶ学習方法です。文部科学省が提唱する「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、アクティブラーニングの手法が全国の学校に広がっています。
たとえば、グループでテーマについて話し合ったり、生徒が課題を発見して解決策を探究するプロジェクト型学習(PBL)、模擬討論やプレゼンテーションなど、生徒が能動的に学びに関わる形式の授業が増加しています。アクティブラーニングによって、単なる知識の習得にとどまらず、課題解決能力やコミュニケーション能力の育成が期待されています。教員の指導力向上の面でも、アクティブラーニングの授業づくりに向けた研修や事例共有の機会が増えています。
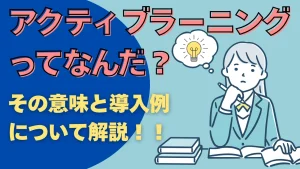
教育の多様化
教育現場では、子どもの個性や多様なニーズに応じた教育手法が広がりを見せています。近年注目されているのが、「アントレプレナーシップ教育」「インクルーシブ教育」「オルタナティブ教育」などの多様なアプローチです。最近トレンドのキーワードを一気に紹介します。
アントレプレナーシップ教育
一言で言うと、起業家精神を育てる教育のこと。ただし、将来起業家にならない人も、自ら社会課題を見つけ、問題解決に向けて取り組むことで、他者との協働により解決策を模索できるようになることを目指します。
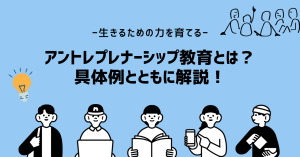
これらの教育手法は、単に知識を伝達するのではなく、「どう学ぶか」「なぜ学ぶか」を重視し、子どもが自己理解や社会とのつながりを深める場として注目されています
ウェルビーイング教育
生徒の幸福や心の健康を大切にした教育のこと。若者が明るい未来を描ける状態を作ることを目指します。
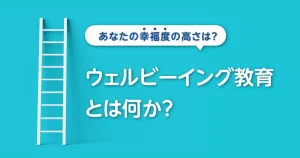
STEAM教育
STEAMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(芸術、リベラルアーツ)、Mathematics(数学)の頭文字を取った言葉。さまざまな分野を横断的に学習し、多様な知識やスキルなどを組み合わせて課題解決をする経験をもたらす教育です。
ギフテッド教育
「ギフテッド(Gifted)」とは、知的能力や創造性、または特定の分野で優れた才能を持つ子どものことを指します。ギフテッド教育は、そのような特定の分野に対して優れた才能を持つ子供への教育です。
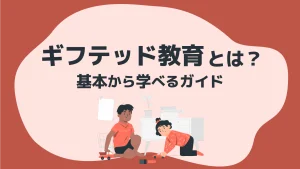
オルタナティブ教育
オルタナティブ教育とは、文科省が定めた学校外での教育機関のことを指す用語です。伝統的な公立学校とは異なる教育理念やカリキュラムを持ち、生徒の個性や興味に応じた柔軟な学びの環境を提供することを目指しています。
シュタイナー教育
オルタナティブ教育の一つで、子どもの個性を尊重する教育法です。発達段階にあわせて「身体」「心」「頭」をバランスよく育てることを目標としています。また、音楽と芸術の2本の柱を大切にしています。
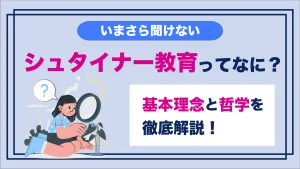
モンテッソーリ教育
オルタナティブ教育の一つで、子どもの自立心を育むことを目的としています。教師や親は子どもの興味を尊重し、子どもが自然に学びたいと感じる環境を整え、その環境での自発的な活動を促します。
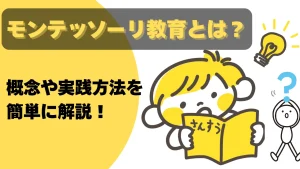
インクルーシブ教育
障害の有無に関わらず、すべての子どもが同じ場でともに学び合うことを目指す教育の考え方です。「特別扱い」するのではなく、誰もがその場に「包み込まれている(inclusive)」状態を作ることが目的です。
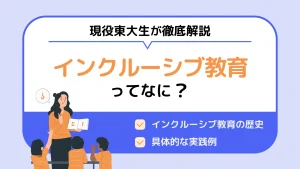
他にも、教育に関するさまざまな考え方が生まれています。これらの教育手法は、単に知識を伝達するのではなく、「どう学ぶか」「なぜ学ぶか」を重視し、子どもが自己理解や社会とのつながりを深める場として注目されています。
おわりに
教育を取り巻くトレンドは、テクノロジーの進化や社会の多様化を背景に、これまで以上に急速に変化しています。こうした動きのなかで、学校や教師、保護者が果たす役割も変化しています。子どもたちが未来の社会で主体的に生き抜く力を育むためには、大人が学び続ける姿勢をもち、教育をともに支えていくことが求められています。本記事が、現場の先生方や保護者の皆さまにとって、今後の教育を考える一助となれば幸いです。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。