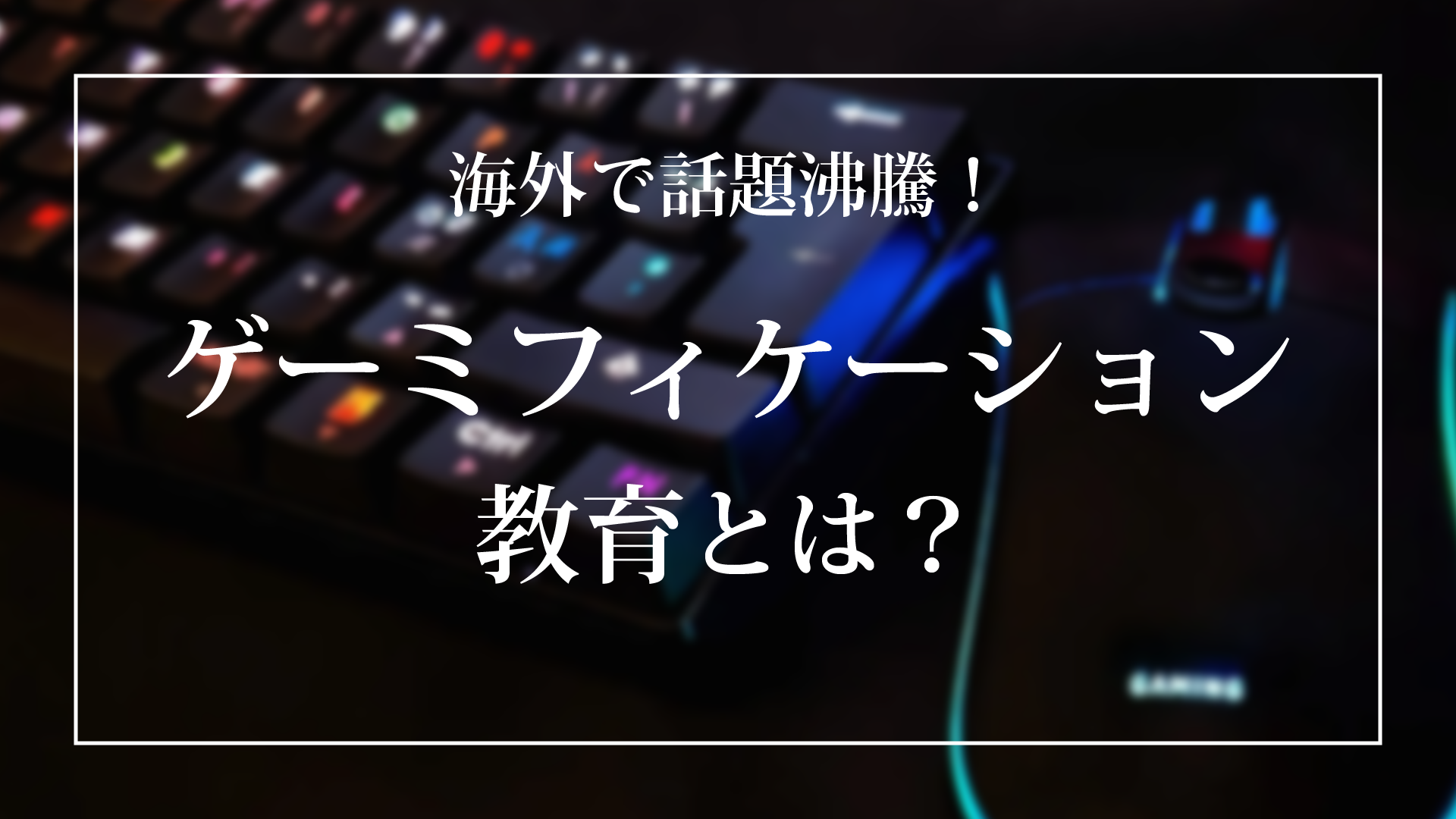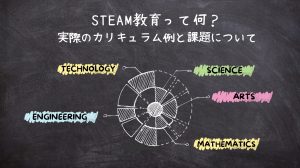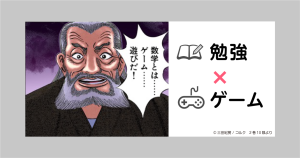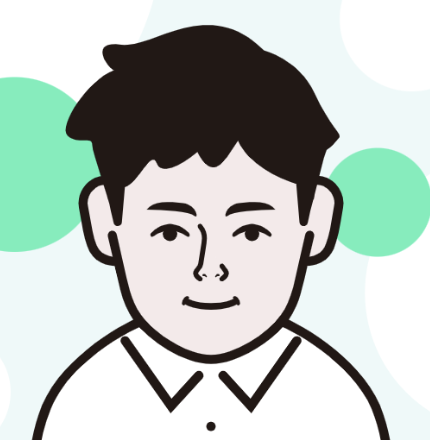ゲーミフィケーション教育という教育法を皆さんはご存知でしょうか?
これは「ゲーム」と「教育」という、一見真逆にも思える二つの考え方を融合させ、教育効果を高める教育方法のことを指します。世界で人気の外国語勉強アプリなどでは、ゲーミフィケーション教育の考え方が非常によく使われています。
本記事では海外でどのようにゲーミフィケーション教育が注目されているのか、使われているのかという点を紹介します。日本での教育にも応用できる考え方やポイントがふんだんに含まれており、役立つこと間違いなしです!
ゲーミフィケーション教育とは何か?
ゲーミフィケーション教育の利点とは?
ゲーミフィケーション教育とは、その名の通りゲームのメカニズムやその要素を教育に応用し、従来の教育よりも学習の質を高める教育手法のことを指します。
その利点としては生徒の勉強・学習に対するモチベーションの向上、また内発的な勉強への興味の芽生えが挙げられます。
実際にこのゲーミフィケーションが生徒の学習結果に良い結果を与えていることを示す研究結果も多く、特に大学生へのSTEM教育について多く研究がなされているそうです。
ゲーミフィケーション教育が着目されている理由
ゲーミフィケーション教育が海外で着目されている理由は主に2つあります。一つ目は生徒の授業への関わり度合いの低下が問題視されていること、二つ目は多くの若者にとってゲームが親和性の高いコンテンツであることです。
既存の一方向的な授業の仕方では、参加意欲が持続できない生徒の問題に対処するために、ゲームの手法を持ち込む授業方法が検討され出したわけです。
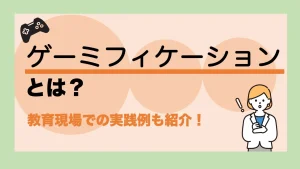
ゲーミフィケーション教育が抱える問題
ゲーミフィケーションを教育に導入する際、最も重要な要素の一つがゲームデザインです。ゲームデザインとは、一言で表すと、勉強をどのようにゲームに落とし込むかということ。それは決して簡単ではなく、いくつかの懸念点が存在します。
勉強内容を正しくゲームに反映できるか
まず、教育内容とゲーム要素の衝突が挙げられます。
例えば、複雑な勉強内容を理解しなければならないにも関わらず、ゲームのルールや目標が複雑だとそちらにも意識を向けなくてはならないため、どちらも中途半端に終わってしまうことがあります。これでは学習の本質から生徒の注意を逸らしてしまいます。
一方で、ゲームの楽しさに重点を置きすぎると、勉強内容を深く理解できなかったり、単純化したために必要な知識を正しく吸収できないことがあります。そのため、ゲームの作成の際には教育目標との整合性を常に考慮する必要があるのです。
モチベーションをなくさないか
次に、生徒のモチベーションを継続させるデザインの難しさです。初期段階ではゲームの目新しさや報酬によってモチベーションが高まるかもしれませんが、時間が経つにつれてその効果は薄れていく可能性があります。単調な繰り返しや、生徒の能力に合わない難易度設定は、かえって学習意欲を低下させる原因となります。生徒一人ひとりの学習進度や興味に合わせたパーソナライズされた体験を提供し、達成感や成長を実感できるようなデザインが求められます。

「やりこみすぎない」ゲームにできるか
そして、過度な競争や依存の誘発も重要な課題です。ゲームは本質的に競争心を煽る傾向があり、生徒によっては過度に勝ち負けにこだわったり、ランキングや報酬に執着することが考えられます。これにより、学習そのものへの興味が薄れ、ゲームの成績を取ることだけが目標となってしまう危険性があります。また、ゲームのシステムが生徒の依存性を高め、そのゲームだけをやり続けてしまう可能性もあります。そのため健全な学習習慣を妨げないような配慮が必要不可欠です。
これらの問題に対処するためには、教育内容とゲーム要素の間の適切なバランスを保つことが極めて重要です。単にゲームの要素を取り入れるだけでなく、それがどのように学習効果を高め、生徒の深い理解や主体的な学びを促進するのかを慎重に検討する必要があります。
参考・出典:Harrow International School Hong Kong, Gamfication – What is it, and How Can it Be Used in Education?

ゲーミフィケーション教育の質を高めるポイント
先ほどゲーミフィケーション教育導入の際の懸念点について解説しましたが、これらの問題に対処するために最も重要なことはゲームデザインを調整することです。この節では実際に海外でゲーミフィケーション調整の際に行うべきポイントについて解説します。

クリア報酬を平等にする
ゲーミフィケーション教育において、クリア報酬を成績上位者のみに限定することは、ゲームのデザイン的には効果的です。しかし教育に当てはめた時には、このゲーミフィケーション教育を行う意味を損なうことになりかねません。
ゲーミフィケーションの本来の目的は、生徒が自ら積極的に学習に参加し、その過程で知識と技能を習得することです。しかし、報酬が一部の生徒にしか与えられないとなると、それ以外の生徒は参加へのモチベーションを失い、学習への意欲が低下する恐れがあります。
全員がそれぞれのペースで学習の恩恵を受け、達成感を育むことが重要です。個々の生徒が自分の成長を実感できるような報酬システムを導入することで、学習への継続的な意欲を促し、自己肯定感を高めることができます。
魅力があり、かつ実用的なクリア報酬を用意する
ゲーミフィケーション教育では、バッジや達成度を通じて生徒が有意義な課題に取り組み、学習レベルを向上させることを促します。このためには魅力的なクリア報酬が不可欠ですが、生徒の関心が学習そのものよりも報酬に移らないよう注意が必要です。
そこで、クリア報酬は、生徒の学習意欲や主体性を高める「学習パス」のようなものにすべきです。
コラム:学習パスとは
学習パスとは、座席の選択権、図書館や校内での座席利用権、特定の授業での作業環境の指定権、共同作業ペアの指定権(同じバッジを持つ生徒からのみ選択可能)など、学習に関連する特権を指します。

ゲームのクリア方法に自由度を持たせる
ゲーミフィケーション教育において、生徒が学びの主体性を獲得するためには、達成したいバッジや実績を自分で選べる機会を作ることが効果的です。これらのバッジや実績を得るために必要な課題は、生徒が興味を持って取り組めるよう、複数の選択肢を提供すべきです。これにより、生徒は自分に最適な学習方法を主体的に探求できます。
例えば、「宿題免除バッジ」の取得を目指す場合、課題の選択肢として読書、動画視聴、特定のスキルの練習などを提示し、生徒自身がリストから取り組む項目を選択できるようにします。
複数の選択肢を用意することで、生徒は自分にとって最も良い選択をし、その選択に対して責任を持つことができるようになります。
参考・出典:Using Gamification to Ignite Student Learning, Edutopia
https://www.edutopia.org/article/using-gamification-ignite-student-learning
海外での実際の活用例
ではゲーミフィケーション教育の実際の導入例をみてみましょう。
ウィンチェスター大学のLim Keong Teoh先生は次のような催しを行ったようです。
ミニオークションを開催
学生の期末試験対策を支援するため、学習をサポートする復習セッションを複数回実施しました。セッションへの参加意欲を高めるため、参加度と成績に基づいてクレジットを獲得できる報酬制度を導入。例えば、各授業への出席だけで50クレジットを獲得でき、週ごとの学習課題を完了すると追加で100クレジットを獲得できました。
さらにオンラインクイズを実施し、得点に応じてポイントを獲得できるようにしました。このポイント報酬制度により、生徒は積極的に参加し、学習課題を完了するよう促されました。
復習セッション終了時、生徒が獲得した全ポイントはトークンに換算されました。このトークンはミニオークションに参加するために使用されました。出版社からの協賛や研究資金を活用し、教科書やその他の有用な物品を賞品として用意しました。
このミニオークションは学生たちの間で大きな盛り上がりを見せました。学生たちはトークンの使い道を慎重に検討し、欲しいアイテムを戦略的に入札する方法を学びました。この活動は楽しいだけでなく、競争の激しい現実のビジネス環境における重要な意思決定スキルを学生に身につけさせるのに役立ちました。多くの学生が「最も楽しい学習体験の一つだった」「復習セッションがより効果的でストレス軽減された」と述べています。
このように、授業への参加や宿題をポイント制にする「ゲームらしさ」と、それを使ってお金の使い方、ビジネススキルを学べる「学習機会」を組み合わせることで、生徒が主体的に考え、学ぶようになるのです。
出典:https://www.timeshighereducation.com/campus/four-ways-use-gamification-engage-your-students-learning
まとめ
ゲーミフィケーション教育が導入されたきっかけである生徒の意欲低下は日本においても存在する大きな問題です。ゲーム大国である日本、生徒とゲーミフィケーション教育の親和性は他国より高いでしょう。
適切なゲームバランスを意識し、日本の学校課程に応用できるゲーミフィケーション教育を導入してみてはいかがでしょうか?
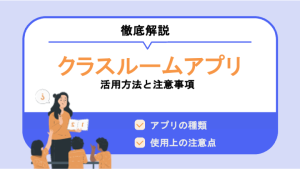
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。