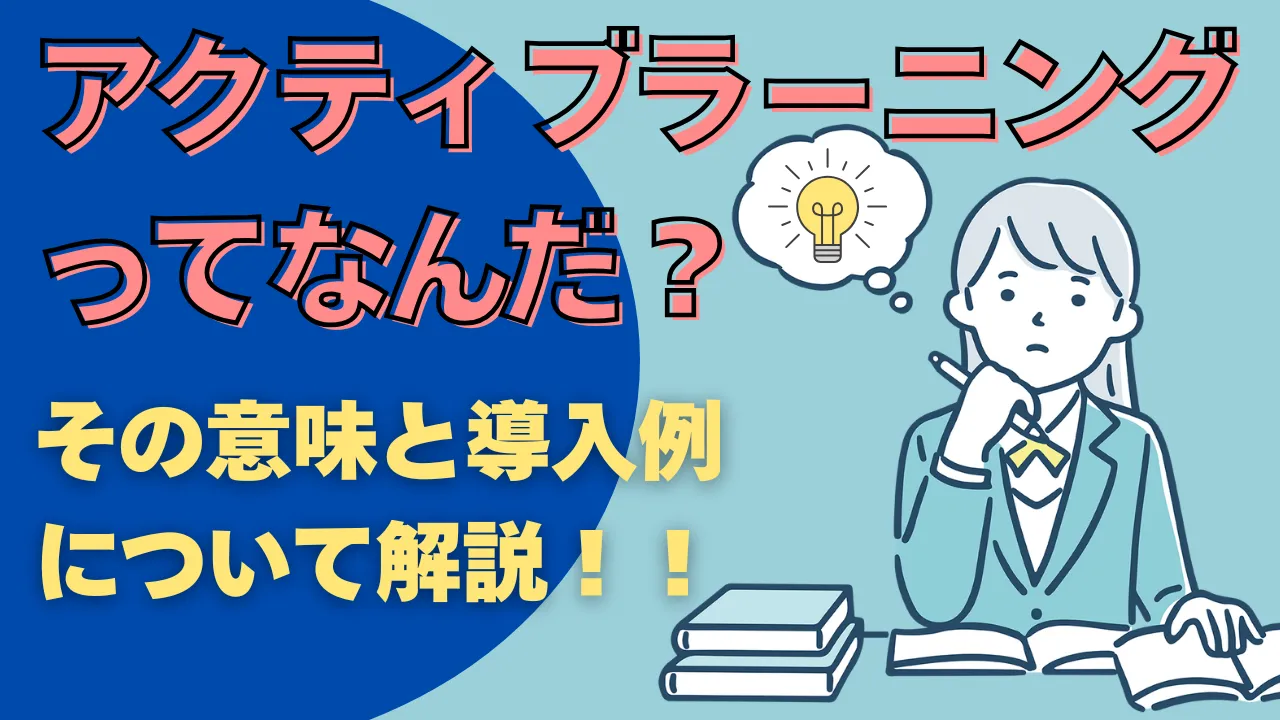みなさん、「アクティブラーニング」という言葉を聞いたことありますか?
アクティブなラーニングだから「積極的に学ぶ」っていうことでしょ! という考えではあなたはアクティブラーニングについて何も理解していない状態です。アクティブラーニングは今後の日本の子どもの教育に必要な概念です。アクティブラーニングは言葉だけ知っていても意味がありません。その中身を知ることが重要です!
この記事ではアクティブラーニングについてを解説し、そもそもアクティブラーニングが日本に導入された背景や実際にどのような方法があるのかを説明していきます!
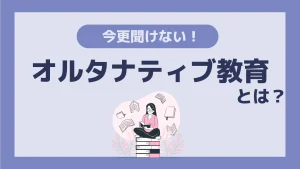
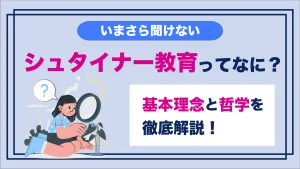
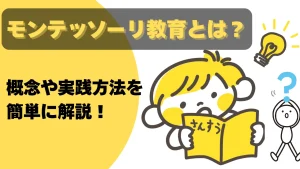
アクティブラーニングとは
児童生徒の能動的な学びを促す教育法!
アクティブラーニングとは、児童生徒が主体的に学びに取り組むことを促す教育法です。従来の講義形式では、教員が一方的に知識を伝えることが主でしたが、アクティブラーニングでは児童生徒が積極的に参加し、学びを深めることが重視されます。この手法により、子どもたちは探求心を育み、自ら問題を解決する力を養うことができます。さらに、アクティブラーニングを通して、児童生徒はコミュニケーション能力や協力する力を身に付け、学校以外の社会でも役立つスキルも自然と習得することができます。
学びの過程で生まれる疑問や好奇心は、児童生徒の内なる知的探求心を刺激し、自発的な学びの持続可能性を支える力となります。アクティブラーニングは、教育手法の枠を外れた、未来の社会における生徒の姿勢や態度を育てる重要な教育手段として位置付けられています。
アクティブラーニングの歴史的背景と必要性について
はじめは大学教育の用語だった!?
実は、アクティブラーニングの始まりは大学教育にありました。
アクティブラーニングという概念は、2012年の「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」中教審答申にて初めて広く認識されました。この答申は、従来の大学講義形式を見直し、学生の能動的な学びを取り入れることで教育の質を向上させることを目的としていました。
生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力を持った人材は、学生からみて受動的な教育の場では育成することができない。従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修(アクティブ・ラーニング)への転換が必要である。(中央教育審議会答申)
この転換は、学生にとっての学びの意義を再確認する機会を提供し、より実践的な知識を得る基盤となりました。アクティブラーニングは、学びの柔軟性を高め、学生が自らの興味を追求するための道筋を提供します。これにより、学生は単なる知識の受け手ではなく、知識の創造者としての役割を果たすことが可能になります。
なぜ子ども教育に取り入れられるようになったのか
現代社会では、少子高齢化やグローバル化、人口減少といった問題が深刻化しています。未来を担う子どもたちがこれらの課題に立ち向かうためには、主体的に問題を発見し、協力して解決する能力が必要です。
アクティブラーニングはこうした力を養うための重要な教育手法であり、時代の要請に応えるための教育改革として位置づけられています。未来の社会では、変化が激しく複雑な状況が予測される中、単に知識を詰め込むだけではなく、知識を実際の問題解決に活かす力が非常に重要です。教育の現場では、児童生徒が新たな課題に対する解決策を模索するための柔軟な学びの環境を整える必要があります。アクティブラーニングは、教育の質を向上させ、児童生徒が未来における社会貢献を実現するためにピッタリの考え方だったというわけです!
アクティブラーニング型授業の種類
アクティブラーニングについて知ることができたところで、次は実際にどのような形式でアクティブラーニングを勧めているのか解説していきます!
①ジグソー法
ジグソー法は、児童生徒が異なる資料を担当し、それぞれが深く学んだ知識をグループ内で共有することで、テーマ全体への理解を深める手法です。生徒は、情報を共有し合いながら協力して課題を解決する力を育むことができる上に、児童生徒は他者の視点を尊重し、異なる考えや意見を受け入れる姿勢を学ぶことができます。ジグソー法はチームワークの重要性を実感する機会を提供し、個々の役割と責任を果たすことの必要性を身をもって体験することができます。児童生徒は、互いの意見を尊重し合いながら、共通の目標に向かって協力する力を養うことができます!
②PBL(Project Based Learning)
PBLは、児童生徒が実際の問題に対し自ら解決策を考え、実践することで能力を養う学習法です。例えば、地域社会の課題をテーマにしたプロジェクトを立ち上げ、児童生徒が現地調査や協力者との対話を通じて解決策を探り、実際に実行することで実践力を養います。児童生徒は単に知識を得るだけでなく、得た知識を応用し、問題を解決するための具体的な行動を起こす力を身につけます。実社会で直面する問題に対するアプローチ方法を学ぶことにより、未来のリーダーとしての資質を持つ生徒を育成することができるのです。
③KP法
KP法は、紙芝居プレゼンテーション(この略でKP)として知られ、事前に内容を紙にまとめ、黒板やホワイトボードに貼り付けて授業を進行する手法です。KP法を通じて、児童生徒は自らの思考を視覚的に表現する方法を学び、情報を体系的に整理する力を養います。この方法は、視覚的な情報を活用することで、聴衆の理解を深め、説得力のあるプレゼンテーション能力が鍛えられます。
ここで紹介したものは単なる一例で、このほかにも様々な方法があります!
アクティブラーニング授業の成功に向けた注意点
この記事をここまで読んでいる皆さんはアクティブラーニングは魅力的だと感じるかもしれません。しかし、アクティブラーニングの導入で失敗している学校も存在します。アクティブラーニング授業を失敗しないためにもいくつか注意しなければならないことがあります。
全ての児童生徒へ配慮する
前提として、アクティブラーニング実現のためには教師や親が児童生徒が安心して意見を交わす場を提供しなければなりません。特に苦手意識を持つ子どもたちを適切にフォローすることが重要です。教師は多様な視点を尊重し、積極的に参加できる環境を整えることで、学びの効果を最大化します。さらに、児童生徒一人ひとりの特性や興味関心に応じた指導を行い、自らのペースで学びを進められるような柔軟なアプローチを取り入れることが求められます。個々の学びのスタイルを尊重することで、児童生徒は自信を持ち、意欲的に学ぶ姿勢を持ち続けることができます。教育の現場での教師や親の配慮は、児童生徒の自らの学びを支える重要な要素と言っても過言ではなく、学びの質を高めるための不可欠な取り組みです。
ICT機器を活用した授業進行の改善
アクティブラーニングはその特性上従来の授業や学習と比べると時間がかかります。したがって時間を節約する工夫が必要になってきます。タブレット端末やデジタルホワイトボードなどのICT機器を活用することで、授業の効率を改善し、時間を節約すると良いでしょう。ICT機器により教室内外での情報共有がスムーズになり、児童生徒は自己学習の機会を広げることができます。さらに、ICTを活用した授業は、デジタルリテラシーを向上させ、児童生徒が未来の社会で求められるスキルを身に付けるための土台を築きます。このようなアプローチは、教育の現場における新たな可能性を広げ、児童生徒が主体的に学びを進めるきっかけを作る重要な要素となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
最初にも書きましたが、アクティブラーニングという言葉だけ知っていても意味がありません。ぜひ導入を検討したり、もっと深く調べてみてください!
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。