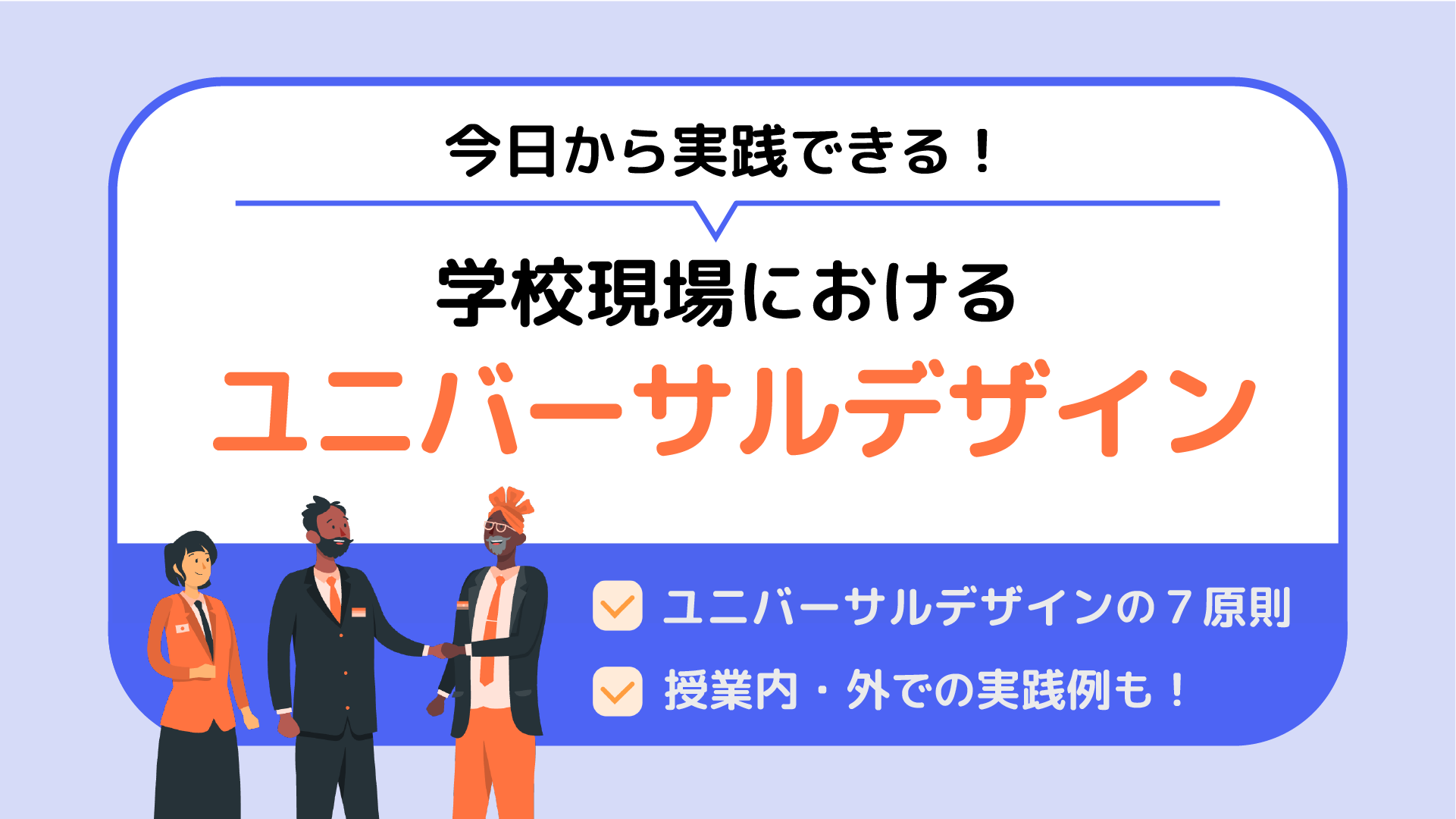最近では耳にすることが多くなった「ユニバーサルデザイン」。ユニバーサルデザインとは、年齢や性別などの多様性に関わらず、誰にとっても使いやすく設計されたデザインのことを指します。学校現場では一体どのような形で受け入れられ、実践されているのでしょうか?
この記事では、学校におけるユニバーサルデザインの重要性と具体的な実践例について詳しく解説していきます。すべての生徒が学びやすい環境づくりのヒントとして、ぜひお役立てください。
ユニバーサルデザインとは何か
ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、文化、能力(身体的・精神的な違いを含む)の多様性に関わらず、誰にとっても使いやすく設計されたデザインのことを指します。特定の障がいを持つ人だけのためではなく、すべての人々のニーズに応えることを目指しています。
例えば、駅のエレベーターやスロープは、車椅子利用者やベビーカー利用者だけでなく、大きな荷物を持っている人や高齢者にとっても非常に便利です。このような設備は、特定の誰かのためだけでなく、多様な人々が公共交通機関を円滑に利用できるようにするための代表的なユニバーサルデザインと言えるでしょう。
ユニバーサルデザインの七原則
ユニバーサルデザインを定義づける上で、ロナルド・メイスによって提唱された以下の7つの原則が重要な指針となります。
1.公平な利用:誰でも分け隔てなく利用できること。
2.利用における柔軟性:さまざまな能力を持つ人が、それぞれのやり方で利用できること。
3.単純で直感的な利用:利用方法が分かりやすく、直感的であること。
4.分かりやすい情報:必要な情報が、誰にでも効果的に伝わること。
5.間違いの許容:誤操作や危険が最小限に抑えられること。
6.少ない身体的負担:少ない労力で効率的に、楽に利用できること。
7.アクセスしやすい広さや空間:適切な広さや空間が確保されており、誰でもアクセスしやすいこと。
これらの原則は、特定の「もの」や「場所」だけでなく、サービスや情報、そして教育の設計においても、すべての人が最大限に能力を発揮できるような環境を創造するための重要な視点を提供します。
(参考:Udit ユニバーサルデザイン7原則, http://www.udit.jp/report/ud_7rules.html)
なぜ今、学校でユニバーサルデザインが必要なのか
なぜ学校教育において、ユニバーサルデザインの視点が必要とされているのでしょうか。それは、学校が多様な子どもたちが集まる場所であり、すべての子どもたちが等しく学び、成長できる環境を提供することが求められているからです。ここでは、学校にユニバーサルデザインが求められるようになった背景を解説していきます。
多様性を尊重する教育環境
現代の学校には、さまざまな背景を持つ子どもたちがいます。身体的な特性、発達の特性、文化的な背景、家庭環境など、一人ひとりが異なる個性を持っています。このように多様な背景を持つ子どもたちが、それぞれの特性に応じて最適な学びを得るためには、画一的な教育ではなく、多様な学び方に対応できる環境が不可欠です。ユニバーサルデザインの視点を取り入れることで、すべての子どもたちが孤立することなく、安心して学びに参加できる環境を整備できます。
ユニバーサルデザインとインクルーシブ教育の関連性
ユニバーサルデザインは、「インクルーシブ教育」の実現と深く関連しています。インクルーシブ教育とは、障がいの有無やその他の特性にかかわらず、すべての子どもたちが同じ場でともに学び、ともに育ち合うことを目指す教育の考え方です。
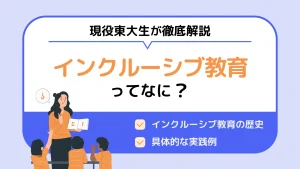
ユニバーサルデザインは、このインクルーシブ教育を推進するための具体的な手段の一つと言えます。例えば、教室のレイアウト、教材の提示方法、教員の指導方法などをユニバーサルデザインの視点から工夫することで、特定の子どもだけでなく、すべての子どもが理解しやすい、参加しやすい学習環境を構築できます。これは、特別な支援が必要な子どもたちを「特別扱い」するのではなく、誰もが自然に学びに参加できる「当たり前」の環境を作り出すことにつながります。
文部科学省も、共生社会の形成に向けて、一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導の充実が求められる中で、インクルーシブ教育システムの構築を目指しており、その中でユニバーサルデザインの視点も重要であると示しています。
参考:文部科学省 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進
学校で実施できるユニバーサルデザインの種類
学校におけるユニバーサルデザインは、物理的な環境だけでなく、情報伝達やコミュニケーションの面でも多岐にわたります。ここでは視覚・聴覚情報と言語情報に分けて紹介します。
視覚・聴覚情報の工夫
学習は主に視覚や聴覚からの情報によって行われるため、これらの情報伝達の工夫は非常に重要です。
掲示物や資料においては、誰にでも読みやすいユニバーサルデザインフォント(UDフォント)を使用することや、色弱の子どもにも識別しやすいよう文字と背景のコントラストを高くすることが推奨されます。また、文字だけでなくイラストやピクトグラムを多く取り入れることで、言語の壁や発達の特性に関わらず理解を促進できます。情報は詰め込みすぎず、箇条書きや太字を活用して視覚的に分かりやすく整理することも大切です。
音声情報については、聴覚に障がいがある子どもに対して手話通訳や要約筆記、あるいはデジタル機器による音声認識字幕などを活用し、情報保障を行うことが考えられます。教員が話す内容をホワイトボードに書き出す、プロジェクターで提示するといった視覚補助具の利用も、音声情報と視覚情報を同時に提供する有効な手段です。
多言語対応
国際化が進む現代社会において、多様な言語背景を持つ子どもたちが学校に在籍する機会が増えています。
学校案内や緊急連絡、イベント案内などを主要な言語に翻訳して掲示・配布する多言語化対応は必須と言えるでしょう。保護者との面談や緊急連絡の際には、翻訳アプリや翻訳サービスを積極的に活用することも効果的です。さらに、必要に応じて子どもの母国語を話せる生活指導員や支援員を配置し、学習や生活のサポートを行うことも検討されます。日本語を母語としない子どもに対しては、平易な言葉遣いである「やさしい日本語」を用いて説明するよう心がけるなど、日常的なコミュニケーションへの配慮も重要です。
授業内での実践例
ユニバーサルデザインの視点は、日々の授業実践においてその真価を発揮します。
授業においては、教科書だけでなく、視覚的な資料(図、写真、動画)、聴覚的な資料(音声、音楽)、触覚的な教材(模型、実物)など、さまざまな感覚に訴えかける教材を用意することで、子どもたちの多様な学習スタイルに対応できます。例えば、さいたま市の小学校では、漢字の学習において、部首のパズルを導入したり、磁石を使った書き順練習を取り入れたりするなど、多角的なアプローチで教材を工夫しています。
参考:さいたま市 ユニバーサルデザインの考えを取り入れた授業ガイドマップ
また、全体一斉の授業だけでなく、少人数でのグループ活動や個別での探求学習を取り入れ、多様な参加形態を認めることも重要です。発表方法についても、口頭発表だけでなく、板書、タブレットでのプレゼンテーション、ジェスチャー、絵など、子どもが表現しやすい方法を選択できるようにすることで、表現の機会を広げます。さらに、課題や活動に与える時間を固定せず、個々の進度や集中力に合わせて柔軟に調整することも、すべての子どもが取り組める授業環境を作る上で不可欠です。
評価においては、テストの点数だけでなく、ポートフォリオ評価、発表、実技、グループでの貢献度など、さまざまな方法で子どもの理解度や努力を多角的に評価することが推奨されます。何を基準に評価するのかを事前に明確に伝えることで、子どもが目標を持って学習に取り組めるようになります。
授業外(給食・掃除など)での実践例
ユニバーサルデザインの視点は、授業以外でも学校生活のあらゆる場面に適用できます。給食の時間では、アレルギーを持つ子どもに対して具体的な成分表示を明確にし、代替食の提供や個別対応を徹底することは基本です。また、車椅子の子どもや手が不自由な子どもでも安全に配膳できるよう、配膳台の高さや動線を工夫することも大切です。
足立区の小中学校では、食物アレルギーを持つ児童生徒のために「アレルギー対応献立表」を配布し、保護者との綿密な連携を図っています。さらに、落ち着いて食事ができるよう、過度な刺激を避けた空間づくりや、必要に応じて個別スペースの確保を検討することも、すべての児童生徒が安心して給食を楽しめる環境につながります。
(参考:足立区「学校教育教育におけるユニバーサルデザインの活用」, https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-sienkanri/universaledu.html)
清掃活動においては、子どもたちの身体能力や特性に応じて、清掃場所や担当を柔軟に割り当てることが求められます。重いものを運ぶ作業を避けたり、特定の箇所を重点的に行うなど、無理のない分担を心がけましょう。また、持ちやすく、負担の少ない清掃用具を選定することも、すべての子どもが参加しやすい環境を作ります。清掃の手順や注意点を、視覚的な情報(写真、イラスト)を交えて具体的に示すことも、理解を助ける上で有効です。
施設・設備の改善も不可欠です。昇降口の段差解消のためにスロープの設置やエレベーターの導入を進めることは、車椅子利用者だけでなく、ベビーカーやけがをした子どもなど、誰もがスムーズに移動できる動線を確保するために重要です。藤枝市では、学校施設のバリアフリー化計画に基づき、スロープ設置やトイレの改修などを進めています。[6]また、車椅子対応の広いスペースや、オストメイト対応設備、おむつ交換台などを備えた多目的トイレの設置も必要不可欠です。教室名や案内表示を、大きな文字やピクトグラムで表示し、視認性を高めることも、特に視覚に課題がある子どもにとって大きな助けとなります。触覚点字や音声案内なども有効な手段として考えられます。
参考:藤枝市 ユニバーサルデザインにつながる「学校環境の整備」
まとめ
「この〈私〉は、もしかしたら他の誰かなのかもしれない」
という哲学者、永井均氏の言葉があります。私たちは他者と接する際、無意識のうちに相手を「私にとっての客観的存在」として捉えがちです。しかし、永井氏が示唆するように、私たちの「〈私〉」が、他の誰かであった可能性は常に存在します。
身体的、あるいは内面的な特徴において、自分とは異なる相手に対して、私たちはしばしば「あの人は自分とは違う」「助けてあげなければ」といった、無意識の区別や優劣の感覚を抱いてしまうことがあります。しかし、その考えは本当に正しいのでしょうか。それぞれの違いに優劣はなく、表面化していないだけで私たち自身もまた、得意なことや苦手なことを持ち合わせているはずですし、その違いに目を向けずにただ他者に対して区別を行うことは、傲慢であると言えるかもしれません。永井氏の言葉を借りれば、「自分は他人であり、他人は自分である」という視点に立つことで、相手も自分もそれぞれに得意や不得意があり、多様な違いが存在する、と自然に解釈できます。
そして、そのような多角的な視点を持つ子どもたちを育むために、対話ではなく区別を先に持ち出してしまわないように、本記事でご紹介したようなユニバーサルデザインの教育を、学校側が率先して実践していく必要があるのではないでしょうか。子どもたちは皆、無限の可能性を秘めています。一人ひとりの個性を最大限に伸ばし、誰もが尊重される社会を築くために、教育におけるユニバーサルデザインの重要性はますます高まっています。読者の皆様も、この教育のあり方にぜひ興味を持っていただければ幸いです。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。