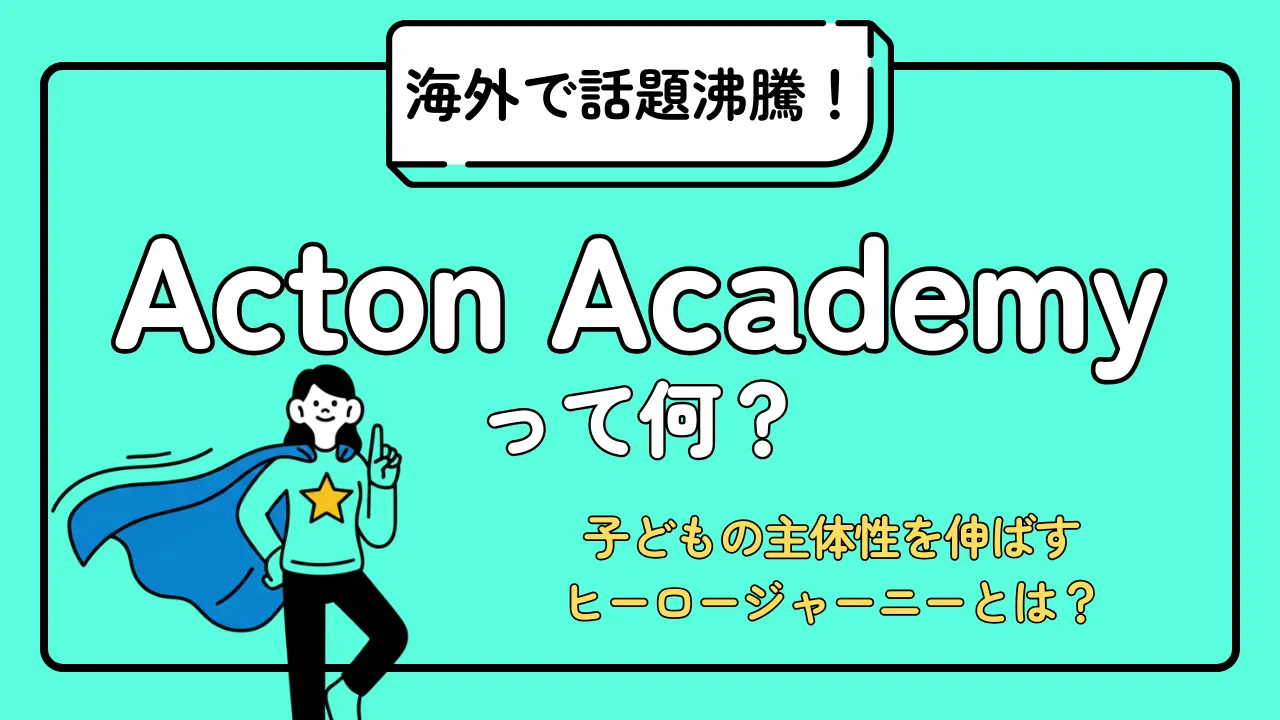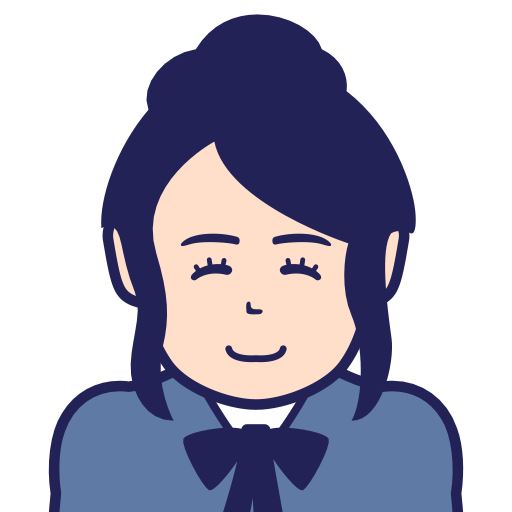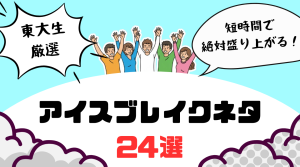現代の日本の教育現場は、学習指導要領の改訂、「GIGAスクール構想」の推進、そして「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)」の重視など、大きな変革の渦中にあります。このような状況の中で、世界中の教育者から熱い視線を集めているのが、アメリカ発の革新的な教育モデル「アクトン・アカデミー」です。
本記事では、このアクトン・アカデミーの理念と実践を、日本の教育関係者の皆様にとって興味深いであろう視点から深掘りし、これからの日本の教育のあり方を考える上でのヒントを探ります。
アクトン・アカデミーとは?――「教えない」学校の衝撃
アクトン・アカデミーは、2009年にアメリカのテキサス州で設立されたマイクロスクール(小規模な私塾)です。その最大の特徴は、従来の「教師が教え、生徒が聞く」というスタイルを完全に覆した「学習者主導の学び」にあります。今回はそのうち4つを抜粋して紹介します。
ヒーローズ・ジャーニー(英雄の旅)
生徒たちは「イーグル(鷲)」と呼ばれ、自らを物語の主人公と捉えます。彼らは自らの目標を設定し、困難を乗り越えながら成長していく「英雄の旅」を歩みます。この物語のフレームワークが、内発的なモチベーションと探究心、そして失敗から学ぶ強靭な精神力を育みます。
ソクラテス式問答法
ここには「先生」は存在せず、「ガイド」と呼ばれる大人がいます。ガイドの役割は答えを教えることではなく、ソクラテス式の対話を用いて生徒たちの思考を深め、彼らが自ら答えを見つけ出す手助けをすることです。
実社会と連動したプロジェクト
学びの多くは、実社会の問題解決に繋がるプロジェクトベースで進められます。子どもたちはチームを組み、企画立案から実行、そして成果発表までを自律的に行います。時には地域の企業と連携した徒弟制度(アプレンティスシップ)を通じて、リアルな職業体験を積むこともあります。
異年齢の「スタジオ」
アクトン・アカデミーでは、学年別のクラスではなく、様々な年齢の子どもたちが集う「スタジオ」と呼ばれるコミュニティで学びます。年長者は年少者のロールモデルとなり、教えることを通じて自らの学びを深めるなど、自然な協働学習が生まれます。
アクトン・アカデミーのここが面白い!
このユニークな教育モデルは、奇しくも、日本の教育が現在目指している方向性と驚くほど強く共鳴します。しかし同時に、その「徹底した」やり方ゆえに、私たちの既存の教育観に対して大きな問いを投げかけるのです。
文科省が掲げる「生きる力」と「探究学習」の究極形
文部科学省が長年推進してきた「生きる力」、そして新しい学習指導要領の最大の柱である「探究学習」。アクトン・アカデミーの教育は、まさにこれらの理念を、妥協なくシステムとして具現化したものと言えるでしょう。
「生きる力」とは、「確かな学力(知識・技能、思考力・判断力・表現力)」と「豊かな人間性」「健康・体力」の3要素で構成されます。アクトン・アカデミーは、これらを以下のように育みます。
- 確かな学力(知識・技能):
生徒は「コアスキル」の時間に、アダプティブ・ラーニング(個別最適化学習)が可能なオンラインツールを使い、自分自身のペースで読み書き計算や基礎知識を習得します。ここでは「知識の伝達」をテクノロジーに任せ、効率的に基礎を固めます。 - 確かな学力(思考力・判断力・表現力):
「生きる力」の核とも言えるこの能力は、日々の「ソクラテス的問答」と、数週間単位で取り組む「プロジェクト(Quest)」によって徹底的に鍛えられます。生徒たちは自ら問いを立て、情報を収集・分析し、他者と協働しながら答えを探求していきます。重要なのは、知識を「知っている」ことではなく、それを「どう使うか」です。 - 豊かな人間性(学びに向かう力):
アクトンの根幹にある「英雄の旅(Hero’s Journey)」の考え方そのものが、生徒の内発的動機(学びに向かう力)を刺激します。生徒は自らスタジオ(教室)のルールを作り、「契約(Contract)」を結び、コミュニティの一員として責任を果たします。
「やらされる探究」ではない、「本物の探究」
特に注目すべきは「探究学習」との親和性です。
日本の多くの学校現場では、「探究」の時間が設けられながらも、「何をテーマにすればいいか分からない」「どう評価すればいいか難しい」「結局は調べ学習で終わってしまう」といった課題に直面しがちです。
しかしアクトン・アカデミーでは、「探究(プロジェクト)」こそが学習のメインディッシュです。生徒たちは、単なる調べ学習ではなく、「起業家としてビジネスプランを立案し、実際に商品を販売する」「地域の歴史家としてドキュメンタリー映像を制作する」「エンジニアとしてロボットを設計し、競技会に参加する」といった、実社会と地続きの「本物の課題」に挑みます。
このプロセスは、知識の習得にとどまりません。予算管理、チーム内の対立、予期せぬトラブルといった生々しい困難に直面し、それを乗り越える体験そのものが、変化の激しい社会を生き抜くための実践的なスキル育成に直結しています。
アクトン・アカデミーの学びは、日本の教育が理念として掲げる「生徒主体の学び」や「探究学習」が、もし既存の枠組みや評価の制約から一切解放されたとしたら、どのような形を取り得るのか——その一つの「究極形」を示していると言えるでしょう。
文科省が掲げる「生きる力」と「探究学習」の究極形
文部科学省が長年推進してきた「生きる力」、そして新しい学習指導要領の柱である「探究学習」。アクトン・アカデミーの教育は、まさにこれらの理念を具現化したものと言えるでしょう。生徒たちは自ら問いを立て、情報を収集・分析し、他者と協働しながら答えを探求していきます。このプロセスは、知識の習得にとどまらない、変化の激しい社会を生き抜くための実践的なスキルの育成に直結します。
日本のアクトン・アカデミーが抱える3つの課題
一方で、アクトン・アカデミーの在り方は、その革新性ゆえに、日本の現在の教育システムにいくつかの根源的な問いを突きつけます。既存の枠組みの中で、このモデルはどのように機能し得るのでしょうか。
「知の探究」は「受験」を突破できるか
保護者や教育関係者が最も懸念する点、それは「大学受験との両立」かもしれません。
アクトン・アカデミーには、定期テストや偏差値といった、日本の教育現場における画一的な評価尺度は存在しません。学習の進捗は、個々の進度に合わせて設計された独自のオンラインツールや、自らの学びの成果をまとめたポートフォリオ、そしてプロジェクトの成果発表(Exhibition)によって測られます。
しかし、日本の大学入試、特に一般選抜は、依然として広範な知識の正確な暗記と、ペーパーテストにおける高い得点力を要求します。アクトンで培われる「探究心」「自ら学ぶ力」「プロジェクト実行力」といった非認知能力は、既存の入試システム、特にマークシート式の共通テストや各大学の個別学力検査と、どのように接続できるのでしょうか。
この点において、アクトンの学びは、知識の詰め込みを主眼とする一般選抜よりも、むしろ総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜において強力な武器となる可能性があります。自らの「英雄の旅」を通じて得た深い洞察や、社会課題に取り組んだ経験、そしてそれらを論理的に説明し、説得する能力は、面接や小論文において他の受験生との明確な差別化要因となり得ます。
とはいえ、基礎学力の担保や受験テクニックの習得をどうするか、という課題は残ります。アクトン・モデルを導入するスクールが、日本の入試制度とどう向き合い、どのような「解」を用意するのか。あるいは、「大学全入時代」において、既存の入試を突破すること自体を学びのゴールとしないという、新たな価値観を提示するのか。これは、日本版アクトンが直面する大きな岐路です。
「個の尊重」は「和」を乱すか
アクトン・アカデミーの教育哲学の核には、「英雄の旅(Hero’s Journey)」という概念があります。これは、生徒一人ひとりが自らの情熱を見出し、困難に立ち向かい、独自の道を切り拓いていくプロセスを尊重するものです。このアメリカ発の「個」を最大限に重視する文化は、集団の「和」を重んじる日本の風土と相性が悪いように思えるかもしれません。
日本社会において「和」はしばしば、「同調圧力」や「出る杭は打たれる」といった形で、個性の発揮を抑制する方向に働くことがあります。アクトンのような環境は、ともすれば「自分勝手」や「協調性がない」と見なされるのではないか、という懸念です。
しかし、草稿で指摘されている通り、真の協調性とは、単に他者に合わせる「同調」ではなく、自立した「個」と「個」が、互いの違いを認識し、尊重し合った上で協力関係を築くことではないでしょうか。
アクトン・アカデミーでは、個の探究と並行して、「ソクラテス的問答(Socratic Discussion)」が日常的に行われます。これは、生徒同士が対等な立場で本質的な問いについて意見を交わし、互いの考えを深く掘り下げるプロセスです。ここでは、他者の意見に耳を傾ける傾聴力と、自らの考えを明確に伝える表現力の両方が鍛えられます。個の確立と協働スキルの育成は、アクトン・モデルにおいて表裏一体なのです。日本の「和」の文化も、こうした「自立した個の協働」という形で、より成熟したステージへと進化できる可能性を秘めています。
「教える教師」から「問うガイド」へ:最大の壁は教育者の変革
アクトン・モデルが日本で普及する上で、最も大きく、そして最も困難な挑戦は、教育者自身の役割変革かもしれません。
日本の教師は伝統的に、学習指導要領に基づき、クラス全員に等しく知識を伝達する「ティーチャー(Teacher)」としての役割を強く求められてきました。しかし、アクトン・アカデミーに「ティーチャー」は存在しません。そこにいるのは「ガイド(Guide)」です。
ガイドの役割は、知識を教え込むことではありません。生徒の学びを促進する「ファシリテーター」であり、彼らの探究を見守り、本質的な「問い」を投げかける伴走者です。これは、「教えない」という勇気と、生徒が自ら答えを見つけるまで「待つ」忍耐力を必要とします。
この変革は、単なるスキルの習得を超えた、教育観そのものの根本的な転換(マインドセット・シフト)を要求します。生徒一人ひとりの興味や進捗を正確に把握し、適切なタイミングで、答えを教えるのではなく、さらなる思考を促す「良い問い」を投げかける。これは、従来の教授法とは全く異なる、高度な専門性です。
日本の教師がこの「ガイド」へと変わるためには、継続的な専門的トレーニングと、教師自身が学び合い、支え合うコミュニティが不可欠です。これは容易な道ではありませんが、もし実現すれば、教師は「知識の伝達者」という重圧から解放され、生徒一人ひとりの「英雄の旅」に伴走するという、より創造的で本質的な喜びに満ちた役割を担うことになるでしょう。
ActonAcademy修了者の声
実際にアクトン・アカデミーを修了した生徒は、何を学びどう過ごしていたのでしょうか。
創設者である両親のもと、小学校から高校までをアクトン・アカデミーで過ごしたチャーリーとサム・サンデファーの言葉は、机上の空論ではない、実践から生まれた力強い示唆に満ちています。
「失敗は最高の学び」恐れを乗り越える力を育む
「アクトン・アカデミーで最も価値があったのは、”失敗を奨励される”ことでした。」 兄のチャーリー氏は、インタビューでこう断言します。従来の学校が成績を重視し、失敗を避ける文化であるのに対し、アクトンでは「早く、安く、頻繁に失敗すること」が奨励されます。プロジェクトベースの学習では、大人が答えを教えないため、生徒は何度も壁にぶつかり、間違いを犯します。
「失敗することで、精神的な強さと回復力が身につきます。それは現実世界で本当に重要なスキルです」。 この文化は、生徒が自らの限界に挑戦し、たとえ失敗してもそこから学び、再び立ち上がる強さを育む土壌となっているのです。
天職は探すものではなく、”創り出す”もの
弟のサム氏は、アクトン・アカデミーが「自分自身を深く知る機会を与えてくれた」と語ります。その中心にあるのが、実社会の現場で働く「アプレンティスシップ(徒弟制度)」です。
彼は元々、大好きな自動車整備士を目指していました。しかし、実際に自動車整備工場で働いてみると、「何かが違う」と感じます。そこから彼の探求は始まりました。機械工学、製造業のコンサルティング、そしてついにはSpaceXでの短期インターンシップへと、興味の赴くままに挑戦を続けたのです。
「もし最初の一歩を踏み出す機会がなければ、僕は今でも自動車整備士が夢だと信じ込んでいたでしょう。様々な経験を通して、自分が本当に情熱を注げるのは、製造業のオペレーション分野だと気づくことができました」。 アクトン・アカデミーは、生徒が自らの興味を実際の経験に繋げ、試行錯誤の中から「天職(Calling)」を見つけ出すための冒険の場を提供します。
https://www.ealingtimes.co.uk/news/25392559.level-3-strong-set-results-ark-acton-academy
教育の未来を映し出す「鏡」として
アクトン・アカデミーのモデルを、そのまま日本に導入することが正解だというわけではありません。しかし、その革新的な理念と実践は、私たち日本の教育関係者にとって、自らの教育観を問い直し、これからの教育のあり方を再考するための「鏡」となり得ます。
- 子どもたちが本来持っている「学びたい」という情熱を、どうすれば最大限に引き出せるのか?
- テストの点数では測れない「非認知能力」を、日々の教育活動の中でどう育んでいけば良いのか?
- これからの社会で本当に必要とされる力とは何か?
アクトン・アカデミーという「鏡」を通して、私たち自身の教育現場を改めて見つめ直すこと。それこそが、日本の未来を担う子どもたちのために、私たちが今始めるべき最も重要な対話なのかもしれません。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。