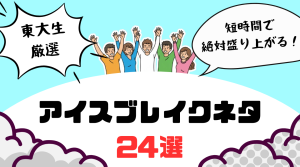コロナ禍やAIの広がりなどさまざまなことが起き時代の大きな変換点とも言われてる昨今。そんな中で教育現場でも大きな変化が起きるのは当然です。今、「オルタナティブ教育」という新たな教育スタイルが注目されています。
そんなオルタナティブスクールについての特徴や種類、メリットやデメリットまで詳しくお届けします。
オルタナティブ教育の特徴
オルタナティブ教育とは、文科省が定めた学校外での教育機関のことを指す用語です。伝統的な公立学校とは異なる教育理念やカリキュラムを持ち、生徒の個性や興味に応じた柔軟な学びの環境を提供することを目指しています。
独自の教育理念があることは、保護者と子どもが学校を選ぶ際の一つの大きな指標になります。理念に共感できることで、スクールと保護者、子どもの間で同じ目標に向けてまっすぐに頑張ることができます。
オルタナティブ教育の種類
さて、その学びの性質上、オルタナティブスクールにはさまざまな種類があります。世界ではどのようなオルタナティブ教育が行われているのでしょうか。代表的な例をいくつか紹介します。
シュタイナー教育
シュタイナー教育は、1900年代初頭のヨーロッパで「子ども自身のための教育」という観点から生まれたオルタナティブ教育の代表格です。国家のための教育ではなく、「社会の中で自分らしい人生を生きられる人間を育てる」ことを目指しています。ルドルフ・シュタイナーが提唱したこの教育法は、子どもの発達段階(7年周期)に合わせたカリキュラムが特徴で、「自由への教育」を掲げています。
例えば1〜8年生は一人の担任が持ち上がり、詩・歌・リズムなど芸術的要素を取り入れた授業で感覚を全開にして学びます。点数評価ではなく文章による評価を行い、知識の暗記ではなく感情と結びついた体験として学びを深めていきます。1919年に始まったシュタイナー学校は、現在では世界に1200校以上広がり、日本にも7校が登録されている国際的な教育運動です。
モンテッソーリ教育
モンテッソーリ教育は、イタリアの医師マリア・モンテッソーリによって20世紀初頭に考案されたオルタナティブ教育の一つです。子どもには「自己教育力」が備わっているという前提にたち、子供が自らの興味や発達段階に合わせて自由に活動できる環境を整え、自発的な学びを促進します。その特徴として、異なる年齢の子供が一緒に学ぶ「縦割りクラス編成」や、子供の発達段階に合わせた専用教具の使用があります。子供が活動を自由に選び、自分のペースで集中して取り組める環境を重視し、自立していて、責任感と他人への思いやりがある人間を育てることを目的にしています。
モンテッソーリ教育は、子どもの自発性と環境の重要性を強調する点で、芸術的な教育を重視するシュタイナー教育とは異なるアプローチをとっており、世界中の多くの教育機関で採用されています。
イエナプラン教育
イエナプラン教育は、子どもたちが「ともに生きることを学ぶ」環境を重視したオルタナティブ教育です。その最大の特徴は、異なる学年の子どもたちが一緒に学ぶ「異年齢グループ」での学習形態にあります。このグループでは、年上の子が年下の子を教え、子どもたちがお互いから学びあう関係性を大切にしています。
カリキュラムでは「ワールドオリエンテーション」という科目横断的な探求学習を通して、実生活と結びついた学びを展開します。子どもたちは自然や社会について自ら問いを立て調査し、発表する活動を通して知識を深めていきます。
イエナプラン教育では、教師は子どもたちの学びのコーチや並走者としての役割を担います。自分で考えて判断し、行動できる人間を育てるという理念のもと、教育機関を運営しています。
オルタナティブ教育のメリット
このようなオルタナティブ教育には、次のようなメリットが挙げられます。
少人数制で手厚い教育を受けられる
多くのオルタナティブスクールではその特性上、少人数の学校が多く、一人の生徒に対して一般校よりも手厚い指導シュタイナー学校では8年間同じ担任が持ち上がることもあり、子どもの個性や特性を深く理解した上での指導が可能になります。
モンテッソーリ教育では、子どもの「自己教育力」を引き出すための細かな観察と環境作りが行われ、オルタナティブ教育では一人一人の個性に合わせた成長を促すような手厚い教育が受けられます。
自主性・個性を伸ばせる
オルタナティブ教育では子どもを「教育される対象」ではなく「自ら育つ主体」と捉え、内発的な学びを大切にします。自分で考え、選択し、行動する機会が豊富に用意されているため、自主性や創造性が自然と育まれます。また、一人ひとりの個性や関心を尊重する教育方針により、自分のペースで得意分野を伸ばせる環境が整っています。このような環境があることで、子どもたちは「与えられたものをこなす勉強」から、「自分で考え責任を持ちながら前向きに取り組む勉強」の姿勢を育てられるのがオルタナティブ教育のメリットです。
オルタナティブ教育のデメリット
選択肢が限られる
日本ではオルタナティブスクールの数はまだ限られており、地域によっては通学可能な学校がないケースも多いです。特に地方では選択肢は非常に少なく、一言にオルタナティブスクールと言ってもその種類は千差万別である以上、オルタナティブ教育を受けるために引っ越しを検討する家庭もあります。
現在オンラインで受けられるオルタナティブスクールもありますが、その数はまだまだ少ないです。
学費が高い
多くのオルタナティブスクールは私立や学校法人として運営されており、公立校と比べて学費が高額になります。年間50万円から100万円以上かかる学校も珍しくなく、教育の選択肢が経済状況によって左右されることは大きな課題です。
単位として認められないことがある
学校教育法に基づかない教育施設の場合、その学びが公的に認められないケースがあります。高校卒業資格が得られない場合は、高等学校卒業程度認定試験の受験が必要になることも。進学や就学の際に、一般的な学歴と異なる経歴が不利に働く可能性も考慮する必要があります。
一般校との違い
カリキュラムの柔軟性
一般校が学習指導要領にそった統一的なカリキュラムを展開するのに対し、オルタナティブスクールでは柔軟な教育内容を提供できます。季節の行事や子供の関心に合わせた学びの展開、教科の枠をこえた総合的な探求活動など、生きた知識を獲得するための工夫が凝らされています。
評価方法の違い
一般校では定期テストや通知表による数値評価が主流ですが、オルタナティブ教育では異なるアプローチを取ります。テストの点数ではなく、子どもの成長プロセスや理解度を文章で丁寧に記述する評価方法や、子ども自身による振り返りと自己評価を重視するなど、多角的な視点から子供の成長を促せるようにしています。
フリースクールとも異なる
オルタナティブスクールと混同しやすいのが「フリースクール」。フリースクールが主に不登校の子どもたちの居場所としての側面が強いのに対し、オルタナティブスクールは確立された教育哲学と体系的なカリキュラムに基づいて運営されています。「子供の自由」を尊重しつつも、計画的・意図的な教育活動を通して子供の成長を支援する点が特徴です。
まとめ
オルタナティブ教育、いかがだったでしょうか?今までは大学受験を巡って熾烈(しれつ)な争いが行われていましたが、最近では少子化の影響で定員に達しない大学も存在しています。そのような状況では大学の在り方の多様化が生じ、入試制度の変化も起きています。実際、文科省の調べでは推薦入試とAO入試経由の入学者の割合の合計は、一般入試のものと同等というデータも出ています。
そのような状況の中で、今まで通りの「詰め込み型」授業からの変革が求められているのではないでしょうか。教育機関ではGIGAスクール構想やアクティブラーニングといった学習法を取り入れるなどしています。同時にこのような背景がオルタナティブ教育の広まりを後押ししているのかもしれません。
一人ひとりが選択をできる自由があるからこそ、今一度子どもの、自分の在り方を考えてみてもいいのではないでしょうか。
スクールによって特色がさまざまなので、事前に学校の見学などを通して検討してみましょう!
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。