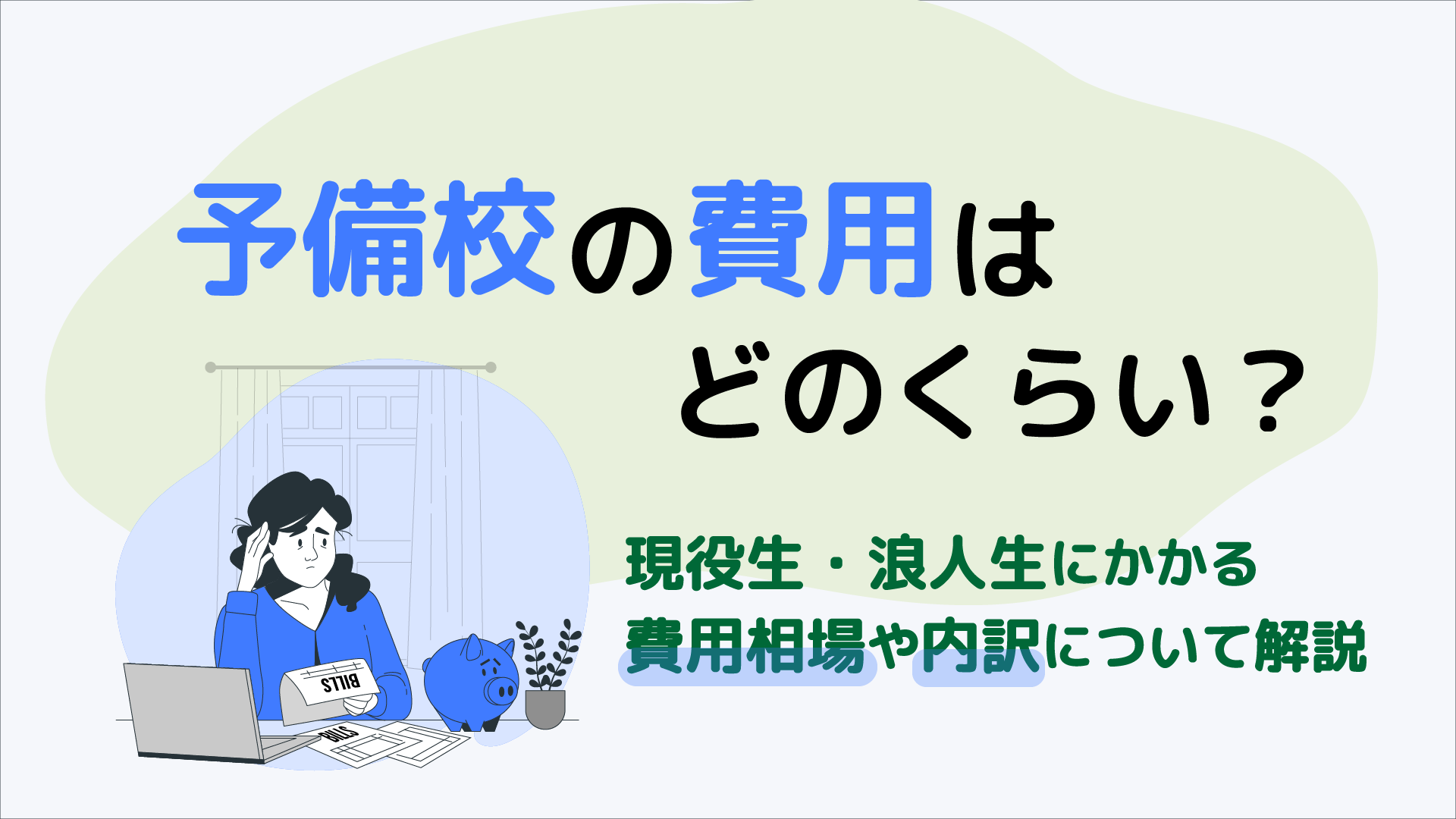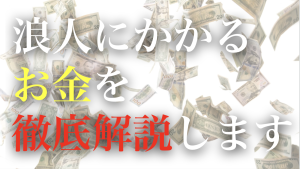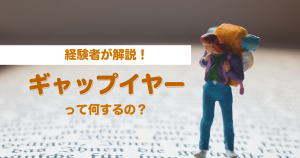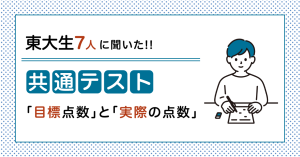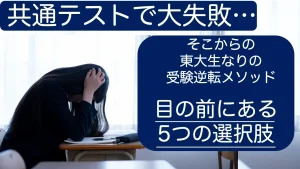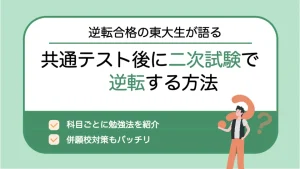大学受験を控えるとまず気になるのが「どの予備校に通うか」という点ですが、その際に大きな要素となるのが予備校にかかる費用ではないでしょうか。
実際にいくらぐらい準備しておけば良いのか、いつ頃支払いが発生するのかなど、事前に知っておくだけで心の準備ができるはずです。特に、浪人生の方は現役生よりも長期間にわたって予備校を利用するケースが多く、結果的に高額になることも少なくありません。
ここでは、予備校費用の相場や内訳、そして費用を抑えるための方法までを幅広く解説します。
予備校費用の年間でかかる金額相場
予備校に通う場合、現役生と浪人生とでは通う期間や受講する講座数が異なるため、年間でかかる金額相場にも差が生じます。それぞれの立場によって、どの程度の費用がかかるのかを把握しておくと、早めに予算計画を立てやすくなるでしょう。
現役生の場合
現役生は学校の授業や部活動と両立しながら予備校に通うため、通常は必要最低限のコースだけを受講する方が多いようです。その結果、年間の費用相場としてはおおよそ50~80万円程度になることが一般的です。
ただし、苦手科目の補強や志望校対策の講座を追加受講すると、費用はさらに上乗せされます。夏期講習や冬期講習といった季節講習を集中的に受けるかどうかによっても、最終的な支払額は変動します。
浪人生の場合
浪人生の場合は、年度の始めから予備校にフルタイムで通う形が多いため、より高額な費用が必要になります。年間で100万円以上かかることも珍しくなく、上位大学を目指すコースや個別指導を加えると、さらに高額になるケースもあります。
予備校に通いながらアルバイトをする人もいますが、学習時間の確保や生活リズムとの兼ね合いを考えると、予備校費用だけではなく家計全体の計画をしっかり立てることが重要です。
予備校費用の内訳
「予備校費用が高い」と漠然と感じていても、実際の内訳を把握してみると、どこにお金がかかっているのかが見えてきます。
入会金や授業料、さらにはテキスト代や模試費用など、思いのほか細かな出費が重なることもあるので注意が必要です。
入会金
予備校に初めて入学する際に求められるのが入会金です。大手予備校の場合、2万円〜8万円程度と幅がありますが、早期申込やキャンペーンの適用で割引になることもあります。
授業料
授業料は、受講する科目数やクラスのレベルによって異なります。現役生向けの週末コース、浪人生向けの通年コースなど、コース内容が豊富であるほど選択肢も増えますが、そのぶん費用も変動します。全科目をフルカバーするコースを選ぶと高額になりやすく、必要な科目だけを選択して受講すると比較的費用を抑えられるでしょう。
テキスト・教材費
授業で使用するテキストや問題集、映像教材などにかかる費用も見逃せません。最初にまとめてテキスト代を支払う場合もあれば、季節講習ごとに追加テキストの購入が必要になる場合もあります。1冊あたり数千円〜数万円単位でかかることがあるので、どのくらい購入する必要があるかを事前に確認しておくと安心です。
模試費用
予備校主催の模擬試験を定期的に受ける場合、模試費用がかかります。受験料は1回あたり数千円~1万円程度であることが多いですが、受験する模試の種類によって異なります。
その他の見落としがちな出費
通学に電車やバスを利用するなら交通費、合宿や特別講座に参加するなら宿泊費・別途受講料など、細かな出費が積み重なる可能性があります。遠方から通う場合には下宿や寮の費用も考慮しなければならず、予備校の料金だけでは済まない点に注意が必要です。
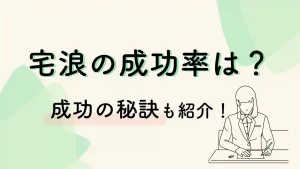
費用を抑えるための方法
予備校への支払いは、家計にとって大きな負担となるケースが多いですが、工夫次第である程度は費用を抑えることも可能です。特待生制度やスカラシップ制度を活用したり、教育ローンをうまく利用したりと、さまざまな方法を比較検討してみましょう。
特待生制度やスカラシップ制度などを活用する
予備校によっては、成績優秀者に授業料を減免する特待生制度やスカラシップ制度を設けていることがあります。一定の試験に合格すると入会金が免除されたり、授業料が半額になったりするため、大幅に費用を抑えられる可能性があります。自分の学力や目標校に応じて、挑戦してみるのも一つの方法です。
教育ローン・分割払いの活用
まとまった金額を一度に用意するのが難しい場合は、教育ローンや分割払いを検討してみましょう。銀行系の教育ローンや信販会社が提供するプランなど、選択肢は複数あります。ただし、金利や手数料が発生するケースもあるため、実際に支払う総額がどのくらいになるのかを事前にシミュレーションしておくことが大切です。
オンライン予備校や映像授業の選択肢
近年、オンライン予備校や映像授業を提供するサービスが増え、通学型よりも費用を抑えやすい選択肢が広がっています。自宅での学習が中心となる分、通学時間や交通費を削減できるのもメリットです。ただし、対面指導に比べてモチベーションを保ちにくい人もいるので、学習スタイルとの相性を考えて選ぶと良いでしょう。
予備校と共同のプロジェクトはこちら https://carpe-di-em.jp/media/5874
東大生の事例を紹介〜そもそも予備校に通うのか〜
現役で予備校に通わなかったパターン
東大生の中には予備校に通わずに東大に合格した人もいます。特に進学校の中には普段の授業で入試対策をおこなうところもあり、「公立高校+予備校の費用よりもうちの私立高校の学費の方が安いよ」という宣伝をしている学校もありました。
予備校に通わない場合は、当然ながら予備校の費用はかかりません。しかしそのような学校でも予備校と提携しているなどの事例が多く、予備校が提供する模試を受験したり浪人となった場合に学校から特定の予備校を紹介するということもあります。
予備校に通ったパターン
予備校に通って東大に合格した人も多くいます。学校の授業は聞かずに、授業中は予備校の課題をやっていたという人や、中学生の頃から予備校に通っていたという人もいます。
このタイプは入試対策をあまりやらない高校出身の人に多い傾向があります。逆に入試対策をする学校で予備校にも通っていた人は大量の課題をこなすことができず学校と予備校の双方が中途半端になり失敗することが多いです。なお、浪人生の場合ほとんどの合格者が予備校に通っています。
まとめ
予備校にかかる費用は、入会金や授業料といった基本的なものから、教材費や模試費用、通学費などの細かな出費まで多岐にわたります。特に浪人生の場合は年間の支出が大きくなりがちなので、早めに目標を定めて学習計画と予算を両立させることが大切です。特待生制度の利用やオンライン学習の活用など、費用を抑える方法も多様化しているので、情報をしっかり集めながら自分に合った選択肢を見つけてください。結果的に合格を勝ち取るためには、費用と指導内容のバランスを見極めることが何よりも重要です。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。