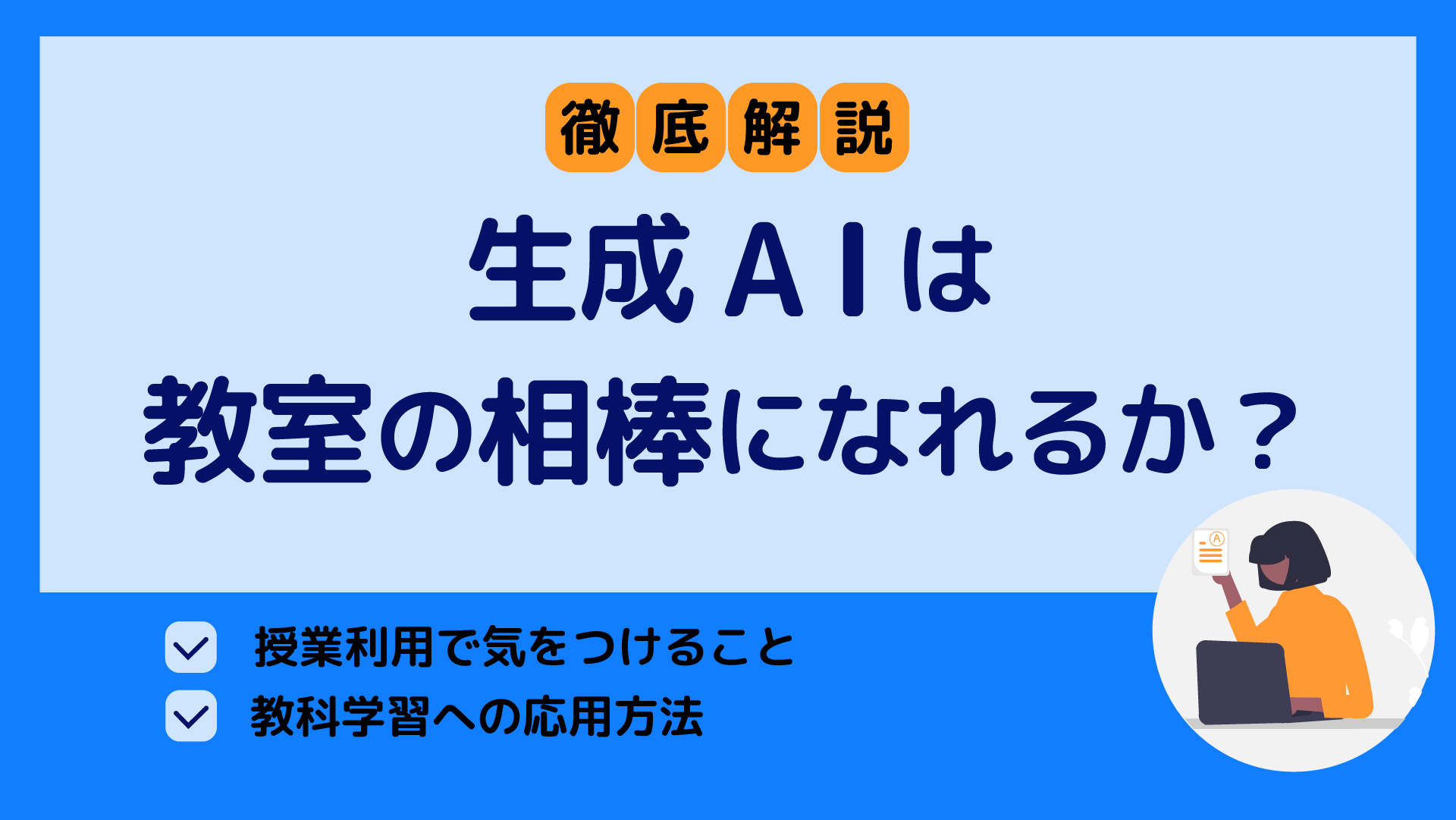学校現場でいま起きている変化とは?
ChatGPTやClaude、Geminiなど、生成AIが話題になることが増え、身近なツールとして使われ始めています。動画をつくったり、レポートのアイデアを整理したりと、私たち大学生にとってもAIは無視できない存在になってきました。
では、学校現場ではどうでしょうか?先生たちは生成AIをどう活用していて、生徒との関わり方にどんな変化があるのでしょうか?
今回、学校現場でのAI活用について調べてみると、授業づくりや時間の使い方に工夫が生まれていたり、先生と生徒のコミュニケーションに新しい形が生まれていたりと、いろいろな気づきがありました。
本記事では、実際の現場での取り組みを紹介しながら、「生成AIは本当に“教室の相棒”になれるのか?」を、学生の視点で考えてみたいと思います。
文部科学省からみる生成AIを授業で使うときの「5つの指導視点」
実は、文部科学省からも生成AIの活用に関するガイドラインが出されているのをご存じでしょうか?
これは、生成AIが教育現場でも無視できない存在になってきていることを示す、ひとつの大きなサインだと思います。
ガイドラインでは、「利便性とリスクの両面をふまえ、適切に活用していくこと」が重要だとされています。
では、実際に学校現場で使うとしたら、どんな点に気をつければいいのでしょうか?
今回、私たちはこのガイドラインを読み解きながら、生成AIを学校で活用する際のポイントや注意点を整理してみました。
安全性を考慮した適正利用
「開発者や提供者の想定する範囲内での生成AIサービスの適正な利活用を行うことが重要である」(p.10)
利用する生成AIのサービスの利用規約や年齢制限、保護者の同意などを確認したうえで、安全な環境での使用が求められます。教育委員会の方針に基づき、校長や担当教員が責任を持って運用する体制が必要です。
情報セキュリティの確保
「情報セキュリティの確保が重要である」(p.10)
「教育情報セキュリティポリシー」に基づき、成績や健康情報などのセンシティブなデータは絶対に入力しないこと。また、私用端末・私用アカウントの利用は厳禁です。
AIが出力する情報を鵜呑みにせず、情報の正確性や信頼性を確認する方法やAIの倫理的な使用についても教育し、生徒が責任ある情報の取扱者として成長するよう導くことが求められます。
個人情報や著作権の保護
「生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトの入力を行う場合には、…違反となり得る」(p.16)
「授業の過程における利用であれば、著作権者の許諾なく利用することが可能である」(p.17)
児童生徒の氏名や写真など個人情報の入力は禁止。また、生成された文章や画像が既存の著作物に酷似していないか、必ずご確認を。授業内利用であっても、外部公開やコンクール応募には別途注意が必要です。
公平性の確保とバイアスへの配慮
「出力された内容を取り入れるかどうかは教職員が判断しなくてはならない」(p.16)
生成AIは学習データに含まれる社会的バイアスを再生成する可能性があります。教師による出力内容の確認と、児童生徒への「AIの限界と向き合う指導」が必須です。
透明性の確保と説明責任
「生成AIの利用目的やその態様、リスク等の必要な情報を整理し、関係者に提供することが重要である」(p.11)
「出典・引用として記載する等の対応が必要」(p.20)
生徒が生成AIを利用する場合は、プロンプト(簡単に言えばAIへの指示内容)・サービス名・使用日を明記するなど、引用ルールを徹底すること。また、保護者には学校での活用目的や方針を事前に共有しておくことが大切です。
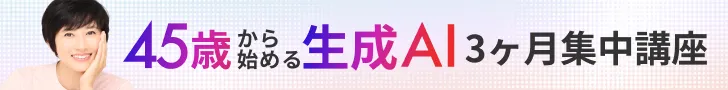
教科別:生成AIはこう使える!授業実践ヒント集
指導のガイドラインの考え方を踏まえて、次に気になるのは「では、実際にはどう使えるの?」という点ではないでしょうか。そこで今回は、生成AIがどのように授業や学びの中で活用されているのかを調査し、科目ごとに整理してみました。
英語:AIと会話しながら正確な表現力を磨く
英語の授業では、生成AIを使うことで言語学習に新しい可能性が広がっています。
たとえば、AIと英語で会話することでスピーキングの練習ができたり、発音や表現についてリアルタイムでフィードバックをもらえたりします。まるで“個別の英会話練習相手”ができたような感覚です。
また、生徒のレベルや興味に合わせて、例文や単語帳をその場で作ってくれるのも便利なポイント。市販の教材では難しい“パーソナライズされた学習”が、簡単に実現できるようになります。
こうしたツールを上手に活用することで、生徒が英語に自信を持てる環境づくりが進んでいます。
国語:文章をAIに推敲してもらう
国語の授業では、生成AIを“自分の書いた文章の相棒”として活用する方法があります。
たとえば、自分で書いた文章をAIに推敲してもらうことで、「自分の表現とどう違うのか」「どこを直すと伝わりやすくなるのか」といったことを客観的に見直すことができます。
AIの出力をそのまま“正解”にするのではなく、そこからさらに自分なりに修正を加えていく。このプロセスそのものが、自分の文章と対話する貴重な学びの時間になるのです。
こうした使い方は、「一度書いたら終わり」になりがちな従来の国語の授業とは異なり、書く力を育てる新しいアプローチとして注目されています。
総合学習:AIと議論して課題を深める力を養う
総合的な学習や探究の時間では、生成AIが生徒たちの“議論のパートナー”として活躍する場面が増えています。
たとえば、グループで考えをまとめたあとに、「他に考えられる視点は?」「反対の立場ではどう見える?」とAIに問いかけることで、第三者の意見に触れることができます。こうしたやりとりを通じて、生徒たちの視野が広がり、議論の深まりにもつながっていきます。
さらに、AIの提案をそのまま受け入れるのではなく、「これって本当に正しい?」「どうしてそう言えるんだろう?」と検討し直すプロセスも重要です。
生成AIは、使い方によっては学びをより“自分ごと”として捉え、深く掘り下げていくための強いツールになり得ます。
学校文化に合わせた「共感ベース」の導入支援
学校現場に生成AIを導入するには、単に技術を提供するだけではなく、学校ごとの文化や目標に寄り添ったサポートが欠かせません。
「共感をベースにした支援」が重視されており、教師の方々が安心してAIを授業に取り入れられるよう、学校ごとの特性に合わせて、研修や導入支援を丁寧にカスタマイズしている企業も多く見られました。
こうした取り組みによって、先生方が自信を持ってAIを活用できるようになり、生徒にとってもより良い学習環境が整います。教育に関わる企業の役割は、技術提供だけでなく、現場とともに“学びの未来”をつくっていくことにあるのかもしれません。
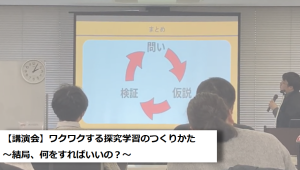
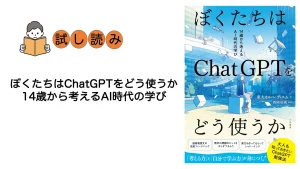
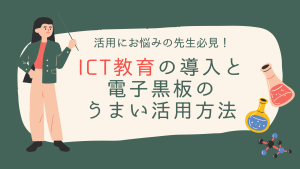
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。