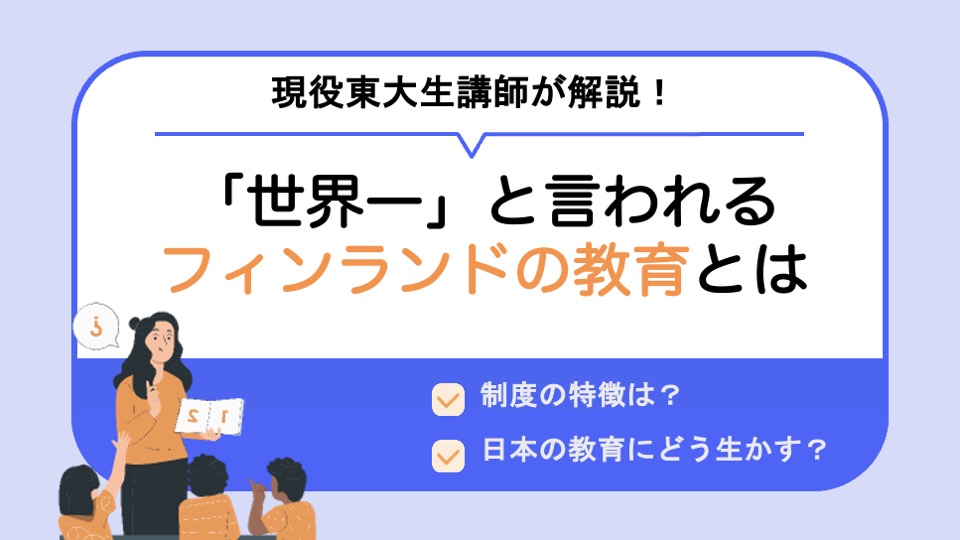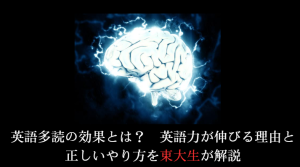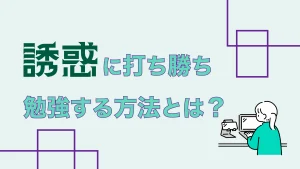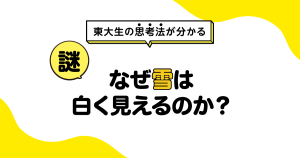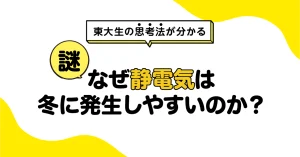フィンランドの教育は、平等性や質の高さを高く評価され、世界から注目されています。「世界一」とも言われるフィンランドの教育は、日本の教育とどのような違いがあるのでしょうか。本記事では、弊社カルペ・ディエムで講師をしている筆者が、フィンランド教育の特徴、その背景や子ども観、そしてフィンランドの教育が大切にしている価値観を整理しながら、日本の教育にどう生かせるかを考えていきます。
フィンランドの教育は世界一?
フィンランドは長年にわたり「教育先進国」として世界から注目されてきました。その背景には、OECD(経済協力開発機構)が3年ごとに実施する国際学力調査PISAでの好成績があります。最新の2022年調査では、フィンランドの生徒は数学で484点、読解力で490点、科学で511点を記録しました。
OECD加盟国の平均点(数学472点、読解力476点、科学485点)と比べると、数学で12点、読解力で14点、科学では26点もの差があり、特に科学分野で際立った強さを見せています。こうした高い水準を安定して維持していることが、フィンランド教育が「世界一」と評価される大きな理由の一つです。
さらに注目すべきは、近年重視されるようになった「創造的思考力」です。PISA 2022では、最上位であるレベル5〜6に達した生徒が39%と、OECD平均の27%を大きく上回りました。つまりフィンランドでは、学力の高さだけでなく、子どもたちの「創造力」を伸ばす取り組みでも成果を上げています。
フィンランドの教育の前提
フィンランドの教育が優れていると言われるのは、「すべての子どもに平等な学びを保障する」という考えが社会全体に根づいているからです。お金の心配なく誰もが学べる仕組みがあり、教育は家庭の状況に左右されません。また、先生は子どもの成長を支える専門家として大きな信頼を得ており、教育を重んじる文化そのものが学校を支えています。
子どもに対する考え方
フィンランドでは、子どもを受け身の存在ではなく「主体的に学ぶ存在」として認識し、その可能性を広げることが教育の根本にあります。学力の高さだけでなく、幸福感や自己肯定感といった要素も重視されています。さらに一律の基準で評価するのではなく、一人ひとりの個性を尊重し、それぞれに合った学びを支える姿勢を大切にしています。
理念
フィンランドの教育が大切にしているのは、「子どもの幸せと健やかな成長」です。点数や序列を重視するのではなく、協働しながら学ぶ環境を整え、子どもが自分らしく成長できることを大切にしています。そのため、学校は競争よりも協働を重んじ、休憩や遊びの時間も大切な学びの時間と位置づけています。先生が一人ひとりの声に耳を傾け、安心して学べる環境をつくることが、子どもの意欲や創造性を引き出す基盤となっています。
フィンランド教育の特徴
フィンランドの教育が評価されている理由を紹介してきました。では、実際にフィンランドの教育にはどんな制度や授業の特徴があるのでしょうか。
制度の特徴
フィンランドの教育制度は、「平等性」と「教師の専門性」に基づいています。全国学力テストや序列化がないため、子どもたちは無用な競争にさらされず、自分のペースで安心して学べます。また、教師は修士号取得が必須とされ、高い社会的信頼と授業の裁量を持つプロフェッショナルとして教育にあたっています。さらに、学校にはキャリアカウンセラーが配置され、子ども一人ひとりの希望や興味を尊重して進路設計をサポートする体制が整っています。こうした制度の設計は、日本の先生方にとって、「評価よりも成長」「一律ではなく個に応じた支援」を意識するヒントになります。
授業・カリキュラムの特徴
フィンランドの授業は「詰め込み」ではなく、子どもが自分で考え、学びを広げていけるように設計されています。1コマは45分が基本ですが、途中に休憩を多く入れ、集中力を保てるように工夫されています。
また「クロスカリキュラム」という授業が導入されています。クロスカリキュラムとは、複数の教科を横断して、1つの現代的な課題学ぶ学習方法です。授業各教科の視点からテーマを探求することで、知識の統合や応用力を高めることを目的としています。例えば、「生命倫理」をテーマに、社会科では人権意識、理科では生態系、英語では関連するキーワードを学ぶといった形で、教科を跨いで学習を進めます。
こうした取り組みは知識の暗記だけでなく、問題解決力や協働性を育む狙いがあります。さらに、評価もテスト点数だけでなく、日常の取り組みや成長の過程を重視しています。子どもの力を「見える部分」だけで測らず、プロセスごと認める姿勢を大切にしています。
フィンランド教育の事例
ここまで制度や理念について見てきましたが、実際にフィンランドの学校ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。フィンランドの教育は「子どもを一人の人間として尊重する」という考えを基盤に、日々の授業や学校生活に具体的な形で落とし込まれています。ここでは、その中でも特徴的な実践を3つ紹介します。
企業と連携した職業体験
フィンランドの小学校高学年(5、6年生)になると、地域の企業や団体と協力した授業や職業体験が行われます。子どもたちは社会の現場で「自分の学びがどのように役立つのか」を体感することで、学習意欲が高まります。さらに、自分の得意や関心を見つける機会にもなり、「自分は社会に貢献できる」という自己肯定感の育成にもつながります。
フェノメノンベースラーニング
2016年から始まったフェノメノンベースラーニングは、環境問題などのテーマに対して、複数教科を横断して学びを深めるものです。子どもたちは協力しながら調査や発表を行うため、知識の統合だけでなく「協働する力」「自分の考えを伝える力」が自然と養われます。つまりこれは学力テストでは測りにくい、非認知能力を伸ばす実践となっています。
カウンセリング体制
フィンランドの学校では、「キャリアカウンセラー」という学校の先生がおり、生徒を「一人の人間」として尊重し、その思いや希望に寄り添う体制が整っています。進学や就職だけでなく「どんな人生を歩みたいか」という本人の意思を尊重して支援しています。この姿勢が、生徒の自己肯定感を育み、主体的にキャリアを描く力を支えているのです。
日本の教育に生かすには
ここまで見てきた通り、フィンランドの教育は日本の教育と大きな違いがあります。日本の教育に、フィンランドの教育の良いところを取り入れるにはどうすればよいのでしょうか。
クロスカリキュラムを導入する
クロスカリキュラムといっても、フィンランドのように大規模なカリキュラム改革を行うのは難しいかもしれません。その場合でも、日常の授業に小さく「教科を横断する視点」を取り入れることは可能です。あるテーマを複数の教科から考えることで、生徒は知識を結びつけ、自分なりに整理する力を伸ばせます。こうした取り組みは、学力だけでなく思考の柔軟性を育てる基盤になります。
たとえば、歴史的な事件を題材にその時代の資料や文学を読むことで、社会と国語を組み合わせて、歴史を生きた人の感情を理解できます。また、社会系の科目と英語を組み合わせ、調べたことを英語で発表することで、英語力と地理的な知識を同時に伸ばすこともできます。
話し合い活動を増やし、協働する経験を重ねる
PISA2022でも注目された「創造的思考力」は、一人で黙々と勉強するだけでは育ちにくい力です。授業中にグループで意見交換したり、結論をまとめて発表したりするようなアクティブラーニングの機会を意識的に増やすことで、生徒は協力して課題を解決する力や、自分の考えを伝える力を自然と伸ばすことができます。これがまさに非認知能力の基盤です。
学校全体で非認知能力を育む視点を共有する
非認知能力の育成は、一人の先生の努力だけでは十分な成果につながりません。大切なのは、「知識やテストの点だけでなく、生徒の自信や協働性も重視する」という価値観を学校全体で共有することです。教育方針をそろえて取り組むことで、生徒は安心して挑戦でき、仲間と学び合う文化が少しずつ育まれていくのではないでしょうか。
おわりに
フィンランド教育から、子どもを大人の理想に当てはめるのではなく、子ども自身が「こうなりたい」と願える瞬間をつくることの大切さを学べます。学力や点数ももちろん重要ですが、それだけでは人は幸せになれません。自信を持ち、仲間と協力し、挑戦を楽しめる。そうした測ることができない非認知能力こそが、子どもたちが自分の未来を切り開いていく基盤となります。弊社で講師をしている筆者を含め、教育に関わる人々が、そのきっかけを共につくり出す存在でありたいと思います。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。