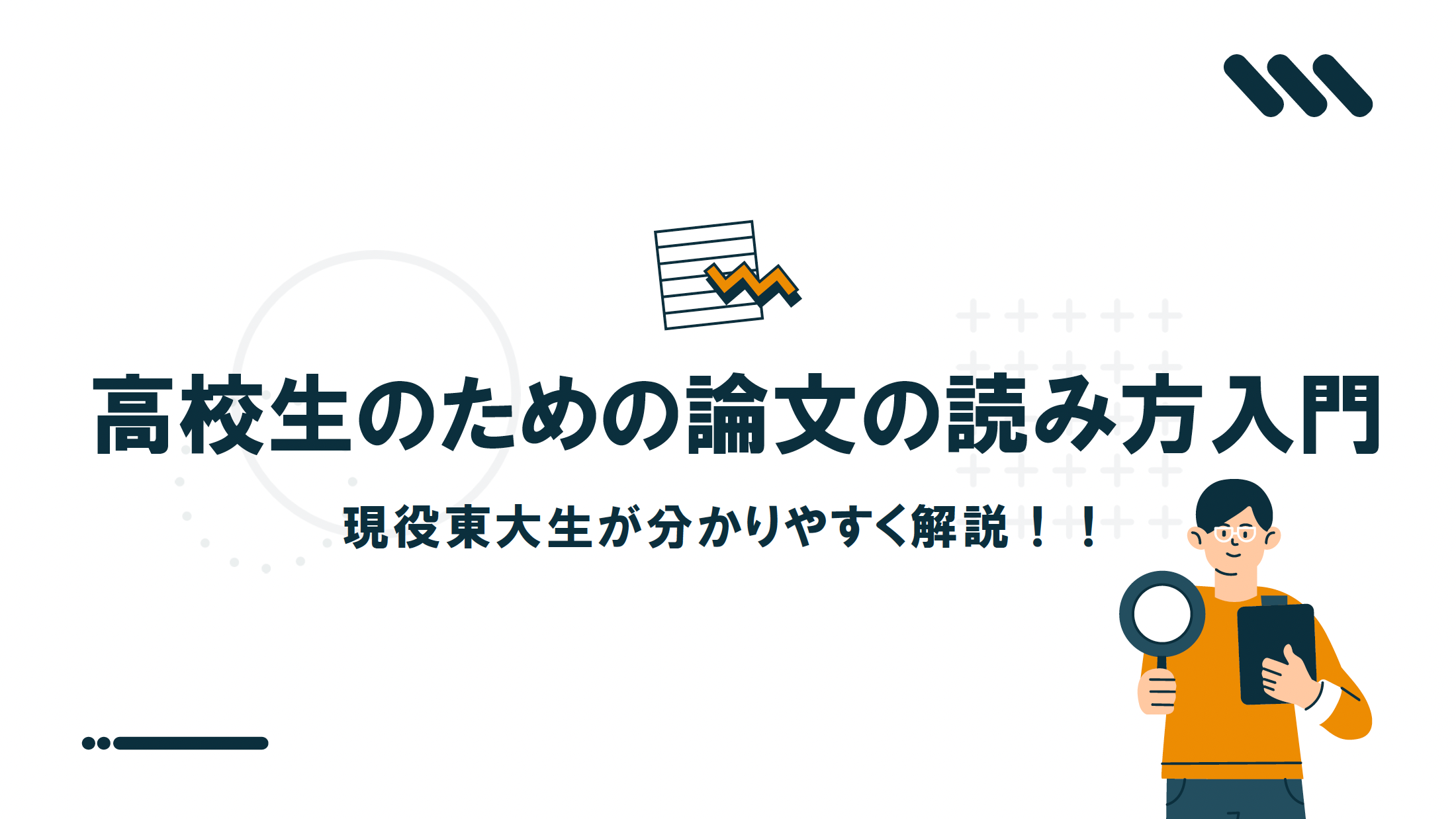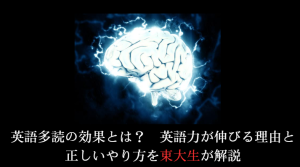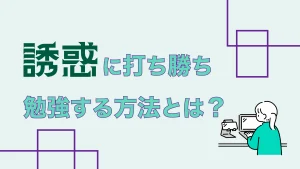これまであまり「論文」を読む機会はなかったかもしれません。
ですが、探究学習や課題研究などで自分のテーマを深めていくときには、論文がとても役立つ情報源になります。
最初からすべて理解する必要はありません。ポイントを押さえて読むことで、難しく取っつきづらいと感じていた論文も、ぐっと身近なものになります。
この記事では、実際に大学で日常的に論文を読んでいる東大生ライター碓氷明日香が、高校生にもわかりやすい「論文の読み方」を解説します。
そもそも論文とは?
論文とは、研究者が自分の研究内容をまとめ、他の人に伝えるために書いた文章のことです。
テーマや課題に対してどのように調べ、どんな結果が得られたのかが、筋道を立てて説明されています。
単なる感想文やレポートと違い、根拠となるデータや先行研究が必ず示されており、「学問の世界で共有される知識」としての役割を持っています。
多くの場合、論文は専門家による「査読」という審査を経て学術雑誌に掲載され、それを書いた研究者の業績として認められます。
なぜ高校生にとって論文が役に立つのか
では、高校生が論文を読めるようになるメリットは何でしょうか。ここでは、2つのメリットを挙げていきます。
探究学習やレポート作成に活用可能
高校の探究学習やレポート作成では、テーマを深め、根拠をもって主張することが必要になってきます。そのときに役立つのが論文です。
論文には、研究者が時間をかけて調査・実験を行った結果がまとめられており、自分の考えを支える「確かな材料」として引用できます。
単にインターネットで見つけた情報を並べるのではなく、論文を根拠に使うことで、より説得力のある発表やレポートに仕上げることができます。
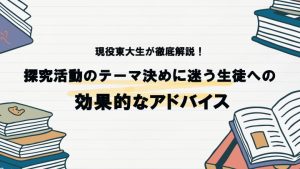
信頼できる情報源としての価値
いまの時代、SNSやネット記事には真偽のあいまいな情報があふれています。その中で、論文は研究者が厳密な調査や議論を経て公開するものなので、信頼できる可能性が高い情報源といえるでしょう。
もちろん、論文の中にも査読がきちんとなされていない質の悪いものもあるようですが、ほとんどの論文は「確かなデータに基づいている」価値ある研究成果です。
論文を読めるようになると、正しい情報を見極めようという態度が身につき、また見極める力自体も成長していきます。これもメリットのひとつです。
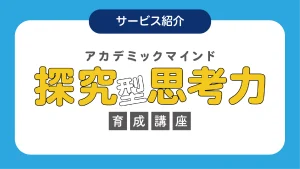
論文の基本構造を知ろう
論文の構造を知ることで、それぞれの章で何に注目すればいいかがわかり、一気に読みやすくなります。ここでは、論文の基本構造を5つにわけて説明していきます。
要旨
論文の最初にある「要旨(アブストラクト)」は、研究の目的・方法・結果・結論がコンパクトにまとめられている部分です。
ここを読むだけで、その論文で著者が言わんとするところを大まかにつかむことができ、自分の探究テーマに関係するかどうかもすぐにわかります。一番最初にチェックするべき部分です。
序章
「序章」では、研究がどんな背景から始まったのか、過去の研究でどこまでわかっていて、どんな課題が残っているのかが説明されます。
つまり、「なぜこの研究をやるのか」を説明する部分です。
ここでは、論文を通して答えを見出していく「問い」が提起されます。この「問い」を追っていく形で読み進めるとわかりやすいので、序章をしっかり読むことで、「問い」を押さえることが大切です。
本論
「本論」は論文の本体となる部分です。
実験方法や結果、考察などが書かれており、序章で提起された「問い」に対する「答え」が論理的に証明されます。実験や調査のデータや、資料などの根拠を踏まえて、客観性を重視しながら自身の仮説を検証していくのです。
筆者がどのようなことを言おうとしているのか、何を検証しようとしているのか、「問い」とそれに対する「仮説」を意識しながら読み進めるとわかりやすいでしょう。
終章
「終章」は「結論」とも書かれる、論文の中で示した内容について簡潔にまとめる部分です。研究結果からわかったことや、それが社会や学問にどんな意味を持つのかが書かれています。
主張が端的に書かれているので比較的読みやすく、要旨と終章を読むだけでも、ある程度全貌を把握できることがあるのです。
参考文献
最後に書かれているのが「参考文献」です。その論文を書くにあたって引用した先行研究や資料の情報が一覧になっています。
著者名、発表年、論文タイトル、掲載雑誌などが書かれ、一定のルールで表記されているので、自分のテーマに関連する他の文献を探したいときには、このリストをたどるのが有効です。
分野によって表記のルールは変わりますが、一般的には次のような形で書かれています。
【参考文献の表記】
書籍:著者名.書名.出版社,出版年,[総ページ数],[シリーズ名].
論文:著者名.表題.雑誌名.出版年,巻数,号数,pp.始め〜終わり.
論文を読むコツ
では、実際に論文を読むときには、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。
ここでは、私が実践している3つのコツを紹介します。
要旨と終章から読む
論文を最初から順番に丁寧に読もうとすると、専門用語や細かい方法に戸惑ってなかなか進みません。
そこでおすすめなのが、まず「要旨」と「終章」から読む方法です。研究の全体像とゴールを先に知ることで、細かい内容も理解しやすくなります。
実際、筆者もまず要旨と結論だけを確認して、「読む必要がある論文か否か(自分の研究テーマと関連があるかどうか)」「何についてどんなことを論証しようとしているのか」を判断、把握してから読み始めることが少なくありません。
最初からすべてを理解しようとせず、要旨と結論を出発点にして全体像をつかむ読み方を習慣にすると、論文へのハードルがグッと低くなるはずです。
「問い・論証・答え」の3点を整理する
論文は「どんな問いを立てたのか」「どのような方法や根拠で論じているのか」「どんな答えが出たのか」の3点を整理すると理解がスムーズに進みます。それぞれ、明らかになったタイミングでメモをしておくと、意識しながら読み進めやすいです。
途中、専門用語が出てきてよくわからなくなってしまっても、この3点がはっきりしてさえいれば、ひとまず置いていかれることはないでしょう。論文の主軸を常に頭の片隅に置きながら読んでみてください。
キーワードや気づいたこと、疑問点を必ずメモする
よくわからない専門用語や重要な表現は、すぐにノートや付箋に書き留めておきましょう。
また、「ここはまだよくわからない、なぜ?」「自分のテーマにも応用できそう」といった気づきや疑問も残しておくと、あとで自分の探究やレポートに生かしやすくなります。
読み終わってから疑問点を整理しようとしても、どこで何を考えたか、大抵忘れているものです。
気になったらすぐにメモをすることが大切です。タブレットなどを使って、ダウンロードした論文に直接メモを書き込むのがおすすめです。
高校生でもできる! 論文の探し方
自分の探究テーマに沿った論文を探し出すためには、どうすればよいのでしょうか。ここでは、2通りの方法を丁寧に解説します。
論文の探し方① Google ScholarやCiniiを利用する
インターネット上で無料で使える論文検索サービスが「Google Scholar」と「CiNii」です。
Google Scholarは世界中の研究論文を幅広く検索でき、CiNiiは日本語の論文や大学の紀要などを探すのに強みがあります。検索エンジンと同様に、キーワードを入れるだけで論文が出てくるので、高校生でも簡単に使えるものです。
【論文を探す手順】
①調べたいキーワードを決め、検索窓に入れて検索
自分のテーマを短いキーワードにわけます(例:「睡眠」「学力」)。
検索窓にキーワードを入力して検索をかけます。日本語・英語両方で試すと効果的です。
②要旨を読む
気になった論文のタイトルをクリックして、要旨を読んでみましょう。
そして、自分の探究テーマに関連があるかを判断します。
③フルテキストを探す
「[PDF]」や「本文あり」のリンクから無料で全文が読めるものもあります。
全文が有料となっている場合は、学校や図書館を通じてアクセスできないか確認してみましょう(詳しくはこのあと説明します)。
論文の探し方② 学校図書館・大学図書館を利用する
学校や大学の図書館は、本だけでなく学術雑誌や電子ジャーナルにもアクセスできる「学びの拠点」です。
学校の規模によっては電子データベースが整備されていないこともありますが、司書に相談すれば、必要な論文を探したり取り寄せたりすることができます。
また、近隣の大学図書館を利用できる制度もあるので、学校図書館で手に入らない論文は、大学図書館で探してみるのもひとつの手です。
【論文を探す手順】
①学校図書館のOPACを使う
学校図書館にはOPACという蔵書検索システムがあります。それに論文タイトルやキーワードを入れて検索をかけてみましょう。
電子ジャーナルを契約している学校なら、図書館のデータベース一覧からログインして、全文を読むことができるかもしれません。
②学校の図書館司書に相談する
「この論文の全文がほしいのですが、取り寄せられますか?」と聞くと、探し方や取り寄せサービスについて教えてくれます。
③近くの大学図書館を利用する
学校で取り寄せることができなかった場合、近くの大学図書館を利用してみましょう。
大学によって、「学外利用可」や「閲覧のみ」など利用ルールがある場合があるので、事前にウェブページで利用条件を確認し、必要なら身分証明書を持参します。
大学図書館では、学術データベースや学内契約の電子ジャーナルにアクセスでき、そこから有料論文でも無料で閲覧できることが多いです。高校よりは扱っている論文が多いはずなので、ぜひ活用してみてください。
論文を活用するときのマナー
探究活動やレポート作成に論文を引用するとき、気をつけなければならないマナーが2つあります。そのマナーについて、詳しく見ていきましょう。
出典を明記する
まず、論文の内容を引用したり参考にしたりするときは、必ず出典を明記しましょう。出典を示さずに使う行為は、他者の文章・図表・思想・アイデアをあたかも自分のもののように用いる「剽窃(ひょうせつ)」に当たります。
剽窃は研究の世界では重大なマナー違反とされ、信用を大きく失う原因になります。また、著作権侵害として法的な罰則につながる可能性もあります。
それは、高校のレポートであっても同じことです。たとえ数行だけの引用でも、「誰の、どの論文からの言葉なのか」をはっきり書くことが大切です。
もとの論文の趣旨と異なる形で「切り抜き」しない
論文から一部分を切り取って引用する際は、その文が本来の趣旨と違う意味にならないように注意が必要です。
例えば、あるカフェインの危険性に関する論文に「カフェインには集中力を高める効果がある。ただし、飲みすぎると健康に悪影響が出る」と書かれていたとします。このとき「カフェインには集中力を高める」という部分だけを取り出してしまうと、「飲みすぎると害がある」という重要な注意点が抜け落ち、論文の意図をゆがめることになるでしょう。
引用は自分に都合よく使うためではなく、著者の主張を正しく伝え、自分の主張の根拠とするために行うものです。文脈を大事にし、意図を損なわない形で引用することが、論文を活用する上での大切なマナーです。
まとめ
高校生でもチャレンジできるように、論文の読み方を解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
高校生のうちから論文に触れておくことは、将来必ず役に立ちます。
大学に入ると、授業やレポートでは「論文を読んで調べること」が当たり前になりますが、そのとき初めて取り組んで、つまずく人が多いです。いまから少しずつ慣れておけば、大学での学びをスムーズに始められます。
また、情報の真偽を判断し、根拠をもとに意見を組み立てる力も早くから伸ばすことができるでしょう。論文を読むことは、自分の世界を広げるチャンスにつながるのです。
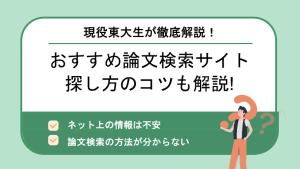
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。