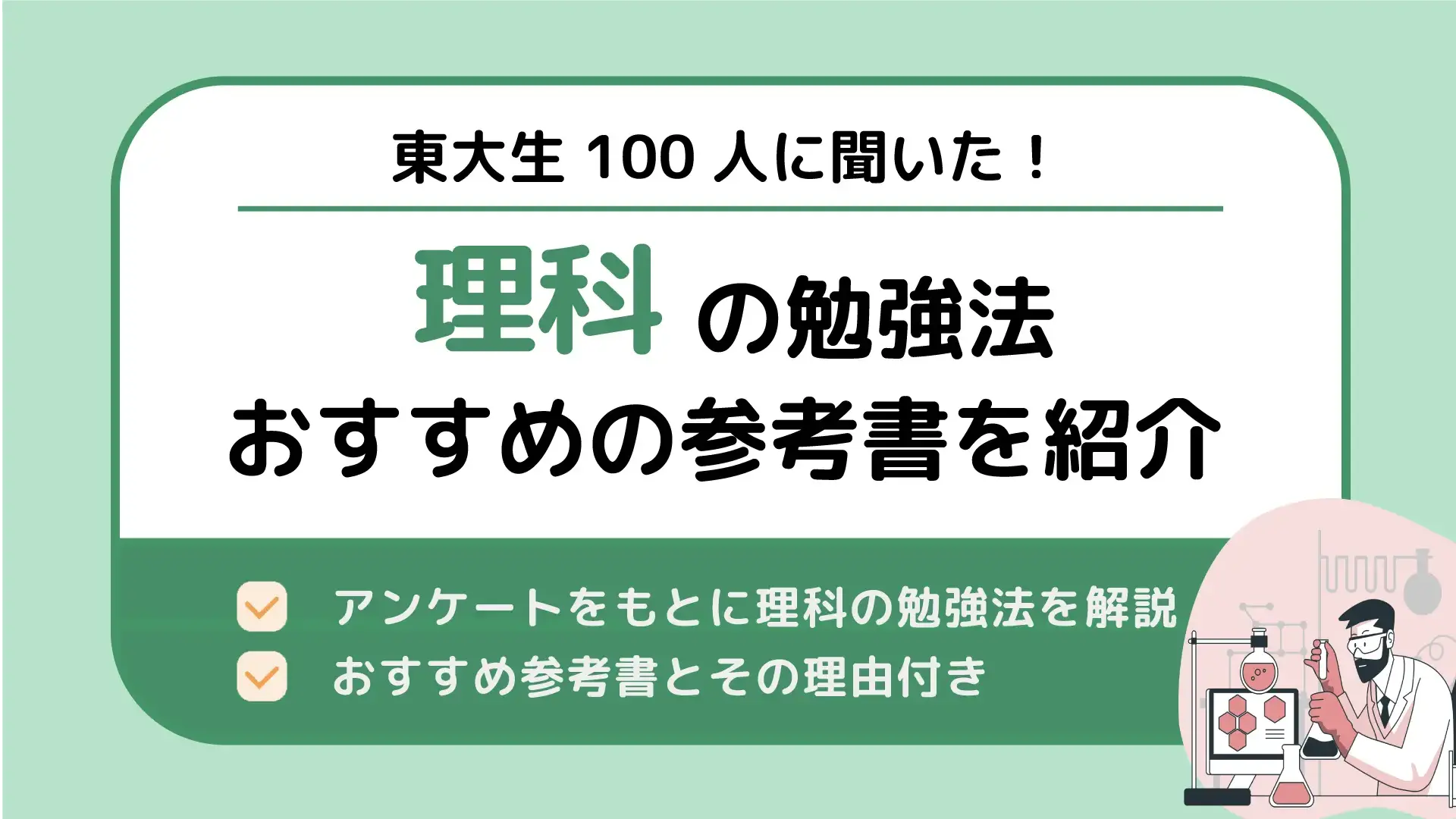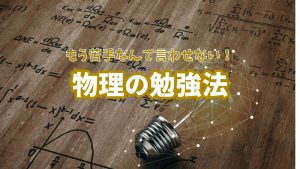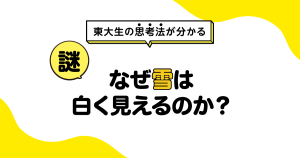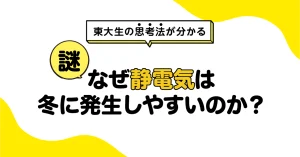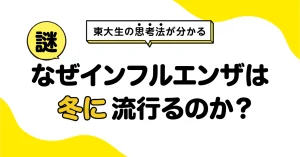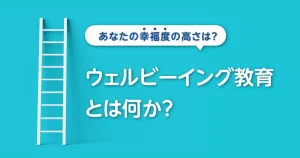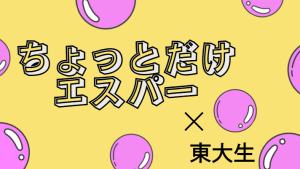「理科、どうやって勉強すればいいんだろう」
「自分の勉強法あっているのかな」
そんな悩みを持つ高校生に向けて、弊社カルぺ・ディエムは現役・元東大生100人にアンケートを実施。
この記事では、その結果から見えた“本当にやっていた勉強法”と“使われた参考書”、さらに選び方のポイントを、リアルな声だけでお届けします。
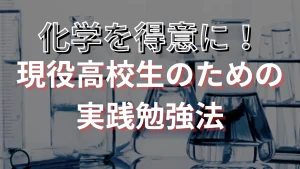
※注意:地学はデータが少なく、参考にならない可能性が高いです。
【勉強法編】最も行われていたのは「問題演習で理解を深める」こと
物理・化学・生物・地学の教科に全て共通して、最も多くの東大生が挙げたのは「問題演習」でした。理科科目において演習が非常に重要であることが、東大に受かった人たちの中で共通して認識されているようです。
具体的な解答をいくつかピックアップしてみました。
- 物理
- 「解いて、答え合わせをして、間違えていたら『なぜ間違えたか』を分析し、ポイントをまとめる」
- 「夏休みまでに教科書附属問題集『セミナー物理』を3周して基本事項を固め、塾の講義テキストを2周しました。夏休み以降はひたすら東大型の問題演習を繰り返し、経験量を積みました。」
- 化学
- 「参考書の問題を解く→わからないところを理解→解く の繰り返し」
- 「演習→復習のサイクルで、理論は特に苦手だったので間違えた・苦手なポイントをノートにまとめなおしていた。」
- 生物
- 「問題を解きながら覚えていないことがあれば教科書や資料集を見て知識をインプットした。」
- 地学
- 「解いて、答え合わせをして、間違えていたら『なぜ間違えたか』を分析し、教科書で復習しつつポイントをまとめました」
これらの回答をよく見てみると、共通する事柄があることがわかります。
それは、「ただ演習をするだけではなく、わからないところを分析する」ということです。
分析して見つかった課題を克服するために、教科書、参考書、資料集などに戻って知識を再インプットしています。
さらに、「ポイントをまとめる」「ノートにまとめなおす」といった形で、自分なりに知識を整理し直し、次に活かせる形で定着を図っています。
こうして、自分の弱点が“なぜ”生まれたのかを突き止め、次に同じミスをしない仕組みを作っているようです。
教科書・基礎参考書の徹底読み込み
意外なほど多かったのが「教科書を何周も読む」という声です。
特に化学・生物では教科書の記述や図表がそのまま入試問題の背景になるため、深く読み込むほど有利になります。
具体的な回答をいくつかピックアップしてみました。
- 物理
- 「学校の授業を中心に学習した。特に教科書の内容は重点的に身につけるように心がけたことで、実戦的な演習にも適応していくことができた。」
- 化学
- 「ひたすらに基礎を叩き込む、そしてひたすら解いて使えるようにする。」
- 生物
- 「生物は現象を正確に理解することが重要なので、教科書を読み込むことが重要。」
このような回答からわかるように、応用問題より前にまず土台となる基礎知識や根本的な現象の正確な理解を大事にしている人が多いようです。
東大生独自の工夫も!
また、アンケートからは、定番以外のユニークなアプローチも見えてきました。
- ただひたすら知識を書き出して確認する
- 「白い紙に、知っていることを全部書き出していく。」
- 「白い紙に、知っていることを全部書き出していく。」
- まとめノートをつくる
- 「自分で教科書を作るつもりでまとめノートを作り、そこに高校化学のあらゆる知識を収めて、あとは問題を見たときに応用するだけと思っていた。」
- 「間違えたものをノートに再度まとめる。」
- 先生に添削を頼む
- 「学校の授業を中心に学習した。特に、先生が作成した添削問題に積極的に取り組んだ。」
【参考書編】東大生の参考書と選び方
回答で特に多かった参考書と理由は以下の通りです。
物理
- 物理のエッセンス
- セミナー物理
- 良問の風
- 名問の森
- 難問題の系統とその解き方(難系)
化学
- 化学の新演習
- 重要問題集
生物
- リードα
これらからわかるように、東大に合格した人たちの選び方の基準は「レベルの適合」「解説のわかりやすさ」「範囲を網羅しているかどうか」であるようです。
また、難しい問題集にいきなり飛びつくのではなく、基礎→標準→発展の順に段階を踏んでいることも分かります。
今日から真似できる理科勉強法まとめ
東大生100人に実施したアンケートをもとに東大に受かった人たちが実際に行っていた理科の勉強法や使っていた参考書を紹介していきました。
その中で、東大生に共通することを改めてまとめると
- 土台となる知識や根本的な現象理解を重要視する
- ただ演習するだけでなく“なぜ間違えたか”を常に意識する
- 参考書は「目指すレベルにあっているか」「解説のわかりやすさ」「全範囲を網羅しているか」で選ぶ
一番大切なのは、「なぜ間違えたのかを分析する」ことのようでした。
やはり東大生の勉強は“量”よりも、”自己分析”で作られていることがわかりますね。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。