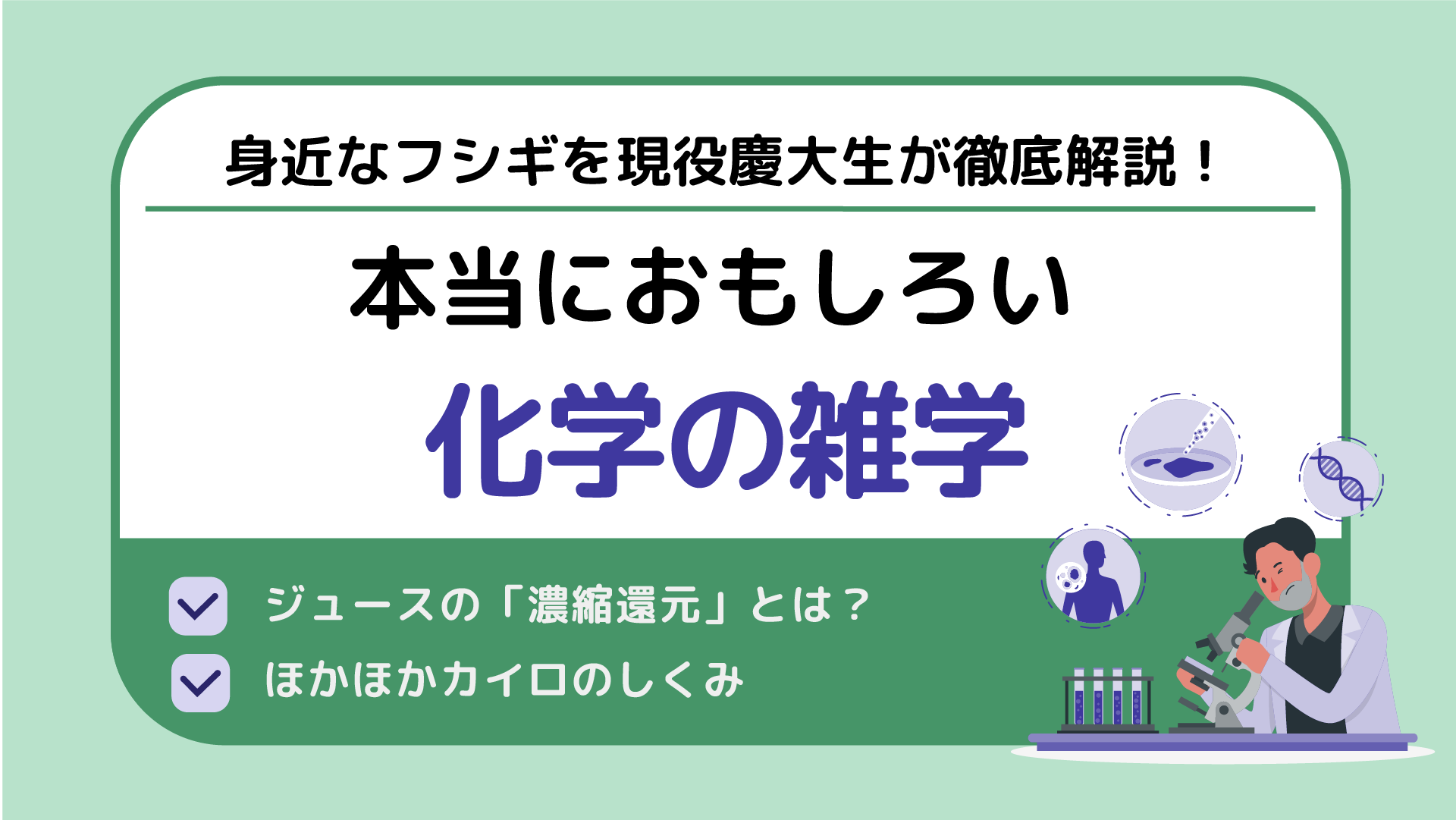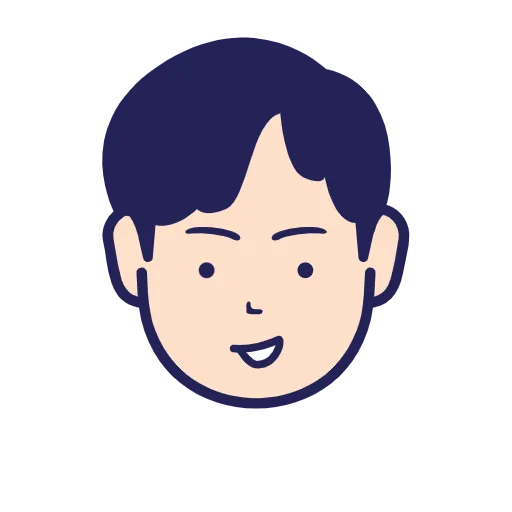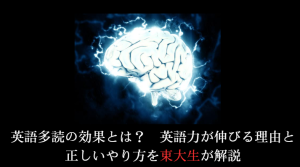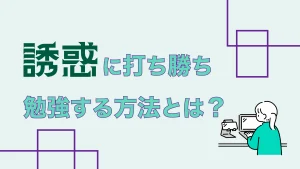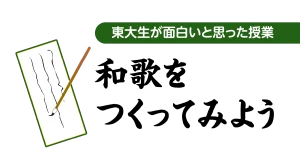「化学は苦手……」「元素記号を見るだけでゾワッとする……」そんなあなたでも大丈夫!
実は、私たちの身の回りには、化学の知識で「なるほど!」と解き明かせる不思議が山ほど隠されています。今回は、現役慶大生の私が、日常の「なぜ?」を高校化学の知識でスッキリ解決する雑学をご紹介します!
もしかしたら、これを読んだら、あなたの「化学嫌い」が少しだけ和らぐかもしれませんよ。
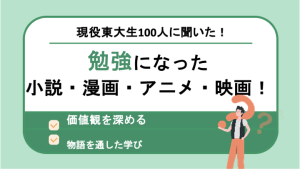
毎日使うアレにも化学の魔法!?「界面活性剤」の科学
油汚れがきれいに落ちる! 洗浄作用の秘密
私たちが毎日使うセッケンや洗剤。お皿を洗ったり、お風呂に入ったり、毎日の生活には欠かせませんよね。
水と油は普通混ざり合わないので、ただ水で流しても油汚れは落ちませんよ。では、なぜ洗剤を使うと、ギトギトの油汚れがスッキリ落ちるのでしょうか?
その秘密は、洗剤に含まれる「界面活性剤」という化学物質にあります。この界面活性剤は分子の片方は水とくっつきやすく(親水性)、もう片方は油とくっつきやすい(親油性)という、ちょっと変わった構造をしています。この特殊な構造のおかげで、油汚れを水の中に引きずり込み、小さな粒々(ミセル)として包み込むことで、汚れを浮き上がらせて洗い流すことができます。
割れないシャボン玉の秘密! 虹色に輝く膜の化学
フワフワと宙を舞うシャボン玉。子どもだけでなく大人も魅了される、あの美しい球体にも、実は化学の力が働いているのです。
水と油のように混ざり合わない物質同士はできるだけ離れようとします。もし、一方の物質がもう一方の物質の中にバラバラになっていると、お互いが触れ合う面(界面)を最小にしようとして、表面積が一番小さい球の形を目指します(水と油の二層に分かれたドレッシングを振った時をイメージしてみてください)。このように、界面を縮めようとする力を表面張力と呼びます。
純粋な水だけだと表面張力が強すぎて、水滴(水のあつまり)にしかならず、シャボン玉を作ることはできません。しかし、水に界面活性剤を混ぜると、界面活性剤の親水基は水側、親油基は空気側を向き、水と空気の間に界面活性剤が入り込みます。そうすることで、水分子同士が直接触れ合う部分を減らし、表面張力が弱まります。
表面張力が弱まった水は、水分子同士の手をつなぐ力が弱くなるため少しの力でも形を変えやすくなります。このおかげで、シャボン玉の薄い膜が安定して、空中にふわふわと浮かんでいられるようになるのです。

喉の渇きを潤す一杯の秘密! 「飲む」を支える化学技術
ジュースが濃くなる!? 「濃縮還元」の驚くべき仕組み
スーパーでよく見かける「濃縮還元」のジュース。濃縮還元とは一体どのような操作なのでしょう?
実は、果物から絞ったフレッシュなジュースは、水分が多くてかさばるため、遠くまで運ぶのが大変です。そこで登場するのが、「濃縮」という技術。水を抜いて、ジュースの成分だけをギュッと凝縮させるんです。
この濃縮の際に使われる技術の一つが、高校化学で習う「逆浸透」という現象です。通常、水は濃度の低い方から高い方へ「半透膜」という特別な膜を通り抜ける「浸透」という現象を起こします。
しかし、逆浸透では、濃度が高い方に強い圧力をかけることで、半透膜を通して水だけを濃度が低い方へ押し出します。これにより、ジュースの美味しい成分は膜の片側に残り、水分だけが取り除かれて濃いジュースができます。そして、飲むときに水を加えて元の濃さに戻すのが「還元」です。
この技術のおかげで、私たちは遠く離れた場所で採れた果物のジュースを手軽に楽しむことができるのですね。
どんな水もきれいに!未来の水を作る「浄水器」の力
私たちが安心して水道水を飲めるのは、浄水場で不純物が取り除かれているからですが、さらに家庭で使う浄水器も、水の安全を守る重要な役割を担っています。
特に高性能な浄水器には、先ほど説明したジュースの濃縮技術と同じ「逆浸透膜」が使われていることがあります。この逆浸透膜は、水分子は通すけれど、水に溶けている小さな不純物やイオンなどはほとんど通さないという、非常に細かな穴を持っています。水道水に圧力をかけることで、水分子だけがこの膜を通り抜け、きれいな水として出てくるのです。これにより、水道水に含まれる微細な不純物や塩素、さらには細菌なども効果的に除去され、より安全でおいしい水が作られます。
逆浸透膜の技術は、海水の淡水化にも使われていて、世界中の水不足の解決に貢献しています。私たちが当たり前のように利用しているきれいな水も、化学技術の結晶なのです。
美容と料理の秘密はここに! 「カラダ」と化学の深い関係
くるくるパーマ、ストレートヘアも! 「髪の毛」の化学
髪の毛にパーマをかけたり、ストレートに戻したり。美容院で用いられるこの技術も、実は奥深い化学の原理に基づいています。
私たちの髪の毛の主成分は、「ケラチン」というタンパク質です。このタンパク質の間には、「ジスルフィド結合(S-S結合)」という硫黄原子同士の強い結合があります。これが、髪の毛の形を保つ骨格のような役割を果たしているんです。
パーマをかける際は、まず1剤と呼ばれる還元剤でこのジスルフィド結合を切断し、髪の毛をカールさせた状態で2剤と呼ばれる酸化剤で再び結合させます。すると、切れた結合が新しい位置でつながり、髪の毛がカールした状態で固定されます。ストレートパーマや縮毛矯正も基本的には同じ原理で、結合を切断した後に髪を真っすぐに伸ばし、再結合させることで、ストレートな状態を維持します。
美容技術の裏には、分子レベルの精密な化学反応が隠されていることが分かりますね。
ゆでる? 焼く? 「卵」の変身はタンパク質の化学反応!
生卵はドロッとしていますが、ゆでたり焼いたりするとプルプル、あるいはカチカチに固まりますよね。そして、一度固まった卵は、基本的には元の生卵には戻りません。この不思議な変化の正体こそ、高校化学でも学ぶ「タンパク質の変性」という現象です。
卵の白身や黄身の主成分はタンパク質です。タンパク質は、アミノ酸がたくさんつながってできたひも状の分子が、複雑に折りたたまれて立体的な構造を保っています。これが生卵の状態です。しかし、熱を加えると、この複雑に折りたたまれた構造が崩れてしまい、ひも状の分子が絡み合って固まります。これが「変性」です。一度絡み合ったひもを元に戻すのは非常に難しく、だからゆで卵は生卵に戻らないのです。
かむほど甘く感じるお米の謎! 体内の化学反応の始まり
白いご飯をよくかんで食べると、最初は味があまりしないのに、だんだん甘く感じるようになる……。こんな経験はありませんか?
これは、私たちの体内で起こる、ごく身近な化学反応の一つなんです。
お米の主成分は、「デンプン」という炭水化物の一種です。デンプンは、ブドウ糖がたくさんつながった大きな分子で、そのままでは甘みを感じません。
しかし、私たちがご飯をかむと、唾液の中に含まれる「アミラーゼ」という酵素が分泌されます。このアミラーゼが、デンプンの大きな分子をプチプチと分解し始めます。デンプンが分解されると、「マルトース(麦芽糖)」という、ブドウ糖が2つくっついた形の糖ができます。マルトースは甘みを感じる物質なので、口の中でデンプンが分解されてマルトースが増えるほど、甘く感じるようになるんです。
食事のたびに、私たちの口の中ではこんなにも面白い化学反応が起きているんですよ。
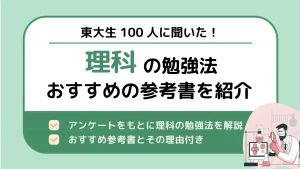
寒い日にはポカポカ、熱い日にはヒンヤリ! 温度を変える化学反応
ホカホカカイロの正体は? 「発熱反応」で冬を乗り切る!
冬の寒い日、ポケットに入れたカイロがじんわりと温かくなるのは、なぜでしょう?
使い捨てカイロの温かさの秘密は、袋の中で起きている「発熱反応」という化学反応にあります。
カイロの中には、主に鉄粉と少量の水、活性炭、塩などが入っています。外袋を開けて空気に触れると、鉄粉が空気中の酸素と反応して「酸化」する、つまりサビるのです。この鉄がサビる反応では、熱が放出されます。普段、鉄がサビるのはゆっくりなので熱を感じませんが、カイロの中では活性炭や塩がその反応を速める「触媒」として働き、効率よく熱を出すように工夫されています。こうして発生した熱が、私たちの手を温めてくれるのです。日常生活の中に隠された、身近な熱化学反応の代表例と言えるでしょう。
冷たいパックでクールダウン! 「吸熱反応」で暑さ対策!
夏場の急な発熱や、スポーツ中のアクシデントの際に役立つ冷却パック。袋をパチンとたたくと、あっという間に冷たくなるあの不思議な現象も、化学反応の力によるものなんです。
冷却パックの中には、主に硝酸アンモニウムなどの固体と、水が入った小袋が入っています。袋をたたいて小袋を破ると、中の水と固体の硝酸アンモニウムが混ざり合って溶け始めます。この「溶ける」という現象が、実は周りの熱を奪う「吸熱反応」なんです。物質が水に溶ける際に、周りの熱エネルギーを吸収して分子をバラバラにする性質を利用しているわけですね。この吸熱反応によって、パック全体が急激に冷たくなり、体を冷やす効果を発揮します。暑い日に体をクールダウンしてくれる冷却パックも、身近な化学反応が支えているんです。
冬の道を守るヒーロー!凍結防止剤が雪を溶かす化学の力
冬に雪が降った後、道路や歩道にまかれる白い粒々。これは、凍結防止剤です。この物質をまくことで、なぜ道が凍りにくくなったり、積もった雪が溶けたりするのでしょう?
その秘密は、高校化学で学ぶ「凝固点降下」という現象にあります。
まず、水が凍るという現象(凝固)について理解しましょう。凝固はバラバラに動き回っていた水分子が、規則正しくきれいに並んだ結晶構造になることです。多くの無秩序に集まっている人々が整列するようなイメージです。
純粋な水は0℃で凍りますが、水に不純物(溶質)が溶けると、水が凍る温度(凝固点)が0℃よりも低くなります。凍結防止剤の主成分である塩化カルシウム(CaCl₂)が雪や氷に触れると、カルシウムイオン(Ca2+)と塩化物イオン(Cl–)に電離します。これらのイオンが水に溶けると、水分子が整列し、結晶構造になる邪魔をします。そのため水が凝固しにくくなるのです。
これにより、水が氷になるにはもっと低い温度が必要になり、結果として雪や氷が溶けたり、再び凍りにくくなったりするのです。私たちが安全に雪道を歩けるのも、化学の力が貢献しているのですね。
日常の「ちょっとした疑問」も化学で解決!
富士山山頂でお湯を沸かすと?気圧と沸点の不思議な関係
富士山の頂上でカップ麺を作ろうとしたら、お湯が沸騰しきらず、麺がふやけない……なんて話を聞いたことはありませんか? 実は、標高の高い場所では、私たちが普段当たり前に経験している「水の沸騰」が少し違った振る舞いをするんです。
水が沸騰するのは、水が水蒸気になる勢いが、空気の重さ(気圧)に打ち勝ったときです。私たちが住む平地では、空気の重さが約1気圧かかっているため、水は100℃で沸騰します。しかし、富士山の山頂のような標高の高い場所では、空気の量が少なくなるため、気圧が平地よりも低いんです。気圧が低いということは、水が水蒸気になるのを邪魔する力が小さいということ。そのため、水は平地よりも低い温度で沸騰し始めます。富士山頂ではおよそ87℃くらいで沸騰すると言われています。これでは、高温が必要な料理はなかなかうまくいきません。身近な水の沸騰にも、気圧という環境要因が深く関わっているんですね。
気温30度は暑いのに水温30度はぬるい?体感温度の化学
真夏の猛暑日、気温が30℃を超えると「暑い!」と感じて汗が止まらなくなります。ところが、プールや海の水温が30℃だと、なぜか「ぬるい」と感じませんか? 同じ温度なのに、この体感の違いはどこから来るのでしょう?
その秘密は、空気と水の「熱伝導率」の違いにあります。
熱伝導率とは、物質が熱をどれだけ伝えやすいかを示す数値です。水は空気よりもはるかに熱伝導率が高い物質です。つまり、水は空気よりも効率的に熱を伝えたり、奪ったりする能力が高いということです。私たちの体温は常に約36℃ですが、気温30℃の空気中では、体温との温度差が小さく、空気の熱伝導率も低いため、体から熱がゆっくりとしか逃げません。そのため、暑く感じます。
一方、水温30℃の水の中では、体温との温度差は同じでも、水の熱伝導率が高いため、体から水へと熱がどんどん奪われていきます。そのため、体感としては「ぬるい」と感じたり、長くつかっていると体が冷えたりするのです。これも、身近な現象の中に隠された科学の面白い一面ですね。
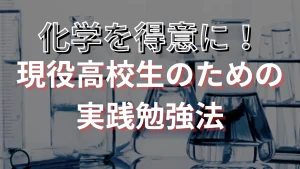
化学は、あなたの世界を「なるほど!」に変える魔法!
いかがでしたか? 化学と聞くと、難しい公式や元素記号ばかりで苦手意識を持つかもしれません。しかし、今回見てきたように、私たちが毎日経験する「なぜ?」の裏側には、いつも化学が隠れています。洗剤が汚れを落とす仕組み、髪の毛の形が変わる理由、お米が甘くなる不思議……。これらはすべて、高校化学で学ぶ知識で説明できる、身近な化学反応なのです。
化学を学ぶことは、私たちの世界が「どう動いているのか」を理解する鍵です。この「なるほど!」の体験が、きっとあなたの好奇心を刺激し、化学をもっと好きになるきっかけになるはずです。さあ、身の回りのフシギを、化学の目で探してみませんか?
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。