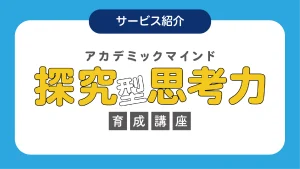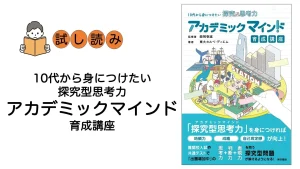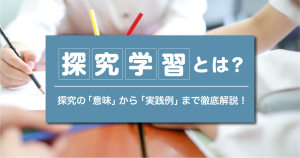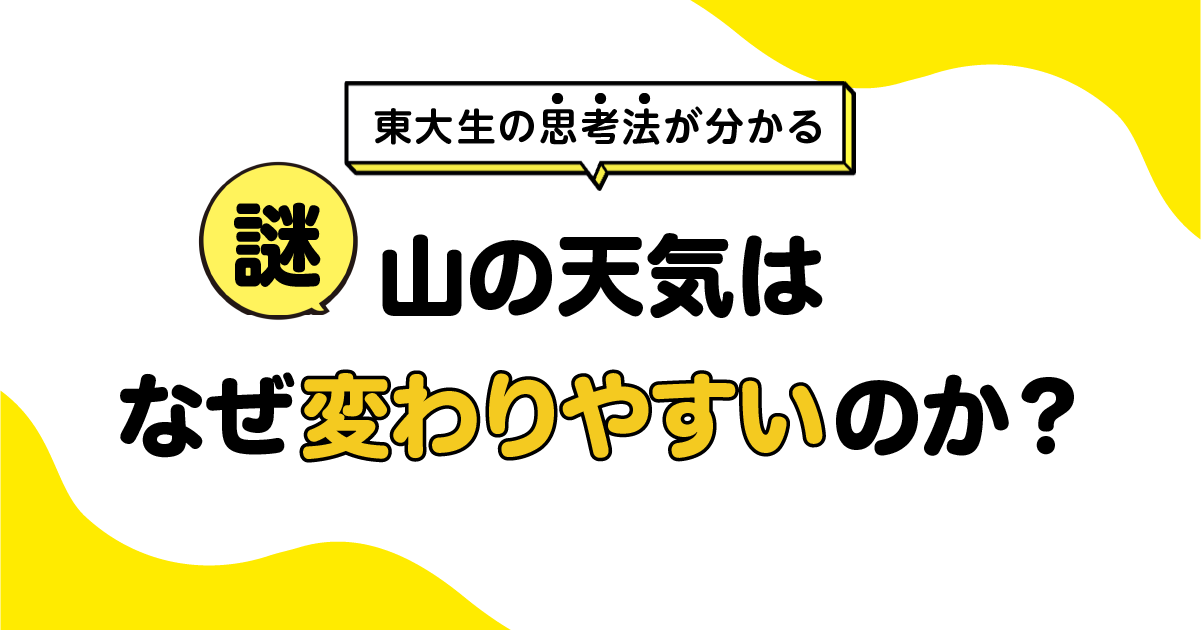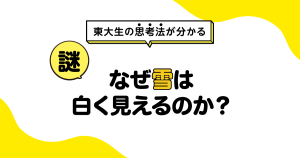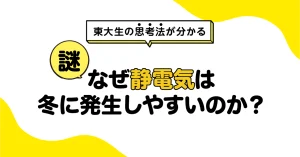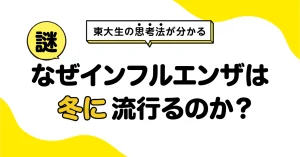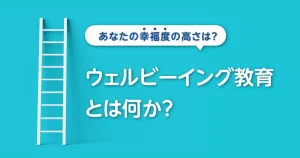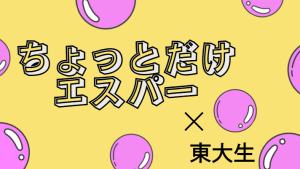山登りをしていると、朝は晴れていたのに昼には曇って雨が降ったり、突然雷が鳴ったりすることがありますよね。
「山の天気は変わりやすい」ってよく聞くけれど、一体なぜなんでしょうか?
アカデミックマインドを使って解き明かしましょう。
問いを分解してみよう!
「山の天気が変わりやすい」という疑問を分けて考えると、次の2つに整理できます。
・天気が変わるってどういうこと?
・山と平地では何が違うの?
天気が変わるってどういうこと?
天気が変わるのは、空にある雲の量や性質が大きく変わることが原因です。
雲が増えると曇りや雨に、減ると晴れに、積乱雲が発達すると雷雨になります。
では、その雲ってどうやってできているのでしょうか。
実は雲は、空気の中に含まれる水蒸気が冷やされて、水滴や氷の粒に変わったもの。
水滴や氷の粒が大きくなると、重力に耐え切れず雨や雪が降るのです。
つまり「雲ができたり消えたりするスピード」が速い場所では、天気が変わりやすいといえるのです。
山と平地では何が違うの?
山に風がぶつかると、空気は横に逃げられず上に押し上げられます。
空気は上昇すると気圧が下がって冷え、飽和水蒸気量が小さくなるため、水蒸気が水滴になって雲ができやすくなります。
特にみなさんが登山することの多い夏には、地面が太陽で温められ、空気の上昇が強くなります。
その結果、積乱雲が急に発達して夕立や雷雨になることも多いのです。
まとめ
山の天気が変わりやすいのは、
・「天気=雲の状態が変化すること」
雲は、水蒸気を含んだ空気が上に押し上げられ、冷えて水滴や氷の粒になったもの。
雲の量や性質が変わることこそが「天気が変わる」ということ。
・山では空気が強制的に上昇して冷やされるので、雲が発生・成長しやすい
山に風がぶつかると空気は強制的に上昇し、急に冷やされるため雲が発生・成長しやすい。
そのため山では、晴れから曇り、雨や夕立へと短時間で天気が変わりやすくなる。
という理由でした。
このような理由から山の天気は変わりやすいので、登山では必ず雨具を持っていってくださいね。
ここまで考えると、さらにいくつかの新しい問いも浮かんできます。
・山の夕立と都会のゲリラ豪雨は同じ仕組み? 違う仕組み?
・雨が降りやすい理由は分かったけど、雷が落ちやすいのはなぜ?
・もし山がまったくない平らな日本だったら、天気はどう変わるんだろう?
こうした「さらに問いを立てる姿勢」こそが、東大生が大切にしている「アカデミックマインド」の第一歩です。
アカデミックマインドとは
このように、1つの問いを「分解」し、「仮説」「検証」する一連の思考法を、「アカデミックマインド」と呼んでいます。
AIなどさまざまな技術が発達する中、これからの世代に求められるのが「思考力」です。共通テストや大学入試でも「自分で考える力」が試されるようになっています。
カルぺ・ディエムでは、現役東大生と一緒に「身の回りにあふれる疑問」と「五教科の勉強」を結びつけた課題に取り組み、自ら問いを立て、仮説を作り、検証する一連の思考法「アカデミックマインド」の獲得を目指す講座「アカデミックマインド育成講座」を実施中です。