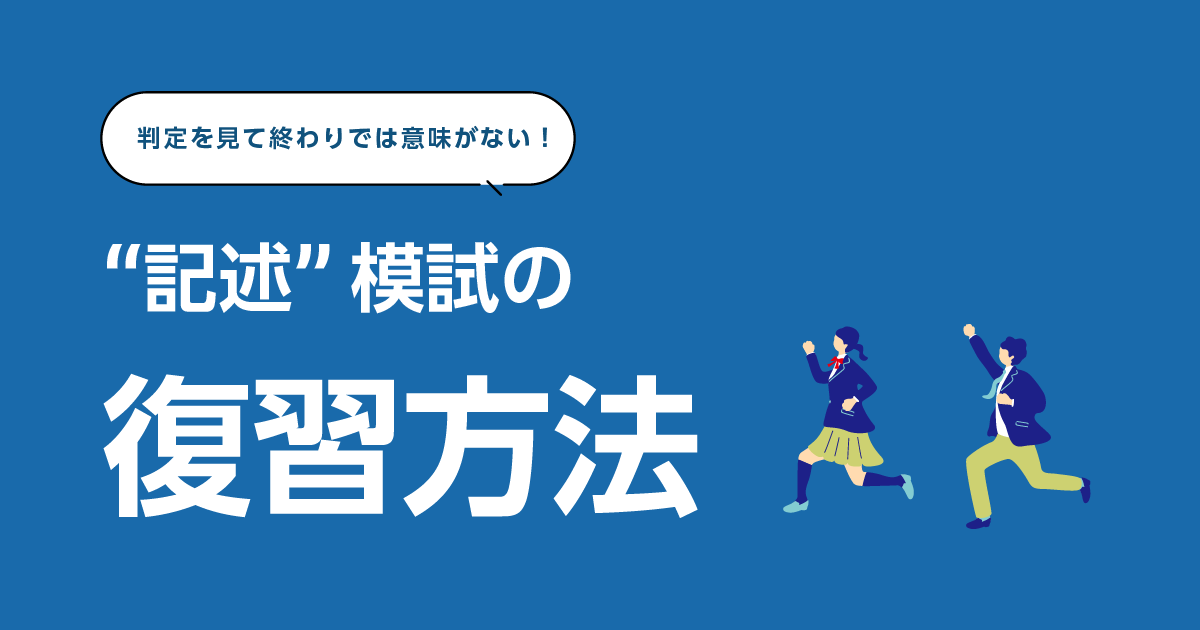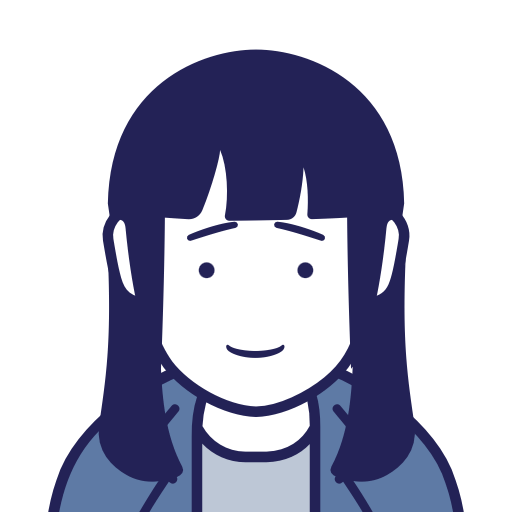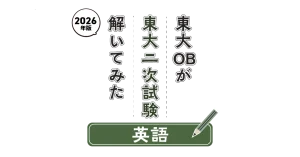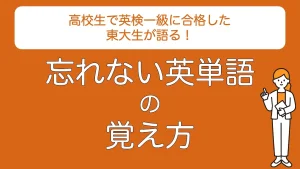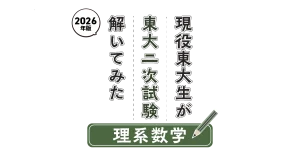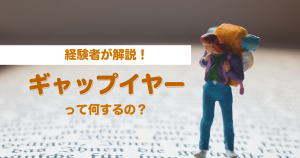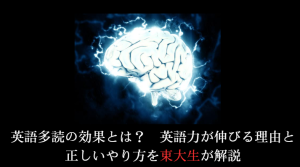はじめに
「記述模試って書くことが多いし、いつも減点されてなかなか満点がもらえないし、苦手!」
そう感じる方も多いと思います。 今回は、記述模試の振り返り方と活用方法について解説します。
前回の記事では共通テスト模試の復習方法について紹介したので、まだ読んでいない方はそちらも合わせてお読みください!
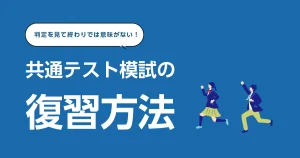
記述模試の落とし穴
なぜ記述模試は、記号問題やマーク問題に比べて難しい、めんどくさいと感じるのでしょうか。 実は、記述問題を読んで解答に至るまでに、みなさんは2つのステップを踏んでいます。
1 本文や設問の情報を正しく読み取る(インプット段階)
2 読み取った情報から、採点者に伝わるように解答を作る(アウトプット段階)
このステップ1、ステップ2のそれぞれに気をつけるポイントがあります。
これに比べ、選択肢から選べばよいだけの記号問題やマーク問題は、ステップ1だけで解答まで完結してしまいます。ステップ2がある分、手順が多く、完答で満点正解しにくくなるので、記述問題は難しいと感じるのです。
そして追い打ちをかけるようですが、記述問題の解答は、「採点者へのラブレター」と言われるほど、ステップ2が大切です。今回は記述模試の特徴であるステップ2(アウトプット段階)に重点を置きながら、復習方法を紹介していきます。
原因を自己分析
共通テスト模試の時と同じように、間違えた問題がなぜ解けなかったのか、分析していきましょう。 記述模試の良いところは、自分が考えた過程が残されている場合が多いところ。がんばって考えを形にした時間は、後に自分に役立つ道しるべになります。そのため、模試本番は、なるべく無回答の問題がないように最後まで粘りましょう。
間違えた原因を探す時は、ステップ1とステップ2のどちらで間違えたのかを常に考えるようにしましょう。
「分かっていたのに」「自分は模範解答と同じことを伝えるつもりで書いたのに」アウトプット段階で減点や不正解にされてしまうのは、よくあることです。ただ、分かっていたから大丈夫だとスルーしてはいけません。自分の解答を見る人に、自分が理解していることを伝えるまでが、解答なのです。
アウトプット段階で間違えた問題は、必要な言葉や式が足りていなかったのか、逆に余分な言葉を入れてしまった(から必要な言葉を入れる余地がなかった)のか、分析するようにしましょう。
無回答、時間不足の問題
無回答の問題や、あとで考えようと思って結局時間が足りず解けずに終わった問題については、共通テスト模試と同じように、解答を見る前に自力で解いてみましょう。マークシートを塗れば解答になる共通テスト模試に比べ、記述模試ではこれらの問題が多いので、今の自分の実力と照らし合わせるために有効活用しましょう。
教科別復習ポイント
記述問題の復習の時に気をつけるべきポイントを、英語と国語の2教科で紹介します。
英語
英語の記述模試とはいえ、設問の大半は要約や説明を日本語で書く問題なので、その復習方法を紹介します。
もしインプット段階でつまずいたと分析したのなら、長文全体を和訳したり、文章構造を把握したりして、全ての構造と日本語訳が正しく理解できている状態にしましょう。特に「that」や「it」の内容を問われる問題は、文章構造が正しくできていないと一発で間違えてしまいます。
アウトプット段階のミスで多いのが、英語を曖昧に訳してしまっている場合です。例えば強調構文「it is ~that…」や「so~that…構文」を無視して、普通の文と同じように訳していませんか?「ここに構文ありますよね!私気づいてますよ〜!訳し方も知ってますよ〜!」と採点者に全力でアピールしなければいけません。
自然な和訳の方が好きな人もいると思いますし、もちろんそれ自体が減点につながるわけではありません。しかし、答えられるかどうかを試されている箇所を、曖昧にスルーしては、元も子もありません。セオリー通りに答えるべき箇所は、「得点を取りに行くぞ!」という気持ちで、受験英語和訳でかっちり固めていきましょう。
国語(現代文)
現代文はインプット段階でつまずく人も多い教科です。英語と同様に、まずは文章を正しく読み取れるようにしましょう。東大生が書いた現代文の勉強法の記事も合わせてお読みください。
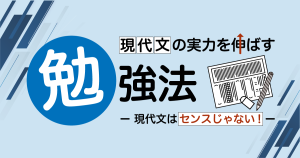
現代文の記述問題では、文章の意味は分かっていたのに、自分の解答と模範解答が「なんか微妙に違う」、まさにアウトプット段階での減点、不正解も発生します。 現代文の30字以内や60字以内の文字制限は、かなりの強敵。文字数が少ないと一見楽に見えますが、少なければ少ないほど情報を精選しなければいけません。 ただ、実はこれらの文字制限は、答える要素がちょうど過不足なく収まるように設定されているので、ヒントにもなってしまうのです!
「何を」聞かれていたのか、「どの文を中心に」解答にすれば良かったのかを理解し、自分の解答と比べ、何が余分で何が不足していたのかを分析しましょう。
まとめ
今回は記述模試の復習方法について解説しました。記述問題を1問1問復習するのは時間がかかります。ただ、繰り返しますが模試は「良問」だらけであり、自分が解いた模試は、自分の苦手が詰まっているさらに貴重なものです。やはり解いて終わりではもったいない!また少しがんばって、未来の自分のために復習してみませんか?
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。