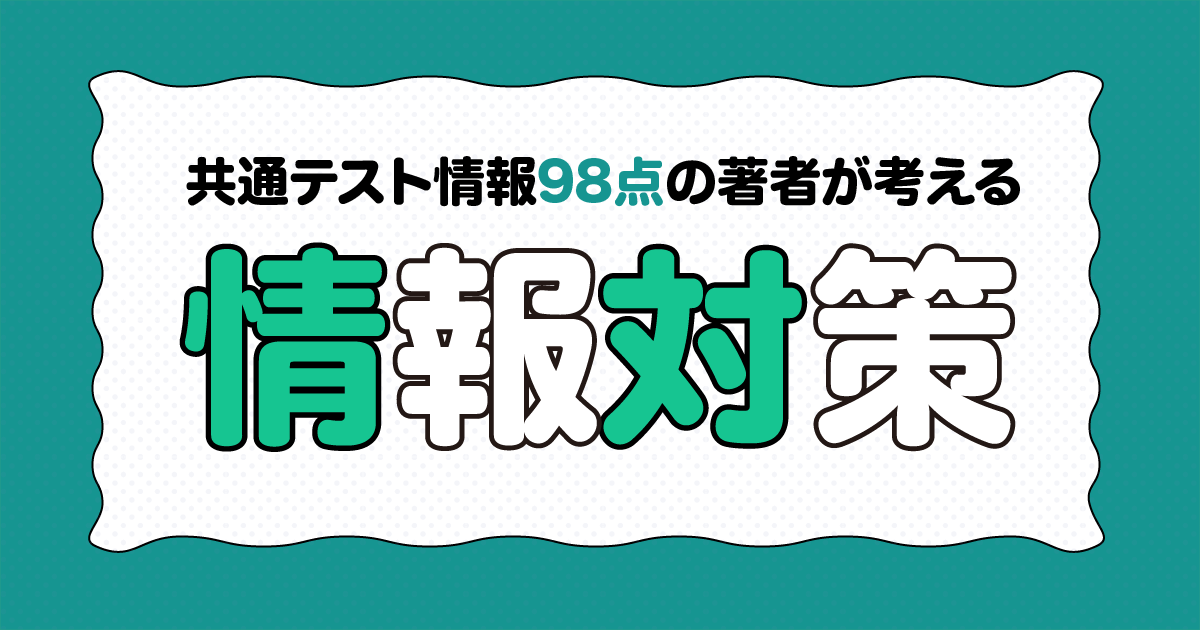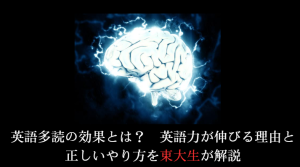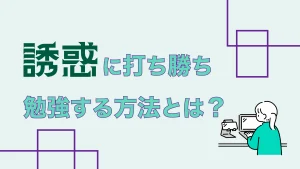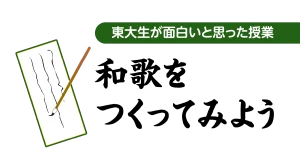昨年度から大学入学共通テストに新たな教科「情報」が加わり、受験生の皆さんは最大7教科9科目を勉強することになりました。
この新教科に不安を抱えている人も多いでしょう。
そこでこの記事では実際に初年度の情報共通テストを受けた筆者の感想を交えて新教科「情報」を紐解きます!
情報共通テストとは
情報共通テストの概要と目的
IoT・AIの進化やビッグデータ活用などSociety5.0に向けた技術革新に伴い、情報に関わる資質・能力は大学教育を受けるために必要な基礎的な能力であるとして,文部科学省は2025年度1月より新教科「情報」を導入することを発表しました。そして2025年1月大学入学共通テストにて約30万人が情報科目を受験し、気になる平均点は69.26点(※「情報Ⅰ」。「旧情報」は72.82点)と、他教科と比べやや高い結果になりました。(※大学入試センター発表資料による)
しかし平均点が高い=簡単と気を抜いてはなりません。情報学科・専攻協議会の講演資料である「令和7年度大学入学共通テスト『情報Ⅰ』の問題評価・分析」では問題の難易度について「初回の試験であることから,受験者の対応を最大限に考慮し、適切な難易度に設定された」としており次年度以降難易度が上がっていく可能性は大いにあるでしょう。
| 日程 | 【2026年度】本試験1/18・追試験1/25(いずれも2日目) | |
| 試験時間 | 60分 | |
| 形式 | マークシート | |
共通テスト情報の勉強法
では、どうやって情報は対策するべきなのか3つの観点でお話しします。
教科書と参考書の選び方
基本的には学校で使っている教科書で十分です。しかし模試などを通じて内容が不足していると感じたら別途参考書を買いましょう。また、共通テスト前は予想問題を用意して60分を通しで解く経験を積み、時間内に全問解ききれるペース配分を練習するとよいでしょう。
勉強スケジュールの立て方
まずは早い段階で情報の問題を見てみましょう。インターネット上には2025年度の過去問やサンプル問題があがっています。まだ習っていなくて分からない問題があっても構いません。まず問題を解いてみて、自分に向いているか、それとも苦戦するか試してみてください。
そして苦手だと感じる問題があれば早め早めに克服しておきましょう。受験生が勉強しなければならない科目は情報以外にもたくさんあります。しかしそこで情報を後回しにしていざ共通テスト前に問題を解いてみたら全然解けない、となれば必ず焦ります。「こういう問題苦手かも」「この選択問題は用語を覚えていたら解けそうだな」というふうにどんな問題が出るのかを知り、自分の得手不得手を考えた上で他教科との優先順位を決め、勉強スケジュールを立てていくのが一番良いと思います。
おすすめの勉強方法
基本は他の教科と同じく教科書の内容を学習し、問題演習をしていくことですが、プログラミングの分野では実際にコードをうって学習してみるのもおすすめです。こちらは比較的時間に余裕のある人向けですが、実際に手を動かすと理解が確実に深まります。またプログラミングの知識とは受験対策に関わらずこれからの社会で確実に学んでおいて損はないと思われるため、もしこの記事を読んでいるあなたがまだ高一高二でプログラミングに興味があれば、これを機にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
大問別対策方法
次にテストの大問構成について見ていきます。詳しくは実物の問題を見てほしいのですが、大まかな見通しを立てる参考になればと思います。
大問1・2 【既習の知識・技能を問う問題とその応用問題。日常生活に関連したシミュレーションなど】
SNSやコンピュータを使う上での注意や判断において適当なものを選びなさい、というリテラシーを問う問題や買い物客の列のでき方や待ち時間に関するシミュレーションなど幅広く出題されています。時にはその場で考えなければいけない応用問題もありますが、基本的には教科書の知識中心という印象を受けます。
情報にはコンピュータの構造や知的財産権など知識として覚えていないといけない範囲がいくらかあります。これは事前にどれくらいちゃんと学習してきたかが顕著になるので、まずはその知識を完璧にしましょう。他にも教科書で紹介されている論理回路だったり画素数の話だったりは考え方、計算方法まで確認しておけば、いざ問題に出た際に安心して臨めます。 あとは16進数や2進数を変換する問題なども頻出なのでよく確認しておきましょう。
大問3 【プログラミング】
共通テストでは「共通テスト手順記述標準言語 (DNCL)」という独自のプログラミング言語を用いて出題されています。字面を見ると、なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、これは所々に一般のプログラミング言語では英単語が用いられるところを日本語で表すなど、一部わかりやすく改変したものと考えることができます。
共通テストのプログラミングで重視されるのは、プログラムの表記方法ではなくあくまで「プログラミング的思考」であり、どういう仕組みを作れば、どうプログラムが実行されるのかを理解することが大切であると言えます。
大問4 【相関係数などのデータ分析】
こちらは数学の「データの分析」に非常に似通った内容であり、数学ほど計算はしないけれどその分グラフや表の読み取りが多く、複数の資料を参照する能力が必要だと思われます。こちらは数学を勉強していればさほど特別な対策はいらないと思いますが、最後の問題だけに時間が足りず解ききれなかった、なんてことがあってはもったいないため時間配分は意識して練習すべきでしょう。
時間管理法
大問4つで60分ですから大体大問1つに15分ですが、例えばプログラミングに時間をかけたいと思ったら、プログラミング20分、大問1、2、4がそれぞれ12分、見直し4分というように工夫してみましょう。
何よりも大事なのは事前に決めておいた時間配分を試験中に変えないことです。分からない問題に粘るあまり、解ける問題に手付かずではもったいないので時間管理をシビアにすることが情報高得点の鍵と言えるでしょう。
試験直前の確認ポイント
情報は2日目最後の科目です。理科や数学が終わった後で疲労が溜まっている、またはあと一教科で終わると思って気が抜けるのか、ケアレスミスが起きやすい時間でもあります。知識系を確認するのも良いですが、直前になったらしっかり休憩を取ることをおすすめします。(逆に気を抜かないために教科書を見るのもありです。自分の性格とよく相談しましょう。)
当日の試験で困ってしまったらどうするか
情報共通テストはまだまだ2年目。出題傾向や難易度が大きく変わる可能性もあります。もし試験中に困ったときは二つの想定をして自分を冷静に俯瞰します。
①自分がパニックになっている、何か見落としている
あれ?解けない……とパニックになって後々見返してみたら問題の条件を見落としていた、なんて経験はありませんか。焦っていると中々ミスに気づきにくいですが、そんな時は違う問題を解いてから戻ってくる、もう一度最初から問題を読み直す、など自分なりに頭をリセットする方法を考えておきましょう。
②その年の試験が難化していてみんな解けていない
模試では問題なく解けていたのに、どの問題も解き方が分からない。そんなときはその年が難化している可能性を視野に入れ、100点からどれだけ引かれるかではなく、0点からどれだけ積み上げられるかという考え方にシフトしてできることをやり抜きましょう。
最後に
ここまで情報の対策や考え方をまとめてきましたが、いかがだったでしょうか。
新しい教科が増えて嫌だな……と思った方もプログラミングやパズルのような問題を解いているうちに楽しくなってくるかもしれません。
この記事が情報を学ぶ方の手助けになれば幸いです。
ご一読いただき、ありがとうございました!
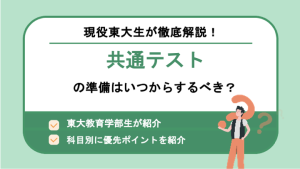
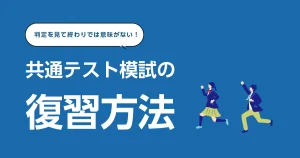
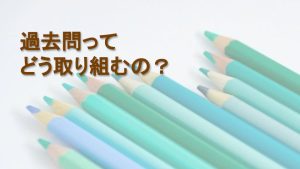
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。