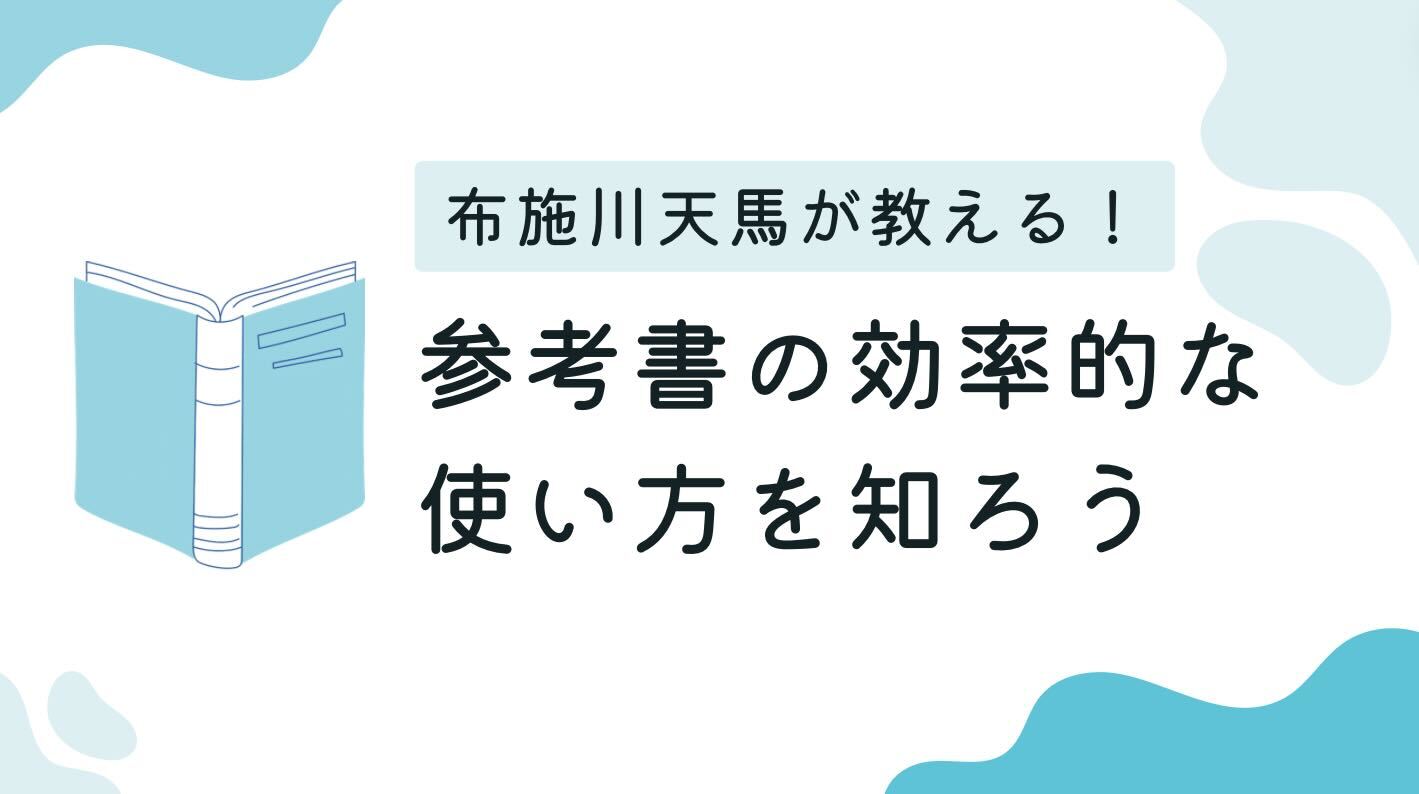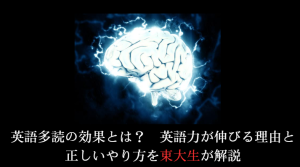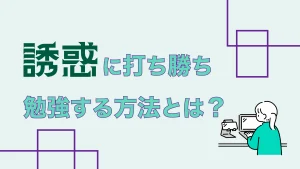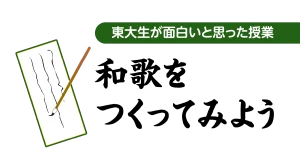みなさんは、参考書の使い方をご存知でしょうか?
最近は、内容がよく練られた素晴らしい参考書も増えており、うまく活用すれば、それだけで東大を目指すことも不可能ではありません。
実際、筆者の知り合いにも、参考書の勉強だけで東大に進学した人が何人かいます。筆者自身も、参考書による勉強だけで全国偏差値を70まであげ、東大に合格することができました。
今回はそんな筆者が、受験生の皆さんに向けて、参考書の選び方、使い方についてお伝えします。参考書を自分で選んでいる人もそうでない人も、ぜひ一度お読みください。【2025年11月1日更新】
参考書の選び方
今や無数に存在する参考書ですが、どれを使ってもいいわけではありません。全体的に学習したいのか、特定の分野だけ特訓したいのか。レベルの高いものがいいのか、基礎から学びたいのか。口コミはどうか。さまざまな面をチェックする必要があります。ここでは、チェックすべきポイントを流れに沿って紹介します。
目的やレベルに合わせて選ぶ
参考書を選ぶうえで、一番重要なのは、目的とレベルです。目的とは、その参考書を使うにあたって、効果を望んでいる効果のことです。
「自分に合った参考書」は、自分のレベル、受験までの時期などによって大きく変動します。
例えば、数学の参考書に『青チャート』というシリーズがあります。IAやIIBなど分野ごとに分かれていて、それぞれが辞書のように分厚い本です。問題数が充実していることが大きな特徴で、これに載っている問題をひととおり解けるようになれば、大抵の大学の過去問に挑戦できるレベルにまで達します。
また、別の参考書に『1対1対応』というシリーズがあります。これは、青チャートの5分の1程度の厚みしかありませんが、多くの良問が掲載されており、受験本番に必要な発想力や対応力を磨くことができます。
『青チャート』や『1対1対応』は、それぞれどのような学生に勧められるでしょうか。青チャートの特徴は、レベル1から5までに分かれた300以上にも及ぶ問題数であり、基礎から数学を学び始めて本番レベルにまで完成させたい学生にはおすすめできます。
ですが、非常に分厚いことから、一周に非常に時間がかかることが難点。高校三年生から始めたのでは、おそらく間に合わないでしょう。遅くとも、高校二年生の段階から解き進めておきたい。これを考えると、『青チャート』は「基礎から受験レベルまで数学を完成させたい高校一年生、高校二年生」におすすめできると考えられます。
一方で、『一対一対応』は薄いながらも受験に対応できるまでの良問がそろっていることが特徴。短期間で実力を養成したいならうってつけです。しかし、基礎レベルの問題は少なく、ある程度の理解力が必要になります。ですから、この本をおすすめできるのは「ある程度の実力を持っていて、本番レベルまで力を高めたい高校三年生」といえます。ほかにも、『確率が面白いほどわかる本』など、分野別になっている参考書も存在します。これらは、特定の分野の苦手を解消したい、もしくは得意をさらに伸ばしたい人におすすめできるでしょう。
このように、「自分に合った参考書」は、自分のレベル、受験までの時期などによって大きく変動します。参考書を選びに行く前に、自分と向かい合って、自分に今本当に必要なものを考えましょう。
口コミや評価をチェックする
次に、口コミや評価を確かめましょう。口コミは、「よかった」のような一言だけではなく、「内容のどこがよくて、どこがいまいちだったか」まで書いてあるものをチェックしてください。
この時に確かめるべきなのは、「どこが悪かったか」です。基本的に、詳細な口コミが付くような参考書であれば、売れている本とみて間違いないです。そして、売れているのは、中身がいいからです。ですので、その参考書は「いい本」と考えていいでしょう。
ですが、どれだけいい本だからといって、自分の使い方や考え方、勉強スタイルにあっているかは別の話ですよね。ですから、「どこが悪かった」を確認すべきなのです。その批判の内容をみれば、その参考書がどのような欠点を持っているかがわかります。
例えば、英文法の参考書にはさまざまなスタイルがあります。解説がメインの「読んで学ぶ」本もあれば、問題演習がメインの問題集もあります。もしあなたが「文法問題について解説が読みたい!」と考えているのであれば、「いい本だけど解説が少なかった」とレビューされている本は、合わない可能性が高いですよね。
優れている点は、なくても許すことができるかもしれませんが、今一つの欠点は、勉強しながらどうしても目についてしまいます。ですから、参考書を選ぶときには、優れた点よりも、欠点を気にしながら選んだ方がよいのです。
実際に本屋で選ぶ
その参考書が自分の学習スタイルに合っているか確かめるために、実際に本屋に行って手に取りながら確かめましょう。例えば、問題を解き進めながら学習を進めたいのであれば、問題数が充実しているものがいいでしょうし、まずは知識をインプットしていきたいのであれば、解説が分厚いものがいいと考えられます。
これらは、ネットの注文ページからはなかなか伝わりにくいです。実際に書店に行った人しかわからない違いがあります。あなたが選ぶたった一冊の参考書の違いで、偏差値が5ポイントも10ポイントも変わってくるかもしれません。時間を惜しまずに、書店へ足を運んで、じっくり選ぶようにしましょう。
参考書の有効活用法
参考書は買っただけでは効果がなく、実際に解き進めなければいけません。その進め方も、やはり効率の良い方法と悪い方法があります。ここでは、参考書の「使い方」についてお伝えします。
問題集
問題集を活用するときには、注意すべきポイントがあります。問題を解くだけでは、学習効果は半減してしまうので、以下の点に注意しながら学習してください。
選択肢式の問題は、「ハズレの選択肢」まで吟味する
選択肢式の問題については、ハズレの選択肢をしっかり吟味しましょう。「正解の選択肢」を選べるだけで満足してはいけません。ハズレの選択肢が、なぜ「不正解」なのか、そこまでしっかりと説明できるようになれて、はじめて問題が解けたカウントに入れます。
なぜハズレの選択肢まで吟味する必要があるのか。それは、自分がなぜ解けたのか、しっかり確認するためです。問題集を解く理由は、もちろん「問題集を終わらせるため」ではありません。目的は、「問題演習を通して、受験本番に耐えうる強靭な学力を養成すること」です。そのために、「同じような問題が何回出たら100%正解できる力」を獲得できていなくてはいけません。
選んだ選択肢が正解だった場合でも、喜ぶのは少し待ちましょう。もしかするとまぐれでアタリを引いただけかもしれません。次に類題が出た時、簡単なひっかけに引っかかってしまうかもしれません。これらを防ぐためには、「自分はこのような理由をもって選択肢を選んだ」と断言できる状態になっている必要があります。
ハズレの選択肢吟味は、「次に間違えない自分」を育むために役に立ちます。必ず、選択肢全てに目を通し、不正解の選択肢はなぜ不正解なのかまで言える状態をつくりましょう。
記述式の問題は、回答が再現できるまで復習する
記述式の問題については、解答解説を暗記してはいけません。もちろん、学習を進めるうえで、新しい考え方や知識を覚えていくことは重要ですが、そのために解説を丸暗記しても意味がないのです。
記述問題を解く上で覚えるべきは、解答解説ではなくて「解答の方針」です。解答のすべての行について、「どうしてそのような記述になるのか」答えられるようにならなくてはいけません。なぜなら、解答を丸暗記しただけでは、少し数字や設定を変えた類題に引っ掛かってしまうからです。
一方で、解答の方針を覚えることができれば、どのような問題であっても対応できます。「自分はこれをしたいから、このような操作(考え方)をしている」と、根拠をもって立ち向かえるようになれれば、対応力が身につくからです。
解答解説を読んで納得するだけではなく、1行1行すべての行について、「どうしてこのような解答を作っているのか」を、自分の言葉で説明できるようになることが重要です。
単語帳の有効活用
続いては、英語や古文の単語帳を使うときに注意したいポイントをお伝えします。
全ての単語を相手にしない
単語帳を使うときには、いくつかのルールを守ると、さらに学習効果が高まります。まず、単語帳を使うときの約束ですが、「すべての単語を相手にしないこと」を守ってください。
これは、「収録されている単語を覚えなくていい」のではありません。「学習範囲を区切って考えよう」ということです。
例えば、ここに2000単語が収録された単語帳があるとします。これを勉強しようとすると、ついつい2000単語を相手にしようと考えてしまいがちですよね。しかし、1回目に覚えるのは、せいぜい1から100までの100単語くらいが限界でしょう。
となれば、あなたが単語帳を開くときに気にすべきことは「2000単語も覚えられるかな」ではなく、「この100単語を覚えられるかどうか」であるべきですよね。2000は無理でも、100ならいけるかもしれないと思えませんか。このように、膨大な量を相手にするときは、どんどん小分けにして、敵の数を減らしていく方法が有効です。
覚えた単語は復習の対象から外す
復習のタイミングでも、「もう覚えた単語」は、わざわざ復習の対象にせず、どんどん触れる単語の数を減らすべきです。1回目にテストするときに、
- 「1秒以内に意味が答えられる単語」にはマル
- 「1秒以上5秒以下で意味が答えられる単語」には三角
- それ以上かかる単語にはバツ
をそれぞれ書き込みます。そして2回目に復習するときは、三角とバツがついた単語だけを対象にするのです。こうすれば、復習のハードルが低くなって楽になります。
筆者の場合は、三角とバツの問題に、さらに正の字をつけていました。そうすれば、何度間違えたのかが一目瞭然だからです。3回目以降の復習の時は、「正の字が2画以上ついている単語」のみに絞るなどの工夫をしていました。
付せんの使い方
よく、重要な箇所に「付せん」を貼る方がいます。一見、重要な箇所がマーキングされていて、実用的な方法であるように感じられるでしょう。しかし、これはおすすめできません。なぜなら、参考書に載っている内容の大半は重要な内容であって、無駄な内容はほとんど載っていないため、この方法では付せんだらけになってしまうからです。
付せんを貼る理由は、ほかのページよりも目立たせるためですが、これが多すぎると、付せんの中に目的の付せんが埋もれてしまい、当初の目的が達成されなくなってしまいます。この方法で付せんを使うのであれば、5枚以上の付せんは貼らないほうがいいでしょう。5枚以上になると、管理できなくなる可能性があります。
筆者のおすすめは、重要な箇所ではなく、「理解した箇所」に付せんを貼る方法です。つまり、自分にとって「もう重要ではない」と感じられる箇所に、付せんを貼っていくのです。こうすれば、いくら付せんが増えてもマイナス効果が出ることはありません。それどころか、自分の達成度が目に見えて増えていく様子がわかるので、達成感が得られます。
復習のしかた
問題演習を行ったら、その日の終わりに必ず復習するようにしましょう。問題を解きっぱなしにしていては、意味がありません。「いま解ける」ことより、「いつでも解ける」ことを目標にしましょう。そのためには、復習を通して、その問題を解く知識を定着させなくてはいけません。
復習の方法ですが、解いた問題をひととおり確認して、頭の中に解法が浮かべば大丈夫です。具体的にどのように解くか、なぜその解き方をするのか。覚えるべきは、答えではなく解答の指針なので、答えの数字や言葉だけが浮かぶのではなく、その理由がわかっているかを確かめるように復習してください。
学習計画の立て方
学習のためには、効率的な学習計画の立案が不可欠です。どの参考書を、いつまでに、どれくらいのペースで終わらせるか。そして、その結果、どのような学習効果を得るか。ここまでを設定したうえで学ばないと、「ただ参考書を読んだだけの人」になってしまいます。やり始める前に、まずは学習計画を立てるようにしましょう。
期限や目標を設定する
まず設定すべきは、最終的な目標です。「○○大学合格」「定期テストで学年一位」「○○模試で全国偏差値70をとる」など、なるべく具体的な目標を立てましょう。
そして、そのために必要な参考書を選定します。参考書の選び方については既にお伝えしました。自分に足りないと思われる要素について、それを補充してくれる本を選びましょう。
次に、どの参考書をいつまでに終わらせるか計画を立てます。例えば、「東大合格」が目標だった場合、数学の参考書である『青チャート』をひととおり終わらせれば、ある程度入試問題に太刀打ちできます。だからといって、入試前日に解き終わるような計画を立ててしまうと、まずいですよね。過去問演習をする時間が残らないからです。
参考書学習を終えたら、過去問演習を通して本番力を身につけたいですよね。そう考えると参考書は、入試本番の半年から3カ月前には終わっていたいです。では、入試本番の半年前、すなわち、入試前年の8月9月ごろまでに、今から数えて何か月の猶予がありますか。そして、その日に終わらせるためには、1日何ページの学習を進めていけばいいですか。
このように考えて計画を立てます。大事なのは、「いつまでにその参考書を終わらせるべきなのか」と、「その期限までに、あと何日の猶予があるのか」を考えること。1日に何ページ進めるかは、その結果として出てくるものです。「1日3ページくらいでいいかな」と見切り発車をせず、そのペースで終わるかを確かめてから、解き進めましょう。
時間の使い方
参考書と言っても、単語帳や、読み物系、問題演習中心の本など、様々な種類があります。これらは、それぞれの特徴によって、解くべきタイミング、そうでないタイミングがあります。
例えば、単語帳は、比較的どこでも勉強しやすいものです。なぜならば、単語帳を引っ張り出して開けば、その瞬間に勉強を開始できるものだからです。読み物系もそうかもしれませんが、単語帳よりも内容を理解する必要がありますから、学習のしやすさは少し劣るかもしれません。
問題演習系の本は、この中では一番勉強しにくいです。普通、演習をするにあたって頭の中だけで解き進める人はいないでしょう。ノートも一緒に開いて、そちらに解いていくものです。そのためには、ノート、ペン、そしてそれらを広げる机が必要になります。
こう考えると、自習室のような、落ち着いてじっくり勉強できる環境で、わざわざ単語帳のためにまとまった時間を割くのは逆にもったいないです。単語帳学習は電車の中でも、家に帰ってから寝る前の時間でも、時と場所を選ばずに学習が開始できるからです。
一方で、問題演習はそうもいきません。電車の中でノートとペンを引っ張り出しても広げる場所がないからです。このように、一口に学習と言っても「いつでもできる学習」と「時と場合が限られる学習」に分けられます。自分に与えられた時間、環境はどうか、今からやろうと考えている学習は、それらにあっているか。これを考えることで、学習効率はグッと高まります。
おわりに
筆者の経験を交えながら、参考書の選び方と使い方について詳しく紹介しました。どんな参考書や勉強法も、使い方によって、良いものにも悪いものにもなります。効果を最大限発揮できる勉強法を実践して、合格までの距離を縮めていきましょう。
文責:布施川天馬/編集:メディア事業部
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。