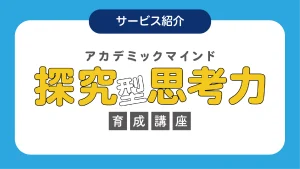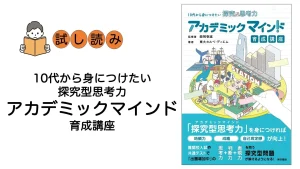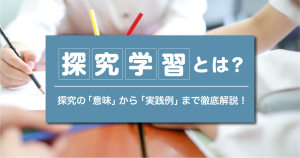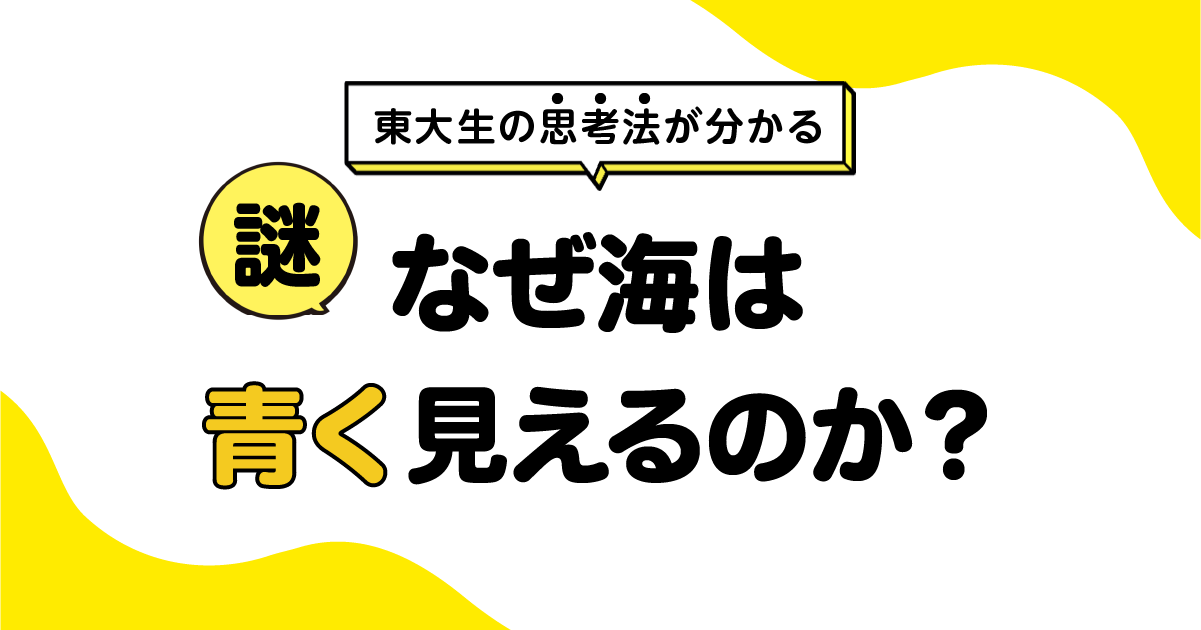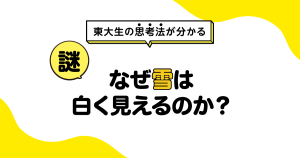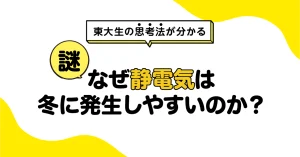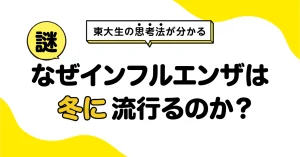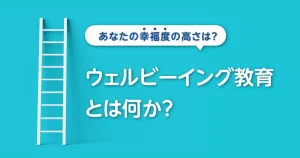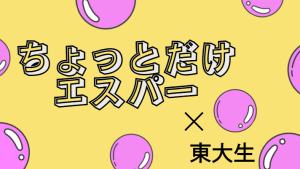海の水は透明ですが、遠くから見ると深い青に見えますよね。「空の色を映してるから」って聞いたことがある人も多いのではないでしょうか? でも、それだけでは説明できないんです。
問いを分解してみよう!
「なぜ海は青く見えるの?」という疑問を、次のように分けて考えます。
・「色」をどうやって認識しているのか?
・「水」はどんな性質をもっているのか?
「色」をどうやって認識しているのか?
私たちが認識する「色」は、光が目に届くときに、どんな光が残っているかで決まります。
例えば、トマトは「赤い光」を反射するから赤く見えますし、木の葉は「緑の光」を反射するから緑に見えます。
つまり「どんな光を反射して、どんな光を吸いこむか」によって色が分かれるんです。
太陽の光は「白」に見えますが、実は「赤・黄・緑・青・紫など」のさまざまな色の光が混ざっています。この複数の色のうち、どの色を反射するかは物質によって異なるのです。
「水」はどんな性質をもっているのか?
水は一見透明ですが、実は、光の中の「赤っぽい光」を少しだけ吸いこむ性質があります。
浅いコップの水だと吸いこまれる量がとても少ないので透明に見えますが、海のように何十メートルも光が進むと、赤い光がどんどん吸い込まれて弱くなっていきます。その結果、「吸い込まれにくい“青い光”だけが残って、私たちの目に届く」ので、海は青く見えるんです。
なぜ海は青く見えるのか?
・太陽の光はさまざまな色が混ざっている
・ その光が海に入ると、水が赤っぽい光を吸い込んでしまう
・青い光だけが残って、あちこちに広がる
・私たちの目には、その青い光が届く
ですので、海は「空の色を映している」のではなく、水の中で“青い光だけが生き残っている”から青く見えるのです。
補足
今回の話では、「水は赤っぽい光を吸いこんで、青い光を通す」と説明しました。でも実は、高校や大学で物理を学ぶと、「なぜ赤い光が吸い込まれるのか」を、光の“波の長さ(=波長)”という考え方から説明できるようになります。
今はまだ難しく感じるかもしれませんが、光を「波」としてとらえると、海の青さのしくみも、もっと深く・美しく理解できるようになるんです。
ここまで考えると、さらにいくつかの新しい問いも浮かんできます。
・夕方の海がオレンジっぽく見えるのはなぜ?
・湖や川はどうして透明に見えるんだろう?
このように「さらに問いを立てる姿勢」こそが、東大生が大切にしている「アカデミックマインド」の第一歩です。
アカデミックマインドとは
このように、1つの問いを「分解」し、「仮説」「検証」する一連の思考法を、「アカデミックマインド」と呼んでいます。
AIなどさまざまな技術が発達する中、これからの世代に求められるのが「思考力」です。共通テストや大学入試でも「自分で考える力」が試されるようになっています。
カルぺ・ディエムでは、現役東大生と一緒に「身の回りにあふれる疑問」と「五教科の勉強」を結びつけた課題に取り組み、自ら問いを立て、仮説を作り、検証する一連の思考法「アカデミックマインド」の獲得を目指す講座「アカデミックマインド育成講座」を実施中です。