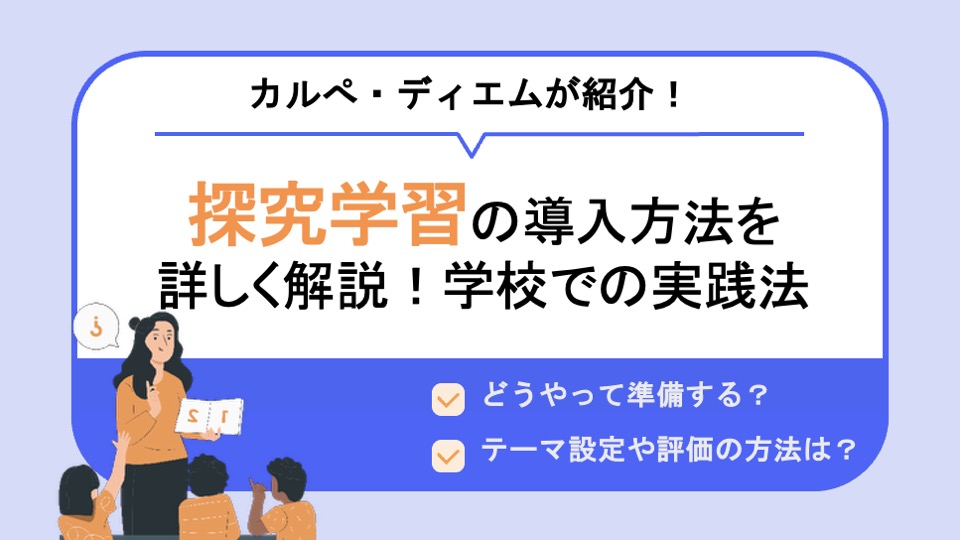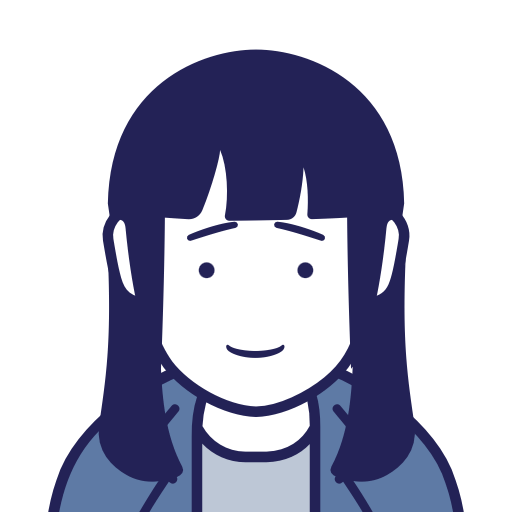新学習指導要領でも重視されている「探究学習」。生徒が自ら問いを立て、試行錯誤しながら学びを深めていくプロセスは、これからの時代に欠かせない力を育むものです。しかし、いざ授業に取り入れようとすると、どのように導入すればよいのか戸惑う先生も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、中学校・高校の探究学習に関するさまざまなパッケージを展開している株式会社カルぺ・ディエムが、探究学習を学校現場にスムーズに導入するための具体的なステップと、実践で役立つ工夫を分かりやすく解説します。
探究学習とは?
今日聞くことが増えた「探究学習」とは、そもそもどのようなものでしょうか。
探究学習の目的と意義
探究学習とは、「日常生活や社会に存在する課題を出発点に、その本質を自ら探り、理解を深めていく学び」のことです。課題を設定し、情報を収集・整理・分析し、最後にまとめや表現へとつなげる一連のプロセスを経て、「主体的・対話的で深い学び」を実現します。日常生活で疑問に思った課題を生徒自身で設定したり、先生が提示したいくつかのテーマの中から課題を選んで深めたりすることが多いのが特徴です。「問いを発見し、仮説を立て、検証する力」は、生徒が将来を生き抜く力を育てるうえで欠かせない学習として位置づけられています。
弊社カルぺ・ディエムでは、この力を「アカデミックマインド(探究型思考力)」と名付け、学校や生徒に合わせてサービスを展開しています。ぜひ以下のサービス紹介の記事もあわせてお読みください。
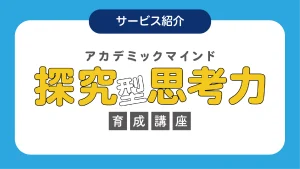
一般的な教科学習との違い
教科学習が「各教科の知識や技能を身につけ、課題解決や表現力の基礎を養う学び」であるのに対し、探究学習は、それらを総合的に活用し、実社会や実生活に関わる課題を多角的に捉えて解決を試みる点に特徴があります。両者とも「主題」や「問い」を軸としますが、探究学習では特に「答えが一つに定まらない問い」を扱い、生徒が自ら考え続けることを重視します。答えのない問いに向き合うことで、忍耐力や主体性など、非認知能力を養うことができます。
探究学習が求められる背景
近年、学力観は大きく変化しています。OECD(経済協力開発機構)のPISA調査では、単なる知識量ではなく「身につけた知識や技能を実社会の課題解決にどの程度活用できるか」が問われるようになりました。こうした国際的な評価基準の変化は、学校現場においても「知識を覚える教育」から「生徒が自ら課題を見つけ、考え、学びを深める教育」へと大きな転換を促しています。
学校への探究学習の導入準備
探究学習の目的と概要が、分かってきたと思います。探究学習を効果的に実践するためには、導入準備が欠かせません。ここでは、学校で探究学習を取り入れる前に準備しておきたいことを整理し、先生方が安心してスタートできる手順をご紹介します。
先生の役割
探究学習では、教師は「知識を教える人」から「学びの伴走者」へと役割が変わります。生徒の興味関心を引き出し、問いを深めるファシリテーション力や、調査・情報収集の方法を適切に指導するリテラシーが重要です。また、すぐに答えを教えるのではなく、見守る姿勢を持ち、生徒が自ら考える余白をつくることも非常に大切です。全体を見守りながら、つまずいていそうな生徒にはヒントの声かけをしましょう。
計画の立て方
探究学習は一度の授業で完結するものではなく、段階的に組み込むことが効果的です。たとえば中学校や高校では、1年次にリサーチの基礎を学び、2年次に実際に自分でテーマを考え、検証し、3年次に成果発表へと進む学校があります。小さな探究活動から始めることで、生徒も先生も無理なく進められます。
学校内の体制づくり
探究学習は、学年や教科を横断して取り組む学習です。担当者を明確にし、定期的に情報共有や研修を行うことで、探究のノウハウを蓄積しやすくなります。その上で、理科系のテーマなら理科の教科担当の先生、歴史系のテーマなら社会科の教科担当の先生といったように、生徒の学習の相談を各教科担当の先生が見る環境を整えるとなお良いです。筆者の中学校では、生徒の探究テーマそれぞれに担当の先生を割り振り、困った時に相談できるしくみになっていました。また、地域や大学など、外部との協力体制をつくると、生徒の学びを広げることができます。
生徒や保護者への説明
探究学習は「受験に直結しないのでは」と誤解されがちですが、探究学習は思考力・表現力を伸ばし、入試改革の方向性にも合致しています。保護者会や説明資料を通じて、将来につながる学びであることをわかりやすく伝えることが大切です。
探究学習の具体的な実施方法
準備が整ったら、いよいよ探究学習を授業として実践していきます。「自由にやらせる」だけではなく、教師が適切なステップを設計し、生徒の主体性を引き出す流れをつくることが大切です。ここでは、探究学習を学校現場で実際に展開するための方法を解説します。
テーマ設定の方法と活動計画
探究学習の出発点は「問い」の設定です。テーマは「生徒の関心」と「社会的な意義」が重なる部分から選ぶと、質の良いテーマで探究学習を行うことができます。先生は生徒の興味を丁寧に聞き取りつつ、社会や地域とどう結びつくかを示せると良いです。「ゲーム」や「アイドル」など一見勉強と関連付けにくそうなテーマでも、「eスポーツは本当にスポーツと呼べるのか?」「ファンビジネスはどうして儲かるの?」など、見方によっては良い探究学習のテーマにすることもできるので、生徒が気づいていない新しい切り口を提示してあげましょう。そのうえで、活動の流れを計画し、小さな探究から段階的に進めると取り組みやすくなります。
調査の指導
課題を深めるには、適切に情報を集め、整理し、分析する力が欠かせません。授業では、基本的なインターネット検索の方法、信頼できる情報の見極め方、データの扱い方を指導する必要があります。特に、インターネットや生成AIの情報が正しいかどうか判断する力を身につけるために、繰り返し指導しましょう。また、生徒が実施するインタビューやアンケートなど、一次情報の収集方法を実践させることで、単なる調べ学習だけではなく、生徒が実際に「調査する」過程を経験することができます。
探究活動の進め方
学びを一層深めるには、実際に行動する体験的な活動を取り入れることが有効です。地域でのフィールドワーク、専門家へのインタビュー、実験や観察といった活動は、生徒に新しい気づきを与えます。その際には、安全面への配慮や事前準備を十分に行い、活動の目的や手順を明確にしてから取り組むことが成功の条件です。また、アポイントメントの取り方や、実際に訪れた時の振る舞い方、お礼のしかたなどを生徒が学ぶことで、今後に役立つ知識やマナーを身につけることができます。
評価
探究学習の評価では、成果物だけでなく、過程そのものを重視する必要があります。問いの立て方や調査の工夫、仲間との協力の姿勢といったプロセスを段階的に評価することで、生徒の努力や成長を適切に可視化できます。また、先生からのフィードバックを繰り返し行うことに加え、生徒自身で振り返る時間を作ることで、自らの学びを振り返る習慣が身につき、次の課題発見にもつなげることができます。
成功事例
探究学習を導入する際、参考になるのが、すでに学校現場で成果を上げている事例です。探究学習を効果的に取り入れた学校の取り組みを紹介し、実践に役立つポイントを整理します。
地元企業と商品開発に挑戦
新潟県のある公立高校では、地元食品メーカーと連携した探究学習プロジェクトを実施しました。生徒たちは地域が抱える「若者の地元離れ」や「伝統食文化の継承不足」といった課題を発見し、「若者にも受け入れられる、現代風にアレンジした伝統食品をつくろう」とテーマを設定。食品メーカーの協力のもと、商品の企画から試作、マーケティング調査、パッケージデザインまでを自ら手がけました。
地域や企業を巻き込んだ「放課後プロフェッショナル」
兵庫県の公立高校では、希望者を対象とした特別講座「放課後プロフェッショナル」を実施しました。地域や企業と一緒に、アイデアの社会実装を目指す共創プロジェクトです。生徒は、空き家解消・観光活性化・地場産業の3つのテーマについて、データに基づいた課題分析や解決策の検討を行い、アイデアをより実現可能なものにするために、ビジネスやエンジニアリングのスキルを持つ企業の社員がフィードバックや助言を行い、課題解決に一緒に取り組みました。
「地域の魅力発信」PR動画
静岡県の私立高校では、「地域の魅力発信」をテーマに探究学習を実施し、生徒が観光PR動画を制作するプロジェクトを展開しました。全国的な観光PR動画コンテストで2年連続グランプリを受賞する成果を上げただけでなく、生徒の主体性やチームワークも飛躍的に向上したとの報告があります。動画という表現活動を通して、地域とつながりたいという気持ちを形にできる点が、この取り組みの大きな魅力でした。
参考:高校生が作る地域PR動画!探究活動の成果に自治体や企業も注目!!
導入で直面しがちな課題とその解決策
探究学習を授業に取り入れようとすると、多くの先生がいくつかの共通課題に直面します。ここでは、探究学習導入時によく起こる課題を整理し、それぞれに対する具体的な解決策をご紹介します。
テーマが広すぎる
探究学習では、「自由にテーマを決めていい」とだけ言っても、生徒が主体性を発揮する前に何をすれば良いか理解できず、圧倒されてしまうことがあります。そのため、まずは身近で興味関心の高いテーマに絞り込み、教師が具体化をサポートすることが効果的です。たとえば「地方創生」「食問題」「環境問題」など、複数のテーマの中から選べるようにするのも一つです。生徒にとってはこれらのテーマもまだ広いくらいなので、さらに絞るのも良いでしょう。テーマが明確になることで、生徒は学びを進めやすくなります。
時間不足
探究活動に十分な時間を割けないと、表面的な学びにとどまってしまいます。これを防ぐためには、年間カリキュラムの中で探究専用の時間を確保し、短いサイクルを複数回設けることが有効です。小規模な探究を積み重ねることで、生徒の探究力を段階的に育成できます。
評価が曖昧
成果物のみを評価すると、探究の本質が見えにくくなります。大切なのは、先ほど紹介した、問いの立て方、調査の工夫、協力の姿勢、表現方法といったプロセスの一つ一つに焦点を当てることです。また、各段階での評価基準を明確にし、形成的評価を行うことで、生徒の努力や成長を正しく可視化できます。
探究学習を続けていくための環境づくり
探究活動を一度導入しても、単発で終わってしまっては生徒の主体的な学びは定着しません。大切なのは、学校で継続的に探究活動を続けていくための環境づくりです。探究活動を持続させるための具体的なポイントと工夫を紹介します。
校内における探究学習の文化の醸成
探究学習を単発の「イベント」で終わらせず、教室の日常や学校の風土へと浸透させることが重要です。「なぜ?」という問いかけを授業の節々に置くことで、生徒が自らの思考を深め、探究的な姿勢が自然と根付きます。さらに、探究の成果やプロセスを校内で共有する機会を定期的に設けることで、体験が先生間・学年間に共鳴し、学校全体で探究文化が醸成されていきます。保護者や地域の方の声も取り入れながら、文化づくりをしていきましょう。
地域や外部機関との連携
地域や大学、自治体、企業と連携することで、生徒の学びは「教室を越えた学び」へと昇華します。たとえば、地域資源を活用したスタディツアーでは、生徒が現場に赴き、地域住民や専門家と対話しながら課題を探究します。このような体験は、生徒にとっての学びをリアルなものにし、探究を続けたいという意欲を育てます。また、学校と地域がWin-Winの関係でつながることで、探究の機会や支援体制が継続的に整備されるようになります。
参考:新時代の探究学習 – 地域と共に成長する高校生たちのスタディツアー
先生間の情報共有とスキルアップ
先生自身の探究指導力を高め、校内で共有する仕組みも肝心です。定期的な校内研修会や研究会を通じて、成功事例や課題、指導の工夫を先生間で共有しましょう。さらに、ICTを活用した教材やツールの共有も効果的です。こうした取り組みにより、先生にとっても探究が継続的に改善される学びのフィールドとなり、探究学習の継続性を支える基盤が築かれます。
おわりに
探究学習は、生徒の主体性や思考力を育む有効な学びの手法ですが、導入や継続には工夫と環境づくりが欠かせません。今、探究学習を取り入れていない学校にも、先生方が少しずつ取り入れながら、自校に合った形で探究学習を深めていくことが、大切な第一歩となります。本記事を読んだ先生方が、探究学習を積極的に取り入れ、生徒の新しい学びの扉を開く手助けをしていただければ幸いです。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。