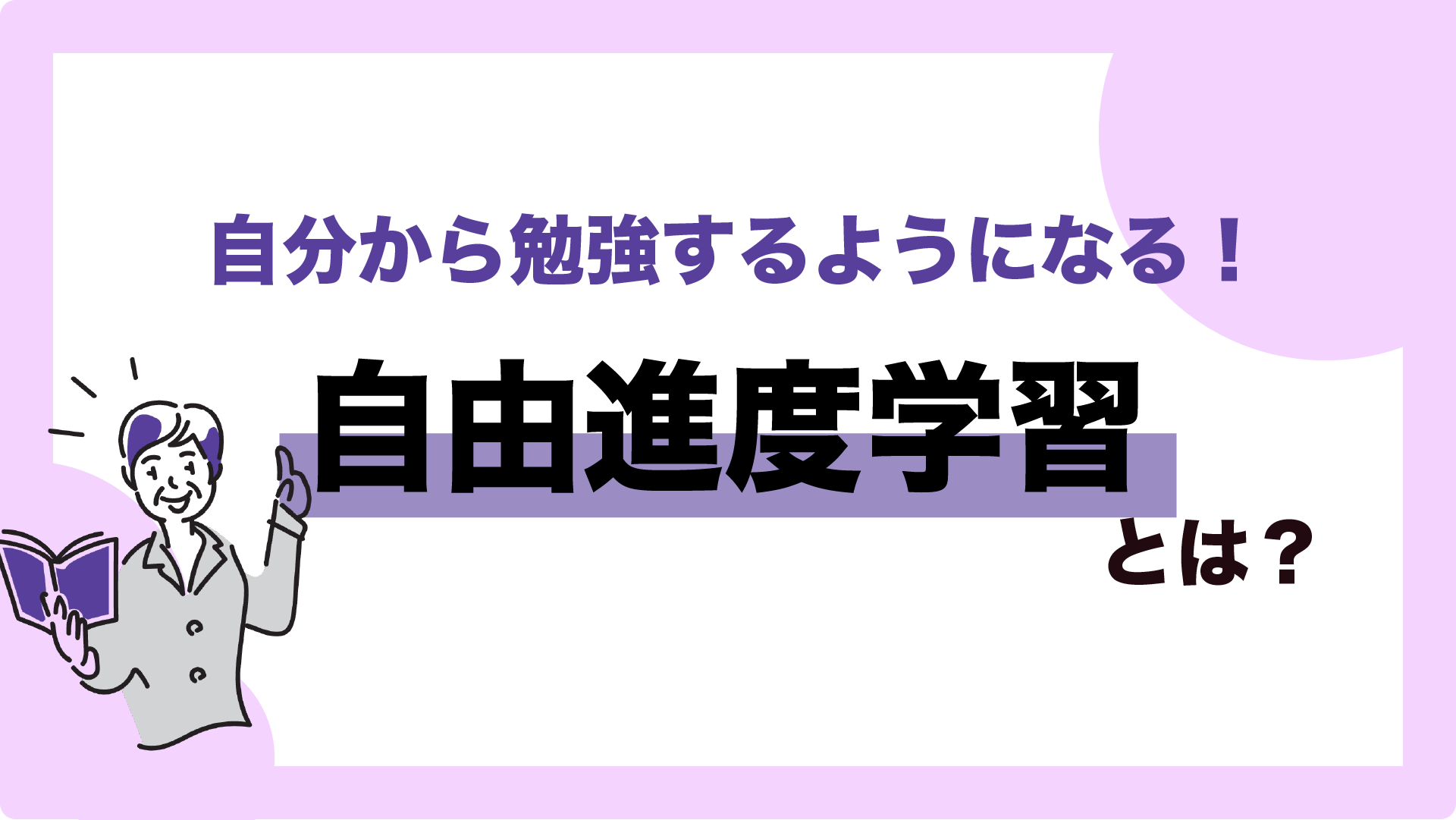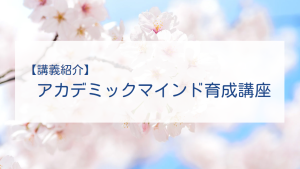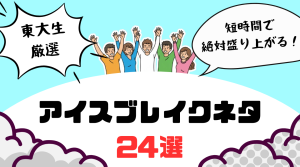昨今の学校現場は、めまぐるしい勢いで進化を続けています。一昔前まではクラスで1個だったタブレットが今では多くの学校で1人1台に。そんな姿を変え続ける教育現場では、最近「自由進度学習」という勉強法が注目されています。
本記事では、生徒の自主性や思考力を重んじるための手法である自由進度学習の中身から導入のメリット・デメリットまでを紹介します。
自由進度学習ってなに?
最近注目されている自由進度学習ですが、一体何をしているのでしょうか? まずはその実態に迫っていきましょう。
自由進度学習の考え方
自由進度学習とは生徒一人ひとりが自分のペースで学習を進めていく考え方。生徒が自分の理解度や興味に応じて学習内容や進度を選択できる点が最大の特徴です。教師は知識の一方的な伝達者ではなく、生徒の学習をサポートする助言者、あるいは伴走者としての役割を担います。
今までの授業方法との違い
従来の一斉授業では、教師が学級全体に同じ内容を同じペースで教えていました。しかし、もちろんですが生徒によって理解度や学習速度は異なります。学校の授業で「全然ついていけないが、授業がどんどん進んでいってしまう」「自分にとっては簡単な内容なので聞く必要がないが、聞かないと注意されてしまう」といった状況になってしまいます。
一方、自由進度学習では、生徒個人に沿った学習教材を使用できることから自分の理解度に合わせて学習を進められ、個々の学習ニーズに対応することができます。またタブレット端末やデジタル教材を活用することで、よりきめ細やかな個別対応が可能になっています。
なぜ今注目されているのか?
さて、ではなぜ最近になって注目されているのでしょうか?
一つにあるのは、環境の整備です。2019年に文部科学省の主導で始まった、GIGAスクール構想による1人1台端末の普及がこの自由進度学習の実現を後押ししています。生徒個人の状況に合わせた教材の準備・配布が容易になるためです。文科省の令和3年の調査によれば、全国公立の96.2%が、「全学年」または「一部の学年」で端末の利用を開始した、というデータがあるように、昔では考えられないほど普及が進んでいます(注1)。
さらに、同省が勧めているアクティブラーニングの観点からも、主体的に学び、問題解決できる人材の育成が求められているという背景が存在します。
自由進度学習のメリット
さて、そんな自由進度学習のメリットについてみていきましょう。
それぞれのレベルに合わせて取り組める
「十人十色」という言葉のとおり、学習の理解度や進度は生徒によって千差万別です。自由進度学習では、この個人差を強みに変えることができます。数学が得意な生徒は先へ先へと進み、じっくり考えることを好む生徒は腰を据えて学習に取り組む。そんな多様な学びのスタイルを生み出す柔軟性が、この学習法にはあります。
子どもが自分から取り組める
「やらされている」から「やりたい」への意識の転換。これこそが自由進度学習の醍醐味です。学習内容や進度を自己決定できる環境は、子供たちの中に眠る「学びたい」という本能的な意欲を刺激します。自分で決めた目標だからこそ、その目標に向けて全力で取り組むようになるのです。そこには、従来の受動的な学びでは見えなかった、子供たちの生き生きとした表情があります。
勉強のやる気が起きる
小さな進歩の積み重ねが目に見えて体験できることで、子供たちは「できた!」という確かな手応えを感じることができます。そしてこの積み重ねこそが、次の学習への意欲を生み出す好循環へとなるのです。
また、子供がやる気を損なう原因の一つには、他人と不毛な比較をすることで劣等感を抱くから、というものがあります。自由進度学習なら、自分専用のチェックポイントとゴールを作り自分のペースで進めることができるため、他人との比較から解放され、学習への不安や焦りが自然と薄れていくのです。
自由進度学習のデメリット
一見導入すると良いことしかなさそうな自由進度学習ですが、デメリットも存在します。
教師の負担が増える
教師は、個々の生徒の進度や学習状況を丁寧に把握し、継続して管理する必要があります。従来の一斉授業とは比べ物にならない準備と工夫が必要となり、そのための時間と労力は決して小さくありません。デジタルツールの活用で効率化できる部分もありますが、より一層教師の創意工夫と献身的なサポートが必要になるのです。
自己管理能力が必要
学習の自由度が格段に高まる分、生徒自身の自己管理能力が試されることになります。計画を立て、それを実行に移し、進捗を管理する。最初は教師のサポートがあるにしても最終的にはこの一連のプロセスを自律的にこなすことが求められます。特に低学年の児童にとっては容易ではなく、そこには教師による適切な足場かけが必要不可欠になってくるのです。これは、前述の教師の負担にも繋がります。
自由進度学習の具体的なやり方
実践方法
自由進度学習の代表的な方法として、一歩一歩を着実に積み重ねていく「単元自由進度学習」があります。
まず、単元の狙いと時間数、学習の流れを示した羅針盤を用意します。これをもとに、生徒たちは自分だけの学習計画を練り上げていきます。45分という限られた時間を、導入の10分、自由進度学習の25分、振り返りの10分と区切ることで、学びにリズムが生まれます。
導入と振り返りは一斉授業にし、両方の形態を織り交ぜることで、生徒たちは「共に学ぶ時間」と「自分と向き合う時間」のバランスを体感できます。一部一斉授業にすることで教師の負担も減らしつつ、自由進度学習の時間で一人ひとりの歩みを丁寧に見守りながらその子なりの学びの発見に耳を傾けます。
(参考:https://surala.jp/school/column/4282/)
実践事例①(広島公立小学校の場合)
広島公立小学校の取り組みは、まさに自由進度学習の真髄を体現する好例と言えるでしょう。2020年から一部の授業に導入された自由進度学習では、画期的な成果を出しています(注2)。
特筆すべきは、算数の授業における「自己選択・自己決定」の仕組みです。生徒たちは配布された学習計画表を見ながら、自分の理解度に合わせて教材を選び、学習を進めていきます。挑戦する順番も生徒が選びます。例えば少数の単元では、ヒントカードを活用しながら、基本的な計算から応用問題まで各自のペースで進めていきます。
さらに注目したいのは、この取り組みを導入した学校の中で、教え合いの文化が自然と根付いていった点です。生徒たちはお互いに教え合い、学び合う中で、「わかる」という喜びと「教える」喜びの両方を体験しています。これは従来の一斉授業では見られなかった、新しい学びの形と言えるでしょう。
この取り組みの成果は、冒頭で言ったとおり数字にも現れています。単元テストの結果は軒並み上昇し、「学び」に対する生徒たちの姿勢は大きく変化しました。「わからないことをわからないと言える」「自分のペースで確実に理解できる」という安心感が、学習意欲の向上につながっていると思われます。教室内にはタブレット端末やヒントカード、個別の学習教材などのような学習ツールが用意されています。これらは単なる道具に収まらず、生徒の「学びたい」という意欲を支える重要な足場となっています。
このように、広島公立小学校の実践は、自由進度学習が単なる理論ではなく、確かな成果を生み出す教育手法であることを実証しています。
実践事例②
茨城県の緑桜学園那阿市立芳野小学校の取り組みは、ICTを活用した自由進度学習の可能性を広げる素晴らしい実践例と言えるでしょう。同校では小学5年生の社会科で、自然斎学をテーマにした自由進度学習を展開しています(注3)。
特筆すべきは、クラウドシステムを活用した学習環境の構築です。生徒たちは「私たちの生活を自然災害から守るために大切なことはなんだろうか」という大きな課題に向き合いながら、災害が起こる理由、起こりやすい地域、避難対策など自分の興味のある視点から4時間の学習計画を立てて、自らの進度を調整しながら、学習を進めていきました。教科書やインターネットで調べた内容は、デジタルメモとして記録されます。
この取り組みの成果は、生徒の学びの質的な変化となって現れます。自分の学習の軌跡をデジタルで振り返ることで、次の学習をどう進めるか自己調整ができるようになります。教師の側も、生徒一人一人の学びをリアルタイムに把握できることで、より適切な支援が可能になりました。
このように、緑桜学園那阿市立芳野小学校の取り組みは、ICTツールを効果的に活用することで生徒の主体的な学びを支援しながら、同時に教師の指導・評価の効率化も実現できることを示しています。
まとめ
教育のパラダイムシフトと呼ぶべき自由進度学習。従来の一斉授業という知識伝達の効率を重視した学びから、一人ひとりが主体的に学んでいく、学びの質を大切にする教育への転換は、確かな手応えを感じさせるとともに、幾つかの課題を浮き彫りにしています。
実践事例でも見てきたように、自由進度学習は、生徒たちの中に眠る「学びたい」という意欲を刺激し、自分から勉強したいという気持ちを引き起こさせます。
しかしながら、その実現の背景には、教師の献身的な協力や創意工夫が不可欠です。生徒一人ひとりの進捗を把握し、適切な支援をするためには、一斉授業に比べて大きな準備と労力が必要になります。
広島県の自由進度学習を導入した小学校の校長によると、この学習法の推進には、教師の努力だけではなく、教職員内での理念の共有、授業感の転換、wifiやタブレット等の環境作りなど総合的な改革が必要、と述べています。(注4)
注釈
(1)文部科学省初等中等教育局修学支援・教育課 『端末利活用状況等の実態調査』令和3年10月https://www.mext.go.jp/content/20211125-mxt_shuukyo01-000009827_001.pdf
(2)講談社コクリコ 『全国の小学校で進む「自由進度教育」実例を紹介!「自己決定」「自己選択」「学び合い」で子どもが驚くほど主体的に』https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/study/gEIBT
(3)sky tech blog 『SKYMENU Cloud 新機能[気づきメモ]実践報告
児童同士で情報をリアルタイムに共有し、課題を追究』
https://www.sky-school-ict.net/class/report/230810
(4)広島県廿日市市立宮園小学校校長中谷一志『「自立した学び手」の育成を目指した自由進度学習の取組』
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20221121-mxt_syoto02-000025909_3.pdf
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。