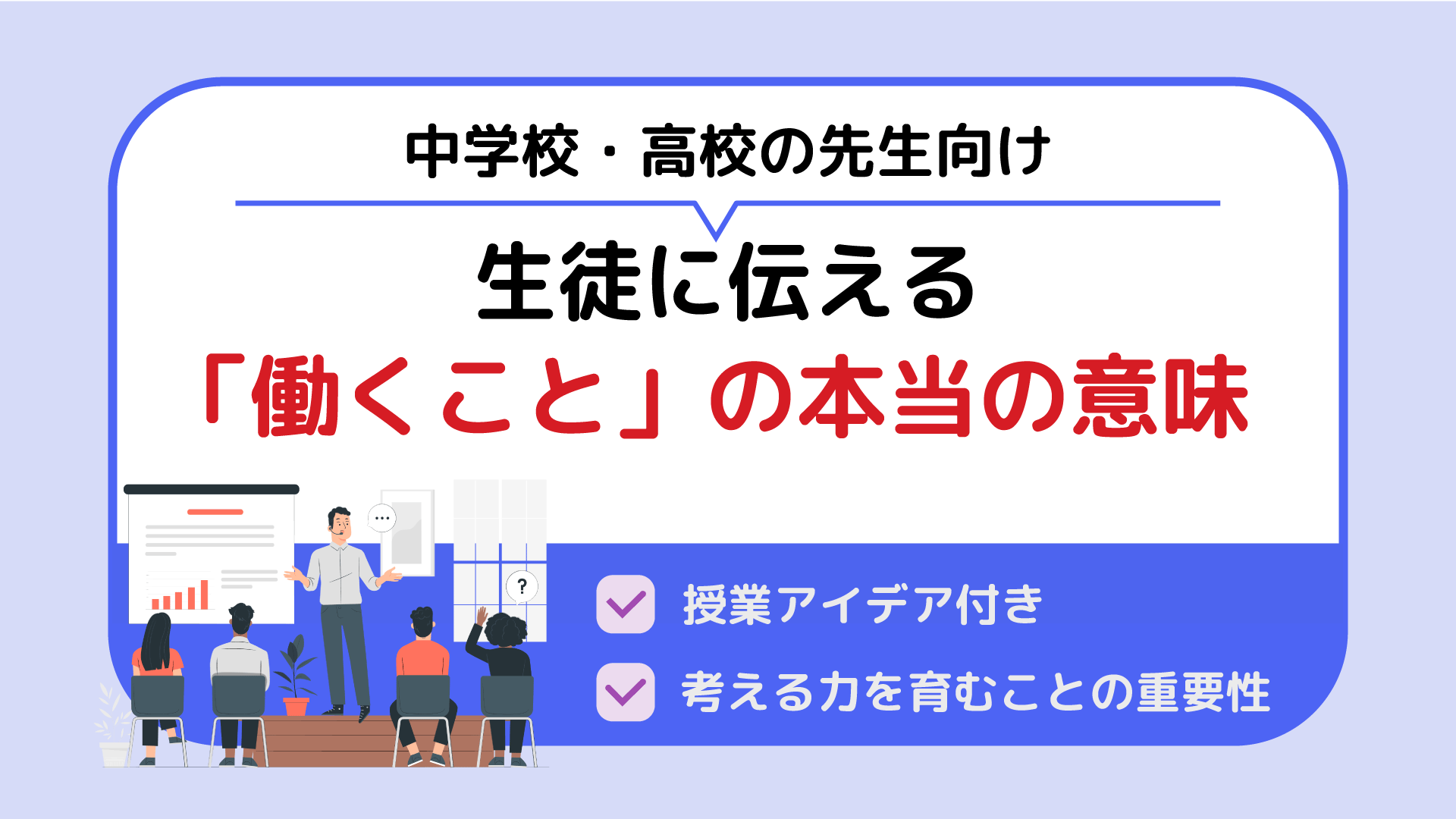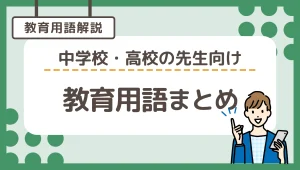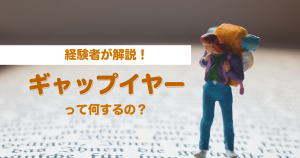いままで学校で「将来の夢」を書くたびに、「そもそも何のために働くんだろう?」と心の中でつぶやいていました。周りの友人も、大学名や企業名は知っていても、その先の働く意味までは考えていないことがほとんどな気がします。
働くことの意義というテーマは、生徒の将来の選択に大きく影響するものですから、先生から生徒の心に響く形で伝わったのなら、きっとその後の進路選びや人生の方向性が変わりるのではないでしょうか。
この記事では、自分の経験や友人の話を交えながら、生徒の心に届くキャリア教育のヒントをお届けできればと思います。
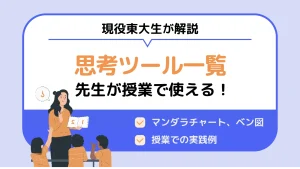
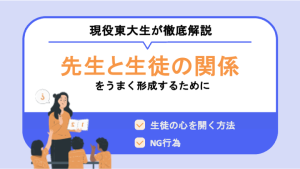
なぜ今、生徒に「働く意味」を伝える必要があるのか
変化の激しい時代における、生徒のキャリアに対する不安
学歴に関係なく活躍している人々が増えている今、いい大学に入ればいい会社に入れるという一本道はすでに揺らぎ始めているように感じます。
さらに、生徒たちが開かれた将来の選択肢をもつということは、「自分は何を選べばいいのか」という迷いも抱えやすいということでもあります。
ゲームが好きだった友人Aは、ゲームに携わることができればいいやという動機はあるものの、実際にどういう業態であって、どれが自分に適切な選択肢なのかあやふやなまま、デジタル系の専門学校に入学しましたが、「思っていたのと違った」らしく退学し、今はコンビニでフリーターをしています。
今重要なのは、曖昧で多すぎる選択肢の中で、自分の選んだ進路が事前の思惑通りにいかないことが往々にしてある、という点です。また、実際に自身の希望通りに事業が進まない際に、転職や退職して起業などの、その事業をやらないという判断を下すことが容易になっているように感じます。
生徒自身が主体的に将来を考える力を育むことの重要性
例えば「将来は地域の役に立つ仕事がしたい」と決めていた人ならば、希望の配属先に就けずとも地元企業で働きながら資格取得に挑戦し、夢に近づくことができるように、自分なりの価値観を早くから持っていた人は、困難に直面しても前向きに行動できるのではないでしょうか。生徒が将来を主体的に考える力は、一朝一夕では身につきませんが、先生から「なぜ働くのか」という問いを投げかけられることで、自分の軸を探すきっかけとなるかもしれません。
先生だからこそ伝えられる「働くこと」の3つの側面
自分の仕事が誰かの役に立つ喜びを感じられる
高校生の頃、清掃のアルバイトをしていた友人が「ただ単純作業をしてるだけだと思ってたけど、お客さんに『ありがとう』って言われるとちょっと嬉しい」と話してくれました。
働くことは、社会の一員として誰かに貢献することです。どんな仕事でも誰かの必要とされているから存在しており、「自分の仕事が社会とどうつながっているのか」を伝えると、生徒は働くことをより身近に感じられると思います。
仕事を通じて成長し、自分らしく生きることが出来る
自分はもともと、行動と思考の連動を細分化したものを体系化するのが好きで、塾講師としてのアルバイトで生徒に指導する際に気を付けていることが、目標を設定する際に細かく中間地点を用意することです。少しの段階ごとに現状を把握することで課題を摘出しやすく、同時に自分の足りない部分にも気づくことができ、どう対処すべきか何回も考えることで実現しやすい計画が立てられると実感しています。仕事は生活費を稼ぐ手段であると同時に、自分を成長させる場でもあります。困難を乗り越える達成感や成長の実感は、自分らしく生きるための大事な要素なのではないでしょうか。
自分の人生を自分で選択するための土台にできる
高校時代の友人で、早くから「海外で働きたい」と考えていた人がいました。アルバイトでためたお金を留学費用に充て、自分の意思で進路を選び取っていった姿はとても印象的でした。経済的に自立していると、やりたいことを自由に選べる可能性が広がります。お金は単なる消費の道具ではなく、未来の自分への投資と考えることで、選択肢はさらに増えます。働くことは、そのための確かな土台となるのです。
生徒の心に響く授業アイデア
ここからは実際に自身の体験や、友人から聞いた面白かった授業をもとに、「何のために働くのか」が伝わる授業アイデアを提案させていただきます。
「もし宝くじが当たっても働く?」ディスカッション
この問いを投げかけると、意外と盛り上がると思います。「お金があっても働く」と答える生徒に理由を聞けば、やりがいや人とのつながりの話が出てきます。逆に「働かない」と答える生徒は仕事をお金を得るための手段として捉えているということですので、意見を収集して議論することによって、働く意味を自然に考えるようになるのではないでしょうか。
キャリアマップ作成ワークショップ
紙やオンラインツールを使って、「やってみたいこと」「得意なこと」「大切にしたいこと」を可視化します。私も高校時代に似たようなことをやって、自分の興味の方向性が意外とハッキリした覚えがあります。完成したマップは将来の進路相談にも活かせるので生徒と先生間のコミュニケーション不足解消に一躍が見込まれると思います。
この活動の一環として、弊社では「アカデミックマインド」でキャリアワークショップで生徒向けの取り組みも行っております。
外部講師によるリアルな体験談
実際に社会で活躍している人の話は、生徒に強いインパクトを与えます。特に、失敗や挫折から学んだ経験は、生徒にとって「働くこと」の生々しい一面を感じさせます。実際の話によって生徒の社会に対する解像度を上げることで自身の選択が有用なものになっていくのではないでしょうか。先生だけでなく外部の力を借りることで、視野を広げることにも繋がると思います。
また、弊社では、外部講師として様々な高校に講義する活動も行っております。合わせてご確認ください。
まとめ
「働くことの意味」を伝えるのは、進路指導だけでなく、生徒の人生そのものを豊かにする大切な機会です。この記事で得たヒントを、ぜひ明日の授業や面談で試してみてください。
なお、弊社(カルペディエム)も講義として外部講師を呼んだりキャリアワークショップで生徒向けの活動を行っていますので、興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、先生向けの記事もまとめているためご確認ください。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。