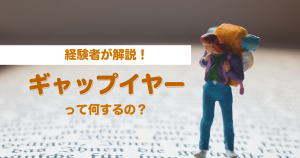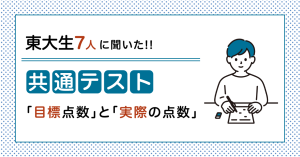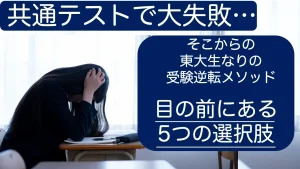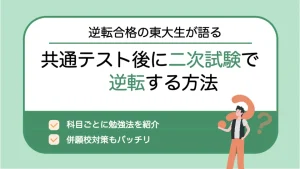大学に入ると「ゼミ」というワードを聞く事が必ずあると思うのですが、実際にゼミとは何か説明できますか?この記事では大学のゼミとはどんなもので、何をするところなのかを実際に東大生や慶應生にインタビューしてまとめました!
ゼミとは何か?
ゼミとは「ゼミナール」の略称です。
活動を簡単に表すと、「能動的で専門的」です。通常は授業や講義で教授から知識を一方的に教えてもらうのですが、ゼミではその限りではありません。自分の学びたい分野の教授につき、同じ志をもった生徒とより具体的かつ専門的な内容を扱っていきます。
3つの特徴
大きな特徴を打ち出すとすれば、「少人数制」「学生が主体的に勉強する場所」「専門分野を学べる」の3つがあげられます。
少人数制
大衆授業とは違い、少人数で行います。
専門的になるほど、自分の学びたい事が具体的になり、自分と同じ事に興味を持つ人が減っていくからです。また、人気な分野のゼミだと意図的に人数制限をすることも少なくありません。より教授と生徒、生徒と生徒が近い距離でディスカッションしたり、意見の共有をしやすくするためです。
学生が主体的に勉強する場所
ゼミは受身ではなく能動です。一方的に教わるのではなく、ゼミ内の人の距離感が近くなる分、討論や情報の共有が多くなります。また、どんどんと専門的になり、自分が「面白い!」と思った事にチカラを注げるようになります。
専門分野を学べる
ゼミでは専門的な知識を、教科書やネットの情報から学ぶという域にはとどまりません。ゼミの教授が研究している分野の最前線ではどの様な事が起きているのかを学べます。これらはgoogleやyahooなどをはじめとする普段使いする検索エンジンで検索してもヒットしません。そういったコンテンツに触れられるというのが大学の醍醐味でもあると思います。
授業とゼミの違い
授業とゼミの違いは、例えていえば「屋台で食べ歩き」か「予約してお店を訪れる」かで表せます。授業は食べ歩きのように種類の違うものに色々触れて、そこまで深堀りはできませんが、広い知識を身に着けられます。一方ゼミでは自分の好みを専門店を予約して、ひたすらそれを食べる、つまり自分の興味分野をさらに深める事ができるのです。
研究室とゼミの違い
簡単に説明すると、文系の人はゼミ、理系の人は研究室に入ります。ゼミは勉強会、研究室は文字通り研究をするといった具合です。しかし、理系でもゼミを行う事はあります。その場合は情報を共有したり、ミーティングをしたりします。
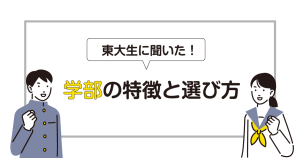
ゼミの種類
ゼミには大きく分けて教養系と専門研究系にわかれます。一体どの様な違いがあるのでしょうか?
教養系
教養系では、論文など参考文献を調べたり、教授と生徒、生徒と生徒同士が討論をし、研究内容を深めていきます。文系のゼミに多く見受けられます。
専門研究系
専門研究系では、実際に実験を行ったりします。理工学部などの研究をイメージすると分かりやすいかもしれません。どちらかといえば理系に多く見られます。また、ゼミよりも少人数になることがあります。
ゼミではどんなことをするのか?
実際にゼミではどんな事をするのでしょうか?いくつかのステップに分けて説明いたします。
テーマ決め
まず、研究するのにはテーマが必要です。テーマは教授が与えるのではなく、自分で考える事がほとんどです。教授の専門分野と大きくかけ離れる場合、助言をもらうこともあります。
調査
テーマが決まったら、情報を集めます。ネットでただ検索するのではなく、書籍であったり、専門家しか入れない論文データベースなどにアクセスし、過去の研究などを調べます。また、ゼミによってはフィールドワークや取材などの調査をすることもあります。
ディスカッション
調査の結果実際にどんな事があったのかゼミ内で共有します。この時研究内容の確からしさなどについても討論します。研究内容は教科書のように絶対あっているというわけではなく、あくまでみんなの知らない事へ立ち向かっているので、内容精査の必要があります。
レポート作成
調査とディスカッションを経て、文章としてまとめます。これを教授に提出します。
発表
これらの工程を踏まえて、ゼミ内で発表をします。いわゆるプレゼンです。
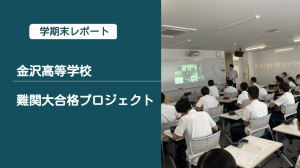
現役大学生のゼミ体験談
実際にゼミでどんな事を学んでいるのか、学生にインタビューしました!
東京大学 一類法学総合コース チャクラ・ティナさん
私は法学総合コースで、現代法過程論の平野・フットゼミというビジネス交渉や仲裁を模擬問題を通して実践形式で行うゼミに所属していました!このゼミではダニエルフット先生というハーバード出身の先生に教わっていました。少し特殊なケースでレポートがなく、あくまで実践で学ぶスタイルのゼミです。
前半は交渉の仕方、契約の仕方、契約書を英語に訳す方法などを講義形式で学び、チームでその内容についてディスカッションをします。それらの講義を経て、一橋、中央、上智、東大が集まって練習大会を行います。後半では世界の人達相手に交渉・仲裁のコンテストに出ます。このコンテストでは、50ページくらいの背景情報がぎっしり書かれている長文問題を用います。私が実際に取り組んだ問題は、ワイナリーとリテイラーの問題でした。
比較的忙しいゼミで、まるで部活のようで、朝から晩まで1日中ロジックを組み立てたりしました。
ゼミに入るメリットとしては、企業に入ってやる事を実際にやるので耐性がついたり、キャリアに繋がるこがあげられます。弁護士や他校との幅広い人脈も得られました。デメリットとしては、作業量が膨大で犠牲にするものが多かったこです。ですが、得るものも大きかったです!
法学部では卒論がないので、3, 4年と別々のゼミに入る友達もいました。
慶應義塾大学 商学部 M.Hさん
私は慶應義塾大学商学部の大野由香子ゼミに所属しています!都市経済学、計量経済学に興味のある学生が集まって活動をしてます。不動産、立地問題、地理的要素が関わる経済現象に興味を持ってこのゼミに決めました。週2回程活動しています。
実際の活動内容は輪読(同じ本を数人が読み、お互いに意見を交換しあう)、データワークをしたり、複数ゼミで論文の展示会などをしています。また、研究や講義だけでなく、商学部ゼミ対抗バレーボール大会など、レクリエーションもありました。
ゼミに入ったメリットとしては私自身、就活をしているのですが、ゼミで深めた専門的な知識を生かしつつ、内定をいただくことができた事です。サークルなど個人的な活動との兼ね合いもできて、いい経験になりました!
ゼミに入るメリット
M.Hさんも先ほどゼミに入ったメリットを仰っていましたが、ゼミに入って得られるメリットはどんな事があるでしょうか?ここでは3つの観点からお伝えします。
専門知識
ゼミの特徴でもお伝えしましたが1つ目は単純に専門知識をつけられるということです。正確にいえばホットな専門知識です。これは本を読めば得られるかというと必ずしもそうではなく、実際に現在進行形で行われている研究に触れる事ができます。
大学生活
大学生活をより充実させるためにゼミは大きな役割を担うでしょう。同輩だけでなく、学年を超えて先輩後輩も在席しますし、教授とのコネクションも作れます。人脈作りができるというとても大きなメリットがあります。
就職活動
就職活動においてもメリットがあります。理系学生の場合、専門職に就こうとするとゼミや研究室で学んだという実績が役に立つ事があります。また、チームワークの大切さを学び、プレゼン発表の実績があるという証にもなります。その他にも、勤めたい会社の先輩とのコネになるという場合もあります。しかしながら、入っていないからといってマイナスというわけではなく、あくまで加点要素となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?もし「ゼミについてもっと知りたいな」と思った時は、大学案内やオープンキャンパスに足を運ぶ、先輩から話を聞く、などでより理解を深めてみてはいかがでしょうか?将来にも響くものですので、自分が何をやりたいかじっくりと検討してから楽しいゼミライフを送りましょう!
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。