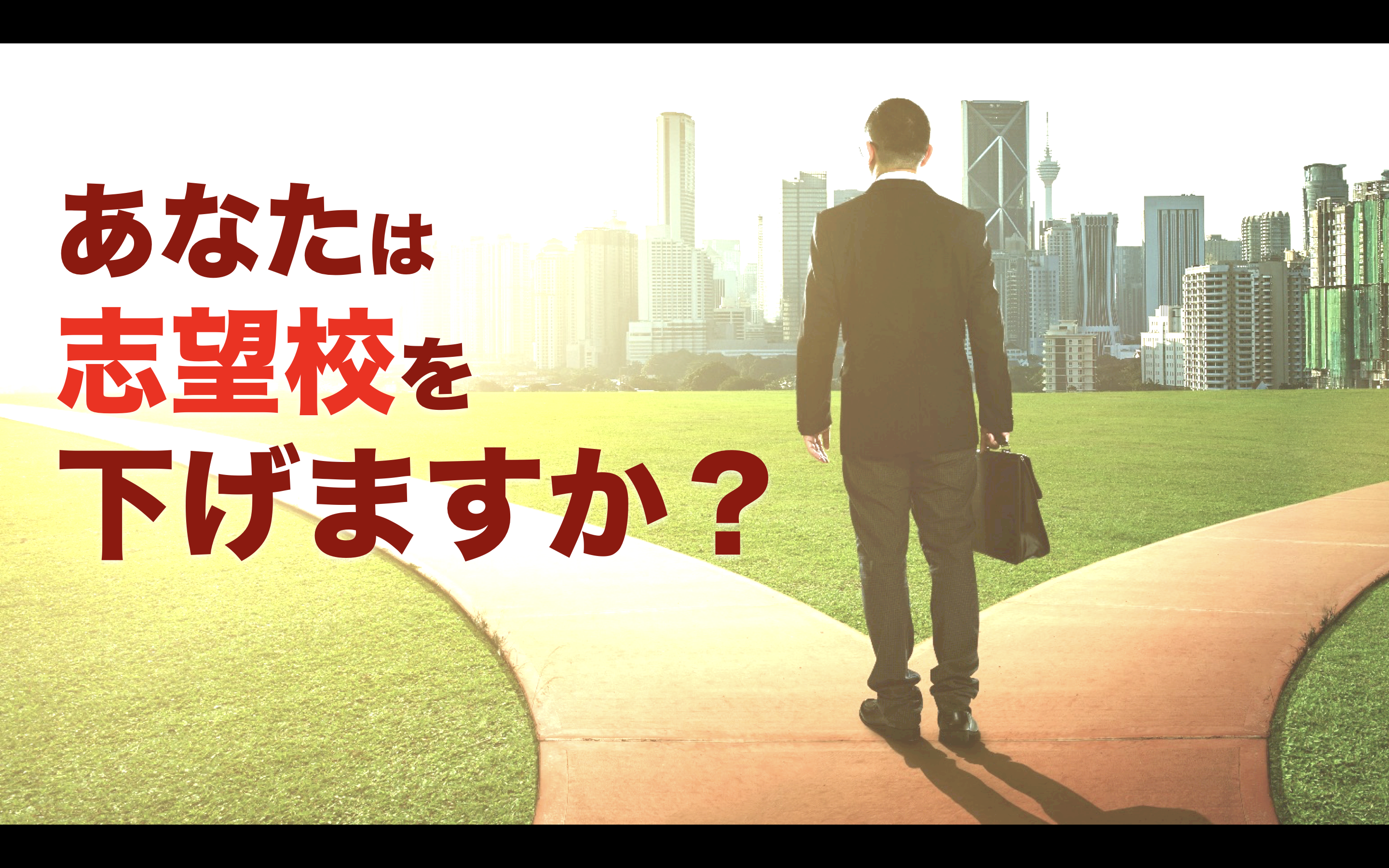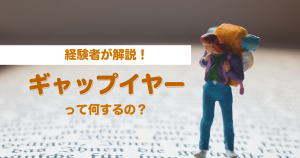受験勉強をすればするほど、過去問が解けないときなどに、「志望校を下げた方がいいのかな……?」と考えてしまう人は多いでしょう。
今回は、志望校は下げた方がいいのかどうか、大学受験で後悔しないための考え方について、現役東大生ライター碓氷明日香が解説していきます!【2025年9月29日編集】
志望校は下げない方がいい!
結論から言うと、志望校は下げない方がいいです!
受験期はメンタルが落ち込むことが多いと思います。ですが、その勢いに任せて志望校を下げてしまっては、その後ずっと後悔することになるかもしれません。
確かに、志望校のレベルを下げることで、勉強はずっと楽になりますし、合格にも一気に近づきます。でも、実はそれには大きなデメリットが伴うのです。そのデメリットを背負ってまで、レベルを下げるべきかどうか、しっかり考えて決めることが大切になってきます。
志望校を下げることのデメリット
では、志望校を下げることのデメリットとは一体何なのでしょうか。ここでは、3つの大きなデメリットを挙げてみます。
勉強の質が落ちる
1つ目は「勉強の質が落ちる」ことです。目標を下げてしまうと、高い目標を持って勉強している時と比べて、どうしても「これくらいでいいや、大丈夫でしょ」という気持ちが出てきて、勉強の質が落ちてしまいます。
何事も、頑張らなきゃ、という思いで取り組む方が集中できますし、その分成果も発揮できるものです。志望校を下げると、その思いが一気になくなってしまいます。その「別にそこまで頑張らなくても大丈夫でしょ」という慢心が中身のない勉強につながってしまうのです。
勉強量が減る
質が下がるだけではなく、「勉強量が減る」というデメリットもあります。これも同様に、そこまで勉強しなくても十分受かるだろうという慢心から、怠け癖がついてしまうのです。
そして、質と量ともに落ちた勉強を続けた結果、下げた先の志望校にすら合格できなくなる可能性もあります。
あとで後悔する可能性も
また、受験が終わって、レベルを下げた志望校に入学したあと、「もしあの時諦めなければ、あの大学に受かっていたのかな」「今頃あの大学のキャンパスに通えていたのかな」とずっと引きずる可能性もあります。これが3つ目のデメリットです。
チャレンジして失敗したことに対する後悔よりも、そもそもチャレンジしなかったことに対する後悔の方が、長く人間を縛り続けます。ずっと後悔するくらいなら、最初からチャレンジした方がいいと思いませんか?
志望校を下げる判断基準とは?
では、どんな場合なら志望校を下げてもいいといえるでしょうか。その判断基準について説明します。
絶対に合格できないとわかっている場合
まずは「絶対に合格できないとわかっている場合」です。例えば、高3の12月まで模試でずっとE判定を取り続けている、一度も安心できる判定を取ったことがない、という場合、戦略として志望校を下げるのはありでしょう。
浪人する覚悟があるなら別ですが、そうではないのなら、今のままの志望校で本当に大丈夫なのか、一度じっくり考えてみましょう。周りの意見なども参考にしつつ、最終的には自分が納得できる選択をすることが大切です。
他に行きたい大学が見つかった場合
また、「他に行きたい大学・やりたいことが見つかったとき」も、志望校を変えたり下げたりした方がいいかもしれません。目指していた大学とは別のところで、やりたい分野の研究が進んでいるのを知った、何かのきっかけで将来やりたいことが定まった、といった場合には、その大学・分野に志望を変更した方がいいです。
というのは、本来大学は自分の学びたいことを突き詰めるために進む場所だからです。心から行きたいと思える大学に出会ったのなら、そこを目指すのが道理でしょう。また、専門の大学でしか取ることのできない資格などもあります。将来進みたい道がはっきりしているのなら、その夢を叶えるために必要な知識や技術を習得できる大学を選ぶべきです。
ただ、その際、しっかり情報収集をして、本当に自分が目指すのにふさわしい大学なのか吟味することも忘れずに。
金銭的に厳しい場合
もうひとつの判断基準に「金銭面」があります。大学の学費は多くの家庭では親が払うものです。突然親の収入が減ってしまって、金銭的にその大学に進むのは厳しい、ということもあるでしょう。また、最近では学費の値上げが発表された大学もあります。
金銭的に厳しい場合は、奨学金などで通うことができないかしっかり調べ上げたあと、それでも難しそうであれば、志望校を下げて、確実に受かりそうで金銭的にも余裕がある大学を選ぶのも手です。もちろん、その際は親の都合だけではなく、自分も納得できる選択をしましょう。
いつ決めたらいい?
では、志望校を最終的に確定させるのはいつがいいのでしょうか。もしレベルを下げるとしたら、どのタイミングがベストなのでしょう。
高3の夏がベスト
志望校は、高3の夏までに確定させるのがベストです。大学受験は大学ごとに対策が大きく変わってくるため、合格するためにはしっかり対策期間を取ることが必要になってきます。直前に志望校を変えて対策を始めても、どの教科も完成できずに受験を迎えてしまうことも。
過去問演習を繰り返しできる十分な期間を確保するためには、やはり高3の夏あたりに最終決定するのが理想といえます。
共通テストが終わってからという手も
また、共通テストが終わってから志望校を変えるという手もあります。出願締め切りを考えると、ここが本当の最終決定ですね。
共通テストの平均点などで倍率が大きく変動することもありますし、自分の出来不出来も鑑みてどこに出願すべきか決めることも、戦略として重要です。かくいう私は、共通テストで大失敗してしまい、東大に出願するかどうしようか、非常に迷いました。そんなこともあるので、共通テストを受ける前から志望校のレベルを下げることも視野に入れて、下げる前と後両方の大学の試験に対応できるようにしておくと無難かもしれませんね。
ただ、もちろん、絶対に本命の大学を受けるんだ、という心意気はギリギリまで失わないようにしましょう。
東大生が語る! 志望校を下げずに挑んだ逆転合格
筆者はもともと東大を第一志望として掲げ、共通テストでは9割を目標に臨みました。ところが本番では、数学をはじめとする複数科目が異例の難化を見せ、結果は8割を切る散々な点数。正直、このまま受験しても落ちてしまうのではないかと、1週間ほど真剣に志望校を下げるか悩み続けました。
それでも「ここで諦めたら、これまで積み重ねてきた努力がすべて無駄になってしまう」と考え、ダメもとで挑戦することを決意。結果として二次試験で逆転し、東大合格をつかみ取ることができました。
受験においては、その大学を受ける限り、数%でも合格の可能性が存在します。しかし諦めてしまえば、その可能性は0%になってしまう。もちろん現実を直視して志望校を下げる判断も大切ですが、最後までチャレンジする勇気も同じくらい重要です。仮に大学受験に失敗したからといって、その後の人生まで失敗に直結するわけではないのです。
諦めずに突き進むことは辛いことでしょう。見えない未来に対する不安も大きいと思います。でも、数%でも可能性を信じてチャレンジしてみてはどうでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。志望校を下げるべきかどうか、判断する上で参考になれば幸いです。
受験期はどうしてもメンタルが落ち込んでしまうもの。そんな時こそ、一度冷静になってじっくり考えてみることが必要です。自分が納得できるかどうか、後悔しないかどうか、そこを一番に考えてみてください。【2025年9月29日編集】
文責:碓氷明日香 / メディア事業部
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。