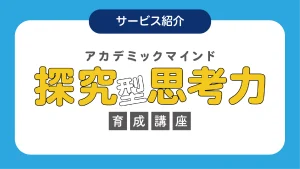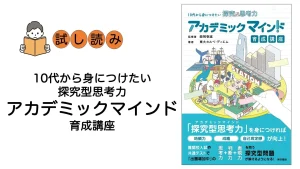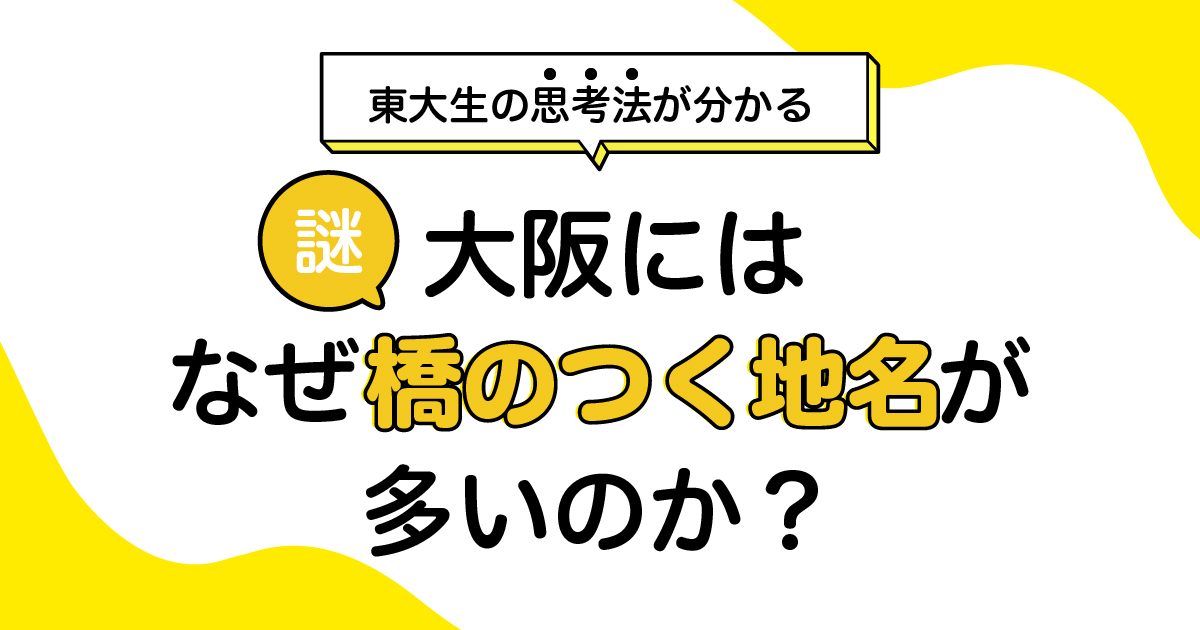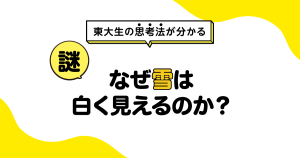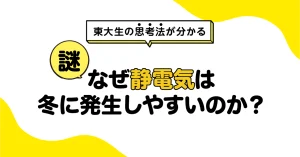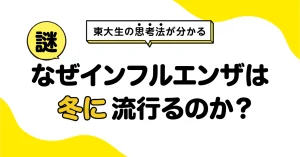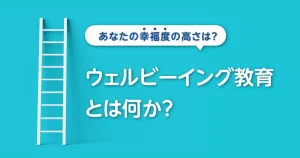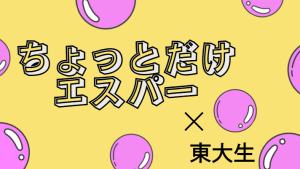みなさん、大阪の地名をいくつか思い浮かべてみてください。
京橋、心斎橋、天神橋、淀屋橋、阿倍野橋……。
気づきましたか? そう、「橋」がつく地名がとても多いんです。
いったい、どうして大阪には「橋」がつく地名が多いのでしょうか?
今回は、東大生の思考法を使って、この疑問を一緒に考えてみましょう!
問いを分解してみよう!
「大阪に橋が多いのはなぜか?」という問いは、一見シンプルに見えますが、実は2つの問いに分けられます。
- 大阪ってどんなまち?
- 橋が多いってどういうこと?
大阪ってどんなまち?
大阪は、昔から「水の都」と呼ばれてきました。
大きな川や運河が数多く流れ、町の中を縦横に水路が走っています。
実は、大阪の平野部は川がつくり出した低地で、水があふれやすい土地でした。
そのため、昔の人たちは川や運河を整備し、船で物を運べるよう工夫したのです。
これが、全国から物資が集まり、商業の中心地となった「天下の台所」——商業都市:大阪のはじまりです。
橋が多いってどういうこと?
川が多ければ、当然その川を渡るための橋も必要になりますよね。
面白いのは、その橋をつくったのが町の商人たちだったということ。江戸の町では橋を架けるのは幕府の仕事でしたが、大阪では、自分たちの商売のために、商人たちが自費で橋を架けました。
「川の向こうにも人が来るようになれば、お客さんが増えて商売も儲かる!」
「橋にお金をかけても、それ以上の利益が見込める!」
そんな商人魂があったのです。
たとえば「淀屋橋」は、大商人・淀屋が自分のお金で架けた橋に由来しています。
地名に「橋」が残った!
こうして架けられた橋は、単なる通り道ではなく、人や物が集まる“にぎわいの場になりました。
橋の周りには店や市場が集まり、橋の名前がそのまま地域の目印=地名として使われるようになっていったのです。
そのため、今でも大阪には「橋」がつく地名がたくさん残っているんですね。
アカデミックマインドとは
このように、1つの問いを「分解」し、「仮説」「検証」する一連の思考法を、「アカデミックマインド」と呼んでいます。
AIなどさまざまな技術が発達する中、これからの世代に求められるのが「思考力」です。共通テストや大学入試でも「自分で考える力」が試されるようになっています。
カルぺ・ディエムでは、現役東大生と一緒に「身の回りにあふれる疑問」と「五教科の勉強」を結びつけた課題に取り組み、自ら問いを立て、仮説を作り、検証する一連の思考法「アカデミックマインド」の獲得を目指す講座「アカデミックマインド育成講座」を実施中です。