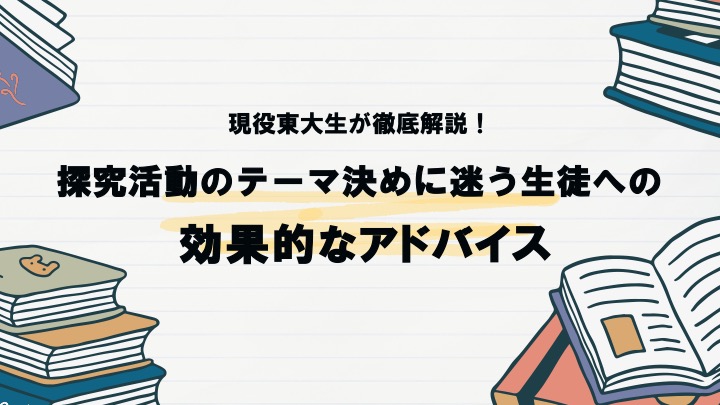学習指導要領の改訂に伴い、ひとつの教科として導入された探究学習。そのはじめの一歩となる「テーマ決め」がなかなかうまくいかず、毎時間をなんとなく過ごしてしまう生徒が多いようです。
先生としては、そんな生徒に良いアドバイスをして、探究学習を軌道に乗せてあげたいはず。
そこで今回は、探究学習のテーマ決めに悩む生徒に、教員としてどのようなアドバイスをすればいいのか、東大教育学部生の碓氷明日香が徹底解説します!
そもそも探究学習とは?
探究学習の導入背景
学習指導要領の改訂により、高校教育では「総合的な探究の時間」が必修化されました。
その背景には、社会の急速な変化と先行きの見えにくさがあります。
昨今、AIの進化やグローバル化の進展により、単なる知識の暗記では対応できない課題が次々と現れる時代になってきています。
そんな中、学習者自身が課題を発見し、情報を集め、考察し、解決策を模索する力を育てる必要があります。
「探究学習」は、科目横断的な学びや地域社会との連携を通して、生徒がこれらの今求められる資質・能力を身につけるために導入されました。
探究学習の目的
学習指導要領では、探究学習の目的は「課題の設定・情報の収集・整理・分析・まとめ・表現を通して、生徒の主体的な学びを深めること」とされています。
つまり、「正解のある問いに答える」力よりも、「自分なりの問いを立てて考え抜く」力こそがこの探究学習を通じて身につけるべきものなのです。
探究学習を経て、問題解決能力を身につけ、自分の進路や生き方を考えることができるようになることをゴールに据えて生徒たちの探究を導いていく必要があるのです。
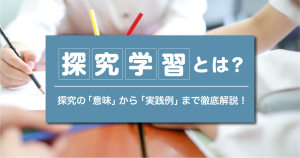
生徒がテーマを決められない原因
その探究学習の第一歩となる「テーマ決め」ですが、ここで止まってしまうと探究を進めることができません。
先生として生徒の歩みを後押しするために、まずはなぜテーマ決めがうまくいかないのかを分析してみましょう。
ここでは、テーマを決められない4つの原因を挙げていきます。
原因その1:何をすべきかわかっていない
まず1つ目に、「何をすべきかわからない」という原因が挙げられます。
詳細な説明もなく、いきなり探究学習を始めてください、と言われても、生徒としては何から手をつけたらいいか、何を求められているのかわからずに手が止まってしまうでしょう。
そこでまず探究学習とは何か、どんな順番で進めていけばいいのかを丁寧に説明することから始めましょう。
他にも先輩たちの探究学習の事例を見せてあげるのもひとつの手です。まずはのイメージを持ってもらい、テーマ設定がスタートラインであることを示すことが大切です。
原因その2:興味・関心の整理ができていない
テーマ決めに際してやりたいことはある気がするけれど具体的に言葉にできない、という生徒も少なくありません。
本来、テーマ決めは自分の興味のある分野、関心事から絞っていくものです。
しかし、日常生活の中で抱いている小さな疑問や好奇心を整理しないままテーマを決めようとすると、何をすればよいのかがわからず、漠然としたまま立ち止まってしまう場合が少なくありません。
そこできちんと考えを整理するために、自分の経験や関心をリスト化、マインドマップに書き出すといった作業を取り入れてみましょう。
どんな小さなことでも書き出して、それが何の分野なのか調べてみるだけであっても、問いにつながる第一歩となります。
原因その3:興味・関心の範囲が広すぎる/狭すぎる
「環境問題を調べたい」「日本史をもっと知りたい」など大きすぎるテーマを設定すると、どこから手をつけていいかわからず、探究活動が進みません。
逆に、興味の範囲が狭すぎても、探究がすぐに終わってしまいます。調べてすぐに答えが出るような問いだと、生徒の考える力は養われず、学習効果は薄いでしょう。
そのため、具体例に落とし込む、もしくは関連する視点をいくつか候補として挙げるなどの指導により、生徒一人ひとりのテーマ案を丁寧に添削し、興味・関心の範囲を適切な広さに収めることが必要になってきます。
生徒の関心を決して否定することなく、高校3年間の探究学習で収まるような問いに仕向けるようにしましょう。
原因その4:「正解」を探そうとしてしまっている
通常の教科学習に慣れている生徒たちは、探究学習にも「答え」があると思い、その「答え」を探しに行こうとしてしまいます。
それにより大人受け、先生受けが良さそうなテーマに寄りすぎて、自らの興味から大きく離れてしまうと、モチベーションが続かず、学習効果も小さくなるでしょう。
もちろん、社会問題に積極的に取り組むことは大事ですが、それを生徒が過度に意識しすぎないように、先生として適度に調節を心がけましょう。
探究学習のテーマやゴールには「唯一の正解」は存在せず、問いを立て、仮説を考え、検証する流れに意味があることを繰り返し伝える必要があるのです。

先生ができる「テーマ決め」のアドバイス
先節では、生徒が「テーマ決め」につまづく原因についてお話ししました。
この節では実際に「テーマ決め」に悩んでいる生徒に対して、先生ができるアドバイスにはどのようなものがあるかを3つに分けて解説していきます。
①日常生活や経験からヒントを得るよう促す
探究学習のテーマは、始めは必ずしも大きな社会問題についてでなくてもよいです。
まずは身の回りの「なぜ?」という疑問や日常生活での体験を深掘りしていくことが大切です。
例えば、「なぜ自販機はあの場所に置かれているのか?」「どうしてSNSの投稿は拡散されやすいものとそうでないものがあるのか」といった素朴な疑問も立派なテーマになり得ます。
テーマが思いつかなくて困っている生徒に対しては、「普段の生活の中で気になったことをその都度メモしてみよう」と促してみてください。何度も繰り返し促すうちに、生徒もなんとなく過ごしているだけの日常に疑問の視点を向けることができるようになるはずです。
ただ、あまりくどすぎると、それはそれで生徒のやる気を削いでしまうので、様子を見ながらアドバイスすることが重要です。
②マインドマップやワークシートで興味を可視化させる
頭の中だけで考えていると、興味や関心はぼんやりしてまとまりません。
そこで有効なのが、マインドマップやワークシートを使った「可視化」のサポートです。
「好きなこと」「嫌いなこと」「将来関わってみたいこと」などのカテゴリを設けて書き出させてみましょう。そうすることで、生徒自身が自分の興味の傾向に気づくことができ、テーマを絞りやすくなるのです。
また、目に見える形にすることで、先生も一緒にテーマ案を整理することができ、助言しやすくなります。生徒同士でアドバイスし合うことも可能になるため、よりよいテーマにつながるでしょう。
③既存のテーマ例からオリジナルへと発展させる
これは最終手段ですが、どうしてもテーマが思いつかない、いくら考えても何も思い浮かばないという生徒に対しては、既存のテーマ例を見せてみましょう。先輩の探究活動の事例や書籍・メディアで紹介されているテーマ例を共有してみてください。
ただ、この手法を行うと、生徒はその模倣に留まってしまう可能性が高いです。
似通ったテーマで探究しようとしても、モチベーションが保ちづらく、効果的な学びになりません。「自分の住んでいる地域ならどうなるか」「自分の関心に当てはめたら何が見えるか」と問いかけながら、既存のテーマにオリジナリティを付与する手伝いをしてあげてください。
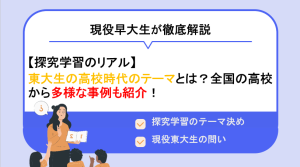
テーマをよりよくするためのポイント
テーマが思いついた生徒に対しても、さらに深い学びを体験させるためのアドバイスが可能です。
この節では、4つの「テーマをよりよくするための助言のポイント」を解説していきます。
ポイントその1:「やらされ感」をなくし、主体性を引き出す
「先生に言われたから」「学校の課題だから」「グループでそう決まったから」といった受け身の姿勢では、探究学習の真価は発揮されません。
生徒自身が「自分で選んだ」「自分の興味とつながっている」と実感できるようなテーマになっているかどうか、しっかりチェックする必要があります。
理想は、授業の時間外でも生徒が「もっと知りたい」「もっと考えたい」と思ってどんどん探究を進めてしまうようなテーマにすることです。好きなことや関心のある分野と関係があるかどうか、そのテーマを心からやりたいと思っているかどうか、確かめながら進めることが大切です。
ポイントその2:社会問題への橋渡しをしてあげる
とはいえ、探究の内容が個人的な問題に止まってしまうと、社会的な問題に対する解決能力が身につきません。それでは、探究学習として意味が薄くなってしまうため、先生がしっかりと役割を社会問題への橋渡しをしましょう。
個人の問いを社会問題へとつなげられるよう、ヒントを出すのです。
例えば、校則に対する疑問は差別や人権の問題や社会における規範について視点を広げることができます。また、自分の好きなスポーツについての問いは、地域の健康増進やスポーツビジネスへと発展させられるかもしれません。
その際、答えを与えるのではなく、あくまでヒントを渡す程度にしておきましょう。あとは生徒自身が自分の力で考え、視野を広げていくことが大切です。
ポイントその3:クローズド・クエスチョンからオープン・クエスチョンへ
「はい/いいえ」で答えられる、もしくはインターネットで調べればすぐに答えが出るような問いでは、探究がすぐに行き止まってしまいます。このような問いは「クローズド・クエスチョン」と言い、探究には向きません。
一方で、単純に答えられない、思考力が必要な問いを「オープン・クエスチョン」と言います。
テーマや問いは必ずオープン・クエスチョンにするように仕向けましょう。
例えば、「日本の高齢化率は上がっているか?」ではなく、「高齢化が今後地域社会にどんな影響を与えるか?」という問いの方が、調査や考察が広がるでしょう。
先生として、生徒の問いをオープンな形に言い換えたり、問い直しを一緒に考えてあげることで、より深い探究へと導いてあげてください。
ポイントその4:実現可能性の検討を促す
生徒が立てたテーマが素敵なものであっても、実際の調査方法や期間を考えると実現困難な場合があります。
例えば、「世界の水問題を解決する」といったテーマは、重要なことではありますが、壮大すぎて高校3年間では取り組み切れないでしょう。そこで、「地域の水使用の実態を調べる」「節水意識を高める方法を考える」など、身近で実行可能な切り口に絞り込むことが大切になってきます。
まずはテーマを立てることが大切ですが、そのあと、それが実現可能なのかどうか、探究テーマとしてふさわしいのかどうか、検討してテーマに磨きをかけていく必要があるのです。
まとめ
探究学習のテーマ決めについて、先生ができるアドバイスをまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
生徒の主体性、やる気を引き出しながら、より深い学びができるように促すことが、探究学習における教員の役割でしょう。教師としての力量が問われる難しいことではありますが、これからの時代を生き抜く術を生徒に身につけてもらうためには大切なことです。
この記事がテーマ決めに悩む生徒をどう導くべきか悩んでいる先生の参考になることを願います。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。