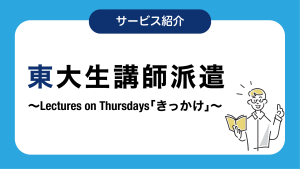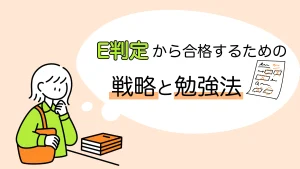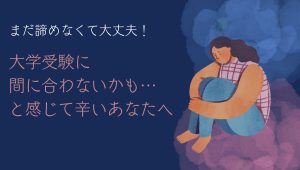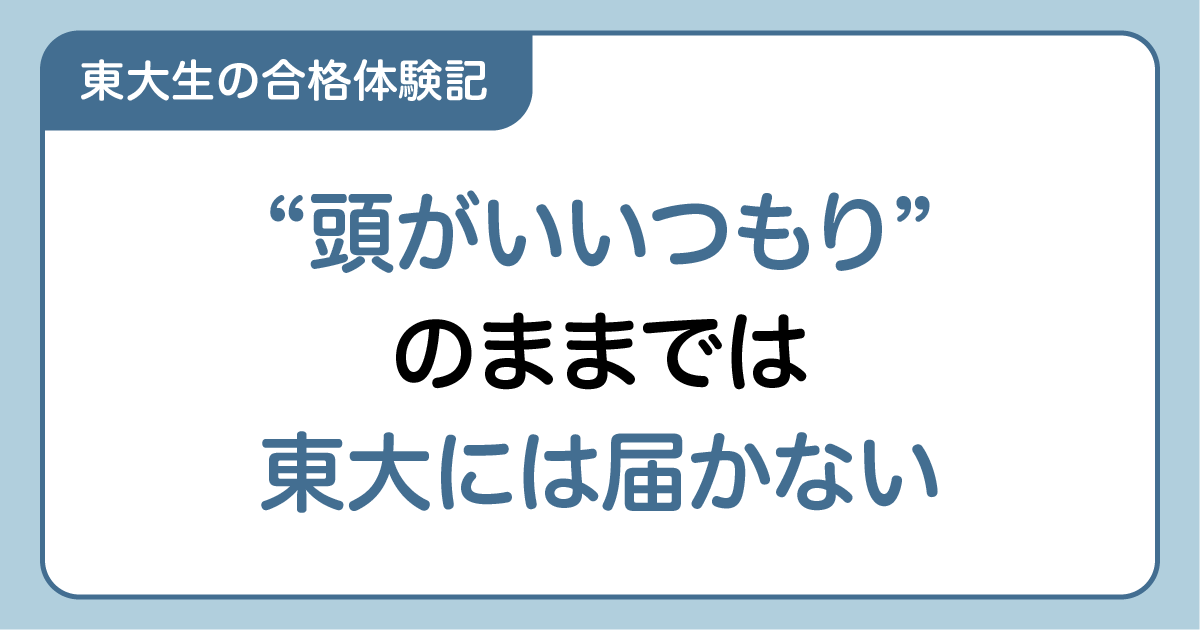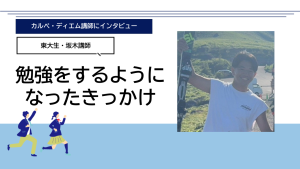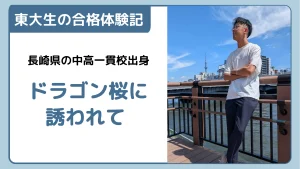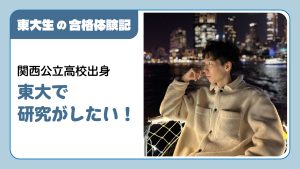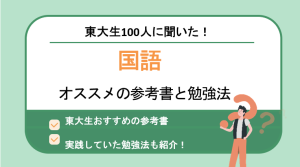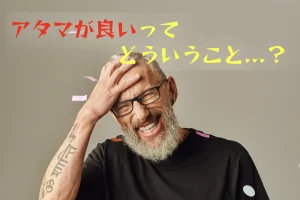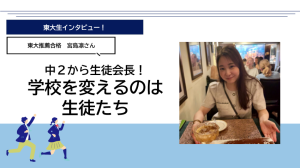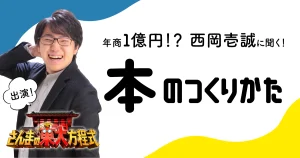東大生の合格体験記 — それぞれの挑戦、それぞれの道
「東大生の合格体験記」では、さまざまな背景を持つ東大生たちに、自身の「合格までのリアル」を語ってもらいます。
今回登場するのは、偏差値50前後の高校から東大合格を果たした、生島(きじま)さん。中学時代は学年トップ10の常連で、「自分は勉強ができる」と信じて疑わなかった彼でしたが、東大模試でまさかの0点を取ってしまいます。
そこで初めて気づいたのは、自分が“井の中の蛙”だったということ。現実を知った彼の逆転劇の鍵とは?
「自分は勉強ができる」という思い込みでスタートした受験生活
自分は、中学時代から勉強には比較的真面目に取り組んでいたほうだと思います。中学には学年に200人ほどいましたが、初めての定期試験で20位を取り、それ以降はゲーム感覚で順位を競うように勉強していました。気がつけば学年Top10の常連となり、「自分は勉強ができる」という自信が生まれていたのです。
ただ、この自信を高校生になっても引きずってしまったのが、のちの受験勉強で苦戦する原因になりました。
通っていた中高一貫校は偏差値でいえば50前後。いわゆる進学校とは言えない環境でしたが、大学受験を重視する校風ではあったため、高1から大学受験を意識するようになりました。その中で自分は「中学からずっと勉強してきたんだから、きっとどんな大学でも受かるだろう」と思い、軽い気持ちで東大を目指し始めました。今思えば、完全に「東大をなめていた」のだと思います。
選んだのは東大!でも、勉強はしなかった
東大を目指した理由には、もう一つ大きな要因がありました。
多くの大学では、受験の時点で学部や学科を決めて出願します。でも僕は、文理選択ですら数か月も悩んでしまうタイプ。進路をひとつに絞るなんて、とてもできませんでした。
そんな中で知ったのが、東大の「進振り」制度。これは、入学後に進学先の学部を決められるという仕組みで、柔軟な進路選択が可能になります。
この制度に強く惹かれたことも、東大を志望した理由です。ですが、高校入学後、新しく買ったPCにのめり込み、1年間ほとんど勉強しない日々が続きました。当然、成績は下降。しかし、当時の自分は「自分は頭がいい!本気を出せばできる!」と根拠のない自信があり、勉強時間を増やすことはありませんでした。
東大模試で0点、現実を知る
そんな自分に転機が訪れたのは、高1の冬に受けた東大同日模試でした。これは、実際の東大入試の問題を、高校1年生が本番直後に解いてみるという模試です。
この模試で、東大入試がいかに「別次元」かを思い知らされました。
東大入試は、高1の時点で解けなくて当たり前。それは分かっていました。
ですが、未修範囲のないはずの国語の問題があまりに難しく、試験時間中に1時間以上も手が止まってしまうという異常事態が起きました。文章の内容が「病床人のケアについて」という社会学・人類学的な文章で読解の方法が全くわからなかったのです。
一番得意だったはずの英語は、120点満点中10点台。タイトな試験時間の中でリスニングや英作文、長文読解、要約問題等々様々な種類の出題に対応しきれなかったことが原因です。
数学にいたってはまさかの0点で、本当に何もわからず、何から手をつけていいのか見当もつきませんでした。
「これはさすがにまずい」と、ようやく焦りを感じました。今まで、自分がいかに勉強していなかったかを思い知らされたのです。この経験をきっかけに、「自分にはまだまだ足りない」と考えるようになり、ようやく謙虚な気持ちで受験勉強と向き合おうと決意しました。
高2から基礎のやり直し!「わかったつもり」をなくす
心を入れ替えた自分がまずやったのは「基礎のやり直し」でした。
高2は、東大を目指す受験生にとって本格的な受験勉強を始めるべき時期です。しかし当時の僕は、それ以前に「自分のできなさ」を埋める必要があると感じ、あえて基本的な参考書に立ち返ることにしました。
国語では、古文用の読解問題集をやらずに、中学レベルの古文・漢文の文法書(学校配布の文法用参考書)を再読しました。単語でも基礎に戻り、学校配布の単語帳を読んで覚え抜けがないよう何度も暗記を繰り返します。
英語では基礎単語帳を読み、中学英語の文法(前置詞の使い方から)やり直しました。長文読解は英文解釈に慣れてきてから行おうとしていたので、簡単な文法用の問題集を買い、英文を1文1文丁寧に構文が取れるようになることを目標に勉強しました。
数学では学校の先生に基礎から数学の全分野を教えてもらうよう懇願し、長期休みには夏期講習や冬季講習の実施もお願いしました。自分は先生に数学を教えてもらいましたが、問題集でも代用できると思います。青チャートのような分厚い網羅系参考書ではなく(ページ数が多かったため自分は数学版の辞書としてチャートを使いました)、エッセンスが詰まった薄い基礎的な参考書をやるといいと思います。
まず国数英(特に英数)を固めなければいけないと判断したので、その他サブ教科の勉強は学校の授業にとどめ、メインの科目の土台固めを意識しました。
「わかったつもり」で流していた知識を、一つひとつ丁寧にインプットし直すことで、自分に足りていなかった“本当の基礎力”が明確になったのです。これが合格の大きなポイントになったと思います。
自分を疑い続けて、成績を伸ばす
高3になると、過去問や他大学の入試問題を使って演習を重ねましたが、自分で解いて終わりにせず、先生に添削してもらうことを徹底しました。
特に論述では、自分では気づけないクセや語彙不足を指摘してもらうことで、着実に改善ができました。これは、もし以前のように「自分はできる」と思い込んでいたら絶対にできなかった取り組みだと思います。その結果、模試の成績はみるみる上がりました。
「自分は頭がいい」と変なプライドを持っていたら、絶対にできないことです。受験勉強が本格化する前に謙虚な気持ちになれたおかげで、自分に必要な勉強にしっかり取り組むことができ、その結果、無事に東大合格を勝ち取ることができたのだと思います。
まとめ:自信と謙虚さ、そのバランスが鍵
「自分は努力している」という自負は大切です。でも、それが変なプライドに変わってしまい、他人の意見を聞けなくなったり、勉強法を見直さなくなったりしたら危険です。
勉強においては、「まだできる」「もっと良くできる」という謙虚な視点が必要です。
自己流にこだわらず、参考書選びや勉強法を見直し、試行錯誤しながら自分に合った方法を探っていく。それが、最終的に合格へとつながる道だと思います。