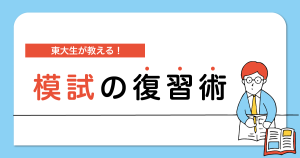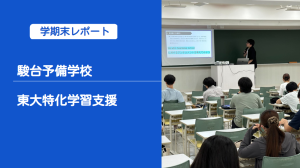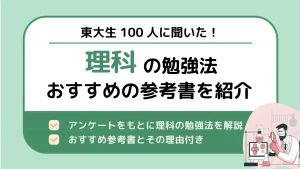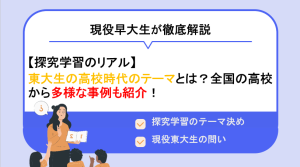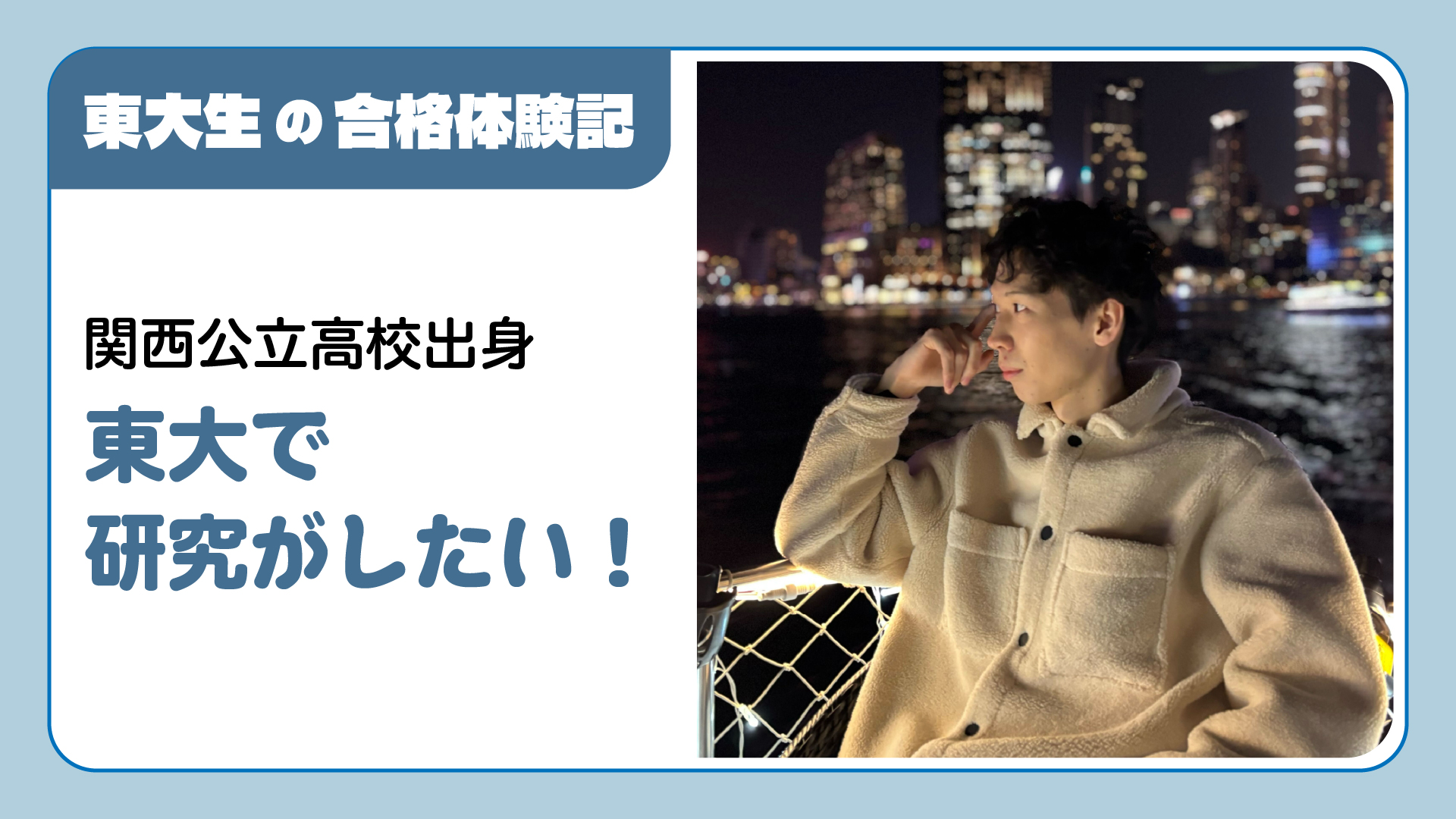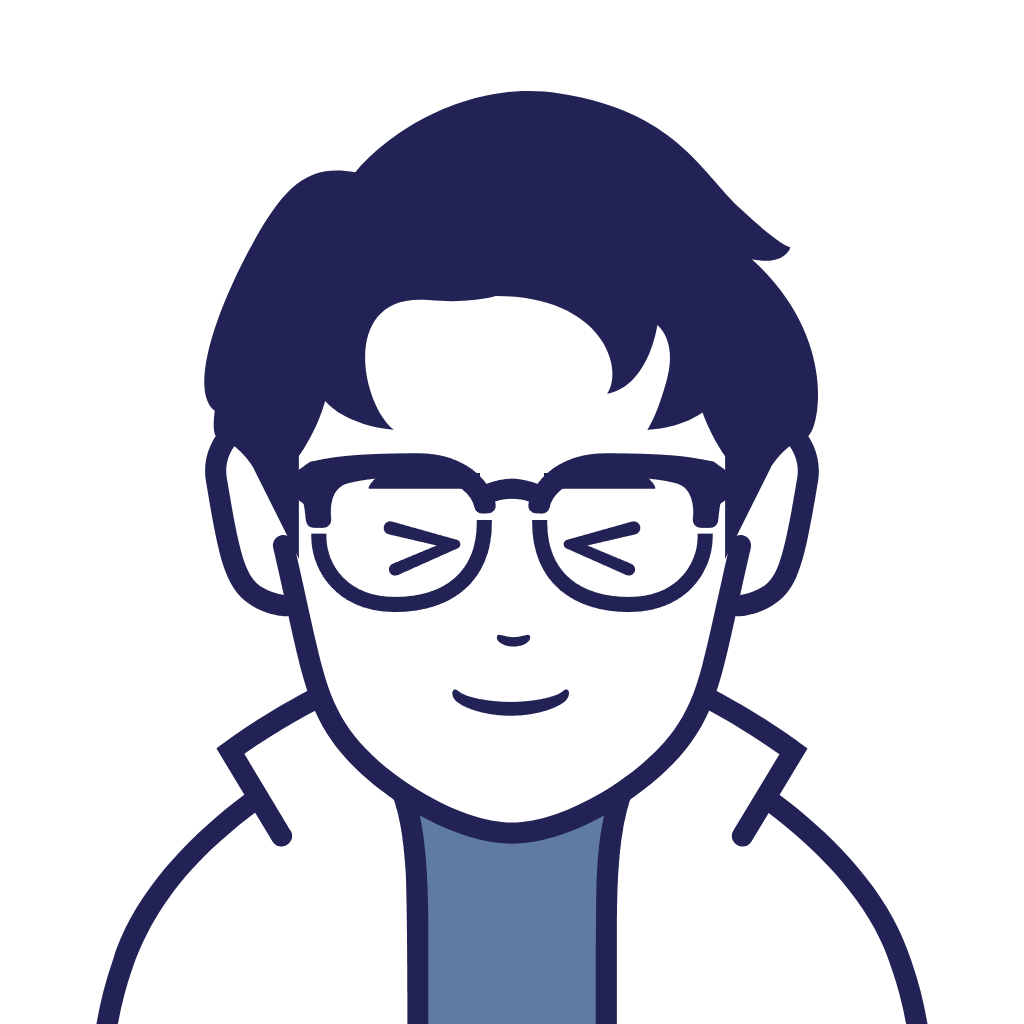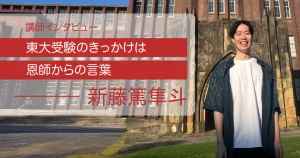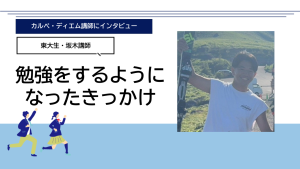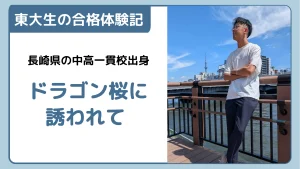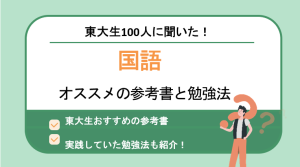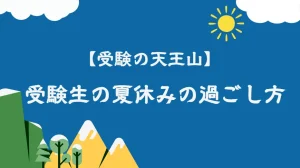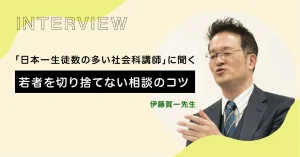オープンキャンパスで出会った研究テーマ
僕は関西の公立高校出身で、東大へ進学する生徒は数年に1人のような学校でした。というのも、関西には京大・阪大・神戸大・大阪公立大などの国公立大学へ進学する選択肢が一般的で、わざわざ東京へ進学しようというモチベーションが高くないので、頭が良くても京大へ進学するパターンがほとんどです。
そんな環境の中で、僕が東大を目指したきっかけになったのは、高2の時に「東大で研究したい!」と思えるテーマに出会ったことです。高校の課外活動の一環としての東京研修で、理化学研究所や東大のオープンキャンパスにいった際に、オープンキャンパス特別講座で、ある先生の「重力波」に関する講座を受けました。
当時から物理学や数学が好きだったこともあり、「重力波」に強く興味を引かれて、「東大に行けばこんな研究ができるんだなぁ」「こんな研究をしたいなぁ」と感じたのを覚えています。ただ僕は高校の中でも特段頭がいい方というわけでもないし、現実的には無理なんだろうな、と少し諦観した気持ちになったことも覚えています。
受験勉強を始めても決まらない志望校
高3になり本格的に受験勉強がスタートしましたが、結局志望校は確定せず、「なんとなく」勉強している状態が高3の秋まで続きました。
志望校は、東大理科一類、京大理学部、阪大理学部物理学科の3択でした。今考えると、この優柔不断なところが明らかに良くなかったと感じています。もちろん高3の初めの方は基礎学力の醸成が主なので、過去問演習などに多くの時間を割くことはありません。しかし、高3の夏くらいには志望校を確定させその大学の出題形式に合った勉強を始めるべきです。
具体例を挙げるとすれば、東大の英語でしょうか。
東大の英語は時間がタイトで、かつ様々な形式の問題が出題されます。ですから、要約は要約、リスニングはリスニング、ライティングはライティング、といったように個別で対策の時間を割かなければなりません。しかし、僕は志望校が確定していなかったことを言い訳に個別の対策をしていませんでした。結果、秋からの対策では過去問演習の時間が足りず、現役時は最低点から約10点の差で落ちてしまいました。
浪人を決め、一から基礎を見直した春
浪人を決めた3月。僕は、もう一度基礎的な知識の抜けが無いかを確かめることにしました。というのも、得点開示を見たところ、得意な数学で思うように得点ができていなかったことが主な敗因と分析したからです。
その一環として行ったのは以下の勉強です。
・1対1の演習(数1AIIBIIIC全て)
・鉄壁に掲載されている単語で分からないものを全て列挙
・古典単語・品詞分解・漢文句形を100%できるように
特に数学は、1対1の演習に乗っている問題全てを完璧に解いて解答も書けるようになるレベルまで時間をかけて復習しました。もしこの記事を読んでいる方で、浪人する人がいるのであれば、浪人初めの3〜4月にはこのように基礎の見直し、特に「自分が得意だと思っていたけど点数は振るわなかった科目」は重点的に行うべきだと思います。
たしかに、落ちてしまった瞬間はとても悔しい感情で、「高いレベルの問題をもっと解けるように!」思いがちですが、一旦冷静に基礎を見直しましょう。
具体的な話ですが、僕は現役で東大に落ちた時「対数微分法」を知らなかったのですが、東大の数学の入試問題に、この「対数微分法」を知っていればすぐに解けるような問題が出題されたことがあるんです。ということは「僕はその時点で周りの受験生に差をつけられてしまっていた」ということになります。
浪人で大事なのは「自分ができないことを発見し、それをどれだけ丁寧に潰していけるか」という考え方です。そのために、まずは「本当に基礎的な知識が抜けていないか」を確認する時間を確保して欲しいのです。
予備校の授業が始まれば、予備校のテキストの予習復習で時間が取られてしまうので、「自分が抜けている知識」を確認する時間は取れなくなっていきます。ですので、予備校の授業が始まる前に基礎の見直しの時間を取って欲しいです。
掴み取った合格
予備校では「毎日8時に駿台に行って授業を受けて、自習をして20時に帰る」という生活を1年続けました。
特筆すべきこととしては、僕は浪人中、「分からなかったことをまとめておく」ノート、通称まとめノートを作っていました。先述の通り、浪人で大切なのは「自分ができないことを発見し、それをどれだけ丁寧に潰していけるか」です。一度模試や演習で間違えた問題や抜けていた知識があったとき、それを効率的に復習するため、「まとめノート」にまとめていつでも見返せるようにしていました。
その結果、浪人時に受けた東大模試・京大模試では全てA判定を取ることができ、順調に浪人生活を進めていくことができ、晴れて東大の理科一類に合格できました。
今は、僕が東大を目指すきっかけになった講義をしていた先生の研究室で重力波について研究しています。
亀田 崚:2000年生まれ 東京大学理学部物理学科
関西の公立高校出身の現役東大生。東大を目指す同級生が少ない中、オープンキャンパスの際に見つけた研究室に憧れ、東大へ進学。東大では、自身の興味に合わせて物理学や言語学な多岐に渡る分野の勉強を行い、現在は「勉強した先にある楽しさ」を伝える活動を主に行っている。