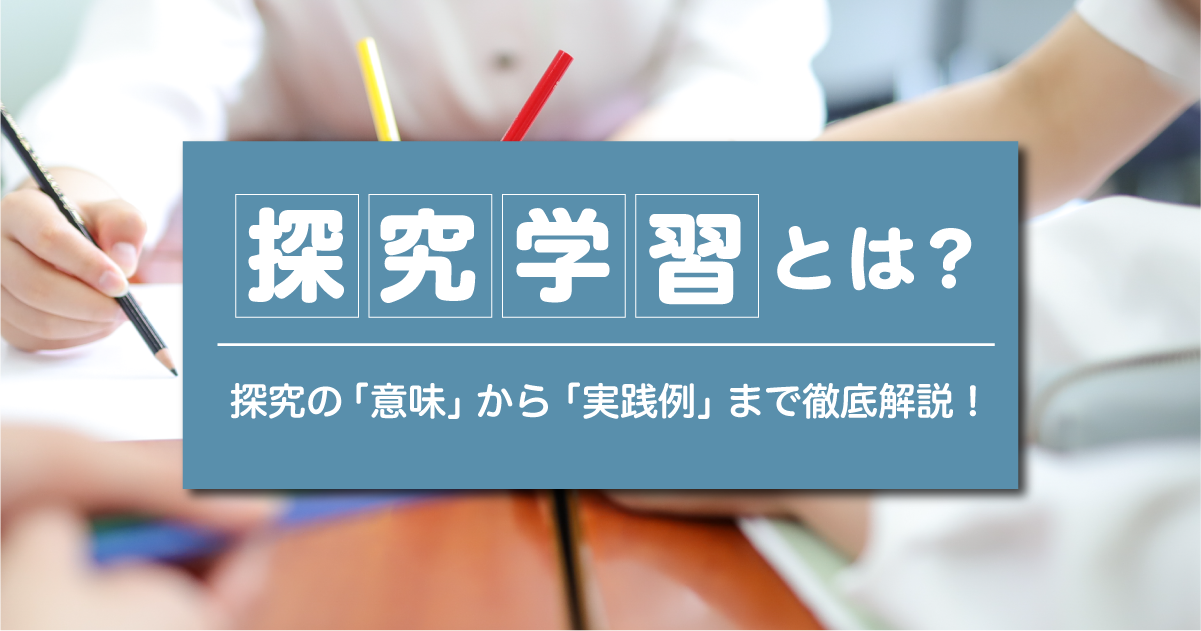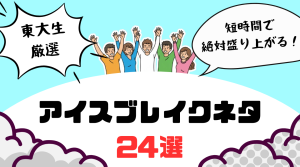高校の学習指導要領の改訂で一躍話題となった「探究学習」。必修科目にもなっている探究学習は、これまで学校で行われてきた科目の指導とは大きく異なります。だからこそ、現場で指導する先生からは、「どうやって指導すればいいのか?」「そもそもどんな授業内容が良いのか?」といった悩みの声をよくいただきます。
そこで本記事では、探究の授業ですぐに使えるお役立ち情報をまとめました。探究学習の意味からその実践例、学校への導入サポートを行うサービスまで徹底解説していきます!【2025年6月28日更新】
探究学習とは何か?
探究学習は、「問題解決型の学習」のことを指します。学校で行われる教科学習とは異なり、生徒自らが課題を設定し、その解決に向けた計画を立てて実践していきます。
探究学習において重要なのは、生徒の主体性を引き出すことです。先生から生徒に知識を教授することの多い教科学習とは違い、生徒自ら学ぶ姿勢が求められているのです。探究学習を通して、これからの社会を生き抜くために不可欠となる「自分で学ぶ力」「自分で考える力」を養うことが目的とされています。
2022年度から施行されている高等学校学習指導要領では、新たに「探究」と名のつく科目が7科目設定されました。下記がその7科目です。
- 「古典探究」
- 「地理探究」
- 「日本史探究」
- 「世界史探究」
- 「理数探究」
- 「理数探究基礎」
- 「総合的な探究の時間」
このうち必修科目となっているのが、「総合的な探究の時間」です。このことからは、探究で養うことが目的とされた「自分で学ぶ力」「自分で考える力」の重要性をうかがうことができます。
探究学習と教科学習・調べ学習の違い
教科学習は、カリキュラムや教科書に基づき、知識や技能を習得するプロセスが中心になります。いわば学ぶ道筋があらかじめ示されていて、生徒が積極的に自分の疑問や興味を掘り下げる場面は限られがちです。
また、調べ学習は、教師が与えたテーマについて資料や文献を検索し、その情報をまとめる学習形態です。たしかに主体的な情報収集は行われますが、探究学習ほど根本的な問いの設定や仮説検証を重視しないため、成果が知識の羅列にとどまるケースも少なくありません。
それに対して探究学習は、生徒自身が「何を問い、どこまで深く掘り下げるのか」を能動的に考えるところから始まります。与えられた問題ではなく自ら課題を設定し、疑問を解決するための道筋を見いだすプロセスを重視する点こそが最大の特徴といえます。
探究学習が注目される背景
近年、社会では急速に情報技術が進歩し、これまで存在しなかった新たな職業や働き方が次々と生まれています。従来の知識詰め込み型の教育では、新しい社会課題に柔軟に対応できる人材を育てにくいという問題意識が高まってきました。そこで、答えのない問いに対して自らアプローチし、周囲と協働しながら解決の糸口を見つける探究的な姿勢が重要視されるようになったのです。
文部科学省も学習指導要領を改訂し、「総合的な探究の時間」を導入するなど、生徒が自分なりの問いを立てる経験を積むことを奨励しています。経済のグローバル化やAIの台頭といった社会構造の大きな変化が、探究学習を単なる一時的なブームではなく、教育改革の中核として注目させている要因といえるでしょう。
参考:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sougou/main14_a2.htm
新学習指導要領における探究学習
そもそも、新学習指導要領で新たに示された「総合的な探究の時間」とはどのようなものなのでしょうか? ここからは、文部科学省が考える探究学習について紹介していきます。
なぜ今「探究」なのか?
現代社会は、AIの台頭や急速な技術革新により、予測不可能な変化の激しい時代と言われています。このような時代においては、従来の知識詰め込み型の教育では対応しきれないと考えられてきました。
それでは、どのような力を身につける必要があるでしょうか? 文部科学省はこの問いに対して、「生きる力」という解答を示しています。
参考:学習指導要領「生きる力」
「生きる力」とは、予測困難な時代を前向きに捉え、自身の人生をより良くしていくためにはどうしたら良いかを主体的に考える力のことです。どんな社会になったとしても、自分で学び、考え、行動し、それぞれの幸せを実現していってほしいという願いが込められているといいます。
この「生きる力」を育むための具体的な教育方策として、「探究学習」が提示されているのです。
「総合的な探究の時間」とは?
「総合的な”探究”の時間」の前身は、「総合的な”学習”の時間」というものでした。これは、総合的な学習を通して課題解決能力や主体的な学びを育む授業として設置されていたものです。これだけ聞くと、「生きる力」を育むことに必要な要素は揃っているようにも感じますが、実際はそうではありませんでした。
というのも、「総合的な学習の時間」で学んだことが日常的に行う教科学習と結びつかないことや、学校の自由な裁量のもと運営されていたがために、本来想定されていた「課題を解決することで自己の生き方を考えていく学び」が得られるような授業が行われていなかったりしたのです。
そこで、新学習指導要領では、必修科目「総合的な探究の時間」として新設されたのです。新学習指導要領では、総合的な探究の時間について、以下のように述べられています。
探究の見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
探究の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究の意義や価値を理解するようにする。
実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。
探究に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造し、よりよい社会を実現しようとする態度を養う。
引用:文部科学省「高等学校学習指導要領(平成30年)」
「総合的な探究の時間」で得られた力を、教科学習や実際に社会に出た後の生活に活かすことに重点が置かれています。
文部科学省は、「総合的な探究の時間」では、知識技能を身につけるだけでなく、それを活かそうとする「学びに向かう力」「人間性」や、未知の状況に対応するための「思考力」「判断力」「表現力」をも身につけることが期待されているのです。
引用:文部科学省HP 平成29・30・31年改訂学習指導要領の趣旨・内容を分かりやすく紹介
「探究」と「探求」の違い
ここで、「探究」と間違えやすい言葉に「探求」があります。どちらも「たんきゅう」と読みますが、意味は異なります。
まず、探究の「究」という字は、「きわめる」とも読みます。つまり探究とは、物事を深く掘り下げて学び、物事を明らかにするということを指します。
一方で、探求の「求」という字は、「もとめる」とも読みます。つまり探求とは、物事を探し求めて得ようとすることを指します。
探究のほうが、得られる学びがより深いということが言えそうですね。
探究学習の進め方:4つのステップ
探究学習には、進めていく上での型が存在します。ここからは、探究学習の効果的な進め方を紹介していきます。
①探究したい課題の設定
探究学習では、生徒それぞれが自分なりのテーマを設定して探究を進めていきます。ここでのポイントは、生徒自身がやりたい!と思えるテーマを設定できるように支援してあげることです。こうすることで「やらされている」という感覚をなくし、生徒の主体性を引き出すことに繋げられます。
「探究学習を通して何を知りたいのか?」「どんなことを課題に感じていて、どんなふうに解決したいのか?」といった問いを通して、生徒自身が主体的に取り組みたいと思える課題を設定できるようにしましょう。
探究学習のテーマの決め方はこちら

②情報収集・調査
課題を設定することができたら、それを解決するための情報を収集していきます。
情報を収集するツールはどんなものでも構いません。一番手頃なもので言うと、インターネットが挙げられるでしょう。ただし、インターネットでの情報だけで完結してしまうと、ただの調べ学習になってしまいます。地域の詳しそうな人にインタビューをしたり、実際にフィールドワークをしたりする中で、多角的な情報を収集することが重要です。
ここで注意したいのが、高校生は世の中にどんな人がいて、どんなものがあるという情報を、大人に比べてあまり持っていないということです。知らないと言うことは、「その人に聞く」「その場所に行く」というような選択肢を思いつくことすらできません。
そこで活躍するのが先生です。生徒がさまざまな視点から情報収集する上で助けとなるような人、もの、場所を紹介してあげると良いでしょう。
③収集した情報の整理・分析
情報を収集することができたら、次はそれを整理・分析し、どんなことが言えるのかをまとめていきます。理科の実験でいう「考察・まとめ」の部分ですね。
探究学習は、大学などで行う研究の練習のようなものです。だからこそ、ただ調べたことをまとめるだけでなく、調べた情報から新しいものを見出す必要があります。
といっても、いきなり考察をしろと言われてすぐにできる高校生はなかなかいません。しっかりとした考察をアウトプットするためには、先生が問いを投げかけてあげながら考える補助線を引いてあげることが必要です。
④探究学習のアウトプット・発表
成果を発表するまでが探究学習です。人に伝えるという目的を持つことで、自分が課題として設定したことやどんなことがわかったのかを改めて整理することができます。
集めた情報、それをもとにした考察を一つの成果物としてアウトプットし、人に伝える機会を設けましょう。
一つの成果物として残しておくことで、その後の学習に役に立ったり、何回か探究学習を重ねた後に見返して自分の成長を実感したりということが可能になります。
探究学習で身につく力
探究学習が新学習指導要領でも注目されている理由の一つには、これからの社会に必要な力が得られるということが挙げられます。ここからは、探究学習で身につく力を紹介していきます。
主体的に学ぶ力
探究学習のポイントは、生徒の主体性を引き出すことです。一方的に教わるだけの教科学習ではなく、自分で課題を設定し、方法を模索しながら探究を進めていく必要があります。
その中では、「先生にこうしろと言われたから」「この課題をこなすと決まっているから」というような受動的な学びではなく、「自分がこうしたらいいと思ったから」「この課題を解決したいと思うから」という能動的な学びが生まれることとなります。こうして、教科学習では身に付かない主体的に学ぶ力を身につけることができると言えます。
AIが人間の仕事の約半数を奪うと言われているこの時代を生き残るためには、主体的に学び続ける力が必要なのです。
情報収集力
探究学習では、調べ学習では終わらない多角的な情報収集が重要だと話しました。自分で情報を集めるための方法を考え、実行する中で、自分にとって必要な情報を取捨選択する力を身につけることができます。
現代社会はさまざまな情報が溢れる世の中となっています。その中で、自分にとって必要で、正しい情報を取捨選択できるというのは、周囲に惑わされず生きる上で重要な力だと言えます。
課題解決力
探究学習では、課題の設定から情報収集、整理分析までを一貫して経験します。その過程で扱う問いは、決まった答えのないものが多数でしょう。
ここで、社会に目を移してみると、そこにあるのは答えのない問いばかりです。それらに対応できるようにするには、学生のうちから答えのない問いと向き合い、課題を解決する力を養わなければなりません。
探究学習で身につく課題解決力は、社会に出てから不可欠な力なのです。
対話力
探究学習の特徴の一つとして、人と対話をしながら考えを深めていくという点があります。というのも、複数人でグループを組んで探究学習をすることや、成果発表の際に他者からフィードバックをもらって次に生かすというような機会が多くあるからです。
AIにはない人間の強みの一つに、他者との協働で新しいものを生み出せるということがあります。探究学習では、その人間ならではの強みを引き出すことができるのです。
探求学習で生徒の主体性を引き出すには?
生徒の主体性を育てるには、「自分で問いを立てられること」が何より大切です。正解のないテーマや身近な問題を扱うことで、生徒は学びを自分ごととして捉えやすくなります。また、テーマや発表方法などに選択肢を与えると、責任感ややる気が生まれます。
教師は答えを教えるのではなく、問いを深める伴走者として関わることが求められます。失敗を恐れず意見を出せる心理的安全性が担保された場づくりや、学びの過程をふり返る機会も、主体的な学びを支える大切な要素です。
心理的安全性に関する記事はこちら
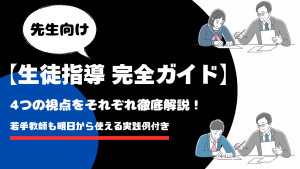
興味・関心に応じたテーマが生む高い学習モチベーション
探究学習では、生徒が自分の興味・関心に基づいてテーマを選べることが、学びへの強い原動力となります。「知りたい」「もっと調べてみたい」という気持ちがあるからこそ、自分から動き、試行錯誤しながら深く学ぼうとする姿が生まれます。
誰かに与えられた課題ではなく、「自分で選んだ問い」であるという実感は、責任感や達成感にもつながります。こうした生徒の内発的な動機づけを大切にすることで、学習のモチベーションが高められ、持続的な学びに繋がります。内発的動機は主体的で深い学びにつながりやすく、探究学習との相性も良いといえます。
知識定着と自己効力感の向上に寄与する探究学習の成果とは
探究学習では、生徒が自ら問いを立て、調べ、考え、表現するという一連のプロセスを経験します。この過程を通じて得た知識は、単なる暗記ではなく「意味のある知識」として定着しやすくなります。
また、自分で調べたことを整理し、発表や共有を通じて他者に伝える経験は、「自分にもできる」という感覚=自己効力感を育みます。特に、自分の問いに対して納得のいく答えや仮説にたどりついたとき、生徒は学びに対して前向きな自信を持てるようになります。
このように、探究学習は知識と意欲の両面で、生徒の成長を力強く後押しする学びの形です。
探究学習の評価方法
探究学習の評価には、成果物だけではなくプロセスにも目を向ける視点が欠かせません。生徒がどんな問いを設定し、どのように情報を集め、仮説や考察を深めていったかというプロセスを捉えるには、ルーブリックの活用が一つの有効な手立てとなります。
ルーブリックとは、評価の観点や達成度を多角的に定義することで、生徒ごとに異なる学習の進み方を可視化する方法です。論理的思考やコミュニケーションスキルの伸びを具体的な指標で示すことで、生徒本人や保護者が「どの部分を伸ばせばよいのか」を把握しやすくなる利点があります。さらに、発表会や振り返りシートを活用すれば、教師だけでなく生徒同士が相互にフィードバックし合う環境を整えられ、学びの質をより深めることにつながるでしょう。
レポートやプレゼンテーションでまとめる探究学習の成果
探究学習では、調べたことや考えたことをレポートやプレゼンテーションとしてまとめる過程が、重要な学びの一部となります。単に情報を集めるだけでなく、それを自分なりに整理し、筋道立てて人に伝えることで、理解がより深まり、知識が定着していきます。
また、発表や共有の機会は、生徒にとって「伝える責任」と「達成感」を伴う経験になります。他者からの質問やフィードバックを受けることで、自分の探究を客観的に見直す力や、柔軟な思考力も育まれます。
このように、成果を「かたちにする」ことは、学びを終えるためのゴールであると同時に、新たな問いや気づきにつながる出発点にもなります。
自己評価・同僚評価を取り入れたプロセス重視の評価方法
探究学習では、結果だけでなく、そこに至るまでの思考や取り組みの過程を丁寧に振り返ることが重要です。そこで有効なのが、自己評価や同僚評価を取り入れたプロセス重視の評価方法です。
自己評価では、生徒自身が目標に対して自分の取り組みを振り返ることで、学びの意味や課題を自覚することができます。また、同僚評価では、仲間の視点を通じて自分の探究活動を客観的に見直すことができ、気づきや改善につながります。
こうした評価を取り入れることで、生徒は「評価される存在」から「自分の学びをつくる主体」へと意識を転換しやすくなります。単なる成果物の出来栄えではなく、思考の変化や試行錯誤の姿勢そのものが評価の対象になることで、学びに対する内発的動機づけも高まります。
このように、プロセスを可視化し、他者と共有しながら振り返る仕組みは、探究的な学びにふさわしい評価のあり方として、今後ますます重視されていくと考えられます。
探究学習のテーマ例
探究学習の効果を最大限引き出すためには、それぞれの生徒にあったテーマ・課題を設定することが重要です。下記のチェックポイントを満たす探究テーマを設定できるように支援してあげましょう。
- 生徒にとって身近な入り口があること
- 生徒が探究したいと思えること
- 答えが一つに決まらないこと
- 調べ学習以上に深められること
とは言ってもテーマをすぐに思いつくことは難しいと思うので、人気の探究テーマの例を紹介します。生徒が探究テーマを選ぶ際の参考にしてください。
- 伝統文化「薩摩切子の良さを広めるには?」
- 健康「AEDが届くまでの時間を短くするには?」
- 食文化「食品ロスを削減するには?」
- 地域活性化 「地元名産品の人参を使った商品開発で地域活性化」
- 職業、キャリア「なりたい自分とは?」
- 国際理解「日本の友達と留学先で出会ったアメリカ人の友達の違いとは?」
- 情報化社会「SNSとの良い付き合い方とは?」
- 環境問題「プラスチックゴミの現状を知ってもらうには?」
- 福祉「おばあちゃんが通うデイサービスの課題とは?」
テーマ設定の手法については以下の記事もご覧ください。

具体的な課題設定のコツ
① 身近な「違和感」や「問い」から出発する
- 生徒自身が「なんで?」「どうして?」と感じたことを出発点にする。
- 例:「なぜ○○市にはコンビニが多いのか」「どうすれば学校のゴミを減らせるか」
→ 身近であればあるほど、当事者意識が生まれ、調べる意欲が高まる。
② 正解のない問いを設定する
- 答えが一つに決まらないテーマを選ぶ(例:価値観や社会的な課題に関する問い)
- 例:「幸せとは何か」「スマホは子どもにとって本当に悪いのか?」
→ 生徒が考え続けられる問いになり、深い探究につながる。
③ 「〜か?」「どうすれば〜か?」という問いの形にする
- 自分なりの立場や答えを持てるように問いを工夫する。
- 例:「AIは人間の仕事を奪うのか?」「若者の投票率を上げるにはどうすればいいか?」
→ 意見や提案に結びつきやすく、プレゼンやまとめもしやすくなる。
④ 探究のゴールをイメージさせる
- 「調べてどうしたいか」「誰に伝えたいか」を考えさせる。
- 例:「地域の人にアンケートをとって提案書をつくる」「学校内でポスター掲示をする」
→ 目的意識が明確になり、活動に集中しやすくなる。
探究学習の実践例
新学習指導要領に先駆けて、学校独自で探究学習に取り組んでいる事例も存在します。ここからは、探究学習の実践例を紹介していきます。
大槌高等学校「三陸みらい探究」
岩手県の大槌高等学校は、2011年に起きた東日本大震災で大きな被害を受けました。その影響で生徒数が激減してしまい、廃校の危機が訪れた際に導入された事業のうちの一つが、この「三陸みらい探究」です。
大槌高等学校HP:http://www2.iwate-ed.jp/oht-h/
同校HPでは、以下のような説明がされています。
大槌高校では、三陸地域の復興とその先の未来を担うリーダーを育てることを目標に、週2時間の「三陸みらい探究」を開講しています。
1・2年の2年間を使い、自分のテーマを立て、自分自身の課題意識に対してプロジェクトプランを実践する活動を行います。
自分の興味関心をみつけるために、自己理解プレゼンや多様な大人との対話、大槌町や三陸地域の課題発見プログラム等を実施します。
引用:http://www2.iwate-ed.jp/oht-h/attractive3.html
実際の取り組みでは、練習として1週間で探究学習に取り組む「1週間マイプロジェクト」や、町内外で働く大人たちの生き方について話を聞く「大槌発みらい塾!」など、探究学習に取り組むために必要な力を育むプログラムが用意されています。
また、探究学習ではテーマに応じてゼミが開かれ、それぞれのゼミで教員が支援をしたり、生徒がお互いにフィードバックをしながら探究を深めていくと言います。生徒が独自にテーマを設定する探究学習に加え、国数英理社の5教科ごとにも探究学習が実施されています。
これらのプログラムは、大槌町から探究学習の支援などを行うNPO法人カタリバへの業務委託で行われ、教員が時間の都合上、手のつけられない細かいプログラムを担当しています。
明豊高等学校「九大専科課題解決型プログラム」
大分県の明豊高等学校では、九州大学に進学することを目的とした「九大専科」というコースが存在しています。このコースでは、九大専科探究プログラムと呼ばれる探究学習が実施されています。
明豊高等学校HP:https://meiho-beppu.jp/
同校HPでは、以下のようなスローガンが掲げられています。
「なぜ」を追究し、粘り強く考え抜く姿勢を持った生徒を育成する。
このスローガンを実現するための一つの要素として、学んだことが活用できる課題解決型プログラム、つまりは探究学習が実施されているのです。
プログラムの一つには、「明豊村の地図」を作ってみようというテーマで実施された協働ワークがありました。ワーク中は東大生も各グループを回り、活動を支援します。このプログラムを受けた生徒は以下のような感想を残しています。
「ワークに取り組んでいる時、一番に共有するべきキーワードが最初に出てこなかったのですが、それでも話を進めることができて、時間内にゴールにたどり着けたことに驚きました。自分たちもすごいなと思いました(笑)。」
「「周りの人と力を合わせて問題を解いていく」という社会に出たときに必要な姿勢を学ぶことができました。 」
この探究学習をプロデュースするのは、日曜劇場ドラゴン桜2の監修を務めた西岡壱誠率いるカルペディエムです。九州大学合格への戦略を緻密に立てながら、探究学習プログラムの作成、実施をしています。
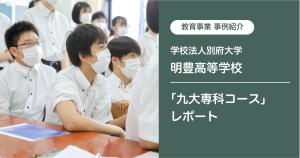
武蔵野中学高等学校「アカデミックマインド講座」
東京都の武蔵野中学高等学校では、「アカデミックマインド講座」が実施されています。これは、日常の中に問いを立て、仮説・検証する一連の思考法を学ぶことで、課題発見・解決能力の向上を目指す講座です。
プログラムでは、「蜂が蜂蜜を作るのはなぜ?」などの身近な問いや、中高生でも解ける大学入試問題を扱っていきます。
中学生、高校生両方に実施されているこのプログラムでは、生徒たちは以下のような感想を残しています。
「江戸時代から明治時代にかけて平均身長が上がったのはなぜか?」という問題を解いたのが一番印象に残っています。最初は「え〜。なんでだろう……。分からない。」と思ったのですが(笑)。講師の先生と一緒に、分解して、解いていったら、腑に落ちて……。自分にもわかる問題だったのかと驚きました。」
「もともとあまり疑問がないというか(笑)。そういうものなんだな〜と受け入れてしまうタイプでしたが、地理の授業で大気汚染のレポートを書いているとき「なぜこの地域では環境汚染が進んでいるんだろう」など、1つの物事に対して、これまでより深く考えられるようになったなあと思います。」
このプログラムも、明豊高校と同じくカルペディエムがプログラムの作成、実施を行っています。
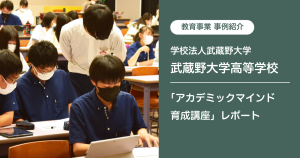
探究学習における教員の役割
探究学習では、教員に求められる役割もガラッと変わってきます。ここからは、探究学習において教員が果たすべき二つの役割について紹介していきます。
メンター
メンターとは、日本語で指導者、助言者という意味です。
例えば、学校の水質をテーマに探究学習を進めている生徒がいるとしましょう。その生徒は分析手法について悩んでいるようです。さて、この時どんな助言をすると良いでしょうか?
例えば、手法を教えるのではなく、それを調べるためのサポートをすると良いでしょう。こうすることで、「先生に言われた方法でやった」のではなく、「自分で調べて、選んだ方法でやった」という感覚を生徒自身が持つことができます。生徒の主体性を引き出すためには、教員は教えてはいけないのです。
あるいは、考察の部分で悩んでいる場合も考えてみましょう。この時も、「先生の意見が正解だ」と思わせないようにすることが重要です。生徒が1人では深められない、気付けない視点について、じっくり対話をしながら考えを引き出してあげるようにすると良いでしょう。
コーディネーター
探究学習では、学校外の資源が必要になる時もあります。例えば、探究学習をより深めていく上で、フィールドワークをしなければならなかったり、地域の人にインタビューをする必要があったりというようなことが考えられるでしょう。
そんな時、生徒は学校外にどんな資源があるのかをそもそも知らない場合が多いです。だからこそ、学校外にこんなものがあるよ、という選択肢を提示してあげるのも、教員の重要な役割です。
ただし、「この人に話を聞いてきなさい!」と強制してしまうのはNG。あくまで選択肢の一つとして提示してあげるようにしましょう。
その上で生徒が必要だと感じたのなら、その資源と橋渡しをしてあげましょう。例えばインタビューをするとなったら、連絡先を教えてあげるだけでも良いのです。
ファシリテーター
探究学習では、教員は「答えを教える人」ではなく、学びを支えるファシリテーターとしての役割が求められます。
- 生徒の問いを引き出す声かけをする
- 話し合いや活動を円滑に進める環境を整える
- 自分で考え、選び、ふり返る力を育てる
- 迷ったときにヒントを与え、背中を押す
- 評価ではなく「対話」として関わる
生徒の探究が深まるのは、「先生が教えすぎない」とき。見守り、問い返し、寄り添うことが、教師にできる最大の支援です。
探究学習を支援するサービス
現在では、学校での探究学習の導入を支援するサポートも多く存在しています。その中でも、先ほどの実践例でも登場した二つの支援サービスを紹介します。
NPO法人カタリバ「マイプロジェクト」
NPO法人カタリバでは、身の回りの課題や関心をテーマにプロジェクトを立ち上げ、実行することを通して学ぶ、 探究型学習プログラム「マイプロジェクト」の提案、支援、大会の実施などを行っています。
各学校に向けては、「マイプロジェクト」を学校で実施するためのカリキュラムやプログラムの考案のほか、探究学習を支援する「伴走者」が運営する学び合いコミュニティへの参加サービスなどが提供されています。
株式会社カルペ・ディエム「探究支援パッケージ」
株式会社カルぺ・ディエムでは、大学受験合格に向けた受験指導に加え、各学校のニーズを踏まえた探究支援を行う「探究支援パッケージ」を提供しています。カリキュラムの作成や導入支援、学校でのワークの実施など幅広いサポートが特徴です。
登壇する講師は、現役東大生講師です。高校生と近い視点を持つ大学生だからこそ伝えられることを大切にしています。講演会のほか、講義・ワークショップ、座談会などさまざまな形式での探究支援が可能です。
まとめ
いかがだったでしょうか? まだまだ授業実施に関する知見が少ない探究学習ですが、その効果は大きいと考えられています。本記事が、探究の授業の参考になりましたら幸いです。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校様・保護者様のお悩みに対応した講演・講座・ワークショップをご提案&実施しております。
生徒の皆さんの大学選び&学部選びのワークショップ、モチベーションアップを目的とした講演、探究学習授業、長期休暇の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しています。
講師は現役東大生!偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめとして、地域格差・経済格差など、さまざまな逆境を乗り越えた現講師たちが、生徒に寄り添って対応します。
ご相談から受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。