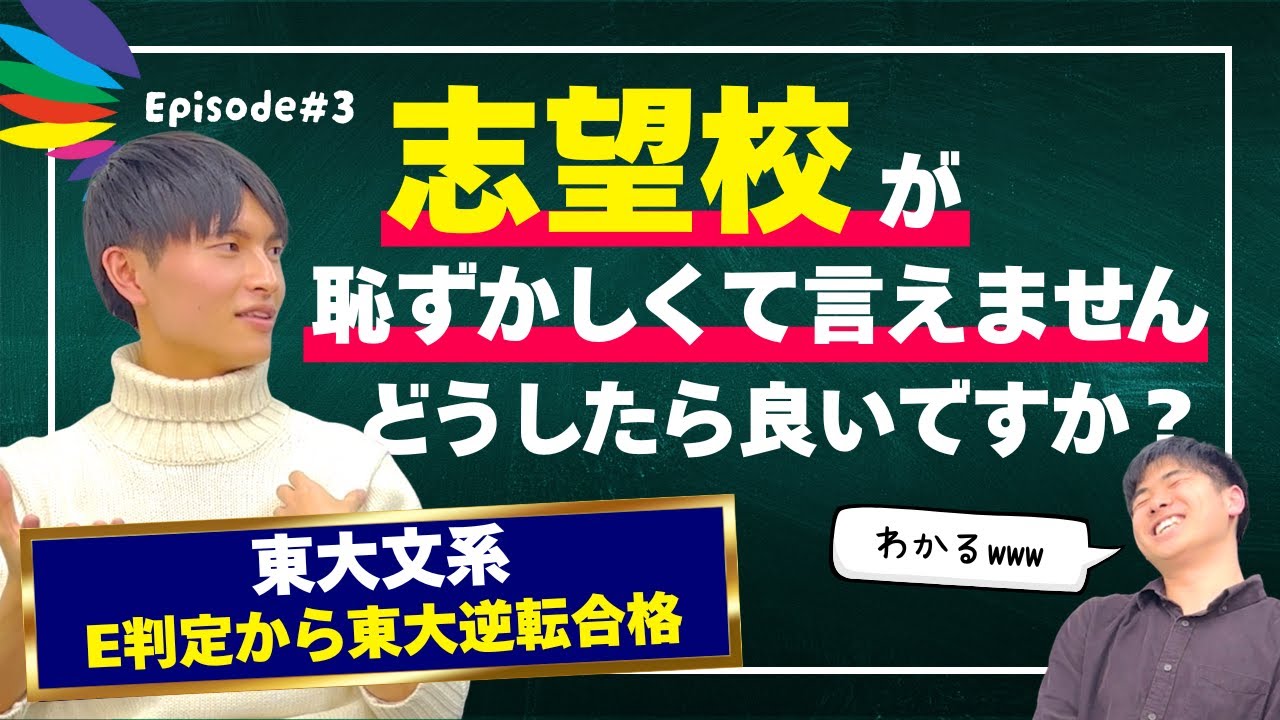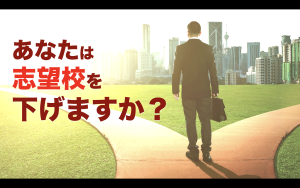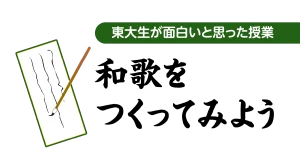志望校を公言してしまうと、周りから笑われてしまうのではないか。お前なんかがあの大学目指すの? と思われてしまうのではないか。そんな不安から、志望校を堂々と言えない人は多いのではないでしょうか。
そんな中、その大学を志望していると自信を持って言うためにはどうすればよいのでしょうか?
今回は、志望校が恥ずかしくて言えないという難題に、東大カルぺ・ディエムの2人が知識と経験を駆使してお答えします!
(出演)
サムネイル右側 永田耕作:東大理系 計算の申し子
サムネイル左側 清野孝弥:東大文系 外国語マスター
なぜ志望校を言えないのか?
まず、恥ずかしくて志望校を公言できない原因を分析してみましょう。なぜ? と考えることが解決への第一歩です。
永田:志望校を言えないのは、自信がないからでしょうね。「自分なんかが」と思ったり、笑われるのが怖かったりするのでしょう。
清野:確かにそうですね。クラスで誰も東大志望がいないのに、高1から「東大に行きます!」なんて言えないですよね。言ったらニヤニヤされることもありますし。
永田:でも、そこでニヤつく人は、心のどこかで嫉妬してるのだと思います。「先を越されてしまったな」と。
清野:結局、同調圧力ですよね。周りの目を気にせず自分の志望を貫く姿勢が問われるのかもしれません。
志望校を公言するメリット
永田さんは「志望校を公言するメリットが大切なのではないか」と言います。周りに言うことで、どのようなメリットがあるか、分析してみましょう。
永田:志望校を公言するメリットがあれば、恥ずかしくても言えるのではないかと思います。清野くんは何かメリットがあると思いますか?
認知的不協和で行動が変わる!
清野:僕は高2の夏に東大を志望することを先生や友達に言いました。すると、模試の成績が悪いと恥ずかしいから、必死に勉強するようになったのです。
これは「認知的不協和」という心理学の現象で、自分の言動と現実が食い違うと、それを埋めようとして行動が変わるというものだと考えられます。
永田:一度「東大志望」と言ったら、もう隠せない。だから勉強せざるを得なくなるわけですね。
清野:そうです。志望を言うことで、行動が変わる可能性があるんです。
自分で自分にラベルを貼ることの重要性
永田:それに近い話で「優等生理論」なるものもあると思います。優等生というものは、誰かが数値化したわけではなくて、周りが勝手にレッテルを貼っているものですよね。
でも一度そう見られると、実際に優等生らしく振る舞うようになるのではないか、と多くの生徒さんを見てきて感じています。
清野:それは「ラベリング理論」と呼ばれていますね。人はレッテルを貼られると、そのイメージに合わせて行動してしまう。
だから「東大志望」と自分で宣言すれば、そのラベルに合わせて勉強するようになるのです。
永田:つまり、恥ずかしい気持ちはあるでしょうが、「その大学を志望する人」というラベルを自分で選んで貼ることが、行動を変えるきっかけになるのですね。
応援してくれる人が増える
永田:もう一つ大事なのは「応援につながる」ということだと思います。
進学に特別なこだわりがない人より、明確な志望を持っている人の方が、周りは応援したくなるはずです。
実は、僕が東大を目指した大きな理由は祖父の存在でした。小さい頃から「耕作は東大に行くんだ」と言われ続けていたのです。高1のとき、そんな祖父が亡くなってしまって、その言葉が俄然重みを増しました。
応援してくれた祖父のために挑戦しようと思ったのです。
清野:いい話ですね……。応援してくれる人の存在って、本当に大きいです。
周りに志望校を伝えることで、応援隊がどんどん増えていく。これもメリットのひとつですね。
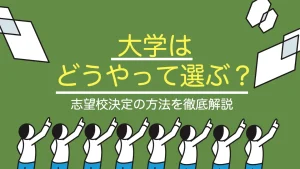

目標は明確かつ達成困難なものに
清野さんは、ただ公言するだけでは応援してもらうには足りないのではないか、と言います。志望校を言うことのメリットを享受するためには、どんな目標を持てばよいのでしょうか?
清野:志望校を周りに言うことは、「目標を明確にする」ことです。
でも、ただ明確なだけでは応援されないのではないでしょうか。例えば、「家までこの時間のこの電車で帰る」という目標を聞いて、応援したくなる人はあまりいませんよね。
つまり、目標は「具体的かつ達成困難」である必要があるのではないでしょうか。
挑戦的で、できるかどうか不安を伴う目標であることが大切だと思います。
永田:確かに。その時点で行ける大学をただ言うだけでは、それは目標ではなく単なる未来予想図ですからね。
受験は一種の競技のようなものです。せっかく舞台があるなら挑戦すべきだと僕も思います。
清野:僕は「たとえ足切りに引っかかったとしても、そのまま東大受験にチャレンジしたい」と言った教え子に感動して泣いてしまったことがあります。応援したくなるのは、そういう「本気の挑戦」ですよね。
永田:受験では、その学校を受けたら必ず何%かの確率では受かりますよね。
受かるかもしれないし、落ちるかもしれない。
でも、それが0%になるのは「受けない」と決めたときだけです。挑戦すれば可能性は必ず残るのです。
清野:そうですね。
だからこそ志望を公言し、応援してくれる人を味方につけることが大事です。受験は一人で戦うものではないと思います。
永田:最終的には「周りとの関係の中でどう挑戦するか」がカギなのでしょうね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
受験は自分ひとりでは乗り越えることができません。
周りの人に応援してもらえるように、明確な目標を持ってそれを口にする。そして、口にしたからには、叶えられるように努力する。
恥ずかしい気持ちもわかりますが、数年後の春に咲く桜に想いを馳せて、宣言してみましょう。
受験は、周りを巻き込み、応援を力に変えることができる絶好の機会です。
ぜひその舞台を最大限に活用して、高い目標に挑戦してほしいと思います。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。