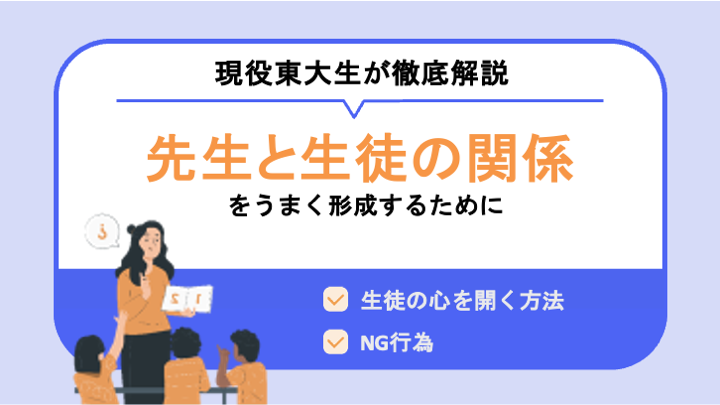突然ですが、この記事をご覧の先生は日々の指導において、生徒との「関係づくり」をどのように位置づけていますか?
私が多くの友人や後輩を見てきた中で断言できるのは、生徒の成長と「信頼できる先生」の存在は、ほぼ常にセットであるということです。
先生との間に信頼関係があると、生徒は安心して質問し、前向きに課題に取り組むことができます。これは、指導の効果を何倍にも高めるための最も重要な土台と言えるでしょう。
この記事では、私が実際に生徒として体験し、大学生の視点で分析した「生徒が心をひらく関係づくりの原則」を、具体的な実践例と共に解説していきます。
原則1:生徒を「大勢の中の一人」ではなく「個」として扱う
まず徹底すべきは、生徒一人ひとりを独立した「個」として認識し、承認することです。これが全ての土台となります。
具体的なアクション
- 必ず名前を呼んであいさつする、質問する。
- テストの点数だけでなく、ノートのきれいさ、授業中の発言、準備の丁寧さといった「行動のプロセス」に気づき、具体的に褒める。
なぜこれが重要か?
生徒は「先生は、集団ではなく自分個人を見てくれている」と感じることで、強い自己肯定感と先生への親近感を抱きます。この「承認されている」という感覚が、信頼関係の第一歩です。
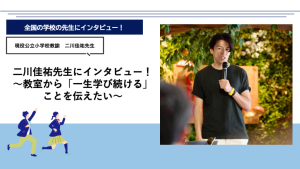

原則2:対話の主導権を「生徒」に渡す
信頼関係を築く段階では、先生が「教える」モードに入るのは得策ではありません。重要なのは、生徒が安心して本音を話せる聞き役に徹することです。
具体的なアクション
- 生徒が話している時は、結論やアドバイスを急がない。「うんうん」「それで?」と相づちを打ち、話を促すことに集中します。
- 生徒が使った言葉をそのまま返す(例:「〇〇が嫌だったんだね」)。これは「あなたの話を正確に理解していますよ」という強力なメッセージになります。
なぜこれが重要か?
生徒にとって「自分の話を評価されずに聞いてもらえた」という経験は、「この先生は安全な存在だ」と認識する上で非常に重要です。この安心感がなければ、生徒が本音を話すことはありません。
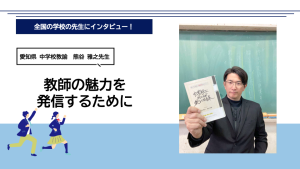

原則3:「公平性」を絶対的なルールとして貫く
生徒は、先生の「えこひいき」や「感情のムラ」を驚くほど敏感に察知します。
具体的なアクション
- 成績や性格によって、声かけの頻度や態度を変えない。
- 叱る時も褒める時も、一貫した基準で行う。感情ではなく、ルールに基づいて接する姿勢を見せる。
なぜこれが重要なのか?
「このクラスは、先生の気分ではなく、公平なルールで運営されている」という認識が、生徒の心理的安全性を確保します。先生個人への信頼は、このクラス全体への安心感の上に成り立っています。
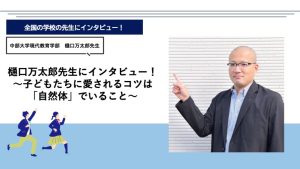
【要注意】信頼を一瞬で壊す2つのNG行動
どれだけ時間をかけて信頼を築いても、以下の行動はそれを一瞬で破壊しかねません。絶対に避けましょう。
NG行動①:人格の否定・他者との比較
「だからお前はだめなんだ」「〇〇を見習え」といった言葉は、生徒の存在そのものを否定する最悪のコミュニケーションです。
「変えられないその子自身」ではなく「変えられる行動」に焦点を当てるといいでしょう。
例えば、
- 「なんで提出物を出さないんだ!だらしないな」→「提出物が出ていないね。何か困っていることがあるなら相談に乗るよ」
- 「〇〇くんはできているのに、なんで君はできないんだ」→「前回の小テストより、ケアレスミスが減ったね。君自身の成長がすばらしいよ」
NG行動②:感情的な叱責
論理的な指導ではなく、先生の怒りをぶつけるだけの叱責は、生徒に恐怖しか与えません。恐怖は信頼の対極にある感情です。
一度冷静になり、「事実」と「なぜその行動が問題なのか」を論理的に伝えることを意識しましょう。
例えば、
- 「うるさい!静かにしろ!」→「話が盛り上がっているのは分かるけれど、今は授業に集中する時間だ。周りの人が聞き取れないから、私語は休み時間にしよう」
- 「いい加減にしろ!」→「君がそういう行動をすると、先生は悲しい気持ちになる。クラスのみんなも残念に思うんじゃないかな」
まとめ
ここまで、生徒との関係づくりのための3つの原則を解説してきました。
- 原則1:生徒を「個」として扱う
- 原則2:対話の主導権を「生徒」に渡す
- 原則3:「公平性」を絶対的なルールとして貫く
これらは、特別な才能ではなく、意識すれば誰でも実践できる「技術」です。
そして、この「信頼」という土台があって初めて、日々の指導や教育活動が意味を持ち始めます。ぜひ、明日からのコミュニケーションで、一つでも実践してみてください。ご覧いただきありがとうございました。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。