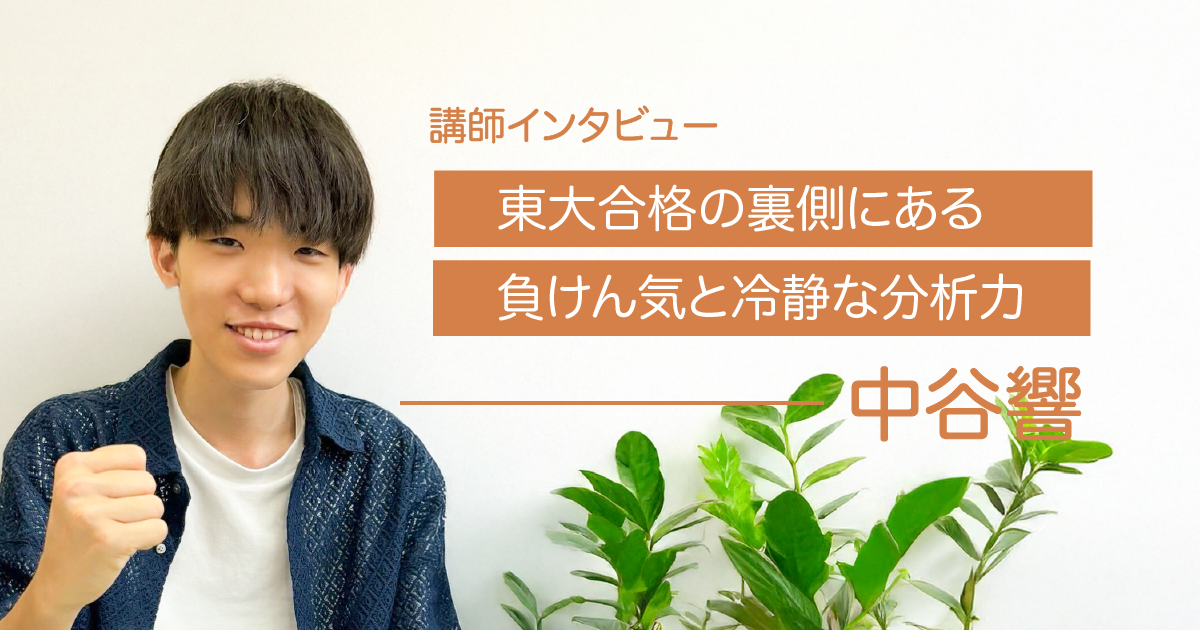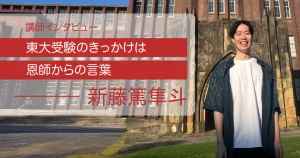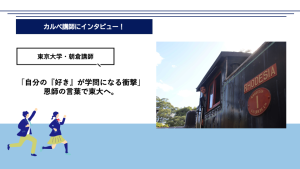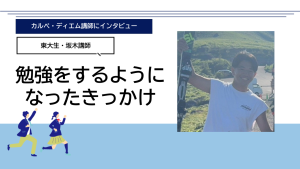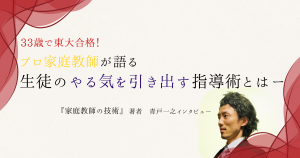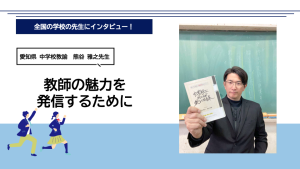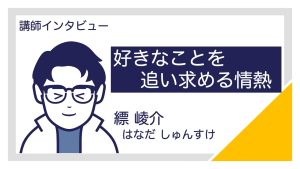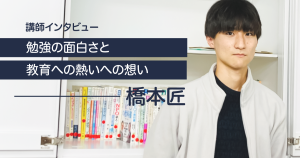負けず嫌いな性格を武器に、冷静な分析力で戦略的に勉強を進めた3年間。努力を積み重ねて東大法学部に合格した中谷響さんに、志望動機から勉強法、そして受験を通して得た学びまで、じっくりとお話を伺いました!
社会をより良くする手段としての東大受験
ーどうして東大を目指そうと思ったのですか?
実は高校に入学した当初から、漠然と東大や京大のような難関大学に行きたいと考えていて。中学から勉強を頑張っていたので、努力が報われる方向に進みたかったのかもしれません。また、母校から毎年10名前後は東大合格者が出ていたことも後押しになりました。
ーでは、なぜ数学が得意な中谷さんが文系に進むことになったのでしょうか?一般的に数学が得意な人は理系を選択しがちですよね。
確かに最初は理系志望でした。生活の中でなんとなく「よりよい社会を目指したい」と感じており、エネルギーや環境に関する研究をしようと考えていました。でも、物理や科学の研究を突き詰めるイメージは湧かなくて…ある日、高校の先生から「社会をより良くするには、研究以外にも政治家や官僚、起業する道もある」とアドバイスをもらい、しっくりきたんです。そこで法学部への思いが強くなり、将来政治家や官僚を目指すならば東大法学部(文科一類)が最適な進路だろうと考えるようになりました。
双子の弟とのライバル関係が原動力に
ー何が勉強のモチベーションでしたか?
双子の弟の存在は大きかったですね。中学の頃は弟が一番身近な良きライバルでした。自分よりも成績が良かった弟に劣等感を抱くこともありましたが、そこから負けず嫌いな性格が形成されたと感じています。
高校では模試を受けるようになって競争相手が全国に広がり、ライバル達に勝ってやる!と「負けず嫌いな自分」を燃やしていました。
周りと差をつけることを意識
ーいつから勉強し始めましたか?
本腰を入れたのは高3ですが、高1から継続的に勉強していました。入学当時は学年300人中50位と東大レベルには届かない成績でしたが、おかげで「トップ10入り」が目標に。それ以降、山岳部で週2回登山をしつつ、平日は3.5〜4時間、休日は8時間と受験生ほどではありませんが、コンスタントに勉強し続けました。そうして高1秋には学年1位をとり、中堅国公立入試レベルまで解けるようになりました。
ー目標を大きく上回る成果が得られたんですね!そのような成果を出すために、どのような勉強法を実践しましたか?
「周りがやっていないことをやる」ことが最大のポイントです。
例えば、母校の古文・漢文の授業では、文章を読みながら、出てきた語彙(ごい)や文法事項を学んでいく形式だったんです。高1の時点では武器が少ない状態で古文・漢文を読み解かなくてはならないので、読み解ける部分も少なく、どうしても理解度が低い状態に留まってしまう。もったいないですよね。せっかく勉強するならば、武器をしっかりと持った上で演習したいと思ったんです。ですから、高1から古文・漢文の基礎知識の先取り学習をしていました。
また、英語については、市販のテキストだけでなく、学校や塾で読んだ英文を元に、間違えやすい単語・熟語集を自作し、授業の合間などのスキマ時間に繰り返し復習しました。
ーむやみに先取りをするのではなく、学校の授業やスキマ時間も活用しつつ先取りをしていく戦略ですね。他にはどのような工夫があったのでしょうか。
エビングハウスの忘却曲線(人が学習した内容をどれだけ早く忘れてしまうかをグラフで示したもの)を活用しました。これを知ったのは中学の頃でしたが、当時は授業で扱った内容について、教科書の該当ページに習った日付を書いた付箋を貼り、その日付を参考に1日後、1週間後、1か月後に復習する勉強法を全科目で試していました。高校に入ってからはもう少し効率化して、英単語暗記など有効と思われる教科にのみ適用する方針をとっていました。
ー勉強内容に合わせて勉強方法を設定したこと、そしてたくさんの勉強法を試し続けたことが、成績アップのカギだったんですね。
戦略的かつ柔軟な受験生活
ー受験を意識した勉強はどのくらいの時期から始めましたか?
東大受験を意識したのは、高2の夏前でした。先生から「過去でも参考書でもいいから、まずはアクションを起こそう」と言われたことをきっかけに、受験までの時間を逆算しました。特に高2の東大模試以降、受かるためにはどの程度の点数が求められるのかを考え、「いつの模試で何点とる」など目標を細かく立てました。
ー目標点数を取るために、具体的にどのような工夫をしましたか?
まず、東大の点数配分を分析しました。
例えば、歴史や地理などの社会科目は国数英と比べて、1科目あたりの配点が少ないんです。また、国語は採点基準が曖昧で、得点が安定しづらい。これらの科目は高得点が狙いにくいため、苦手で配点割合も高い英語をひたすら勉強しました。特定教科が天才的にできるならともかく、基本は全教科で一定のクオリティを保つことが合格への近道だと考えています。
ー合格点数の奪取を念頭に計画を立てられたんですね。他にはどんな工夫を?
模試でやりがちなミスやテストの時間配分などを、いつも見る英単語・熟語集のノートにメモして見直していました。何度も目にする場所に書くことで、テストの緊張の中でも、ミスしづらくなるんです。
ー常に本番を意識して模試に望んでいたことがよく伝わります。模試をフル活用していますね。
毎回のテストから、新しい数学の解法や間違えやすい英単語、得点計画など、何かしら得るものがあるように意識していました。
また、模試では70%強の確率で目標達成しましたが、うまくいかなかった際には、なぜ自分が失敗したのか、記憶が新鮮なうちに振り返り、原因と改善方法を考えて実行していました。
ー分析力と計画性が高いですね。ここまで聞くと、かなり自分に厳しくキツい受験生活だったように思えますが、実際どうだったのでしょうか。
確かに受験生ですから、高2までよりは苦労しましたが、しっかりリラックスすることも重要視していました。例えば、英単語は夜に覚えると良いと言われていますが、夜だけは少しスマホをいじったり、漫画を読んだりしてゆっくりしたいので、単語帳なんて開きたくなくて(笑)だからこそ、スキマ時間を勉強にあてていましたね。
他にも、勉強のタイムスケジュールは作らず、各タスクにかかる時間のみを書いていました。スケジュール通りに行かないと落ち込んでしまうからです。
失敗を恐れず、試行錯誤し続ける
ー中谷さんは現在、学校で講義をしたり、講義内容を考えたりしていると思うのですが、そうしたカルぺ・ディエムでの活動を通して、特に伝えたいことはどのようなものなのでしょうか?
失敗を恐れずに挑戦し、試行錯誤してほしいですね。勉強法一つとっても、まずは試さないと自分に合っているか判断できません。「自分には無理だ」「面倒そうだ」と思わず、新しい視点や方法を取り入れる柔軟さを持つことが重要です。かく言う僕も、かつては失敗を恐れていましたが、挑戦と試行錯誤を繰り返すうちに気にならなくなりました。失敗は誰にでもあるし、完璧でなくてもいい。失敗の原因を問い続け、次にいかすために計画を考え続けることが大事なんです。つたない私の話からでも、ぜひ失敗を恐れず踏み出す勇気を持ってもらえればと考えています。
ー最後に全国の生徒さんに伝えたいメッセージをどうぞ!
現時点では志望校なんて決まっていないかもしれません。ですが、どこに行くとしても、計画と試行錯誤が成功への近道。動くタイミングは今しかありません。今動き始めることこそが、最も効率的な勉強法です!
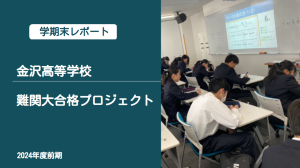
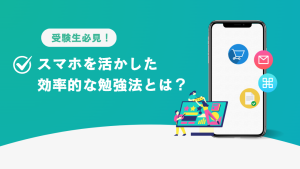
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。