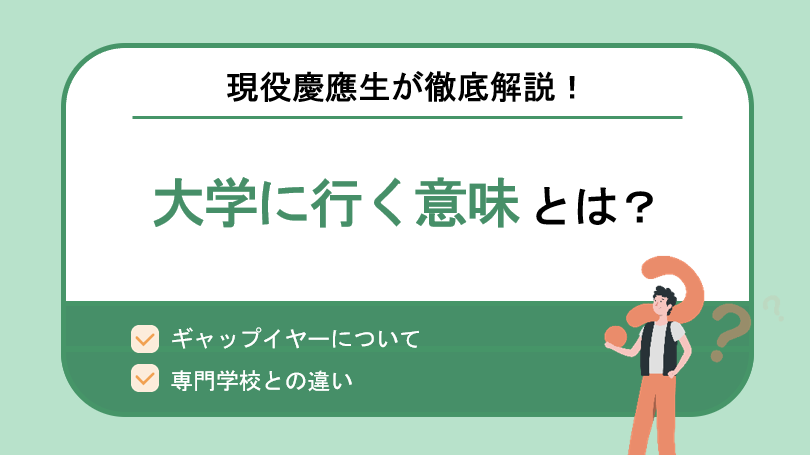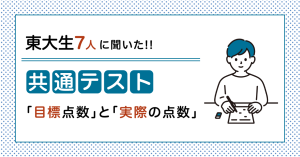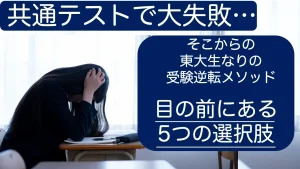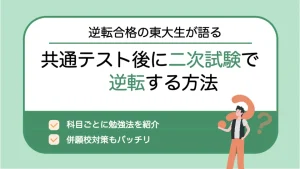大学ってなんのために行くの?東大生らに聞いてみた!
大学に進学する理由は一つではありません。学問を深める場としての機能に加え、社会に出る前の準備期間としての役割もあります。東大生へのヒアリングでは、「将来の選択肢を広げるための猶予期間」「同じ志をもつ学生と勉強する環境の獲得」「人とのネットワーク形成」といった回答が目立ちました。
ちなみに、「周りが行くから行くだけで、大卒としてのブランド付与以外思い当たらない」といった指摘も多く、学生自身も明確な意識をもたずに進学しているのが現状といえます。
大学生だからできることの経験
部活・サークルについて
大学の部活動やサークルは、学問以外の活動を通じて人間関係を築く機会です。異なる学部や学年、時には他大学の学生との交流が日常的に生まれる点が特徴です。こうした活動は、協働力やリーダーシップといった社会で必要とされるスキルを実地で養う場として機能することが多いです。
個人的には、さまざまな人と交流し、自分と波長の合う人が段々と理解できることで、自分の根本的な価値観が浮き彫りになり、主体的に行動する習慣が身につく点が気に入っています。
アルバイト・インターンについて
大学生活の中で多くの学生が取り組むアルバイトやインターンは、社会との接点を持つ経験です。労働の現場で責任を伴う役割を担うことにより、学業だけでは得られない実務感覚が養われます。
また、インターンは就職活動に直結するケースもあり、キャリア形成の早い段階で企業文化や職業観を理解する機会となります。実際の社会人とは異なり責任が軽い分、給料も低いものが多いため、単にお金を稼ぐためというよりも、さまざまな職種の実務経験を積める点が学生バイトの利点だと思います。
大学に行くことが将来に与える影響〜大学に行くと得をする?〜
大学進学による年収の違い
厚生労働省や国税庁の統計によれば、大卒者と高卒者の平均年収には長期的に差が存在します。男女差や業種差を考慮しても、大学卒業者は生涯賃金の面で有利である傾向が見られます。この格差は初任給よりもむしろ中堅以降の昇進や役職手当の段階で顕著になると言われています。
専門学校と大学のメリットの違い
専門学校は職業に直結するスキルを早期に習得できる点が強みであり、就職までの時間が短縮されるという利点があります。一方、大学は幅広い分野を横断的に学べること、また研究活動を通じて新たな知識を創出する機会が得られることが特徴です。
どちらが適しているかは、早期の職業定着を重視するか、将来的なキャリアの幅を重視するかによって異なります。
高校生へのアドバイス
進路選択を考えるためのステップ
進路を考える際には、まず自分が興味を持つ分野や得意科目を整理することが出発点です。その上で、将来的にどのような働き方を望むかを具体的に描き、必要な学歴やスキルを逆算していく方法が有効です。
しかし、実際には「周りと同じような大学へ行き、周りと同じ時期に就活を始めればいいや」となってしまうのが自然だと思います。自分は高校の友達とまだ遊びたかったので首都圏で大学を選びましたが、進路が決まっていない大学の友達とも巡り合えたことで、一緒に進路を考える仲間が増えたのは悪くない選択だったのかもしれません。
オープンキャンパスや大学訪問の活用法
進学先を判断するには、資料やウェブサイトだけでなく、実際に大学を訪問して雰囲気を確認することが有効です。授業内容だけでなく、キャンパスの環境や学生生活に関する情報も得られるため、進路選択の具体性が増します。
個人的には、平日に大学に行くことをおすすめします。食堂や教室を散策してみて、実際の大学生がどのように授業を受け、空いた時間を過ごしているのかを観察することで、将来の自分の姿を想像しやすくなります。それが受験勉強のインターバルとして、ちょうど良いリフレッシュにもなるのではないでしょうか。
関連記事はこちらから
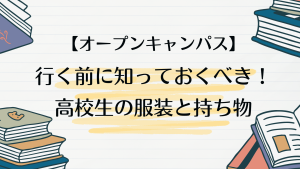
ギャップイヤーについて
進学前に一定期間学業を離れて活動する「ギャップイヤー」は、海外では広く普及している制度です。日本においても導入事例は増えつつあり、留学やボランティアを通じて視野を広げる手段として注目されています。
進学のタイミングを意図的にずらすことが、結果的に学びの動機付けを強化する場合もあります。自分の周りにも、休学してインターンに専念したり、世界一周の旅に出たりと、一年間を自由に過ごす人は想像以上に多く、年々休学するハードルは低くなっているように感じます。
しかし、多くの人は同時期に就活に励むため、単に遊ぶためだけに一年を使ってしまうと、それこそ周囲とのギャップに苦しむことになるかもしれません。大学でのさまざまな交流を通して自分を見つめる意識は、たとえ休学しない場合でも、念頭に置いておくとよいでしょう。
関連記事はこちら

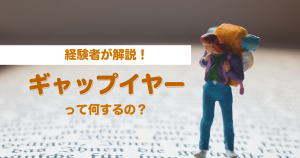
まとめ
大学に進学する意味は、学問を深めるだけでなく、社会に出る前に多様な経験を積む猶予を得ることにもあります。統計的に見ても、大学進学は経済的メリットをもたらす傾向がありますが、必ずしも全員に同じ効果があるわけではありません。進路の選択は、本人の価値観や目的によって異なります。
重要なのは、ある程度の自由が保証される大学生活において、さまざまな活動を通じて自分の成長につなげることなのではないでしょうか。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。