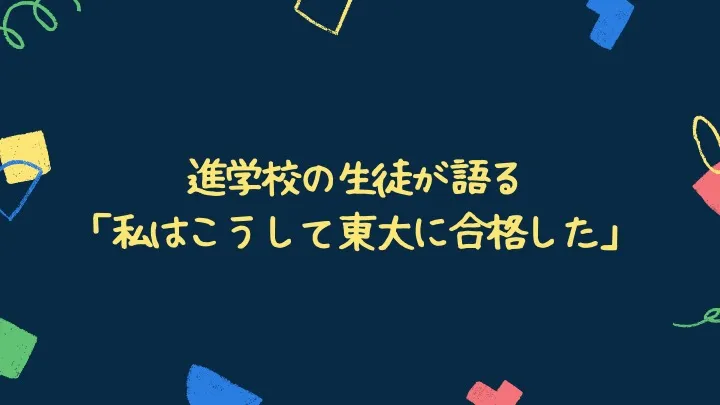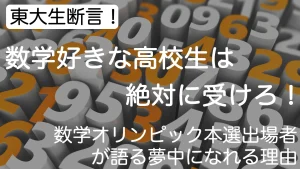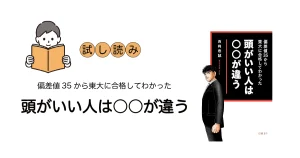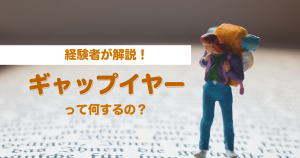東大生といえばみんな必死になって受験勉強を行い、合格を掴み取ったというイメージがありますが、実際はそうではない学生も多々います。
本記事ではそうではない側の受験生生活を送った現役東大生Aさんに合格体験記を語っていただきました。
本記事を読むと、いわゆる超進学校などに所属する学生が何を考え、どのように高校生活を過ごしていたのか、その一端がわかります。
はじめに
まず初めに断っておくのですが、私の東大合格に関する話は、今まさに受験を控えている受験生にとって、あまり聞き心地のよいものではないかもしれません。
それでも、東大や京大、医学部などの難関大を目指す学生の中には、こういう風な学生がいるということを知っておいてもらえたら、少しは参考になるのではないかと思い、私の経験をお話しします。
私は関西地方に生まれ、地元のごく普通の公立小中学校で学生生活を送りました。中学1年生まで続けていた公文のおかげで、数・国・英の三科目についてはかなり先取りが進んでおり、常に学年首位の成績でした。
中学3年生になってから、地元の塾に入って高校受験の準備を始めたのですが、そこでもすでに通っていた生徒たちを抑えて1位の成績を取りました。そして、地元で最難関とされる県立高校の特別進学クラスに、ほとんど苦労なく合格しました。
この時点でも数学は得意科目でした。中3の定期テストの数学では常に満点を取っており、正直言えば「やればできるもの」としか思っていませんでした。好きかどうかも意識しておらず、ただ淡々と解けるから解いているという感覚でした。
数学オリンピックに熱中した高校生活
転機が訪れたのは、高校に入ってからです。進学した特進クラスには、自分と同等か、あるいはそれ以上に数学ができると感じる同級生がいて、強烈な刺激を受けました。また最初の定期テストで初めて総合順位が2位であったこともとても悔しさを感じました。この経験が、自分の中でのスイッチを入れるきっかけになりました。
そこからは猛烈に勉強しました。その成果もあって、それ以降の卒業までの定期テストでは常に学年1位をキープし続けました。そんなある日、数学の先生に勧められて、その2人の同級生と一緒に数学オリンピックにチャレンジすることになりました。私は昔からケアレスミスが多い人間で、その時もケアレスミスにより、私だけが予選を突破できず、非常に悔しい思いをしました。
当時はTwitterで、灘や開成といった中高一貫校の同世代の学生がとっくに高校範囲の数学の勉強は終わらせて、日々大学数学を勉強していたり、科学系オリンピックの成果を投稿していたりするのを見て、自分はまだまだだと、かなり焦りと劣等感を感じていました。彼らのように早くから数学に触れ、先取りしている環境に憧れ、自分も負けていられないと思い、高2に入ってからは大学数学の勉強を本格的に開始しました。
その成果もあり、数学オリンピック協会が主催する夏合宿に参加することができ、大きな刺激を受けました。それまでは進路についてはあまり考えていなかったのですが、そこで初めて、東京大学や京都大学の数学科に進学しようと思うようになりました。
高2の夏以降は、暇さえあれば、すべて受験勉強ではない数学の勉強をしていました。特に大学数学や数学オリンピックの問題に熱中していたので、高校のカリキュラムに対しては自然と余裕が生まれていました。高2の数学オリンピックでは予選を突破し本選にも進出しました。確かな手応えを感じていたのですが、代表には届かず、それもまた悔しい結果でした。
しかし、そのように進んだ範囲の勉強や難しい問題を多く解いていたおかげで大学入試の問題は簡単に感じられ、東大の同日模試では合格点を上回る点数を取ることが出来ました。そのこともあって、自分にとって東大受験はやりがいのある受験ではなく、ただの通過点となってしまいました。
そのため高校3年になってからも、他の受験生のようにいわゆる「受験勉強」をおこなった思い出は一つもなく、大学数学を勉強したり、遊んだりしていました。そんな様子を見ていた両親は「落ちればいいのに」とまで内心思っていたらしいですが、しかしそんな両親の親心も虚しく、結果的には何の問題もなく、現役で点数も含めて余裕で合格しました。
他の東大生はよく自分の受験年度の問題について覚えていたりしますが、私は一切覚えていません。それだけ必死になって受験していなかった、ということでもあります。
数学オリンピックの日本代表になるような学生たちならばもっとこのような経験があるでしょう。
まとめ
この合格体験記を通して言えるのは、東大合格者すべてが死に物狂いで頑張ったわけではないということです。Aさんのように、ただの通過点でしかないタイプもいれば、努力の末にたどり着いた人もいます。Aさんは数学オリンピックなどで優れた人を多く見てきたので、彼らに追いつこうと頑張った経験はありますが、Aさん以上に努力をしないまま合格してしまうような人も実際にいます。
だからといって、真っ向から彼らに勝負を挑む必要はありません。
自分の得意を見つけて、そのフィールドで戦えばよいのです。そのフィールドが見つかるのが大学に入ってからでも決して遅くはありません。
大学は、自分の得意を見つけるための最高の場です。合格した後こそが本当の勝負だと思って、自分の武器を見つける努力をしてみてください。そうすれば、ただ「通過点」として大学に入るのではなく、その後の人生を切り拓く確かな力が養われるはずです。
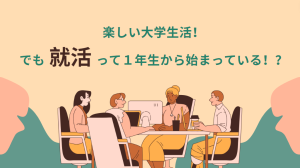
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。