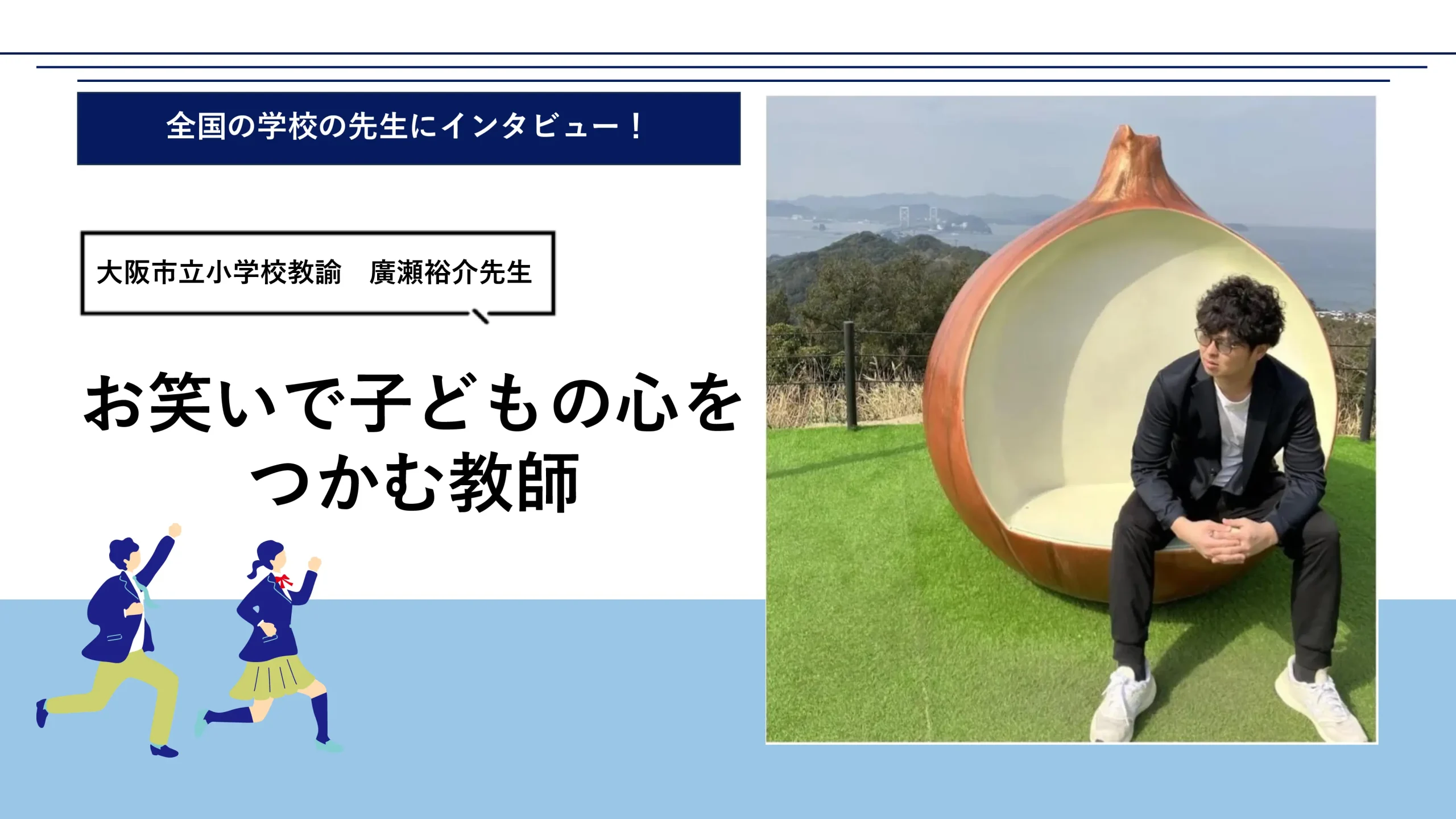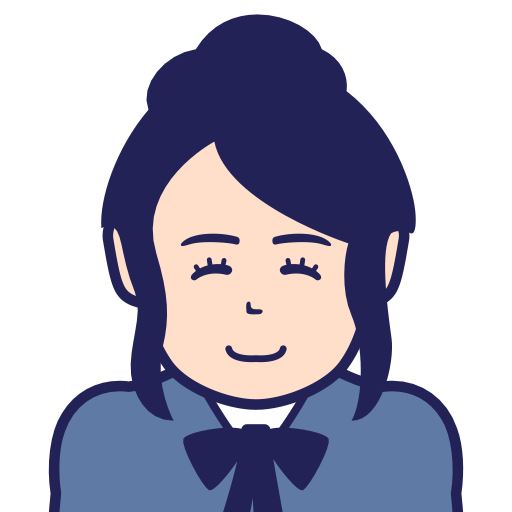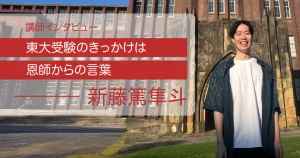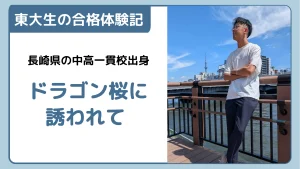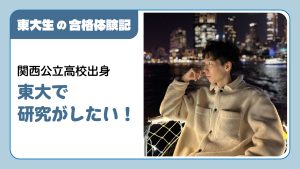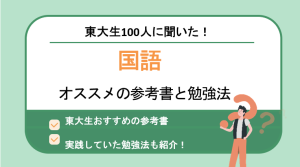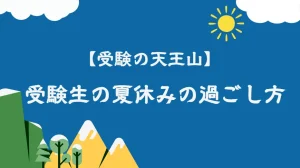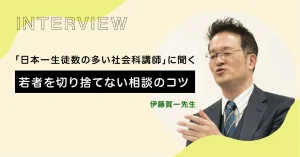今大活躍中の先生方に大学生がインタビューする企画である「先生100人インタビュー」。
お仕事の内容や学校外での活動など、ここでしか聞けない内容を盛りだくさんでお届けします。
今回は、大阪市立小学校で教員をされている廣瀬裕介(ひろせ・ゆうすけ)先生にインタビューをさせていただきました。「笑う子どもの数が減っている」。ある記事との出会いが、廣瀬先生の教育実践の原点となりました。高校時代からお笑いに親しみ、15年近い経験を持つ廣瀬先生による、笑いを取り入れた独自の教育スタイルをお伺いしました。

廣瀬裕介(ひろせ・ゆうすけ)先生
大阪市立小学校教諭
大阪市立小学校教諭
『子どもも僕もオイシク』がモットーで、子どもたちを笑わせることに全力を注いでいる。M-1やR-1など、お笑いの大会にも多数出場し、日々「笑い」について考えている。漫才コンビでの担当は「ボケ」専門は「道徳」。『GP先生』というアカウントで発信しており、Instagramのフォロワーは1.8万人をこえる。教師力向上サークル「crank」代表。
著書に『教室エンタメ 毎日をちょっと楽しくするミニレク&ネタ120(2022, 明治図書出版)』『子どもも先生もオイシイ 笑いの技術(2022, フォーラムA企画)』などがあり、いずれもAmazonランキング「学級運営部門」でベストセラーを獲得している。
お笑い×授業にたどり着いたきっかけ
――お笑いと授業をかけあわせた授業をはじめられたきっかけはなんですか。
昔ある記事を読んで、そこには「笑う子どもの数が減っている」と書いてあったんです。
自分は子どもの頃、学校が大好きで『土日がいらない』と思えるくらいでした。自分が生まれ育った大阪市で恩返しがしたい。そして、たくさんの子どもたちに『学校って楽しい』と思ってもらいたい。そんな思いから教師を目指しました。なのでお笑いを少しでも授業の中に取り入れて子どもたちの笑いを引き出したいと思いました。
――著書を拝読いたしまして、こんな関わり方があるのだと驚きました。授業での工夫を具体的に教えていただけますか。
授業では、ゴールイメージを大切にしています。笑いをまぶしているのは、ただ笑わせたいからではなく、子どもたちの理解を深めるための一助となることが目的です。
例えば、国語の説明文で『頭括型』『総括型』といった難しい用語を教えるとき、普通に教えてもなかなかイメージがつきづらいんです。「先生、めっちゃ腹が立つことがあって。この前冷蔵庫に入れて置いた大好きなプリンが…(中略)だからめっちゃ腹が立ったんだよ!」と言うと、自分の考えをはじめと終わりで伝えているからこれは『総括型』ですね、などと自分の経験を動きをつけ、ミニコントのように演じながら説明すると、子どもたちの記憶に残りやすいんです。(先生がこの前、めっちゃ腹が立つ話してたな…ああプリンを食べられた話だったな。)というミニコントがトリガーとなって、言葉を引き出すこともあります。
また、間違いへの対応も工夫しています。例えば、算数で5×5=30と答えた子がいたとき。直球で間違いを指摘すると児童は悲しい思いをする子も多いと思います。そして答えたい気持ちが下がってしまうと思うんです。そうではなく、『30は次の5×6の答えやな!未来から来たんか!』などツッコミを入れたり、咳をするふりをして正解を伝えたりすることもします。それは、一度クラスの視線を教師に向けさせるためです。そうすることで、間違えた子への注目を分散させ、改めて正解を導き出せる環境を作るんです。
こう言うと関西人だからやん、という指摘も受けますが、これらはあくまでも方法論にすぎません。お笑いに詳しくなくても、関西人ではなくても、すぐに授業内で実践できるのです。
キーワードは”隙”
――児童に馬鹿にされて話を聞いてくれなくなるなど、児童との距離感に悩んでいる先生方もたくさんいらっしゃいますが、児童との関わり方で心がけていることはございますか?
児童と心の距離を縮めるためには決して無理はしません。自分をつくろうとか、キャラを入れようと思うと長続きしません。「持続可能」ではなくなります。教師だって完ぺきではありませんし、失敗もたくさんします。私も、苦手な食べ物があったり、絵を描いたりすることもあまり得意ではありません。しかし、物は考えようです。教師のそういった一面こそ、人間味がつまっていると思うんです。
信頼される教師は「教師的魅力」と「人間的魅力」の両輪が同時に回っています。なので前に進みやすいんですよね。「教師的魅力」とは、授業がわかりやすいということです。「人間的魅力」はたくさんありますが私はその一つのキーワードが“隙”だと思っています。今現在、テレビなどでよく見る、売れている芸人さんはみんなどこか魅力的な“隙”をもっています。この“隙”があれば、そこに子どもたちの心がスッと入ってこられます。売っているお米の袋は、パンパンの状態で売られていますよね。少しお米を取ることでそこに“隙間(スペース)”ができます。この“隙”こそ、新しい考えや思いを取り入れられるスペースになっているんです。
また、普段の生活では場面に応じた切り替えを意識しています。毎年、担任する子どもたちからは「切り替えがすごい!」と言われていました。授業中は真面目に「廣瀬先生」として、休み時間は「廣瀬裕介」として接してメリハリをつけるんです。休み時間はみんなと同じ目線に立っていじられる、つまり負け顔も作るんです。私はパーマをかけていますが、私の似顔絵は描きやすいみたいで、子どもたちは似顔絵選手権もよく独自開催しています。「全然似てへんわー。もじゃもじゃしすぎやろ。」「パーマの中に小鳥が住んでるやないか!」などとツッコんでいます。“隙”って“好き”になる入口なのかもしれませんね。
誰もが主人公になれる探求学習
――探究学習での取り組みを教えてください。
以前勤務していた学校で、学年3クラスで毎月『M-1グランプリ』を開催しました。毎月コンビを組んでネタを作成してクラス内で予選をし、勝ち上がった組は体育館で決勝戦を行いました。
お笑いを通じて、21世紀型スキルを身につけてもらうのが大きなねらいでした。自分たちの課題を発見し、その解決策のために情報を収集する。それらを試していく中で、整理・分析し、自分たちの漫才をつくりあげていくという流れでした。その他にも授業をしていく中で、人前で話す恥ずかしさがなくなり、授業中の発言も活発になりました。課題を発見していきます。キャラを作った方が良いのか、オチの部分はもう少し伏線を回収した方が良いのかなどです。それらを違うコンビに見てもらい、コメントをもらうことで、解決策が見えてきます。しかし、その課題は解決したと思っていても、解決したことによって違う問いが生まれてきます。そうして同じテーマを掲げながらも毎回少しずつ高い視点に登っていく、スパイラル上に学習を進めました。
決勝では実際のお笑い芸人に講評をもらうなど、外部との連携も大切にしています。
漫才のネタ合わせをする中で自分たちのコンビの保護者の方からも「家のカーテンの前で一人で漫才の練習をしている姿を見て“あの恥ずかしがりの娘”が真剣に漫才を練習している!と思うと、新しい一面を引き出してくれているこの取り組みに感謝です」という言葉をいただき、嬉しかったのを覚えています。
――最後に、教育者としての信念を教えてください。
大きく2つあります。
1つ目は、私は「今、この瞬間」をとても大切にしていることです。未来を見据えて進むのもとても重要なことです。ですが、未来のことを考えたり、3月には、○年生が終わるころにはこんな力をつけておかないといけないと自分を追い込んだりしてはいけないと思います。自身の無さや不安、焦燥感はこの未来を意識しすぎた毎日から来るものです。それよりも、目の前の「今、この瞬間」を大切にすることで、鮮度も保たれ、むしろ未来への重要なステップとなっています。まだ来ていない未来のことを考えて不安になるより、今を大切にしていきたいという信念が私にはあります。だって子どもたちとの時間は全てが「生放送」なんですから。
2つ目は、人と比較せず『僕は僕』という考えを大切にしていることです。「僕はキムタクにはなれないけど、キムタクも僕にはなれない」ですよね。比較は人とするものではなく、昨日の自分や、昨年度の自分と比較するものです。(あの人はすごいな…自分は…)なんて思っていても幸せにはなれません。そして何より、人と比較しないことで、人を素直に応援できるようになります。他人の成功が自分と言う存在を脅かすものではないと感じているので、心から「あの人はすごいな。」という優しい気持ちで毎日を過ごすことができます。教師それぞれの個性を活かした教育を実践しながら、目の前の子どもたちの笑顔を引き出せる教師でありたいです。
ーー廣瀬先生、ありがとうございました!
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。