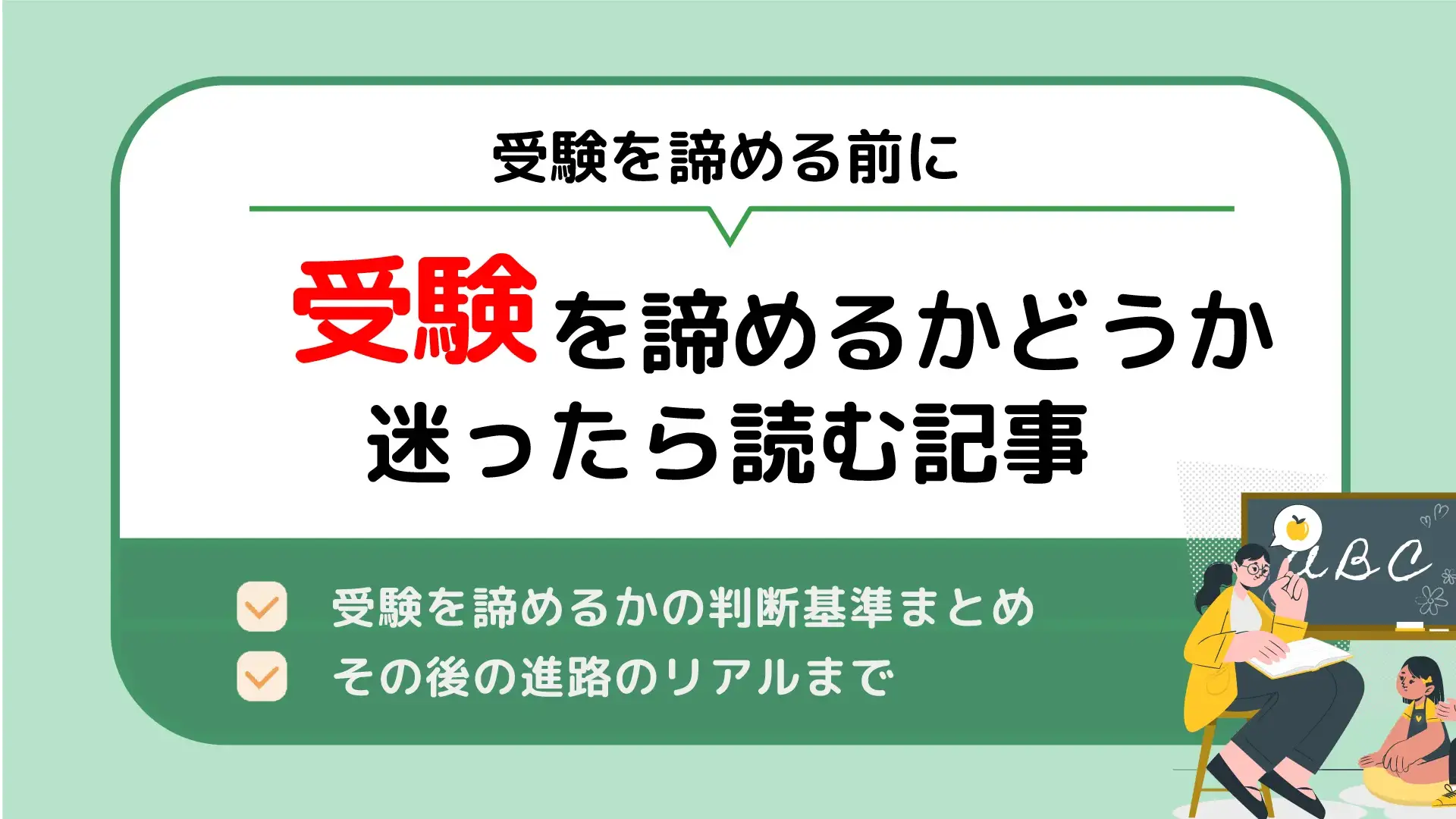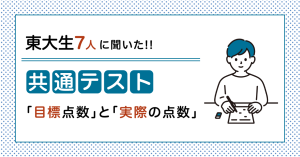前提として、私たちは教育の専門家ではありません。
「自身の経験や、友人の経験談からこういう傾向である」といった形で執筆していきます。
なぜ「受験を諦めたい」と感じてしまうのか?よくある原因
受験勉強に取り組む中で、どうしようもなく「諦めたい」という気持ちに襲われることは、決して珍しいことではありません。あなたが今感じているその苦しみは、多くの受験生が直面する共通の壁です。ここでは、その主な原因をいくつか見ていきましょう。
勉強しても成績が上がらない・E判定しか出ない
「毎日こんなに頑張っているのに、どうして?」
「模試のたびにE判定ばかり。自分には才能がないんじゃないか…」
勉強時間を増やせば増やすほど、模試の度に突きつけられる現実が辛くて、僕自身、現役3年次には模試の判定はすべてE、Dでした。食事が喉に通らない時期もありました。でも、一つ言えるのは、この壁にぶつかっているのはあなただけじゃないということ。つらい現実ほど、往々にして周囲には語られないもの。だからこそ孤独に感じやすいのですが、同じ悩みを抱える受験生は必ずいます。
周りの友達と比べてしまい焦る・劣等感を感じる
SNSを開けば「今日の模試でA判定!」なんて投稿が流れてくる。隣の席の友達がスラスラと問題を解いている。模試の会場で、「今回簡単だったよね?」と誰かが話している。そんな光景を見て焦った経験があるのではないでしょうか。でも、その人がどれだけ努力しているかは外からは見えませんし、SNSは成功だけが切り取られているもの。比較で落ち込むのは自然なことです。
親や先生からのプレッシャーが辛い
「期待しているからね」 「〇〇大学に合格すれば安泰だ」
親や先生が言ってくれる言葉は、きっとあなたのことを思っての「愛情」や「応援」の裏返しです。頭ではわかっていても、それがプレッシャーになり、勉強すればするほど重荷に感じてしまうことがあります。真面目に頑張る人ほど、その期待に応えなきゃと無理をしてしまいます。でも、抱え込みすぎると、いつか心がパンクしてしまいます。不合格になったらこの人達はどんな反応をするのだろうかと、ふと考えてしまうこと、優しい慰めと労いがどれだけ苦しいかなんて、本人しかわからないことかもしれません。
燃え尽きてしまい、やる気が出ない
朝、目が覚めてもベッドから起き上がれず、机に向かおうとしても、なぜか体が動かない。頑張りすぎて心が空っぽになってしまう「燃え尽き症候群」かもしれません。模試の判定が少し上がったことがわかった時、共通テストがうまくいった時、それまで縛りつけられた緊迫感から妙に解放されて、まだ合格までの道のりまでは遠いという倦怠感を忘れさせてくれる一時的な心地よい風に身をまかせているような、ある種、精神の防衛本能でしょう。
その決断、本当に今すべき?後悔しないための3つの判断基準
勉強は孤独な戦いです。しかし、あなたのその「諦めたい」という気持ちは、決して怠け心からくるものではありません。それは、あなたが真剣に、そして一生懸命に頑張ってきた証拠です。だからこそ、その苦しい気持ちに蓋をするのではなく、きちんと向き合ってあげてください。
その決断、本当に今すべきなのでしょうか?
後悔しないための3つの判断基準を一緒に見ていきましょう。
基準1:やるべきことは全てやり切ったか?
後悔の多くは「やり切らなかったこと」から生まれます。
自分に問いかけてみてください:苦手科目の基礎は固めきったか?過去問はしっかり分析したか?苦手分野の克服プランを試してみたか?
僕自身浪人して始めてわかったことですが、勉強が完成することはありえません。受験に受かる可能性が変動するだけです。ここで受験生活に終止符をうつのに相応な理由の基準は個人次第ですが、追い詰められた人は、諦めるために理由を探すような自分すら客観視できないことは、受験界隈ではよくある事例の一つだと思います。
基準2:感情的になっていないか?(まずは一度休息をとる)
模試の判定が悪かった直後や、友達の進展を見た瞬間に「もう無理だ」と思うのは当然です。しかしその感情に流されて大きな決断をするのは危険です。感情というものは現実の後付けで結果論的に生成されるものですから、 一度冷静になるために:1日だけ勉強から離れてリフレッシュする、しっかり睡眠をとる、軽い運動をして気分を変える、といったことがこれから勉強生活に復帰するためのある種のメンテナンスと捉えることで、うまくいったケースは自分が塾講師をしていてよく感じるところです。
基準3:信頼できる大人に相談したか?
一人で悩みを抱え込むのは本当に辛いことです。悩んでいる時は視野が狭くなりがちなので、客観的な意見を聞くことが大切です。信頼できる大人に相談することで、あなたには見えていなかった解決策や、新たな視点が見つかるかもしれません。相談相手は、親や先生だけでなく、塾のチューターや予備校の担任、高校を卒業した先輩、信頼できる親戚や知り合いなど、現代では相談だけなら公式SNSから無料でしてくれるところもあると思います。
【まだ諦めるのは早いケース】E判定・共テ失敗からの逆転プラン
まず、知っておいて欲しいことが、逆転合格は珍しいことだからこそ美談として語られることであり、夢を高くもつのは素晴らしいことですが、それには利子がつくのでそれ相応の覚悟を必要とするものなのです。
秋・直前期のE判定は「伸びしろ」の証
それでも、多くの合格者が語るのは「秋から一気に成績が伸びた」という話。E判定は「合格率0%」ではなく「まだ課題が残っている」というサインです。伸びしろがあると考えると、気持ちも少し楽になります。
共通テストリサーチを正しく活用する方法
共通テストリサーチの判定に一喜一憂しすぎるのは危険です。二次試験の配点や出願者の動向次第で結果は大きく変わります。二次力を活かせる大学を探すなど、データを活用した戦略的な出願を検討してみてください。
モチベーションを復活させる具体的な方法
精神論ではなく、すぐに行動に移せることが望ましいです。実際には、小さな目標設定、勉強場所の変更、大学のHPで楽しそうなサークルを見るなど。
より具体的な対処法はこちらの記事に書いていますのでご確認ください。
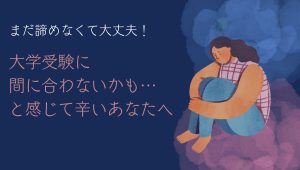
受験を諦めた後の進路は4つ。それぞれの現実とメリット・デメリット
選択肢1:志望校のランクを見直す(戦略的撤退)
ランクを下げることは「負け」ではなく、浪人リスクを避けて安定した大学生活を送るための戦略です。自分の適性に合った環境で輝ける道を探すのも賢明な選択肢です。大学を多めに受ける人ならば、各大学に合わせて勉強する時間の割合を見直すのも手だと思います。
選択肢2:浪人して来年もう一度挑戦する(費用・覚悟・成功率)
浪人は簡単な道ではありません。予備校費用は年間100万円前後、第一志望に合格できるのは2割程度、孤独感との戦いも避けられない、そのうえで覚悟を持てるかどうかが重要です。自分自身浪人しましたが、一番辛いのは高校の友達が誰一人浪人しなかったこと。一人で生活のスケジュール管理をできることは逆に、怠惰な生活に陥る第一歩ともとることができます。
選択肢3:専門学校で専門スキルを身につける(学校選び・就職先)
将来の仕事に直結するスキルを身につけたいなら専門学校も選択肢の一つ。オープンキャンパスに参加し、就職実績を確認することが失敗しない学校選びのポイントです。僕の友人曰く、学校次第で、生徒のその専門スキルを身に着ける本気な生徒数が違うらしいです。いわゆる総合大学よりも慎重な学校調査が求められます。
選択肢4:高卒で就職する(給与の現実・キャリアパス)
高卒で働き始めると、早くから社会経験を積めるメリットがあります。ただし、大卒と比べると生涯賃金に差が出やすいのも事実。とはいえ、公務員や地元の優良企業など、高卒でも安定したキャリアを築ける道もあります。
まとめ
「受験を諦める」という決断は逃げではありません。未来を見据え、自分にとって最も納得できる道を選ぶための一つの選択肢です。
大切なのは「後悔のない選択」をすること。そのために、まずは冷静に、そして一人で抱え込まずに考えてみてください。
よりさまざまな選択肢や勉強については下記のまとめ記事を作っているのでご確認ください。
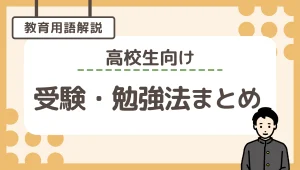
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。