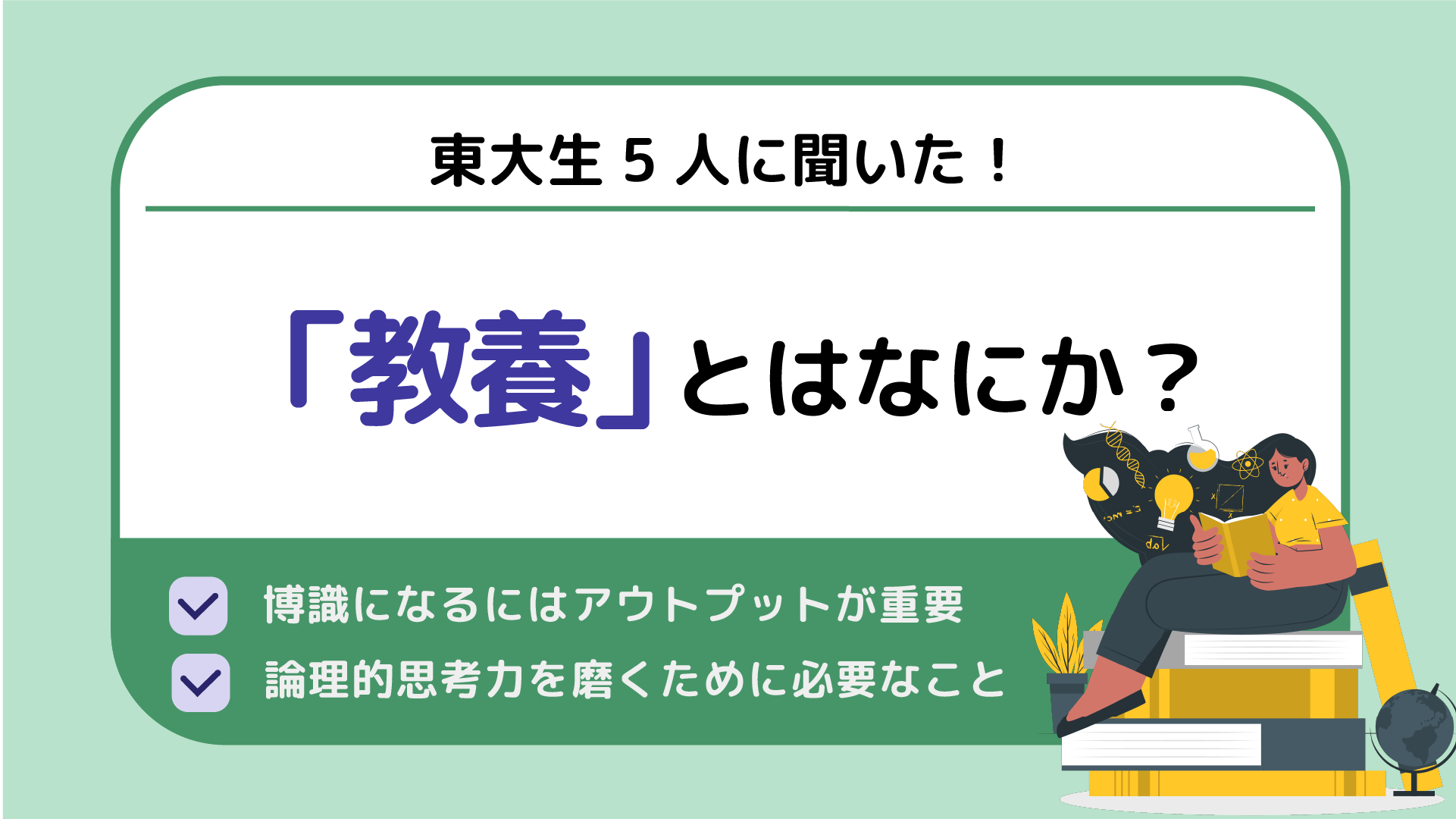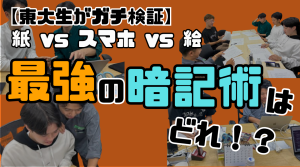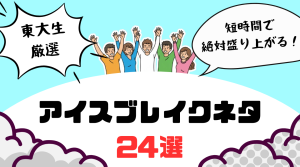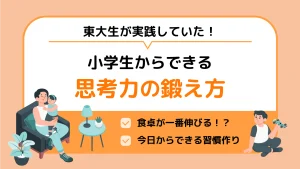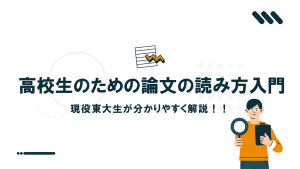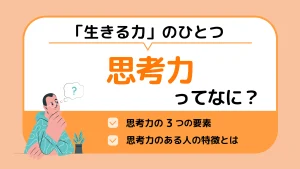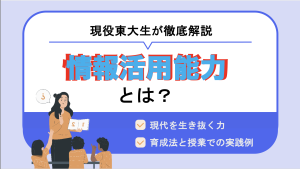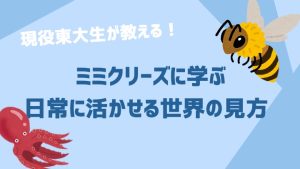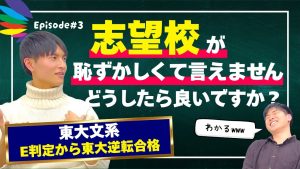教養とは何か、どうすれば教養を身につけられるのか。これらは、多くの人が一度は考えたことがある問いではないでしょうか。
教養教育の重要性が叫ばれるようになり、日本の教育もそれを元に変化してきました。例えば、東京大学では、入学者は全員前期教養学部に入って、幅広い分野の知識を身につけることが求められます。
今回は、そうしてリベラルアーツ教育を受けた東大生5人に「教養」とは何だと思うかをインタビューしてみました! そこから浮かび上がってきた「教養」の中身とは一体……?
この記事では、どうすれば「教養のある人」になれるのかも合わせて、東大教育学部生の碓氷明日香が徹底解説します!
そもそも「教養」という言葉の意味とは?
そもそも、教養という言葉の本来の意味は何なのでしょうか。まずは、この言葉がどのような使われ方をしているのか、簡単に説明していきます。
一般的に使われるときの意味
一般的に、「教養」という言葉が使われるとき、その意味は場面ごとに2種類に分けることができます。まず1つ目はいわゆる「一般教養」のこと。つまり、大学の専門課程に入る前までに学んだ内容全般を指して使っているパターンです。社会に出る前に身につけておくべき知識のことを指し示す言葉です。
そして、もう一つが「教養人」などの意味で使われるパターン。これは幅広い分野の知識を持っているため、それらを使いこなして洗練された会話や身のこなしができることを指していると考えられます。
今回、この記事で深掘りしていくのは、2つ目の方ですね。もちろん、大学の一般教養も後者の意味を兼ね備えているわけですが。
文部科学省の定義
では、文部科学省は「教養」という言葉をどのように定義しているのでしょうか。国として教養教育を掲げているため、明確な定義が存在します。文部科学省のホームページには、以下のように書かれていました。
教養とは、個人が社会と関わり、経験を積み、体系的な知識や知恵を獲得する過程で、人格全体の訓練を行い、蓄積される人間観、世界観、自然観などの価値観の総称であり、教養教育とは「知性と感性の融合を軸とした人格形成」。
出典:文部科学省「資料1 新しい時代における教養教育の在り方について(骨子案)」, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo1/gijiroku/attach/1420835.htm
すなわち、社会的な存在として、人間が生きていくために身につけるべき価値観、ということでしょうか。
東大生に聞いてみた! 「教養」とは何か?
ここから本題に入っていきましょう。今回は東大生5人に「教養とは何だと思いますか?」という質問をしてみました。その解答を一人ずつ載せていきます。
東大の前期教養学部で幅広い教養を学んだ東大生たちは、一体教養をどのようなものと位置付けているのでしょうか?
S.Aさん(教育学部4年)
仕事や専門に直結する知識だけでなく、人としての幅広い知識や考え方のことではないかと思います。物事をさまざまな角度から捉えて批判的に考える力や多様な価値観を理解して対話する力のイメージです。
N.Y(文科Ⅲ類2年)
自分の血肉になった知識だと思います。例えば、名作文学のあらすじや凄みを知っているだけではただ単に知識ですが、それを知って「ああ、○○と同じだな」「こういう時代背景があるからこうなんだな」というように、自分の経験や持ち前の知識とつながると深い知識になりますよね。それが教養であり、蓄積されるにはこのようなプロセスをとるのではないでしょうか。
ただ、「血肉になる」とか「深い」とかがそもそも曖昧なので、単なる知識と教養をはっきり区別できてはいませんが……。
O.T(後期教養学部3年)
ある空間に占める人の中で、希少価値の高い情報を持っている人間を教養が高いと言えると思います。
例えば、生物学の研究者のコミュニティーでいくら生物のことを知っていようとも、「教養が深い」という評価の仕方にはなりません。教養が深いと我々が他者を称賛するときはいつも、我々が通常知り得ない事柄や知識をある人間が知っているときではないでしょうか。
K.R(理学系研究科物理学専攻修士1年)
端的に表現するなら「知識を繋げられる人」でしょうか。
例えば、何か見たことない現象やもの、作品を見るとき、自分が知っている範囲の知識でそれらの意味を考えるのが上手な人のことを教養がある人、と言うような気がします。
もちろん知識量が多ければ多いほどいいのでしょうが、その使い方に焦点を当ててそう呼んでいるのだと思います。
S.T(法学部4年)
昔は貴族の階級の人々が独占していた社会的資本のような、絵画や音楽、演劇、舞踊などの芸術分野に造詣が深く、それに加えて、歴史、地理、物理、化学、生物などの幅広い分野の常識を持ち合わせているような人を教養がある(Civilizedされている)と言っていたのではないかと思います。
また、こうした勉強の科目以外にも、人と接する時のマナー、服の着こなし方、式典や催し物の時の立ち振る舞い、テーブルマナーなど多様な要素も、「教養」という言葉には含意されている気がします。

結局どんな人が「教養がある」と言えるのか?
実際に「教養人」「あの人は教養があるね」と言われる人はどのような特徴があるのでしょうか。その人は何をもって「教養がある」とされているのでしょうか。東大生へのインタビューを踏まえつつ、まとめていきます。
幅広い分野の知識を持っていて、使いこなせる
まず大前提として、教養があると言われて一番最初に思い浮かぶのは、「博識」ということでしょうか。自分の専門領域に限らず、幅広い分野の知識を持っている人に対して、教養があると言うのでしょう。
ですが、知識はただ持っているだけでは意味がありません。頭の中に膨大な知識が詰め込まれていたとしても、使うべき場面でそれをスッと出して来ることができなければ、その知識はただのガラクタに過ぎません。
つまり、「教養がある」と言われるのは、知識を持っていて、かつそれを使いこなせる人だと考えられます。幅広い分野の知識を組み合わせつつ、しかるべき時にそれを提示できる人。これが教養人の1つの特徴と言えるでしょう。
論理的かつ柔軟な思考ができる
また、何かしらの問題にぶつかった時、論理的で柔軟な思考で知識をつなぎあわせて解決に向かうことができる人も教養があると言えます。
特に、この変動が大きく先行きが不透明なVUCAの時代において、生き抜くための力、すなわち問題解決能力を持ち合わせている人が高く評価されることは間違いありません。
問題が起きた時、普通の人は焦ってしまって、解決策をすぐに思いつくことができないでしょう。そんななか、現状を冷静に分析して、持っている知識を使って解決策を探り、困難を突破できる人が、教養があると言えるのです。

説明や会話がうまい
難しいことがらを簡単に説明できる人、会話のタネを多く持っていて、TPOに合わせて話題を用意できる人。こういう人たちも、教養人と呼べるかもしれません。
知識を持っているだけだと、難しい言葉を並べて話してしまい、誰も理解できないということが起こり得ます。立場や状況を踏まえて、適切で的確な表現を選ぶことができるのは、やはり「知識を使いこなす」ことができる証拠でしょう。
文部科学省の定義にあるように、教養がある人はすなわち、人格が優れている人なのかもしれません。相手の立場に立ってものごとを考えることも大事なポイントになってきそうですね。
教養を身につけるために
ここまで、「教養」の正体について考えてきました。ただ知識を身につけるだけでは、教養人には届かないようです。では、一体何をすれば、教養を身につけることができるのでしょうか? 東大生から集めた教養の定義を踏まえて、考えていきます。
新しく得た知識を持っている知識と結びつける
大切なのは、「新しく得た知識をすでに持っている知識と結びつける」ことです。上述のように、ただ知識を持っているだけでは足りず、しかるべき時にその知識を使いこなして、困難に立ち向かい、活路を見出して行くのが教養人です。そのためには、貪欲に知識を吸収しつつ、それを知っていることと関連づけて、いつでも使えるように準備しておくことが必要になります。
授業で習ったこと、日常生活で見聞きしたこと、趣味や文化などで触れたものごとを、以前習ったことと関連づけてみましょう。例えば、ニュースで「再生可能エネルギーの導入拡大」と聞いたとき、地理の再生可能資源の分布や物理のエネルギー変換効率に関する知識と結びつければ、この先起こることを考えられます。また、小説やゲームに出てくる歴史的事件や人物を史実に照らし合わせて見ることも可能ですね。
このように、知識の橋渡しを頻繁に行うことで、単なる暗記が「教養」に変わり、理解した上で使いこなすことができるようになるのです。
「なぜ?」と常に問いかけ、原因を考えてみる
知識を得るためにも、そして思考力を養うためにも、日常生活のなかで何に対しても「なぜ?」と問いかける癖をつけましょう。
科学は問いに対する仮説を立てて、それを検証していく工程です。それを日常でもやってください。わからないこと、疑問に思ったことを素通りせず、すぐに調べて答えをもらうのでもなく、まずは自分で考えてみる。持っている知識を組み合わせて、最善の解答を出してみる。そのあと、正解を調べてみましょう。
この流れを繰り返せば、新しい知識を手に入れることと問題解決能力を身につけることを同時並行でできます。
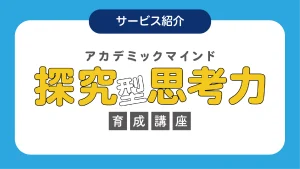
異なる視点から見る練習をする
1つのできごとを、複数の視点から見てみる癖をつけることも大切です。そうすれば、ものごとを多角的に考えられるようになり、他者の立場に立って考えることが得意になります。
この練習方法ですが、ディベートが有効です。ディベートとは、ある政策に対して肯定と否定の立場で分かれて、肯定側は政策導入のメリットを、否定側はデメリットを述べ、お互いに反論しつつ持論を守って、主張の強さを争う競技。実際にやらなくても、ディベートで使うようなメリットデメリットをさまざまな人の立場から考えてみると、多角的な視点が手に入るはずです。イメージが湧かない人は、動画投稿サイトに上がっているディベートの動画を見て勉強してみましょう。
多角的な視点が身につけば、知識の使い方も変わってくるはず。教養人に一歩近づけるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。「教養」という言葉はふわっとしていて、何を指しているかいまいち掴みづらいですが、幅広い分野の知識があり、それを使いこなす力を意味していることが、今回のインタビューから読み取れます。
教養を身につければ、困難にぶつかったとき、解決へと突き進むことができます。そして、社会のなかでさまざまな立場の人とつながりを保つことができるでしょう。人間は社会的な生き物ですから、人とのつながりが成功や幸福に届く鍵であることは間違いありません。
今日から、新しい知識を既存の知識と結びつける、常に問いかけて自分で原因を考える、異なる視点からものごとを見る、これら3つを実践してみましょう。それがあなたの教養を深めてくれるはずです。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。