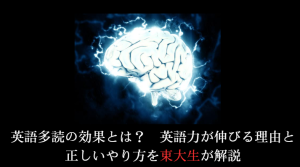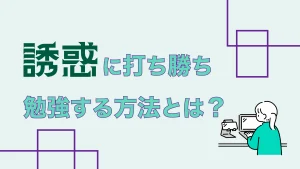AARサイクルという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
AARサイクルとは、「OECD Learning Compass 2030」にて提唱されたAnticipation(見通し)—Action(行動)—Reflection(振り返り)の3ステップを繰り返すことで、子どもたちに時代に適応する力を身につけてもらうという学習プロセスのことです。
今回は、このAARサイクルについて、それぞれのステップがどのような役割を担っていて、何を目的としているのか、実際に学校で取り入れるにはどうしたら良いかといった点に着目して、東大教育学部生の碓氷明日香が詳細に解説します!
AARサイクルとは?
まず、AARサイクルとはどのようなプロセスなのでしょうか。OECDがこのプロセスを提唱した背景と合わせて見ていきましょう。
AARサイクルが提唱された背景
OECDは、2015年からEducation2030プロジェクトを進めてきました。これは、これからの社会に子どもたちが適応できるようにするために、必要な力を身につけられる教育を世界全体で推進するための取り組みです。その成果として、2019年に発表されたのが「OECD Learning Compass 2030(OECDラーニングコンパス2030)」。
そしてその中で、変化の激しい時代を生きる子どもたちが状況に柔軟に適応し、自ら変革をもたらすことができるようになるための学習プロセスとして提示されているのが「AARサイクル」なのです。今後の社会を生き抜くために必要不可欠な力を培うための方法として提唱されています。
AARサイクルの3つのステージ
では、AARサイクルの中身を詳しく説明していきます。前述の通り、AARサイクルはAnticipation(見通し)—Action(行動)—Reflection(振り返り)の3つの段階から成り立っていて、それぞれがこれからの時代を生きる上で重要な力の獲得につながっています。
STEP1 Anticipation(見通し):過去の経験をもとに、自分のこれから起こす行動が周囲にどのような影響を及ぼし、どのような結果が得られるかを想像し、未来を先取りして体験するフェーズ。この「見通し」を適切に行うためには、自分の行動が他者からどのように見られるか、他者にどのような影響を与えるかという視点も必要になってきます。状況に応じてより最適な意思決定をするための練習になるわけです。
STEP2 Action(行動):見通しにもとづいてそれを実行に移すフェーズ。自主的に行動することで、それに伴う責任を学びます。どうしても「見通し」と次の「振り返り」に目が行きがちですが、そもそもこの「行動」フェーズがないと「見通し」が机上の空論になり、経験として蓄積されず、さらには「見通し」と実際の結果の違いを分析することもできないため、この「行動」の段階こそが他の二つの段階をつなげる重要な役割を担っているのです。
STEP3 Reflection(振り返り):事前の「見通し」と「行動」の結果を比較して科学的に分析、評価するフェーズ。なぜその結果になったのか、どのような要素が役立ってどのような要素が足りなかったか、多角的に振り返ることで、次の見通しに経験が活かせるようになります。ここまでの一連の流れを通して、自分の起こした行動を客観的に見ることができるようになるのです。
これらの3つのプロセスを繰り返しながら学習を進めていくことで、OECDのいう変化の激しい時代を生き抜く「コンピテンシー(能力)」が身につきます。
AARサイクルの目的
次に、AARサイクルの目的について説明していきます。OECDはどのようなゴールを見通してこの学習プロセスを提唱しているのでしょうか。
VUCAの時代を生き抜く力を身につける
この先の時代はよく「VUCA(ブーカ)」という言葉で表されます。これはVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を並べた言葉です。1、2年先すらも予測不可能な激動の時代、という意味で使われます。
このVUCAの時代を生きていくために子どもたちが身につける力について、OECDは次のように述べています。
“子どもたちは知識・技能だけでなく、倫理的かつ責任感のある行動に彼らを導く態度や価値観を身につけていかなくてはならない。同時に、彼らは輝かしい未来へ向かって人間性を身につけるために、創造的な工夫をする機会も必要である。”
“Students need support in developing not only knowledge and skills but also attitudes and values that can guide them towards ethical and responsible actions. At the same time, they need opportunities to develop their creative ingenuity to help propel humanity towards a bright future.”
【引用】Future of Education and Skills 2030/2040
つまり、知識や技能を身につけるだけでは足りず、自ら工夫してアクションを起こす姿勢をひとりひとりが意識して持たなくてはならない、ということですね。
また、OECDは次のようにも述べています。
“「ラーニングコンパス」というメタファーは、単に先生の言った固定された指示や方向を鵜呑みにするのではなく、未知の文脈の中を自分たち自身で進み、有意義かつ責任感のある方法で進むべき方向を見定めた上で学ぶということの必要性を子どもたちに強調するために用いられている。”
“The metaphor of a learning compass was adopted to emphasizes the need for students to learn to navigate by themselves through unfamiliar contexts, and find their direction in a meaningful and responsible way, instead of simply receiving fixed instructions or directions from their teachers.”
【引用】Future of Education and Skills 2030/2040
何がどうなるか予想がつきづらい世の中を生き抜くために、先生の指示を待つ人間になるのではなく、自ら選択し行動を起こしていくことが求められる、と書かれているわけです。
そして、これらの力を身につける上で重要な役割を担うのが「AARサイクル」です。子どもたちひとりひとりが自主的・意識的にAARサイクルに取り組むことで、未知の出来事にも対応できるようになっていくのです。
個人・集団のウェル・ビーイングを実現する
また、OECDはAARサイクルを繰り返して「コンピテンシー(能力)」を身につけた先の「個人・集団のウェル・ビーイング」を目指すとも述べています。ウェル・ビーイングとは心身ともに健康が満たされた状態を示す言葉で、短期的な幸せだけでなく、長期的な幸せも含むものです。
変動する社会の中で、それぞれが身体的・精神的・社会的に良い状態であるためには、常に思考をアップデートしていく必要があります。そのためのAARサイクルなのです。
PDCAサイクルとの違い
AARサイクルと似たようなプロセスに、PDCAサイクルというものがあります。ビジネスシーンで使われることが多いですが、学校現場でも使うこともあることでしょう。Plan(計画)—Do(実行)—Check(評価)—Act(改善)を繰り返すことで、プロジェクトを成功に導くサイクルのことを示しています。では、AARサイクルとPDCAサイクルにはどのような違いがあるのでしょうか。
大きな違いは、その目的にあります。PDCAサイクルは、組織の中で運営されるプロジェクトが円滑に進行できるように試行錯誤を繰り返す、というものである一方、AARサイクルは、前述の通り子どもたちがこれからの社会を生き抜く力を身につけるためのプロセスです。
とはいえ、OECDは次のようにも述べています。
“AARサイクルは包括的または排他的であるとは定義されない。むしろ、これは経験学習の理論を始めとした、他のさまざまな学習理論やサイクルを反映しているものです。”
“The AAR cycle is not defined to be comprehensive or exclusive; rather it reflects a range of other learning theories and cycles, such as theories of experiential learning.”
【引用】ANTICIPATION – ACTION – REFLECTION CYCLE FOR 2030
すなわち、AARサイクルはこれまで教育界で提唱されてきた他の理論をまとめたものであり、PDCAサイクルをも含んでいると考えられるのです。よって、この2つのサイクルの違いを無理に強調する必要もないでしょう。
実際の学校現場での活用
では、このAARサイクルを学校現場で実際に活用するとなったとき、どのように使えば良いのでしょうか。ここでは、日常と非日常という視点から、子どもたちにAARサイクルの習慣をつけてもらうための方法を挙げてみたいと思います。
普段の授業でのAARサイクル
まず、日常的にAARサイクルをどのように使うか、についてですが、この学習プロセスは普段の授業にそのまま取り入れることができます。
例えば、中学校の理科の授業において、授業開始時にその授業を通して考える課題を一つ提示します。「金属A、B、C、Dをそれぞれ何の金属か見分けるためにはどうしたら良いだろう?」「全く光が入ってこないところでは、ものは見えるだろうか」といった課題(問い)です。
そして、生徒ひとりひとりに答えを経験や知識を元に答えを予想してもらいます。その後でクラス内で予想とその根拠について話し合いを経て、予想を変えるなり、固めるなりします。この一連の流れがAnticipation(見通し)です。
実験の方法なども生徒たちに考えてもらい、その通りに班ごとに実験を行います。そしてそれぞれ結果を得るのです。この過程がAction(行動)です。
最後に、なぜその結果が導き出されたのか、より良い実験方法はあったのか、バイアスがかかっていないかなどを検討する考察を行います。これも、まずはひとりひとりに考えさせ、その後でクラス内で発表し合う時間を設けると良いでしょう。この過程がReflection(振り返り)に当たります。
このように、普段の授業でAARサイクルを取り入れることができます。もちろん、理科に限らず、どの科目でも似たような流れで授業をすることは可能でしょう。これを毎授業繰り返すことで、子どもたちはAARサイクルに慣れ、自然と普段の思考にこのサイクルを取り入れられるようになっていくのです。
学校行事など「非日常」でのAARサイクル
次に、非日常にどのようにAARサイクルを取り入れるか、についてですが、ここでは文化祭を例にとって説明したいと思います。
まず、文化祭の催し物を考えるとき、「何を出店すれば来る人を楽しませられるだろうか」「どのように運営すれば成功を収められるだろうか」という問いを立て、それに則って話し合います。これがAnticipation(見通し)です。このとき、来場者の立場に立って考えることが求められます。
次に、準備から当日の運営、片付けまで、見通しの通りに進めていきます。これがAction(行動)です。予想通りに全てがうまくいくわけではないことでしょう。それも全て「結果」としてまずは受け止めます。
そして、文化祭が終わった後にクラス全体で催し物の結果の確認をします。売り上げ、来場者を喜ばせられたかどうかなどを共有し、成功した点と改善点を話し合います。それを来年の文化祭の出店にどう活かすかというところまで考えれば、有意義な学びとして蓄積されていくでしょう。これがReflection(振り返り)に当たります。
文化祭などの非日常の行事は、ともすれば「楽しかったね」で終わってしまうものです。それをどう「学び」に変えるかが重要です。その方法の一つとして、AARサイクルは使うことができるでしょう。
まとめ
今回は、OECDが提唱しているAARサイクルという学習プロセスについて、詳しく解説しました。いかがでしたでしょうか。常に変化し続けているこのVUCAの社会を、子どもたちが心身ともに健康な状態で生き抜くことができるように、これからの教育にはこのサイクルが欠かせなくなってくることでしょう。普段の授業と非日常の行事に、それぞれどのようにAARサイクルを取り入れるべきか、教員ひとりひとりが真剣に考える必要がありそうです。
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。