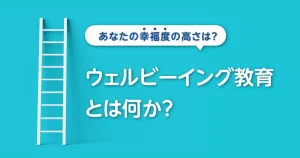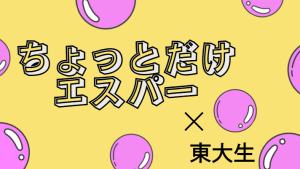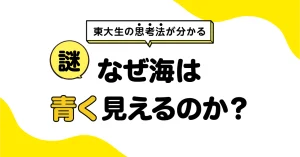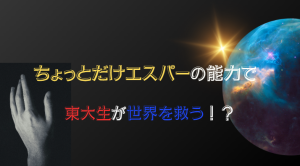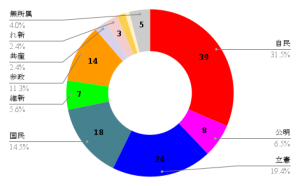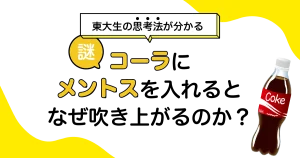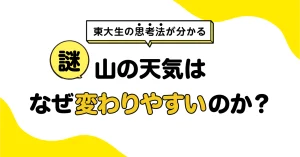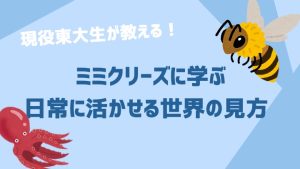みなさんは「おさるのジョージ」を見たことがあるでしょうか。
『おさるのジョージ』は世界中で世代を超えて親しまれてきた人気絵本『ひとまねこざる』『おさるのジョージ』をもとに制作されたアニメです。
好奇心に従ってなんでも挑戦してみることの大切さを伝える教育番組として、子どもに見せている親御さんもいることでしょう。そんな『おさるのジョージ』ですが、実はその作者は波瀾万丈な人生を生き抜いたユダヤ人夫婦。
この記事では、その作者背景から読み取れるこの作品の本当の魅力を、東大生が解説します。
「おさるのジョージ」はどんな作品?
『おさるのジョージ』は、アメリカの絵本作家ハンス・レイとマーガレット・レイ夫妻によって1941年に刊行された絵本シリーズを原作とする作品です。
やんちゃで好奇心旺盛な小さなサル「ジョージ」と、彼を見守る「黄色い帽子のおじさん」の日常を描いています。ジョージが人間の子どものように新しいことに興味を持ち、時に失敗を繰り返しながらも試行錯誤して学んでいく姿が魅力です。
絵本の人気を受けてアニメーション化もされ、2006年からはNHKのEテレでテレビシリーズが放送開始。
番組は「子どもの好奇心を育てる」ことをテーマに、身近な出来事や科学的な疑問を分かりやすく描く構成になっており、幼児向けでありながら教育的な要素が強く盛り込まれています。
子どもが楽しみながら学べる「知育番組」として世界的に親しまれている作品です。
大人が見ても面白い! 「おさるのジョージ」エピソード3選
子ども向けの教育番組である「おさるのジョージ」ですが、大人が見ても勉強になる面白いエピソードがたくさんあります。
実際に3話取り上げてみるので、ぜひ見てみてください。
シーズン3エピソード7「ミミズにょろにょろ」
おさるのジョージ 🐵 ミミズにょろにょろ 🐵TVアニメシリーズ🐵シーズン3
これはジョージや近所の人々が、ミミズを土の山に置いて、土を掘って出てくるまでの速さを競う「ミミズレース」についてのエピソード。
まるでミミズレースが近所で大人気であるかのように描かれていますが、大人が見れば、「ミミズレースって街のみんなで楽しめるくらい一般的なの?」「枕の裏にミミズを飼うなんて!」「黄色いおじさんもそれでOKなの!?」と驚くシーンばかりです。
でも、きっと子どもであればそんな疑問も抱かずに見るでしょう。
歳を重ねるに連れて常識に囚われてしまった大人が、子どもの純粋な発想にハッとし、その大切さに気づかされる話になっています。
シーズン3エピソード10「ながされたー!」
おさるのジョージ 🐵 ながされたー! 🐵TVアニメシリーズ🐵シーズン3
浜辺に下ろしてある錨を「船から落っこちちゃった」と考えて外してしまい、海で迷子になるジョージ。しかし、その経験から、錨が船を固定しておくためのものだと即座に学習します。
大人が見ると、子どもの視点に立って新しいことを学んでいく様子を楽しめる話です。
黄色い帽子のおじさんを始めとする人間も「船がなければイカダを作ろう!」と瞬時にポジティブに動けるからこそ、ジョージも失敗を繰り返しながらたくさんのことを学べるのでしょう。
子どもが「学習」するために、大人がどんな姿勢を見せるべきか、考えさせられるエピソードです。
シーズン6エピソード5「ボーン・チャリーン・パタパタ」
風を使ってシンフォニーを演奏するイベントの設営に協力することになったジョージ。身近なものをたくさん使ってさまざまな音が出るように工夫します。
子ども目線で見れば、身の回りにあるものはいろんな音が出る、ということを学習するエピソードですが、実は大人として見ても学べることがあるのです。
このイベントの主催者は、設営者には無茶を言ってばかり、「きっとなんとかなる、なんとかしてくれ!」とだけ言って現場に丸投げするのです。そして、いざイベントが成功するとその手柄をまるで自分だけのものかのように振る舞います。こういう人はどこにでもいますよね。でも、設営に関わっているジョージも周りの大人も、文句は言わずにさまざまな工夫でイベントを成功させようと努力します。
この構図を見て、社会人ならば何かしら思うところがあるのではないでしょうか。
作者レイ夫妻の波瀾万丈な人生とは
『おさるのジョージ』の生みの親であるハンス・レイとマーガレット・レイ夫妻は、ともにドイツ・ハンブルク出身のユダヤ人。ナチスの台頭によってドイツでの生活が脅かされ、二人はフランス・パリに移り住みます。しかし、1940年、ナチス・ドイツがフランスに侵攻すると、夫妻は命からがら逃亡を余儀なくされました。
彼らは自転車を組み立ててパリを脱出し、南フランスからスペイン、ポルトガルを経由して船でブラジルへ渡ります。長旅の途中、農場で動物たちと寝ることすらあったとか。
でも、心温かい人々に救われながら、彼らは意外にもその旅路を「自由で楽しい」ものとして捉えていたのでした。逃避行の最中には、後に世界的ベストセラーとなる絵本の原稿を自転車の荷台に携えていたことも知られています。
さらにアメリカへと移住し、その地で本格的に『Curious George(おさるのジョージ)』シリーズを執筆・出版。戦火を逃れてたどり着いたアメリカで、レイ夫妻は子どもの好奇心や探究心を尊重する物語を世に出したのです。
こうした背景を知ると、『おさるのジョージ』が作者自身の人生と深くつながっていることが見えてくるのではないでしょうか。
作者背景と作品から読み取れる大切なこと
では、作者背景と作品のテーマから読み取れる、3つの「大切なこと」とは一体何でしょうか。
詳しく解説していきます。
自分で決断し、冒険することの大切さ
レイ夫妻は戦火から逃れる中で、どこに向かい、どう生きるかを自ら決断し続けました。もしかしたら、時代背景が彼らをそうせざるを得ない状況に追い詰めたのかもしれませんが、彼らはその選択を肯定的に捉えています。
パリからアメリカへの旅路は危険を伴う「冒険」でしたが、彼らはそれを重苦しい教訓めいた話ではなく、楽しい逸話として友人に語り、最終的には『おさるのジョージ』という物語に昇華させたのです。
作品の中で、ジョージは好奇心のままに行動し、ときに失敗しながらも周囲に助けられて解決策を見出していきます。
これは、彼らの人生観——「自分で決断し、冒険することの意義」を伝えていると考えられるのではないでしょうか。
身軽で自由であることの大切さ
そんなレイ夫婦にとっては「身軽さ」と「自由さ」が人生の理想であったと考えられます。
波瀾万丈な人生がその結論を生み出したのか、はたまたもとからそんな考え方を持っていたのかはわかりませんが、その考え方が冒険を肯定する根拠となったのでしょう。
アメリカでの自由な生活に希望を見出した彼らは、その精神をキャラクターに重ねています。
作者のハンス自身が非常に強い好奇心を持つ人間で、現実には実現できない自由な探究心をジョージに託したと語っているのです。つまり、ジョージは「制約に縛られず、自由に学び、発見する存在」として、作者の理想像を体現しているといえます。
何があっても相手を許す愛情の大切さ
ジョージのそばには、いつも「黄色い帽子のおじさん」がいます。
彼はジョージを我慢強く助け続け、何があってもジョージを許す愛情を持っているキャラクターです。
この無条件の愛は、ユダヤ人として差別や迫害を経験しつつも、冒険の中で多くの人の温かい助けをもらいながら生き延びた夫妻が、世界に求めていたものではないでしょうか。
誰もが少しずつ他人に優しくできれば、世界はもっと温かくなる——彼らはきっとそう考えていたのです。その思いを、親子間、ひいてはすべての人間関係の理想的な形として物語に落とし込んだと捉えられます。
まとめ
今回は『おさるのジョージ』についてメタ的に解説してみましたが、いかがでしたでしょうか。
『おさるのジョージ』は一見、子ども向けの楽しいアニメにすぎないように思えるでしょう。
しかし、その背景にはナチスの迫害から逃れ、自らの人生を切り開いたレイ夫妻の体験が色濃く反映されています。
ジョージの冒険心や解決策を見出していく姿、黄色い帽子のおじさんの愛情深いまなざしには、大人にとっても人生のヒントとなる深いメッセージが込められているのです。
作者の生き方を知ることで、作品を「子ども向け番組」としてだけでなく、「生き方のヒントを学べる物語」として捉え直すことができます。
視点を変えて作品を見つめることで、私たち大人もまた、新たな学びを得られるのではないでしょうか。
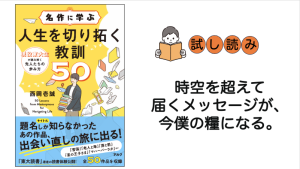
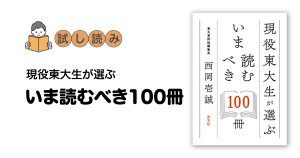
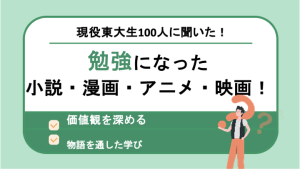
公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!
カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。
生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。
私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。
ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。